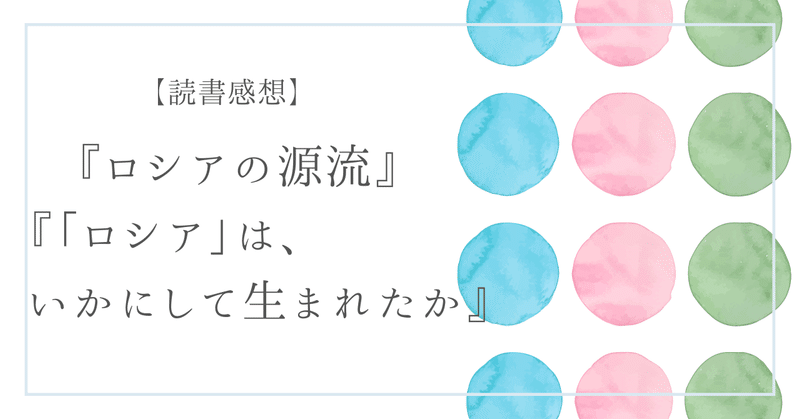
ロシア−ウクライナ問題の起源〜【読書感想】『「ロシア」は、いかにして生まれたか』/『ロシアの源流』
ロシアがウクライナに侵攻して、はや2年以上が経過した。
ロシアとウクライナとの因縁は、別に今日昨日のプーチン時代に端を発するものではない。
根深い紆余曲折を数百年単位で積み上げて来た歴史が地下に横たわっている。
プーチン大統領がウクライナ侵攻の半年前、「ロシア人とウクライナ人の歴史的一体性について」という論文を発表したというのも、(その論文の内容の妥当性はともかく)ロシアとウクライナとの歴史的な因縁を無視できないことを示していると言えるだろう。
1 ロシア−ウクライナ問題の起源
ウクライナとロシアが異なる歴史の歩みを辿り始めたのは、モンゴル=タタール勢力がこの地方に侵出して来た13世紀半ばとされている。
タタールの侵攻以前には、ロシアやウクライナを含む東スラヴ人の「ルーシ」という緩い政治的な枠組みがあった。
しかし、タタールの侵攻を機に、後にロシアにつながる北東ルーシと、ウクライナにつながる南西ルーシとが異なる歴史的展開をたどることになる。
そして、「ルーシ」というかつての共通の枠組みは、中身をモスクワ中心の「ロシア」に換骨奪胎され、後々ロシア国家がウクライナ地域を服属させる際の名目として利用されることとなる。
いわゆる「タタールのくびき」と呼ばれるモンゴル勢力の支配下にあったこの時代。
この時期のロシアを扱った、宮野裕『「ロシア」は、いかにして生まれたか』と
三浦清美『ロシアの源流 中心なき森と草原から第三のローマへ』(講談社選書メチエ 2003年)を読む。
後者は、ロシア史の参考文献として、他所で何度か書名を見かけていた本だ。
ちょうどKindle unlimited に入っていたので、今回読んでみた。

2 宮野裕『「ロシア」は、いかにして生まれたか:タタールのくびき』
『ロシアの源流』と同じく、宮野裕『「ロシア」は、いかにして生まれたか:タタールのくびき』(NHK出版 2023)は「タタールのくびき」時代を扱っている。
大きな文字で印刷された約150ページの薄い小冊子。(山川出版社の「リブレット」シリーズと同じような規格)
歴史の大きな流れだけをコンパクトにまとめている。
タイムパフォーマンスのみを考えるなら、選書サイズの分量である『ロシアの源流』より、こちらの方がおすすめとも言える。
この本で先に話の大筋を確認していたので、『ロシアの源流』を読む時の見通しが良くなった。
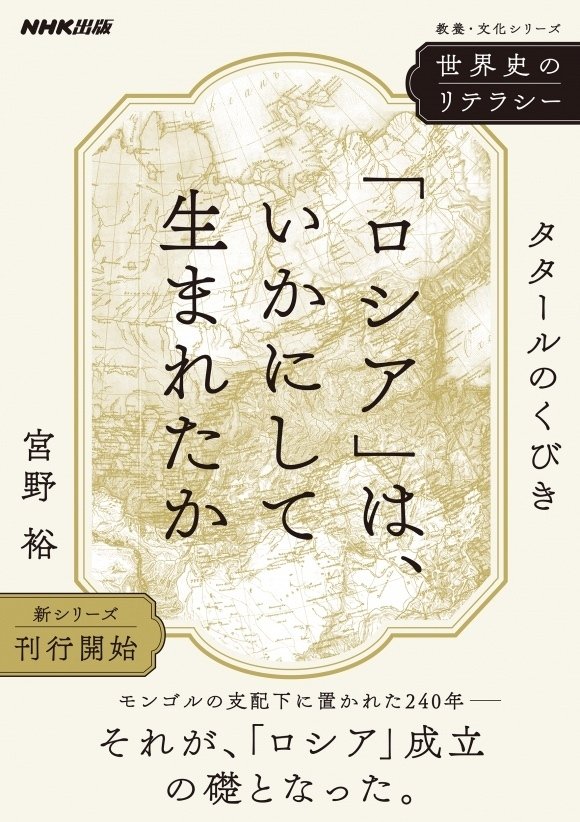
3 「ルーシ」が、モスクワ中心の「ロシア」に生まれ変わる大まかな流れ
ロシアとウクライナ(そしてベラルーシ)の共通の祖先である「ルーシ」がモンゴル侵攻によって壊滅した後、いかにしてモスクワ中心の「ロシア」が出現していったのか。
大きな流れをまとめると、以下のようになると思う。
A 緩やかな諸国連合体としてのキエフ・ルーシ
B タタール侵出により北東ルーシと南西ルーシとが異なる歴史を辿り始める
C 北東ルーシでモスクワ公国が台頭/南西ルーシはリトアニアやポーランドに領有される
D モスクワ国家がタタールやポーランド=リトアニアと対抗しながら勢力を拡大する
A キエフ・ルーシ時代
東スラヴ人が広がる地域は、リューリク朝「ルーシ」国家によって支配されていた。
バルト海、ノヴゴロド、キエフ、ドニエプル川を経由して黒海、コンスタンティノープルにいたる国際交易路を覆う形で、「ルーシ」は広がっていた。
当初はノヴゴロドを、次いで10世紀半ば以降はキエフ(現ウクライナ首都キーウ)を母都市としたためキエフ・ルーシと呼ばれる。
10世紀末にビザンツ帝国よりキリスト正教を導入。
11世紀半ばから各地域は独立性を高め、各地の公国が緩やかな連合体を形成。
中心的な地位を占めたキエフに対して、北東部のモスクワの存在感は低かった。
B タタールのくびき
モンゴル=タタール勢力の侵出により、ルーシ諸国が灰燼に帰す。
その後、ルーシの北東と南西とで異なる歴史を辿ることとなる。
北東部は、宗教的には寛容であったモンゴル勢力へ恭順を示して、ヨーロッパ側の非ギリシア正教の勢力と対抗。
南西部(ウクライナを含む)は、カトリック勢力と協調したガーリチ・ヴォルィニ公国がモンゴル勢力へ対抗。
C モスクワ国家の台頭
北東部内でモスクワ公国の勢力が台頭。
モンゴルの権威や武力を利用して他の有力者やライバル都市を追い落とし、ギリシア正教の府主教座をキエフからモスクワへ移転することに成功する。
一方、南西部はガーリチ・ヴォルィニ公国が分裂し、リトアニアやポーランドに領有される。
D 「ルーシ」の後継者としてのモスクワ=「ロシア」
北西部で地位を確立したモスクワ国家が、タタール勢力やポーランド・リトアニアと対抗して勢力を拡大させていく。
東スラヴ人、リューリク朝の血統、ギリシア正教の府主教座という「ルーシ」の諸要素を兼ね備えたモスクワ国家が、「ルーシ」の後継たる「ロシア」となっていく。
また、ビザンツ帝国の後継者、キリスト正教の保護者として「第三のローマ」という体裁も獲得する。
4 三浦清美『ロシアの源流 中心なき森と草原から第三のローマへ』
上にまとめてみたような歴史の大きな流れというものも、実際の具体的な歴史を辿ってみると、ご多分に漏れず、決して一直線に進んで来たわけではない。
大きな流れからは見落とされてしまう具体的な展開も含めて、三浦清美『ロシアの源流』の方は書かれている。
有力者同士の権力闘争、モスクワのライバル都市トヴェーリとの抗争、ギリシア正教の府主教座の移転をめぐるコンスタンティノープルとの駆け引き、ルーシ北東部内でのノヴゴロドとの微妙な関係など、さまざまな出来事が言及、紹介されている。
「モスクワ国家の台頭」として後世から一括される流れにも、その途上は紆余曲折にあふれているのだ。
場合によっては違う歴史へと至る可能性はいくらでもあった。
ピョートル大帝以前のロシアという、日本の教科書レベルではマイナーな時代の歴史は、読んでいて目新しく、また読み物としても面白かった。
特に、異教国家リトアニアや共和政都市国家ノヴゴロドなど、当時は隆盛を誇りながらも後に歴史の中央舞台からは消えていった存在の記述は興味深かった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
