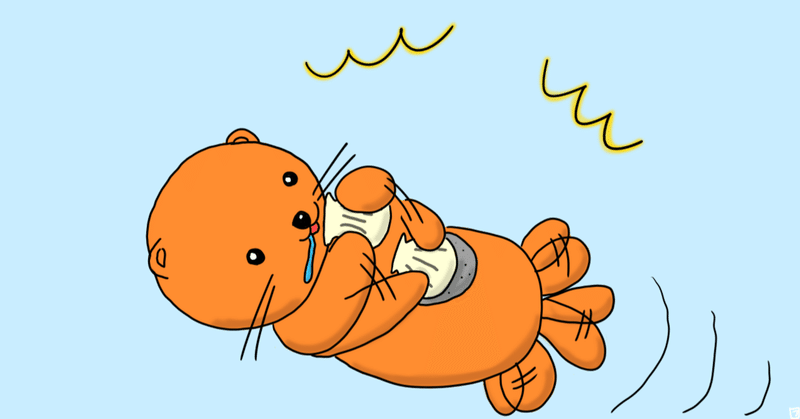
働く時間を減らしたほうがいい人たち
全体的には労働力が不足している(していく)のかもしれません。
都心部のターミナル周辺のコンビニや牛丼屋などは外国人労働者が増えています。
工場や倉庫なども同様です。
タクシーやバスは将来無人化されるのだ、みたいなプランも聞いたことがあります(あまり賛成できませんが)
一方で、一日八時間・週五日を標準とする労働スタイルには根本変化がないようです。
僕は派遣のバイトをやっていて、様々な現場(職場)に行くのですが
一日八時間じゃ物足りない(金銭的に足りないとかも含む)感じの人は、残業の要請があると必ずしていきます。
格差社会といいますが
個人が、一般の職場で活躍できる時間(週当たり)の個人差も広がったようです。
ウルトラマンは地球にたった3分しかいれらません。
リミット(3分)間近になると、カラータイマーが鳴り出します。
職場でもそこに10時間いても、まだヘッチャラ!という感じの人と
終業前にカラータイマーが鳴り出す感じの人もいます。
いわゆる現場みたいなところには様々な人がいます。
僕の見たところでは、先天体力とかにもよりますが
モーレツ型と、余計な(?)親切しまくりの気配り型は、そうでないタイプと較べて消耗が早いようです。
余計な(?)親切しまくりの気配り型は、そうでない人に較べて、正直ムダな動きが多いようです。
そうでない人の1.7倍余計な(?)動きがあるように見えます。
それはともかく、同じ八時間でも、その細胞が負うダメージは個人差が大きいようです。
それでも、40歳くらいまでは、モーレツ型も気配り型も、どうにか(癌などで早死にしなければ)まわりとつじつまが合うようですが
40をすぎると、さすがに、モーレツ型と気配り型は、それまでの労働時間だとガタがくるようです。
そうなりますと、一日八時間・週五日労働では、ダメージを負った細胞のリカバリーが間に合わないでしょう。
もっと、減らす必要がありますね(状況が許せばですが)
一日八時間・週五日労働を60歳(か65歳)まで続けるのが日本の典型的な労働イメージだと思いますが
僕の見たところ、人口の五分の二は、このパターンはムリに思えます(統計根拠に基づきませんが)
月当たりの残業が50時間以上とかをフツーにやってる人とかは、業務内容にもよりますが、人生のどっかで、ノーマルな就業から退かざるを得なくなるのではないかという気がします。
もちろん、全部のはなしは、結局個人差があるんですけど
僕も50歳をすぎて、一般の就労はさらに減らして、noteとかの考え事をする時間や趣味ブログの投稿などに時間を充てています。
労働人口は多分、足りなくなると思います。
バスやタクシーやコンビニなどの完全無人化の時代がそんなにすぐやってくると思えないし、ゴミの収集とか無人化にも限度がある仕事も沢山ありますよね。
にもかかわらず、ある程度の齢(40過ぎとか)になれば、労働時間を減らさざるを得ない人というのが、ある一定の割合でてくると思います。
その場合、状況が許すんであれば、減らすほうがよいと思います。
金とかをたんまり持ってる人だろ?
いや、逆です。
持ってる人は、要医療措置とか要介護の境遇になるのが思いっきり早まったとしても大丈夫です。
金があるからです。
ない人(特にスキルもない人)とかが中高年になって意味もなくモーレツに働いたら、医療措置や介護を受けるには財力が不足してるので困ったことになります。
働きまくってるほうが元気だっていうんならまた別ですけど。
そんなわけで
世間の標準ってのは分かりませんけど
働く時間(一般的な就労)を減らしたほうがいい人というのはいるようです。
(あとがき)
齢くって労働時間減らしてる自分の自己正当化みたいなニュアンスもまったくないわけではない文章ともいえます。
リアルの人からは、就労時間を減らすと、すごくラクをしてる人っぽく見られるんですけど
一般就労は減ったけど、考え事(noteとか)する時間は増えたし
お米を研いだり買いに行ったり(車もバイクもありません)料理つくったり、風呂のカビ取りやったり、実際テキトーに(?)忙しくもあるんですけどね(そんなのわたしも全部やってるけどって言われそうですけど)
細胞のリカバリーもでも大事ですよね。
最近「健康」は大事だなって思うことが多いです。
御一読どうもでした!
(書き始め)
2022年9月19日午前7時42分
(書き終わり)
午前9時08分
サポートされたお金は主に書籍代等に使う予定です。 記事に対するお気持ちの表明等も歓迎しています。
