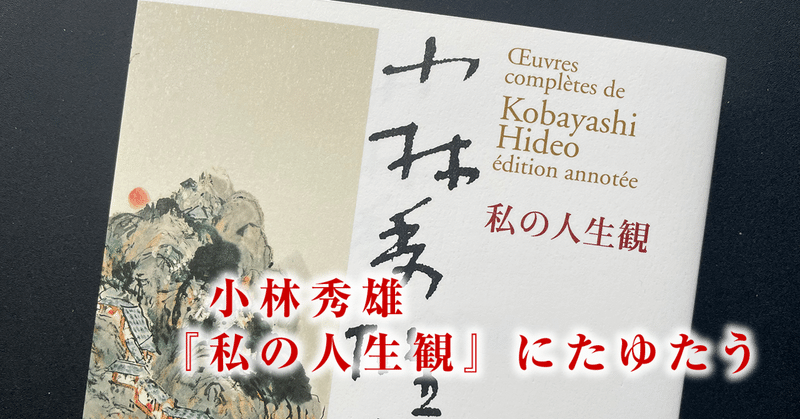
ジャーナリズムは「とってつけた」他人の思想を語っているだけだ
先の戦争では、江戸時代に武士の心得として書かれた『葉隠』における「武士道と云は死ぬ事と見付たり」という部分を、志を果たすためなら死をも厭わないと解釈し、死を肯定・礼讃する根拠として用いた人々がいた。これを小林秀雄は「少壮軍人達の暴挙も、『葉隠』の翻訳ではない」と断ずる。若い兵士たちが死を肯定・礼讃したことは、『葉隠』が本来、「死を意識すれば、いまある生を輝かせることができる。いまを一所懸命に生きろ」という意味を読み解けなかったのだという。
そのような言説を蔓延らせた要素の一つとして、小林秀雄はジャーナリズムについて言及する。
一流のジャアナリズムの論説は何を語ったか。封建主義的思想を語ったか。飛んでもない事です。(中略)彼等は時局便乗派であった、と誰が本当に笑えるでしょうか。知性の奴隷となった頭脳の最大の特権は、何にでも便乗出来るという事ではありませんか。
これは、自らも従軍記者として中国大陸に渡り、記事を配信するといった方法で、結果的に戦争に関わることになってしまった小林秀雄自身をも思い出させる。小林秀雄自身は「政治的に無智な一国民として事変に処した。黙って処した。それについて今は何も後悔もしていない」(『コメディ・リテレール 小林秀雄を囲んで(座談)』「小林秀雄全作品」第15集p34)と、反省することはないと断言している。しかし、関わったという事実は、決して消えない。
それでも戦争を、死というものを観念的にとらえ、それを戦意高揚につなげてしまったメディアやジャーナリズムは、『葉隠』の解釈ができなかったように、知性が備わっていると勘違いしているだけで、結局は自分の頭で考えず、他人の考えに便乗しただけだと指摘する。
自らを経験主義者だと語る小林秀雄にとって、個人の経験は個人の範囲や枠内にとどまるものであり、昇華すること、抽象化することは難しいと分かっている。それは日中戦争という出来事も同様で、国民が経験したことのない、初めてのタイプの戦争であり、どう対処したらよいかという知恵が備わっていないものとして、小林秀雄は「新しさ」という言葉を選んだ。それが『事変の新しさ』(「小林秀雄全作品」第13集)における「新しさ」であり、事変すなわち戦争が、画期的で斬新なものだという意味ではない。
小林秀雄を私淑する哲学者の池田晶子は、哲学を学ぶ、哲学を知る、という言い方を嫌った。哲学は「在る」ものではなく、哲学を「する」ものだ、哲学「する」すなわち「考えること」そのものだという。
そして、哲学「する」ことで何らかの考えを得ることを「知る」と言い、その考えの総体を「思想」と呼んだ。よって「哲学」と「思想」は別のもの。「あの人は○○という哲学を持っている」という言い方は誤用である。
思想が得られたからと考えることをやめてしまった者は、すでに哲学「する」ことをやめてしまったので、哲学者ではなく、「思想家」だという。また、思想は考えの総体である以上、他人の思想を自分のものに「とってつける」ことが可能である。よって思想は「とってつけた」ものであり、自ら「哲学」せずに他人の思想を「とってつけた」者も池田晶子は「思想家」と呼んだ。
この池田晶子の考え方を援用するならば、結局、ジャーナリズムとは「とってつけた」他人の思想を語っているだけであり、自らの経験という具体性なしに物事を抽象化した言説、すなわち観念を述べているに過ぎない。それが戦争に大きな影響を及ぼしたのだと小林秀雄は指摘しているのだ。
そのうえで、『私の人生観』における最後の段落で、ジャーナリズムのあり方に触れながら、小林秀雄が最も言いたかったことは何だろうか。
(つづく)
まずはご遠慮なくコメントをお寄せください。「手紙」も、手書きでなくても大丈夫。あなたの声を聞かせてください。
