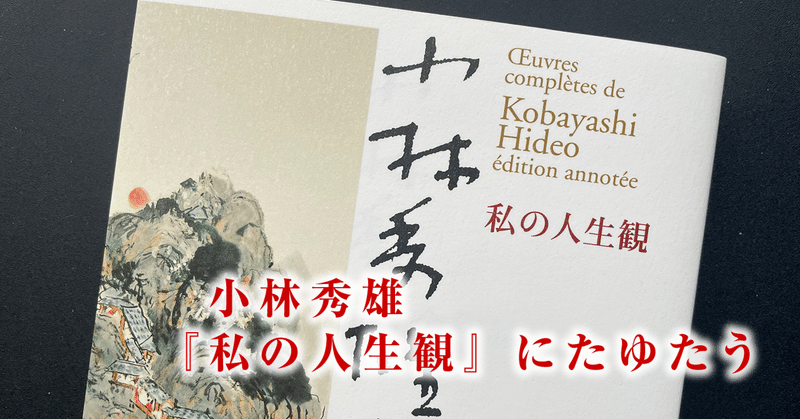
もはや政治に与せず、みずから「文化」を体現する
練達した「手仕事」をする大政治家はもはや現れない。政治には組織化が必要だ。組織化とは機械化であり、人間的な仕事をもはや期待できない。政治は能率的な技術であればよい。政治家は、社会の物質的生活を調整する技術家であればよい。政治家には精神生活の深いところに干渉する技能も権限もないと、小林秀雄は断言する。
政治家は、文化の管理人乃至は整理家であって、決して文化の生産者ではない。科学も芸術も、いやたった一つの便利な道具すら彼等の手から創り出された例しはない。彼等は利用者だ。物を創り出す人々の長い忍耐も精緻な工夫も、又、そこに託される喜びも悲しみも、政治家には経験できない。(中略)こういう常識の上に政治家の整理技術は立つべきだと考えているだけなのです。
「文化活動とは、確かに家が建つという事だ」というのが、小林秀雄の文化論である。どのような形であれ、精神の刻印を打った現実の形を創り出すことが文化であり、勤労または手仕事だという。
敗戦直後、当時の東久邇宮稔彦首相は「軍官民、国民全体が徹底的に反省し懺悔しなければならぬ。一億総懺悔をすることがわが国再建の第一歩だ」と述べ、政治家の戦争責任をあいまいにし、国民の側にまで反省を求めた。戦争中、大新聞が戦意高揚のために軍国主義プロパガンダの一翼を担ったことは、紛れもない事実だが、その新聞社までが首相発言を何の批判もなく報道し、さらに国民に対して一億総懺悔を求めた。我が国の「お上主義」は、当時もいまも根強い。
まだまだ混乱期にあった1948(昭和23)年11月、地方紙の一つである東大阪新聞社が主催する「第二回聴く文庫」という講演会が開かれる。招かれたのが小林秀雄で、与えられた課題が『私の人生観』である。
東大阪新聞社は終戦から半年も経たない1946(昭和21)年2月にタブロイド紙「夕刊新大阪」を創刊していた。まだ大新聞に文化欄がない時代に「夕刊新大阪」は学芸欄や投書欄に力を入れた。執筆陣も多彩で、志賀直哉や坂口安吾、折口信夫、正宗白鳥など、「小林秀雄全作品」ではなじみ深い文学者も多く並ぶ。『私の人生観』の講演抄録ももちろん「夕刊新大阪」に掲載された。「骨董はいじるものである。美術は鑑賞するものである」という名文で知られる『骨董』(「小林秀雄全作品」第16集)も、同紙が初出である。
そんな「夕刊新大阪」の、主筆である井上吉次郎の創刊の辞(社説)を引く。
敗残の国家の背後をなす日本社会は、脈々たる生命を保存する。社会大衆は、その生命力の故に、国家再建の希望を湧かす。元の強大なる軍国を再興しようというのでないから、我々の希望は空想でない。世界の余地の国々が待望する線に沿って、我々の国家生活を見直そう、という希望は達成される。(中略)われわれは基地をこの社会大衆の要望に置きたい。立場を社会大衆に求める。故に如何なる党派の機関でもない。保守勢力は当然にわれわれの排撃するものである。新日本の希望達成を邪魔する何物も、残りなく破壊しよう。希望達成の線に乗る一切のものと手を携えよう。特に或る一派と抱合するようなことはしない。
創刊の辞なので、威勢のいい言葉が並んでいるのは仕方ない。しかし、「夕刊新大阪」の、国家生活を見直し、社会大衆の要望に応えるべく、学芸欄や投書欄といった文化面に力を入れるという方針は、現代に生きる我々が想像する以上に、切実だったのではないか。
「お上」に従ったから、戦争に巻き込まれ、敗戦となっては苦しい生活を強いられているのだ。空腹を満たしたいのは当然だ。しかし、戦争中には満たされず、戦後だからこそ取り戻したいもの。それは、人間としての精神性であり、それに潤いを与えるものとしての「文化」なのだろう。
小林秀雄は1938(昭和13)年3月から大陸に渡り、上海、杭州、南京、蘇州などを従軍記者として移動している。従軍記事も書いたことで、軍国主義プロパガンダに加担した者として、戦後は「戦犯」扱いもされた。そんな小林秀雄が、いくら我が国第二の都市とはいえ、地方紙に繁く寄稿し、講演まで行ったのは、もはや政治には与せず、精神の刻印を打った現実の形をが創り出す「文化」だと信じたからではないだろうか。物を創り出すための長い忍耐も精緻な工夫も、そこに託した喜びも悲しみも知る者として、みずから「文化」を体現しよう、まさに「手仕事」をやっているのだと、小林秀雄は考えたように思う。
(つづく)
まずはご遠慮なくコメントをお寄せください。「手紙」も、手書きでなくても大丈夫。あなたの声を聞かせてください。
