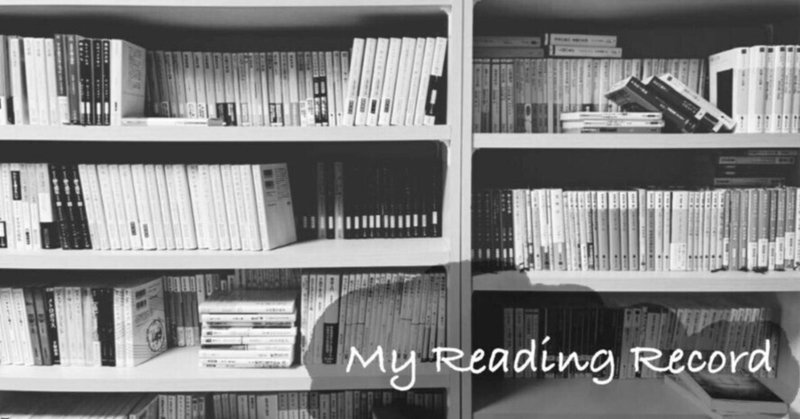
デレラの読書録:村上春樹『街とその不確かな壁』

村上春樹,2023年,新潮社
何が現実であり、何が現実ではないのか? いや、そもそも現実と非現実を隔てる壁のようなものは、この世界に実際に存在しているのだろうか?
自分自身を、存在を、運命を、人生を受け容れる物語。
主人公は自分自身の受容のために、恋をする必要があった。
そして、それを失う必要があった。
不確かな壁に囲まれた街を経由して、現実と非現実が同居した現実世界で生き、とある少年の行方を見届ける必要があった。
人生を受け容れるためには、人生を生きねばならない、というある種のパラドクスがそこにはあった。
にわとりが先か、たまごが先か。
いずれにせよ、生きねばならない。
この物語の中で起きる不可思議な出来事に、読者は戸惑うだろう。
どういうことか。
それは、出来事の説明がほとんどされないまま、物語は結末を迎えるということである。
問いは多く残される。
例えば、この物語に登場する街とは結局何だったのか。
街というのは、主人公が少年時代に出会った少女と一緒に想像した「空想の街」である。
この空想の街について、結局読者は何も分からないまま結末を迎える。
他にもたくさんの謎が謎のままにされる。
主人公が務める図書館にある「半地下の暖炉がある部屋」とは何だったのか。
不確かな壁とは何だったのか。
青春時代に出会った少女はどこに消えたのか、何があったのか。
〈夢読み〉とは何だったのか。
影とは、分身とは何だったのか。
あのイエロー・サブマリンの少年はどのように消えたのか。
結局主人公はどうなったのか。
たくさんの象徴的で不可思議な出来事があった。
迂遠な、何かのメタファーであるかのような出来事たち。
イメージを連想させるような説明はあるが、しかし、確定的な、定義的な、はっきりと明確な説明はない。
端的に言えば、イメージはあるが、定義はないということ。
イメージ ⇔ 定義
イメージというものは、人によってことなるものであり、個人的なものだろう。
わたしのイメージを共有することはできない。
第三者に対して、わたしのイメージを共有するには、言葉や表現を駆使して「一般化」する必要がある。
ようは、イメージを定義化することによって、第三者に明確に伝えることができる。
イメージ = 個人的なもの
⇅
定義 = 一般的なもの
しかし、村上春樹のこの小説は、それを行っていない。
読者のイメージを喚起する表現だけをして、定義はしていない。
作中に最も象徴的な例がある。
それは、イエロー・サブマリンの少年が書いた「街の地図」を主人公は誰にも見せなかった、ということだ。
「見せない」という表現は徹底されていて、読者への提示すらされていない。
この小説で登場する「架空の街」の地図を、巻頭や末尾に付録としてつけても良さそうなものだが、それすらしていない。
ただ物語の中で、口頭での説明があり、それを聞いたイエロー・サブマリンの少年が、ものすごい精度で地図を描いた、ということが提示されるのみである。
地図はあるが、それは絵として見ることは出来なかった。
これは、この不確かな壁に囲まれた街を「イメージできた者」だけが、その街に行くことができるということなのかもしれない。
それが読者に対しても徹底されている、ということだ。
読者は、街をイメージできるだろうか。
この問いは、「この物語の不可思議な出来事に、読者は戸惑うだろう」というわたしの感想とリンクしている。
もうひとつ、定義を避けていることを表す例がある。
物語の中でイエロー・サブマリンの少年は消失してしまうわけだが、その少年の兄二人が、失踪した弟(イエロー・サブマリンの少年)を探すために、主人公の元を訪れるシーンがある。
この二人の兄は、有名大学を出て、医者、そして弁護士の仕事をしている。
ようは、2人の兄は理性的で知的な存在者として物語に関わってくるのである。
その兄が、街というのは「人間の意識構造」なのではないか、という推察を行う。
「僕は思うのですが、街を囲む壁とはおそらく、あなたという人間を作り上げている意識のことです。」
つまり、兄は「街」を理性的に、知的に、それを定義しようと試みる。
しかしながら、読者はその試みが失敗であると感じるだろう。
なぜなら、その「街」の全容について、特権的な立場にある主人公がその説明を「良し」としないからだ。(少なくともそれが真実だという納得感は提示されない)
私はもちろん肯定も否定もしなかった。ただ黙って彼の顔を見ていた。
さて、このように、この物語は、明確化、定義化、一般化を避けており、説明を省き、個人のイメージの領域から出ないように描かれている。
読者には定義は与えられず、イメージだけが与えられる。
誤解を恐れずにザックリと言ってしまえば、この物語に登場する出来事を十全に理解する必要など無いのかもしれない。
いや、本当は何かを表しているのだろう。
しかし、それを定義するかどうかは、この物語においては些細なことなのかもしれない。
壁は意識の壁の、街は精神構造のメタファーかもしれない。
あるいは、街を想像するということが、小説を書く営み自体を表現している、つまり、この小説はメタ構造をしているのかもしれない。
叶わぬ恋、あるいは、性的な挫折がもたらした不能性を中心に構築された精神の壁。
こういう精神分析的な読解は可能だろう。
しかし、わたしにはこれらの解釈は些細なものに感じられる。
ようは、個別の出来事(イメージ)の解釈(定義)は、わたしの読書体験の中ではあまり重要なものに感じられなかった。
では何が重要なのか。
それは、ありきたりなことを言うが、「信じる」ことである。
この物語を通じて感じられたイメージをそのままに抱いて、眼を閉じて信じることである。
「そうです。彼があなたを受け止めてくれます。そのことを信じてください。あなたの分身を信じることが、そのままあなた自身を信じることになります」
主人公は不可思議な出来事(イメージ)を経験しながら、自分自身を、言わばその運命を受け容れる。
運命の受け入れには、定義は不要なのかもしれない。
この人生は何だったのか、わたしは誰なのか、どういう存在なのか、そういうものの定義をすっ飛ばして、イメージを信じるということ。
主人公が自分自身の人生を、運命を受け容れたように、わたしもまた、この物語から想起したイメージを受け容れるということ。
わたしは、わたしの分身(イメージ)を信じることができるだろうか。
今は分からないけれど、この先に。
この感覚(イメージを感じることそのもの)が重要なのだ。
おわり
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
