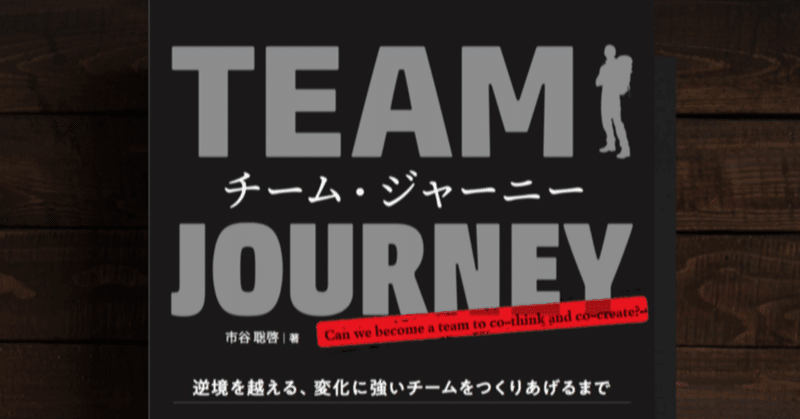
「チーム・ジャーニー 著者による本読みの会 第14話『クモからヒトデに移行するチーム』」に参加しながらまとめてみた
先週はネットワークトラブルのため延期になってしまったので、2週間ぶりの読書会です。
クモからヒトデに移行するチーム
銀の弾丸をなすりつけるチーム
チーム同士の活動がかみ合い始め滞りなく開発が進めているところからこの話は始まります。
プロダクトチームにテスト管理ツールのゼロチームが合流。プロダクトチームの社さんが異動し後任に貴船さんが当たることに。
キャラの濃い人たちが合流することで再度統合に向けた動きをしようという動きになりました。
プロセスヲ標準化セヨ
テスト管理ツールの統合に向けて再び横断チームを結成。さらにはマーケティングチームとの絡みもあり、コミュニケーションを取る先が増え、プロダクトリーダーという役割もこなしているので、コンテキストスイッチが頻繁に発生している状況が続いています。
そりゃ誰に何をどこまで伝えているか分からんくなるわな……。
その様子を見かねた貴船さんが、チーム運営のコンサルを招きます。
各チームのコードレビューでの質を担保、レビューのための申請書を義務付け、さらにテストケースのドキュメント化とそのレビューも徹底されるようになりました。
宇多野チームでやって、自称うまくいっていることを、全チームに適用しようとして軋轢が生じます🙄
そんな時に蔵屋敷さんが現れ太秦にこう言います。
「こんなんでは、ダメだぞ。」
カイゼン・ジャーニーにも出てくる台詞だそうです。
クモからヒトデになろう
さっそく蔵屋敷さんは、今進めている施策の中止を求めました👍
「どこかのチームで上手くいったやり方を他のチームにもそのまま適用して上手くいくとは限らない。チームが異なれば、同じ会社であっても会社の外の現場と大して変わらない。」
銀の弾丸はありません!
QA に専門特化した横断チームの設置も進められました。
ただ太秦さんも蔵屋敷さんにこう言われます。
「太秦は、プロダクトリーダーを降りたほうがいい。」
リーダーが必要なジャーニーはもう終わっているので、逆に意思決定のボトルネックになってしまっていると指摘されます。
そしてクモとヒトデの話が出ます。
「中央集権型、強いリーダーがいて引っ張り続けるのがクモ型の組織だ。司令塔の頭が体全体を活かせているうちは良いが、頭がもしやられてしまったらどんなに立派な体を持ったクモもたちまち動けなくなってしまう。」
「分散協調型、それぞれが自律的に動きながらお互いの協調でもって成り立つのがヒトデ型の組織だ。人ではどこをやられても、活動を停止しない。どの部分も頭になりうる。チームの立ち上がり時は強力な牽引が必要になるだろう。だが、このチームは、もう人手に足る段階に来ている。」
これを聞いて分散協調型は要はティール組織ってやつかなと思いました。
ここでまた人事異動が告げられます。プロダクトマネージャーに社長が就任しました🙄 チームの責任者は太秦に。
あとグレース・ホッパー氏の有名なあのセリフも登場します。
「”事前に許可を求めるより、後でゆるしを得たほうがたやすい”だよ。」
標準化ではなく共同化、共同化から協働へ
詳細と俯瞰を行き来する
マネジメント機能を担う役割は、俯瞰的立ち位置にありつつ、時に詳細へと踏み込むという行きつ戻りつを繰り返すことにより、負荷が高くなる。
越境的なマネジメントリードほど山のようなタスクを抱えることになるので、心がけるべきタスクに対する指針が2つ挙げられています。
①自分の目の前から自分がやらなければならないタスクを一掃する
やらないことリストに移したり、担当をメンバーに振り直したり、チームの外から力を借りてきたり、自分が片付けるのではなく自分の目の前からなくすことを心がける。
自分の手元のタスクで手一杯となり、チームの先を捉えるというその役割を果たせていないとしたら本末転倒だ。
②チームの目の前からやらなければならないタスクを片付ける
間違っても、マネジメントリードがチームの眼前にタスクをひたすら積み上げていくだけの役回りになってはいけない。
プロダクトづくりとは異なる視座(そもそもの事業の目的や組織の狙い)から判断を行ったり、解釈を示したりするのは、マネジメントリードの重要な機能であり、役割だ。
意思決定を立体の中で泳がせる
意思決定の精度はどれだけ前提を問い続けたかという軸と、どれだけ選択肢を挙げられたかという2軸で構成される。
前提の前提、さらにその前提と深く掘り下げ問い続けていくかが重要でさらに、どれだけ前提が成り立たないケースを考えられたかに着眼したいとも書かれています。
現時点では良さそうな施策も、時間を先に送るとそうではなくなる可能性があるため、意思決定の筋の良さを高めるために、さらに時間軸を加えることが挙げられています。
技術的制約で仕方が無くやった実装も、その技術的制約がいつの間にか解消されていたらリファクタリングして綺麗にできますもんね!
先導者はやがて「自分」を手放す
先導するということは、逆にチームがそれ以上の速度で進めない。
チームの立ち上げ時にはクモ型の組織として、強力なリーダーシップが求められますが、チームメンバーの練度と自律性が高まったならばヒトデ型の組織に移行することが勧められています。これはリード役が自ら自分の役割を手放すことです。
標準化ではなく共同化
チームにある考えや志向性(文化といえるだろう)などをひっくるめてチーム個別の文脈を無視した取り組みを強引に導入したところで、ハレーションを起こすだけだ(一方、まだ文脈が育っていないチームにとっては、自分たちの活動の型を決めていく足がかりになりうる。)
それぞれの自律性を残しながら、標準ほど厳格なプロトコルを課すことなく、お互いの把握と歩み寄りを進めるためにはどうしたら良いかというところで、ともにつくることが挙げられています。それが共同化の意味するところで、2つの段階があります。
①時間と場所をともにする
合宿してみたり、他のチームのミーティングをのぞいてみたり、ディスカッションしてみたりといったことが挙げられていました。
こういう情勢なんで難しいですね。。。
②仕事をともにする
モブワークを取り入れて一つの仕事に一緒に取り組むことが挙げられていました。
最も自分の学びが深まる瞬間とは、他人に説明しようとするときだ。
これら共同化を重ねていくことで、その先の協働化の状態に行き着くことができます。
協働とは、ミッションを共有し、お互いに協力しながらその達成へと向かう相互作用のことだ。
---
企業の採用でカルチャーやミッションのマッチを重視する話にも通じていると思いました。そういう業界で働いているので!
今回は自分たちのチームで上手くいっている取り組みを全体に広げようとして上手くいかなかった点と、太秦さんがうまく立ち回れなった点の2点が課題ですね。
前者に関してはチーム間で合意を取らずに、さらには貴船さんが外部コンサルを入れてしまったので、全員やらされている感出てしまっているように感じました。コミュニケーション大事。気をつけなきゃ。
来週は第15話! 社長が出てきてどうなるのか楽しみです。
😉
