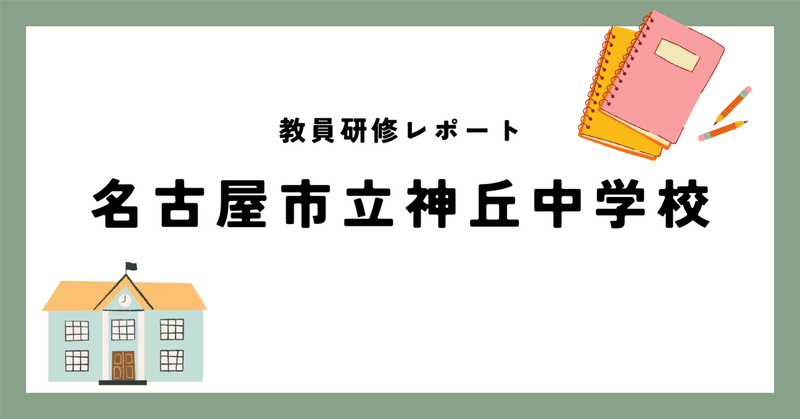
【研修レポ】名古屋市立神丘中学校の現職教育研修でお話をさせていただきました
少し前のお話になりますが…2023年3月に、名古屋市立神丘中学校の先生方の現職教育研修があり、以前からご縁のあった弊社の壷屋が現地でお話をさせていただきました。
神丘中学校では、2022年度より「心理的安全性」を先生方の共通テーマとして掲げており、「心理的安全性」について同夏に脳の観点からも学び、日常での実践を重ねておりました。
心理的安全性とは?
『チームの心理的安全性とは、チームのメンバーが、リスクを冒し、自分の考えや懸念を表明し、疑問を口にし、間違いを認めてもよく、そのいずれをもネガティブな結果を恐れずにできると信じていることである。エドモンドソンに言わせれば、「率直であることが許されるという感覚」である。』
組織運営などで、この心理的安全性が大切であるとGoogleさんを筆頭に謳われはじめ、近年では、学校現場でも注目されるように。
神丘中学校の先生方も、心理的安全ではない状態(🟰心理的危険な状態)がもたらす脳への影響に対する理解が深まり、そういった危険な状況を作らないような意識づくりを進めてこられたそうです。
そんな中、新たな疑問と葛藤が。
心理的危険な状態は、学びに繋がらないし、避けた方が良さそう。でも果たして回避することだけが正解なのか?それは子どもたちの成長の機会まで奪いかねないか?
「心理的危険な状態に気づけるようになってはきたが、回避以外の具体的なアクションのイメージが湧きづらい。もう少し理解を深め、行動に繋げていくためにも、改めて話してもらえないか」と(当時の)校長先生より直々にご依頼をいただき、先生方の前でも、急遽、お話させていただくことに!
限られたお時間ではありましたが、復習も兼ねて、心理的安全な状態と危険な状態の脳の働きの違い、あわせて、ストレスのお話もさせていただきました。

心理的安全とは(DAncing Einstein Lecture Version)
心理的安全な状態と危険な状態では、脳の前頭前野の機能が変わってきます。感情的になって普段やらないようなこと、言わないようなことを言ってしまったり、冷静な判断が難しくなってしまいます。

では、どういうときに心理的危険な状態に陥ってしまうのでしょうか?

はい、そうです、ストレスが過剰になってしまったとき、です。
ただ、「過剰」の定義は、人それぞれ異なります。強いストレスで、一気に「過剰」レベルに到達してしまうケースもあれば、日々の積み重なりから、ちょっとしたきっかけで「過剰」水域に入ってしまうことも。
また、ストレスへの反応は多様なものであり、自分が大丈夫だからと言って、他の人も大丈夫とは限りません。更に、同じ人であっても、ベースの状態が異なれば、反応も異なってきます。
みなさんもご経験ないでしょうか。
普段なら気にも留めないようなことでも、寝不足が続いたり、仕事でのプレッシャーなどのストレスの積み重ねによりイライラしてしまったというようなこと。
人間には、ストレスを排出する仕組みも備わっていますが、強い刺激が多く、変化も目まぐるしい現代においては、それだけではなかなか排出が追いつかないことも。
なので、子どもたちの心理状態がどうかということを推し量ることも大切ですが、お互いにとって学びとなる対話を繰り広げるためには、まずは自分自身の状態を確認することも大切でしょう。
とはいえ、ストレスは完全悪ではなく、バケツに余裕がある状態であれば、成長を促す要素にもなってくれます。心理的安全性の土台の上に、「適切な(これも人によって異なる)」ストレスが加わると、成長にも繋がっていくのです。(テスト直前になると、わー頑張らなくちゃ!!って勉強が捗るのも、ストレスがポジティブに作用している表れ)
そこまでお話をさせていただいて、その後、ミニワーク&シェア。
ワークでは、事前に共有いただいていた、昨夏の研修で先生方から挙がった「心理的安全性を脅かすかもしれないコミュニケーション」リストの中から「(授業などで)突然、指名する」という事案を取り上げ、生徒に成長してほしいと願う先生の立場から、そして人前で話すことが苦手な生徒の立場から、心理的危険な状態に陥らないためにはどうしたらいいか、自分だったらどうするか、どうしてほしいかを考え、シェアすることを実施しました。

もちろん、唯一解などありません。
生徒を思ってのことでも、押し付けるような形ですとその思いは伝わらないでしょうし、とはいえ何も働きかけないと、なかなか現状は変わりにくい。
対話が必要そう。でもどんな対話?
そもそもみんなの前で話せるようになることがそんなに重要なのか?
自分の意見を持ってシェアすることが大事とするなら、ICTも活用できるんじゃないか?
様々な新しい問いと共に、多様な意見の交換が行われました。
短い時間ではありましたが、日頃から「心理的安全性」について考えられている先生方だからこそ、建設的な議論が進んだように感じます。
研修後に先生からご質問をいただいたり、前向きなコメントをいただいたり、我々も新たな気づきや学びをさせていただきました。
本当にこのような機会をいただけたことに感謝です。
これからもご縁を育んでいけたらと、心より脳より思っております。
神丘中学校のみなさん、誠にありがとうございました!
学校・教育機関での講演&研修のご依頼はこちら!
DAncing Einsteinでは、全国の小学校、中学校、高校、大学といった学校現場、また教育委員会をはじめ教育行政、その他民間の教育機関等において、①児童・生徒を対象とした講演、②教職員向けの講演・研修などをご提供させていただいております。
<主な講演テーマ>
▶️ 子どもの自律 ▶️ メタ認知 ▶️ ストレスとの付き合い方 ▶️ 集中 ▶️ モチベーション など…
講演・研修をご検討の教育機関ご担当者様は こちら よりお問い合わせ・ご相談くださいませ!
DAncing Einsteinの取り組みをご紹介しております。
noteマガジン DAE Report では、DAncing Einsteinによる講座・講演のほか、これまで携わらせていただいたプロジェクト等の実績の一部をご紹介しております。
どんなことをしている会社なのだろう?と興味をもっていただけた方は、覗いてみていただけると幸いです。
(※随時更新してまいります)
