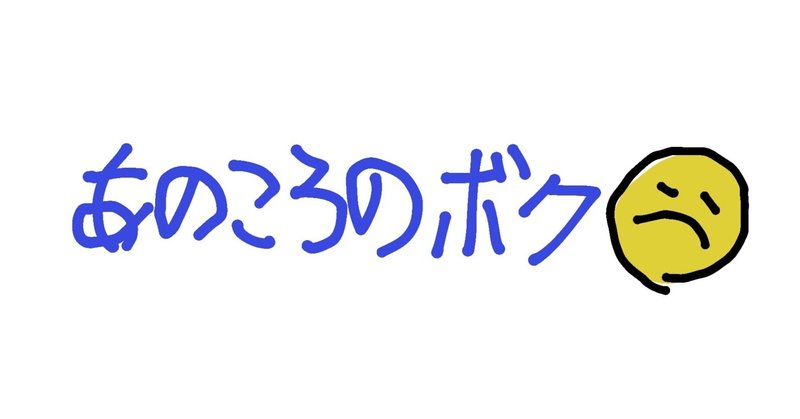
「死なないでいる理由」を読んで
鷲田清一の「死なないでいる理由」を読んだ。今日はその評論ではく感想だ。読んでいて思い出すことがあった。
感情が切羽詰まって逃げ出す、その表現に受験のころの自分を思い出だす。塾に通っていた僕は、先生の優しさのあまり自分の無知さがさまよう、その場所が嫌になるときがあった。家を出て塾とは反対方向の道を進む。勉強から逃げたその先は、何も満たされない空白の時間があった。当然会う人もいないので、話す相手は自分自身。言葉にできない心情をニュアンスで誤魔化しては、なんだか否定的で自虐的な考えにたどり着く。
現代社会は意味を求める必要があるのだ。今ならそう考える。生きる意味も、勉強する意味も、もとめられる。求めないことにも、きっと、どうしてと疑問を投げかけられるだろう。そうして、意味と感情の交差した先が諦めとなる。僕が自虐的な考えに至ったように。
受験のときはストレスフルな生活を強いられた。心の中は整理がつかず、流れるように過ぎていく日々に身を委ねるだけだった。
大学生として振り返ると、あの頃の僕にとってあの感情の整理は難しすぎたと思う。しかし、それを勉強しない理由や言い訳にするつもりはない。それはそれとして、僕は今を生きるにどうするかを考えている。再度、あの虚無の空間に追いやられ、ついには自己嫌悪に陥るようなことが起きるやもしれない。そんなとき、どのような心情をもてばいいのか、まだ分からない。
結論を焦らないということを意識したい。あらゆる実験を経て深く考察した末、導き出した結論でも、当然反する意見から覆る可能性を十二分に持っている。つまりはどれも考えの域を超えていないのだ。
なにかを定めるには、世界や現代社会はあまりに不確定で、定めなければならないことは、太陽の動きや生物の生死のように、もう既に定まっていると考えるべきだ。
意味を問うことに意義を見出せば、それが結論として、あらゆる思考に居座るだろう。そうするより先に、この世に存在する限り意味はあり、意味のないものはそもそもこの世には存在していないと考えるほうが合理的だ。意味のないことですら意味のないこととして意味を持つのだから。
幼い頃に外に向けていた好奇心が、青年期にはうちを向く。社会をある程度知ってしまったために、自分を他者をもって測るようになる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
