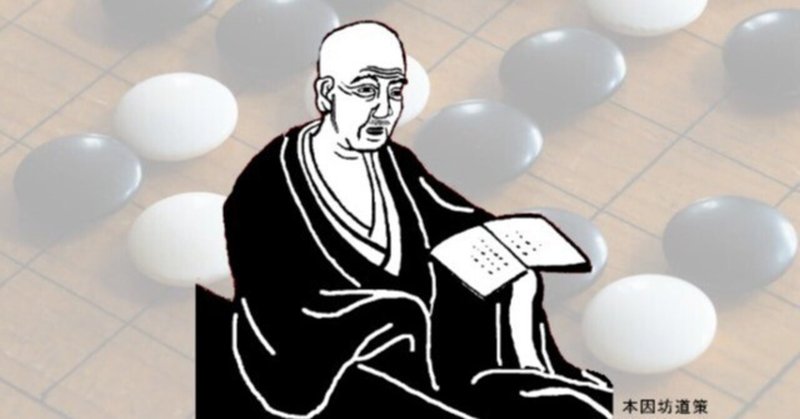#囲碁
囲碁史年表(算砂~道策)
本因坊算砂が生まれた永禄二年 (1559)から、本因坊道策が亡くなった元禄十五年 (1702)までの間の囲碁に関する出来事を年表にまとめてみた。
色々な出来事を時系列に並べてみると、その背景や伝承の矛盾点が見えてきて、なかなか興味深いものである。
なお、出来事は伝承なども含まれるため、史実ではないと考えられるものもあるがご了承いただきたい。
・添付のExcelのデータをダウンロードして御覧く
囲碁史記 第7回 織豊時代の碁打ち
碁打ちの立場と浸透
室町時代の後半、戦国時代と呼ばれる時期になると多くの「碁打ち」と呼ばれる人達が登場する。十六世紀中頃を過ぎたあたりで、末期には江戸時代へと続く本因坊たちが登場するが、その一世代前の碁打ち達である。代表的な人物として初代本因坊算砂の師匠といわれている仙也をはじめ、宗心、樹斎、庄林など多くの上手達がいる。
当時の公家や神官などの日記類にはこれらの碁打ちが多く登場している。それ
囲碁史記 第20回 本因坊道策の登場
四世本因坊道策は本姓山崎、幼名を三次郎という。正保二年(一六四五)に石見国馬路村(現在の島根県大田市仁摩町馬路)に生まれた。
馬路にある延長約1.4kmの円弧状の砂浜「琴ヶ浜」は、歩くとキュッキュッと音が鳴る鳴砂として知られ、「日本3大鳴き砂」の一つとして国指定天然記念物及び日本遺産に認定されている。幼い頃の道策も砂浜を歩いていたのかもしれない。
石見(島根県の西半分)の人々が尊敬している偉