
囲碁史記 第17回 大橋家の記録に見る算知・道悦の争碁
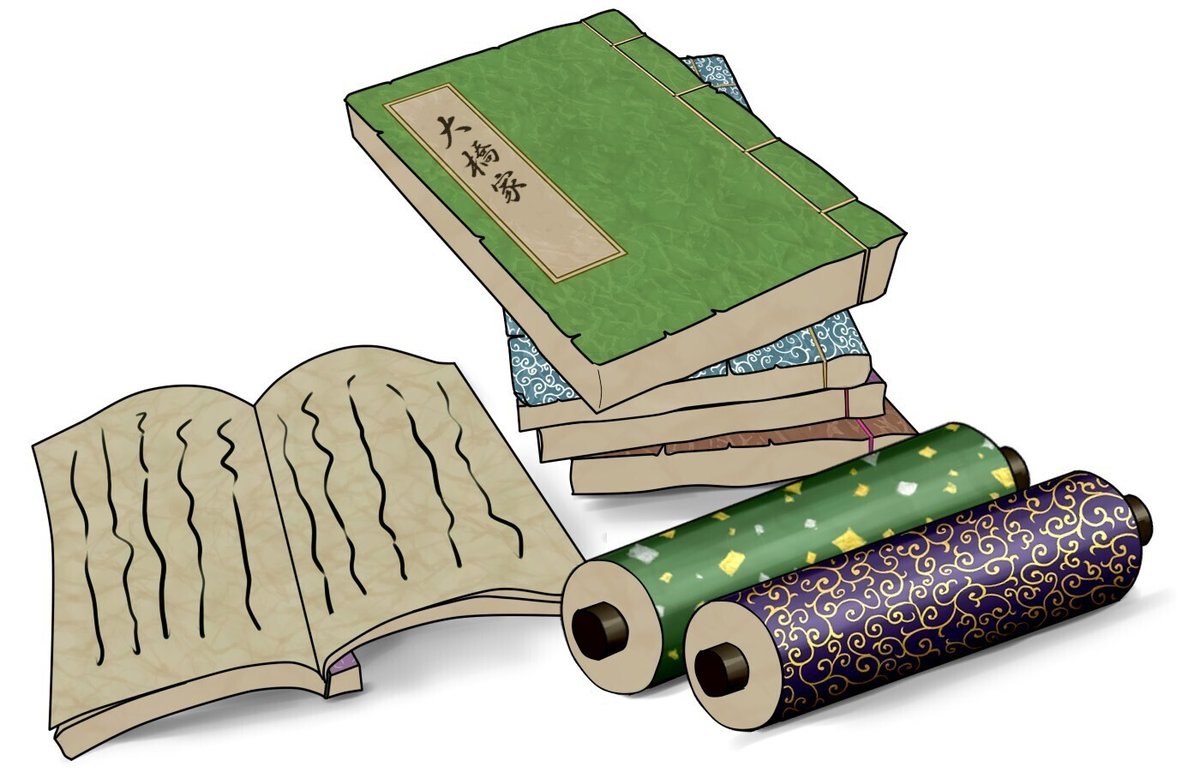
遊戯史研究家の増川宏一氏により、伝承や逸話ではなく、日記や書簡等、確かな史料に基づく史実としての囲碁史(のみでなく将棋史を含む盤上遊戯史)が見えてくるようになった。その中で「大橋家文書」というものがある。大橋家は将棋の家元で、記録を遺すことに熱心であった各代の当主たちが記した文書である。中でも熱心であった五代目当主三世大橋宗桂が記した延宝二年(一六七四)の覚書には御城碁・御城将棋に関するものがあり、碁家では算知、算哲、道悦の動きを中心に将棋家との御城碁・御城将棋をめぐるやりとりが記されている。
文書は関西将棋会館の収蔵庫より発見され、増川宏一氏が『碁打ち・将棋指しの江戸』(平凡社一九九八年)にて紹介している。
延宝二年の囲碁界の状況
御城碁・御城将棋をめぐるやりとりを紹介する前に、まずは延宝二年当時の囲碁界の状況を整理しておこう。
安井算知は五十八歳、本因坊道悦が三十九歳。この二人の争碁は前年の延宝元年までで二十番のうち十九番までが打たれている。最終局が打たれたのは翌延宝三年である。道悦が算知を打ち込んで十七番からは御城碁として年に一局のペースで打たれるようになっていた。この争碁に関しては前に述べている。また、延宝二年の八月は会津藩初代藩主保科正之を祀る神社の宝物の受納期である。
他の顔ぶれは次のとおりである。
〇安井算哲 三十六歳、安井知哲 三十三歳、安井春知 二十二歳
〇本因坊道策 三十歳、
〇林門入 三十五歳(算知の弟子)
〇井上因碩(道砂) 二十六歳(道策の弟)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

