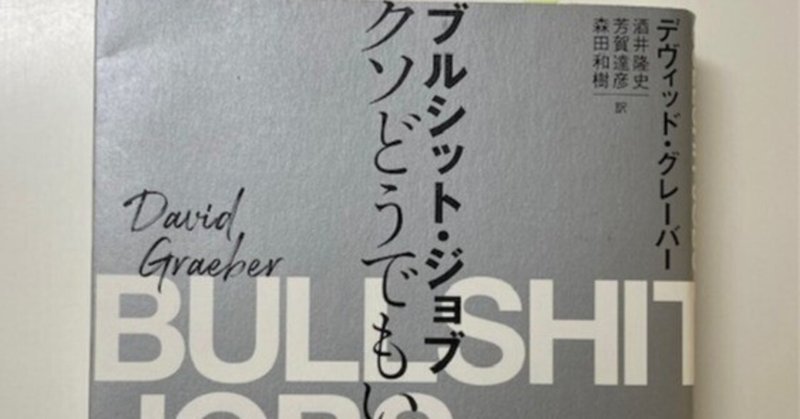
「働くひとの芸術祭」はじめます④-「虫の眼」「鳥の眼」「魚の眼」で世界を観る-
「人は『働く』『生きる』を自分の作品として価値生成できるのか」という問いを立てて書いた大学院の修士論文をかみ砕いてお伝えしている本連載。前回は、揺らいでいる「日本的雇用システム」の推移と、日本人の働くことやキャリアが直面する現在地について考察した。今回は、世界に眼を向けてみたい。
経済学者の視点
カウンセリングの世界では、3つの眼が必要だと言われる。第一に「虫の眼」。対応するクライアント一人ひとりをきちんと知ろうとする姿勢を指す。第二に「魚の眼」。時間的経過や文脈から考える視点を指す。そして第三に「鳥の眼」。俯瞰的に社会全体から見る視点を指す。働き方や生き方をめぐる視座も、かつてない変化が訪れる現在だからこそ、魚の眼と鳥の眼を持ちながら、変化に直面する一人ひとり(あるいは自分)を虫の眼で見る必要がある。
「行き過ぎた資本主義」という言葉を聞かない日は無い。18世紀半ばに興った産業革命によって生まれた資本主義は欧米を中心とする近代国家の「社会システム」となった。1917年のロシア革命によって世界初の社会主義国・ソビエト連邦が誕生する。欧米では、1980年代アメリカのレーガン大統領が主導する「レーガノミックス」やイギリスのサッチャー政権によって進められた「サッチャリズム」を中心とする市場原理主義の経済政策「新自由主義」が、1991年のソビエト連邦崩壊によって世界を席巻した。日本でもバブル崩壊以降、「失われた90年代」と呼ばれた経済低迷期を脱するために、2001年より小泉首相が推し進めた郵政民営化などの構造改革という形でこの新自由主義が急速に導入された。この新自由主義の世界的潮流によって、経済面での「グローバリゼーション」が生まれると共に、経済格差や地球温暖化が進展することとなった。
いま、世界は「人新世(Anthropocene)」と呼ばれる。これは人類が地球の地質や生態系に影響を与えた時代区分の呼称で、ノーベル賞科学者パウル・クルッチェン(Paul Jozef Crutzen,1933-2021)らが2000年に提唱した概念である。2020年に出版された、大阪市立大学准教授の斎藤幸平による『人新世の「資本論」』(2021年)では、人類の経済活動が地球に大きな危機をもたらす状況の中で、改めて資本主義を見直す意義が解き明かされ、大きな話題を呼んだ。同書は、資本とは「絶えず価値を増やしながら自己増殖する運動」であり資本主義とは「あらゆる物を『商品』にしようとするのが特徴」とするマルクスの理論を紹介しながら、一見、自己の意思によって仕事を選ぶ労働者に何か起こるのか?それは資本家によって都合のいいメンタリティを労働者が自ら内面化することで、資本の論理に取り込まれた結果、過労死が発生すると指摘している。
加えて、マルクスが最も問題視していたのは
資本(家)による支配が強力になるに伴って、構想と実行が分離され、人々の労働が無内容になって行くこと
であり、この構想と実行の分離を乗り越えて労働における自律性を取り戻すことこそが、彼(マルクス)が望んだことだと指摘している。その上で、マルクスを再解釈するいくつかの概念を紹介している。第一は「コモン」。これは、専門家に任せることなく、進取的・水平的に共同管理する富のことを指し、日本では経済学者の宇沢弘文が「社会的共通資本」で提唱した。第二は「アソシエーション」。これは労働者たちの自発的な相互扶助(アソシエーション)を指し、コモンによって実現された社会の在り方だ。こうした概念は、現在「ミュニシパリズム(Municipalism)」と呼ばれる地域自治主義の形態によってスペイン第二の都市バルセロナを中心として現実化している。これは、国家に対して地域において住民が直接参加して合理的な未来を検討する実践である。
文化人類学者の視点
文化人類学の立場から、グローバル規模で直面している働き方の実態に鋭く切り込んだのが、アメリカの人類学者デヴィッド・グレーバー(Davis Rolfe Graeber)だ。その著書『ブルシット・ジョブ-クソどうでもいい仕事の論理』(2020年)で以下のような問題提起をしている。
グレーバーは、現在の私たちの社会を「まるで何者かが、わたしたちすべてを働かせ続けるためだけに、無意味な仕事を世の中にでっちあげているかのようだ」とした上で、ブルシット・ジョブを
被雇用者本人でさえ、その存在を正当化しがたいほど、完璧に無意味で、不必要で、有害でもある有償の雇用の形態である
と定義してる。
その上で、グレーバーは以下のような問いを投げかける。わたしたちの社会では、はっきりと他者に寄与する仕事であればあるほど、対価がより少なくなるのはなぜか。どのようにして創造性(クリエイティビティ)とは苦痛を伴うものだと考えられるようになったのか。どのようにして人間の時間の売却が可能であるという考えが生まれたのか。自分を他者に貸し出すことを民主主義国の自由な市民が自明とみなすような状況がなぜ生まれたのか。1970年代以降、生産性は上昇し続ける一方、報酬は平行線をたどっているが、では生産性上昇から得られた利益はどこに行ったのか。生産性総体に重大な影響を与えることなく、わたしたちが従事する仕事の半分を無くすことができると言われるのに、なぜ残りの仕事を再分配してあらゆる人が一日4時間の労働ですむようにできないのか。あるいは、せめてもっとのんびり過ごせるようにならないのか。最後は、エデンの園の神話が生まれて以来、分裂して来た仕事そのものについての問いである。すなわち、仕事は「罰」であり、誰もすすんでやりたがらないものなのか、あるいは仕事は仕事それ自体を超えた何ごとかを達成するためにおこなっているものなのか。
また、グレーバーは執筆にあたり収集した証言のほとんどで「意味のある(meaningful)」という言葉は「役に立つ(helpful)」ということと同義であり、「価値のある(valuable)」という言葉は「有益な(beneficial)」という言葉と同義であった、と述べている。
同時に、ほとんどの証言がやりがいのあるものとしてあげるのが創造的な活動であり、芸術、音楽、文章、詩の追求に多数のひとが注いでいる粘り強い努力は、かれらの「現実の」支払い(payed work)の無意味さに対する「解毒剤」として作用していると述べている。
源流(アーツ・アンド・クラフツ運動と宮沢賢治)
次いで、「魚の眼」として、19世紀後半に興った「芸術運動によって労働の価値を見直そうとした試み」について考察してみよう。18世紀後半に発生した産業革命によって工業化が飛躍的に進展し大量生産された製品が市場に流通する一方、中世以来受け継がれて来た造形の製品生産システムや職人の社会的地位に大きな影響を及ぼすに至った。こうした問題意識から興ったのが、ウィリアム・モリス(William Morris,1834-1896)が中心となって取り組んだアーツ・アンド・クラフツ運動である。モリスの邸宅に集まった芸術家仲間から会社設立の動きが出て、モリス・マーシャル・フォークナー商会(その後、モリス単独経営となった)が設立され、その製品が1862年のロンドン万国博覧会に出品され評判を呼び、1888年にはアーツ・アンド・クラフツ展示協会が成立した。その後、運動はフランスやドイツに伝播し近代デザイン誕生の礎となった。
その理念は、モリスの母校オックスフォードでの講演(芸術と民主主義)における
芸術は労働における人間の喜びの表現である(Art is man`s experience of his joy in labor)
という言葉に象徴される。それは、労働者の解放を生活に芸術を取り戻すことと考え労働や生活の美しさを目指す「芸術社会主義」「ユートピア社会主義」あるいは「共同体社会主義」と称される。その思想は、日本における民藝運動にも多大なる影響を与えた。柳宗悦が民藝運動の思想をまとめた『民藝とは何か』(1941年)の以下の言葉から、その影響を知ることができる。
商業主義は競争の結果、誤った機械主義と結合します。ここに創造の自由は失われ、すべてが機械的同質に落ちてゆきます
単なる労働の苦痛から何の美が現れましょうや
マルクス=エンゲルス研究の全貌を解明するプロジェクト「MEGA」では、労働者たち自身が自由に発案や挑戦ができる「アソシエーション(自発的な結社)」を構想していたことが明らかにされているが、これを具体的な行動にしたのが、モリスが取り組んだ芸術家やデザイナーによるギルドだった。民藝運動と共に、このモリスの運動に影響を受けた宮沢賢治(1896-1933)は『農民芸術概論綱要』(1926年)でこう述べている。
誰人もみな芸術家たる感受をなせ。個性の優れる方面において各々止むなき表現をなせ
なぜ「アートの力」が必要なのか
なぜ「鳥の眼」「魚の眼」で考える必要があるのか。日本のキャリア教育の柱となっている考え方は「Must-Will-Can」と表現される。会社の命じることに自分の意志も能力も合わせることが大前提という意味だ。しかし、そのMust(=経営戦略)は環境の変動によっていとも簡単に変更を余儀なくされる。企業同様に一人ひとりの働き手も、環境を俯瞰する視点や歴史の推移を辿る文脈的な視点が求められて行く。私自身も、かつては会社やクライアントのために働くことがすべての「24時間働く」サラリーマンだった。しかし、会社が急速にグローバル化し、それまで当たり前だと思っていた制度が180度転換するという「青天の霹靂(へきれき)」を体験して初めて「キャリア」という言葉を認識した。
現在、再び「キャリア自律」ブームが訪れている。「自分のキャリアや人生を自分でつくる」ことは当たり前のことだが、それが「自己責任論」のように扱われてしまうことは危険だ。「無敵の人」という言葉がある。「社会的に失うものが何もないために犯罪を起こすことに何の躊躇ものない人」という意味であり、2008年に「2ちゃんねる」を開設した西村博之(1976-)が使い始めたとされる。21世紀に入って以来、こうした「無敵の人」によって多くの痛ましい事件が発生している。その背景には、自己責任という言葉のもとに弱者を救うセーフティーネットを撤廃して来たシステム的な要因がある。「自分のキャリアを自分でつくる」ことを支援する伴走者や関係づくりの仕組みをつくらないままに個人にキャリア形成や働き方を丸投げすることは、さらに多くの「無敵の人」を生むリスクを内包する。
だからこそ、一人ひとりにますます求められるのは「倫理観」である。どのような状況、時代や文化的な背景があっても「人としての在り方」に自覚的であることが必要となる。
アートは「Why」を自らに問い直す力を持つ
それは、人間性を回帰させ「自分の働き方や生き方を自分でつくる」ことと共に「自分ひとりでは働き方や生き方をつくることはできない」ということを思い出させる。次回は一見、二項対立するかのようなこの2つの命題についてアートがどのような価値生成を行っているのかを考察して行く。
第1回 「働くひとの芸術祭」はじめます①(旅のおわり、旅のはじまり)|sakai_creativejourney|note
第2回 「働くひとの芸術祭」はじめます②(妄想と当事者研究)|sakai_creativejourney|note
第3回 「働くひとの芸術祭」はじめます③(あなたには「創造性」がありますか?)|sakai_creativejourney|note
#キャリア #アート #働き方 #ブルシット・ジョブ #人新世
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
