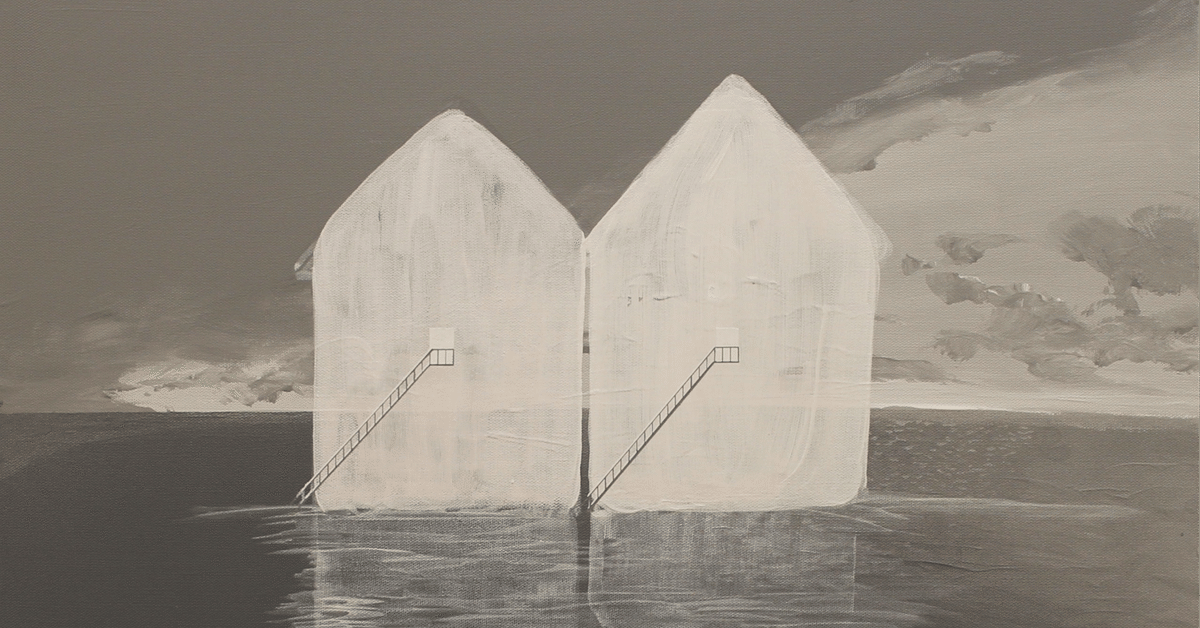
1.バイバイ・バッドマン
♥
「いいんだ」と僕は言った。
「でも、君の友達はそれを望んでないよ」
僕は手をこすり合わせた。UFOはまだ、遥か上空にいたが、その目に見えない熱は僕の全身の骨を内側から確実に痛めつけていた。
「もう、疲れてしまったんだ。多分、年を取りすぎたちゃったんだね」
「でも、君は随分上手くやってるよ。みんな褒めてる」
「ねえ、一つ聞いていい?」
「いいよ」
「君は今まで一体どこにいたの?」
「・・・私はいつも、どこかであなたのことを考えていた」
遠くの方から猛スピードでこちらに向かうモーターボートの音が聴こえていた。僕は体を起こして座り込み、ポケットから拳銃を取り出した。何もかもがスローモーションで過ぎ去っていくようだった。
「遠足の帰り道のことを憶えている?」と彼女は言った。
「私たちは久し振りに同じクラスになって隣の席に座った。外はオレンジ色の太陽の光に照らされて、松並木の切れ目からは、煌めく海が見えていた」
「うん」
「あなたはリュックサックの後ろのポケットからイヤホンを出して、私たちは一つずつそれを耳にあてた」
「憶えてるよ」
「あの時、聴いた曲を憶えている?」
「もちろん」
その時のことを思い出してと彼女は耳元で囁いた。
「忘れないで。本当のことはそこにあるの」
辺りに乾いた銃声が一つ響いた。僕は物のように倒れ、視界が一瞬で真っ赤に染まった。でも、それが誰の血なのか僕にはわからなかった。
0
それは明るい昼の光が差し込む浴室の窓から顔だけを出して言った
私は無視し、日常の決まりごとを果たした
つまり、顔を洗い、髭を剃り、タオルで拭き、清潔な服を身につけた
1
朝起きると部屋は死体安置所のように冷え切っていた。昨日クーラーを入れっぱなしで寝たせいだ。僕はまとわりつく掛け布団を体から剥ぎ取るようにして、部屋のカーテンも開けずに階下に降りた。
1階は陽の光でいっぱいだった。眩しいくらいに。僕はキッチンに入り、冷蔵庫を開けて牛乳を取り出し口をつけてがぶ飲みをした。時計を見ると、もう午後2時だった。12時間ちかく寝ていたことになる。
空になった牛乳パックをゴミ箱に捨て、クーラーをつけた。水をコップに入れ、テーブルの前に座る。今日はアルバイトもないし、数少ない友達との約束もない。僕は階段下の電話機をぼんやりと眺めた。何人かの顔が目の前に浮かんでは消えていった。特に電話をかけてみる気にはなれなかった。今日は何にもなければ一人で過ごすことになりそうだった。
歯を磨いてからシャワーを浴びた。ふかふかのバスタオルで体を拭いて、あらかじめ用意してあった紺色のショートパンツと、白地のウィンドペンの半袖のシャツに着替える。服からは古い洗剤の匂いがした。そのまま脱衣所の鏡の前に立ち、ポマードで髪を整えてから浴室を出た。
キッチンでまた水を一杯飲み、居間のソファーに深く座り込んで、爪を切った。外の光は最盛をすぎて、少し優しくなっている気がする。カーテン越しに庭の木がもったりと揺れているのが見えた。実際には蒸し暑いのかも知れないが、冷たく乾いた室内から見ると、それは午睡を誘うそよ風のように見える。僕はソファから立ち上がり、爪を綺麗にかたずけた。
⭐︎
水色のリトルカブを走らせながら、どこに行こうかと考えた。のんびりと海に行ってもいいし、横浜や東京に行ってもいいなとも思う。
考えがまとまらないまま走っていると、なんとなく駅前まで来てしまったので、バイクを停めてブラブラと歩くことにした。
本屋で立ち読みをし、雑貨屋で買う予定のないものを物色したりしていると、おなかが減ってきたので蕎麦屋に入った。たまに行く蕎麦屋だけど、味の良い割にいつもあまり人が入っていないのが気に入っている。その日も空いていたので、人が側にいないテーブル席に座った。すぐに注文を取りに来た女性に冷やしたぬき蕎麦と生ビールを注文し、待った。
先に来たビールを飲みながらカウンター上のテレビを見るともなく見ていると、男のテレビリポーターが噴水で遊ぶ子供達を背景に東京が36度越えの猛暑日であることを伝えていた。へえ、そんなもんかなと僕は思った。
この街は海風が通るから、割と涼しいのかもしれない。
勘定を終えて外に出ると、急に蝉の声が耳についた。緑の木々は強い日差しを受けてさらに輝き、全てが夏めいて見えた。大きく息を吸うと海の匂いがした。目を閉じて耳をすますと遠く波音が聞こえてきそうだった。軽い酔いが頭の中を万遍なく水びたしにしているような感覚があった。気持ちがいい。電車に乗ってどこか、知らない街に行ってみようと思った。
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
