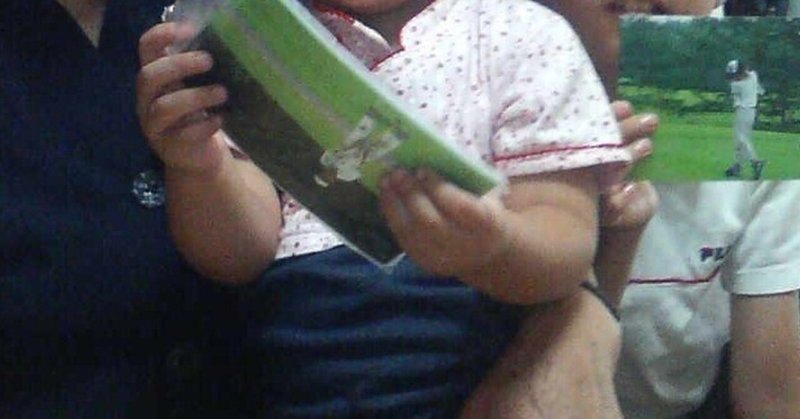
2013年の作文・8月
2013.8.1
今朝、娘たちが、従姉妹と一緒に新幹線に乗って、軽井沢へ向かった。小学生3人だけの旅である。軽井沢駅では、ぼくの両親が迎えに来て、別荘へ。避暑地で、御祖父様、御祖母様と一緒に過ごせる娘たちは幸せだと思う。ぼくも学生の頃、夏は毎年のように軽井沢へ行っていた。ピアノを弾いたり、詩を読んだり、森を散歩したり、テニスをしたり、今から思えばずいぶん優雅な暮らしをしていたのだ。その頃から、有島武郎、室生犀星、堀辰雄、立原道造などの軽井沢ゆかりの文学者たちに興味を持つようになっていた。あの避暑地の香りは独特で、木立から立ち込める水気を含んだ冷たい空気を胸いっぱい吸い込むと、とても癒される。きょうは、軽井沢を舞台にした曲を聴こう。
◇レモネードの夏 松本隆◇
冷えたレモネード
白いカフェーから
揺れる木洩れ陽を見たの
あとあなたに逢えれば
もうひと足早い夏
樹にもたれた貸自転車
コテージから光を縫って来た
想い出には縛られない
もう恋などする気も無い私
少し淋しげな深い青空が
肩に降り注ぐ避暑地
あとあなたに逢えれば
もうひと足早い夏
今は私も二十歳
自由に生きる事を憶えながら
一人で生きてる
時が消した胸の痛み
忘れるのに一年かかったわ
逢いたいのは未練じゃなく
サヨナラって涼しく言うためよ
冷えたレモネード
薄いスライスを
噛めばせつなさが走る
あとあなたに逢えれば
もうひと足早い夏
揺れる木洩れ陽を見たの
あとあなたに逢えれば
もうひと足早い夏
曲はユーミン、歌は松田聖子。考えたら凄いメンバーだ。聖子ちゃんに失恋の歌を明るく歌わせたら天下一品である。実に爽快な曲である。そして歌詞はいじらしい。
2013.8.2
◆軽井沢幻想曲第1番 2013.8.2◆
第1楽章
白い日傘の下
マドモアゼルの微笑
ゆっくりとすれちがう自転車
ポエジイの欲情
店先に並ぶ御面
1 仮面ライダー
2 ウルトラマン
3 アッコちゃん
4 マグマ大使
5 ひょっとこ
6 おかめ
7 見た事のない妖怪
ラケットがボールを弾く
子どもが口の中に指を入れて同じ音を出す
唇を歯と歯の間に挟んで一気に離すだけでもよい
振り向いたマドモアゼル
視線が欲情と交差する
虫の声
蝉(セミ)か
飛蝗(バッタ)か
蝗(イナゴ)か
蜻蛉(トンボ)か
虫の影
蜂(ハチ)か
蜥蜴(トカゲ)か
蟻(アリ)か
蜘蛛(クモ)か
風が忍び寄る
ドレスがなびく
レースもなびく
窓辺に運ぶ
野薔薇の香り
真夏
高原の
高原での夏
シューズの紐を結ぶ
顔をあげる
君がいる
美しい夕暮れ
「軽井沢」をモチーフにした連作を試みたくなったので、書いてみた。第2楽章以降も気まぐれに作るつもり。夏は汗をかきながらもせっせと読書をしなくてはならない。きょう図書館で借りた本:小島政二郎『長篇小説 芥川龍之介』講談社文芸文庫。これで三回目。何回読んでも面白いし、エピソードがぎゅっと詰まっているので、読み落としている箇所がたくさんある。
《軽井沢の旧道に、「つるや」と云う軽井沢と共に古い宿屋がある。古風な大きな入口の右側に、別荘風な洒落れた門とも云えない門があって、そこを入ると、右側に二タ間ぐらいの離れがあった。一ト夏そこを借りて二人で共同生活をしたのだ。》(154頁より)
二人とは、芥川龍之介と室生犀星である。
《「ホテルへ行くとね、室生は出来るだけ西洋人の近くのテーブルに坐りたがるのだ。会話が分る訳ではないが、感覚で西洋人を理解しようとしているのだね」/そんなことも聞かされた。/「僕達と違って、室生は羨むべき勤勉家だよ。朝は早起きだし、起きるとすぐ原稿を書く。午前中に必ずと云ってもいゝくらい十二枚ずつ書く」/「僕達は昼間遊んでいて、夜、疲れた体で原稿を書くのに、室生は午前中の、最も状態のいゝ時に仕事をして、夕方には晩酌を楽しんで寝るのだ。実に合理的だし、健康的だ」》(154頁より)
こんな風に芥川龍之介の証言を小島政二郎は紹介している。ちなみに、小島正二郎は、1894年の1月31日、古賀釥太郎・志満の次男として東京市下谷区に生まれている。もともとは古賀さんで、どこかでぼくとも繋がっているかもしれない。100歳まで生きた作家である。この本は、もともと1977年11月に読売新聞社から刊行されている。小島さんが83歳の時の作品だ。どうりで面白いわけである。
2013.8.3
大学生だった頃の話だが、ぼくは親友のAを誘って夏休みのあいだ軽井沢へ行く計画を立てた。Aは、男二人ではつまらないので、女子を誘ってみないかと提案してきた。Aには意中の女性がいるということをぼくは知っていたので、「Kちゃんはどうかな」とその名をわざと出してみた。もちろん、Aは小躍りして喜んだ。そのことをKに話してみると彼女はぼくの計画に快く賛同してくれた。それにYというぼくのお気に入りの友だちを入れて、男3人女1人の計4人、ぼくらは東京駅から電車に乗って楽しい旅が始まった。
軽井沢にはぼくの家の別荘がある。駅からはだいぶ離れているが、街を抜け、ゆるやかな山道に入ると自然を満喫できるので、道中はまったく退屈しない。別荘に到着すると、ぼくは早速夕飯の準備に取りかかる。3人は、物珍しそうに部屋のあちらこちらを覗いてまわり、バルコニーに出て、外の景色を眺めたり、缶ビールを片手にくつろいだりしている。夕飯のカレーライスを食べ終わると、いつものように他愛も無い会話がはじまる。ぼくは、時間を見計らって、ピアノを弾き出す。ショパンの練習曲やサティの曲などがお気に入りだが、即興で現在の気持ちを表現したくなるのが常で、武満徹風な曲を弾いて一人で悦に入る。そのあいだ3人はそんなぼくにお構いなくトランプに興じている。Aはとても満足そうだ。そして笑い話に拍車をかけて、懸命にKを喜ばせようとする。そんな時、Yの役割がほどよいクッションになっていて、AとKが面と向かって深刻にならずに済んでいる。もしもAがKと二人きりなら、緊張のあまり、いつもの調子が崩れ、冗談ひとつも言えなくなってしまう。ぼくはマイペースに時を過ごす。そうしながらも、AとKがより親密になることを願っている。夜空がきれいだ。東京では味わえない。みんなで散歩に出かける。Aはわざと怖い話をする。そしてスリラーの踊りをしてみせて、みんなを笑わせる。ぼくらは逃げる。Aはゾンビのまま追いかけてくる。Kがぼくの身体にしがみつく。その時、ぼくはシマッタと思う。ぼくはAを見る。Aは笑っているが、ぼくには分ってしまう、心が曇っていることが。ぼくはYにしがみつく。それで精一杯。「流れ星!」とぼくは叫ぶ。場の空気を換えるために。次から次へと流星がきらめく。その夜は、Kだけベッドのある部屋で寝て、男3人は、畳に布団を敷いて寝る。話題は異性の話になる。あの子がいい、この子はダメだ、とKを棚にあげて話は盛り上がる。しかし、Aの話のニュアンスで、彼がKに気があることはぼくにもYにも分かる。こういう時、男は嘘がつけない。二日目が何事もなく過ぎてゆく。ただ食べて、飲んで、喋って、笑って。Kは女1人であることで気を遣わせないように自然に振る舞っている。ぼくも、Kをなるべく異性として見ない振りをする。カラオケが始まる。Aはへたくそな歌を大声で歌う。Yは流行の歌をぶなんに歌う。Kはデュエット曲を選ぶ。そしてぼくにマイクをわたす。「銀座の恋の物語」。Kの視線がぼくに向けられる。ぼくは歌に夢中である振りをする。Kは酔った振りをする。ぼくの肩にもたれかかってくる。アブナイ。Aがこれに気づいたらたいへんだと思う。さりげなくかわす。散々歌って暴れて、みんな満足そうに床につく。ぼくは不安を抱える。Aの恋を邪魔しているもの、それはぼくなのではないかと。こんな皮肉なことがあるだろうか。
女を挟んだ男と男の関係。友情と恋愛の相克。そのような兆しがちょっぴり感じられた一夏の旅。想い出の中の小さな旅。
2013.8.4
軽井沢シリーズは続く。きょうは、堀辰雄の文章をじっくり読もう。ぼくの手元にあるテキストは筑摩書房から出ている『堀辰雄全集 第一巻』だ。そのなかの「美しい村」から、いまぼくがいちばん感じるところを引用したい。
《私はなんだか急に考へごとでもし出したかのやうに黙り込んだ。私たちはその橡の林を通り抜けて、いつか小さな美しい流れに沿ひ出してゐた。しかし私はいま自分の感じてゐることが何処まで真実であるのか、そんなことはみんな根も葉もないことなんぢやないかと疑つたりしながら、気むづかしさうに沈黙したまま、自分の足許ばかり見て歩いてゐた。さうして私は、そんな自分の疑ひに対するはつきりした答へを恐れるかのやうに、いつまでも彼女の方を見ようとはしないでゐた。がとうとう私は我慢し切れなくなつてそんな沈黙の中からそつと彼女の横顔を見上げた。そして私は思つたよりももつと彼女がその沈黙に苦しんでゐるらしいのを見抜いた。》(全集384頁~385頁より)
軽井沢で、主人公の「私」がある少女と出会い、いつしか彼女と一緒に散歩するまでになった。そして、絵を描くのが好きな彼女には他に若い画家の知り合いがいて、「私」と彼女がふたりで歩いている時にすれちがい、彼女と画家は会釈をかわす。そこで「私」は、その画家と彼女の間柄に嫉妬を覚える。このような微妙な距離にいるときの三角関係ほど、人の心を乱すものはない。カブトムシのオス同士が一匹のメスをめぐって争うように、人間の場合も、心理的な火花を散らして、どっちが彼女の心を獲得するか、勝負しているわけだ。堀辰雄の筆は、そんなグロテスクな争いを、とてもしなやかに描いてみせる。このあとの場面が素晴らしい。クールな中にも熱い情感が湧き出ていて、読む者の胸を打つ。
《さういふ彼女の打ち萎れたやうな様子は私には溜まらないほどいぢらしく見えた。突然、後悔のやうなもので私の胸は一ぱいになつた。》(385頁より)
恋に落ちた瞬間の描写である。
《……私がほとんど夢中で彼女の腕をつかまへたのは、そんなこんがらがつた気持の中でだつた。彼女はちよつと私に抵抗しかけたが、とうとうその腕のなかに切なさうに任せた。……それから数分経つてから初めて、私はやつと自分の腕の中に彼女がゐることに気がついたやうに、何んともかんとも言へない歓ばしさを感じ出した。》(同頁より)
まだ恋人になったと決まったわけではない相手の身体に触れることがどれほど勇気のいることか。この瞬間は息を呑む。緊張が走る。そして弾みが必要で、それがしばしば嫉妬の炎である場合がある。堀辰雄は、軽井沢の自然の細かい描写のあいだに、このような心理描写を挟み込んで、男女の心の機微を美しく、詩的に描いてみせる。
2013.8.5
小説家は、ぼくらをどこへ連れて行こうとしているのだろう? ふとそんな疑問が湧いてきた。積み木細工のように、またはジグソーパズルのように、一つ一つの文を丹念に紡いでいくという気の遠くなるような作業を彼らは選ぶ。それに比べ、詩は、ドミノ倒しのような遊戯に似ている。カタカタと倒れていったドミノが最終的に何か美しい模様を描く。同様に、詩は読む前と後では風景が一変しているのだ。そのような最終的な模様が想定できているからこそ、詩人は言葉を省略し、表現を削除しながら、効果的なフレーズの配置を極めていこうとする。また、つくり方の観点で言えば、小説は、油絵のように、何度も色を上塗りしていける。それに対して、詩は、一つの石から美しいビーナスを削り出す彫刻のように、余計なものをあやまたずに落としていかなくてはならない。ぼくは、堀辰雄の小説を読んでいて、実は、彼の作品にはこの二つの性質が同時に存在しているような気がした。積み木細工のように、一文一文積み上げているかと思うと、突然それがドミノ倒しのようにカタカタと音を立てて倒れ、読後には風景が一変している。小説と詩のあいだ。そこに、堀辰雄文学が目指したゴールがあったのではないか。否、優れた文学作品は、みな同様で、結果的にはそのような効果を有しているのかも知れない。堀辰雄が、詩誌『四季』を創刊し、多くの詩人に作品発表の場を与え、リルケやアポリネールやヴァレリーなどの作品を翻訳して紹介してきたことは、その証左であると思う。もう一度、小説と詩の定義を示そう。小説はパズルであり、詩はドミノである。
2013.8.6
原爆のことを考える時、ぼくは沖縄出身の詩人、山之口貘さんのことを思います。沖縄はアメリカとの戦争でいちばん犠牲の多かった場所であり、戦後も変わらず苦しみ続けている。きょうのニュースのなかにも米軍のヘリが墜落した事故のことが問題になっている。広島原爆の日に、やっぱり貘さんの言葉を読みたい。
◇鮪に鰯 山之口貘◇
鮪の刺身を食ひたくなつたと
人間みたいなことを女房が云つた
云はれてみるとついぼくも人間めいて
鮪の刺身を夢みかけるのだが
死んでよければ勝手に食へと
ぼくは腹立ちまぎれに云つたのだ
女房はぷいと横にむいてしまつたのだが
亭主も女房も互に鮪なのであつて
地球の上はみんな鮪なのだ
鮪は原爆を憎み水爆にはまた脅やかされて
腹立ちまぎれに現代を生きてゐるのだ
ある日ぼくは食膳をのぞいて
ビキニの灰をかぶつてゐると云つた
女房は箸を逆さに持ちかへると
焦げた鰯のその頭をこづいて
火鉢の灰だとつぶやいたのだ
貘さんは、一篇の詩を作るのに原稿用紙を100枚も200枚も使って何度も推敲する詩人だ。出来上がった詩をみて、簡単に作られていると思ってはいけない。ひとつひとつ、熟慮と心血を注いで選ばれた言葉たちだ。技巧の詩人ではないし、奇想の詩人でもないし、純情な詩人でもない。詩人の魂だけをもって、詩に取り組んだ本物の詩人はほんの一握りしかいないだろう。貘さんは、間違いなく、その一人である。代表的日本詩人の五本の指に入る。この「鮪に鰯」に高田渡さんが曲をつけて歌っている。
2013.8.7
とても複雑な心境である。ぼくはなぜ今のような生き方を選んだのか。これはぼくが人間だからなのか、それとも男だからなのか、それとも日本人だからなのか、それとも東京生まれの東京育ちだからなのか、それとも長男だからなのか、それとも転校生だからなのか、それとも80年代バブルの時代に思春期を過ごしたからなのか、それとも短気で、せっかちで、大ざっぱで、無責任で、身勝手で、横柄で、頑固で、意地悪で、根性なしで、天邪鬼だからなのか、それとも人間が嫌いだからなのか……。ああ、そうだ、ぼくは人間が嫌いだったのだ。人間が怖い。人間が苦手。人間が恐ろしい。人間が、人間が、ああ、人間が近づいてくるぞ。こういう文章を書いているあいだ、ぼくはぼくだけが安心で、ぼくだけが好きで、ぼくだけが正しく、ぼくだけが清く、ぼくだけが重要で、ぼくだけが真実なのだと考えている、にちがいない。書くことが自己正当化の唯一の手段だ。セルジュ・ゲンスブールの歌声が流れている部屋で、一人キーボードを叩いているカタカタカタ。詩人になりたいと思って詩を書いてきた。詩を書いている時だけぼくの本性が前面化する。それ以外のことはぜんぶ煩わしい。ああ、煩わしい。友人Kは自由を手に入れている。彼は全ての煩わしさから解き放たれている。ぼくはKになりたい。Kは孤独で、淋しい。でも幸せだ。好きな時間に起きて、好きなものを、好きなだけ食べて、好きな番組を好きな時に合わせ、言いたいことを言いたい時に云う。だから、ぼくはKにじぶんを投影する。Kが生きていることは、もうひとつのぼくが別の世界で生きていることと同じだ。Kはある時、野獣になった。本能のままに生きようと思った。Kはアプローチをかけた。壮大なアプローチを。13年ごとに地上に出現しては、泣き叫ぶ蝉がいる。「13年蝉」で検索すればわかる。この13という素数にぼくは重要な意味を見る。ぼくも13年ごとに鳴きたい。今年は2013年。ミレニアムから13年。何かが起こる。何かを起そう。Kが動いた。ぼくも動いた。Kがアタック。ぼくもアタック。果たして、どうなるのか。これからどうなるのか。文学が待っている。ぼくの未来は、文学の地平線の向うにある。(Kを主人公にした小説を書きたいと思っている。これはそのプロローグに使う文章の原案だ。)
2013.8.8
8と8が会う。はちあわせ。8×8は64。むしだ。虫だ。8は蜂でもある。だから蜂×蜂=虫。いったい何のことだ? と思うだろう。実はぼくにもよく分からない。夏の暑さの所為である、と言えばいいのか。脳みそに歯止めが利かない。たらたらと流れ出す思考と言葉。シュルレアリスムです、なんて云う言い訳が通用するか? しないだろう。ぼくは動揺している。しょうがない。ショーもない。ショーもチョーもチューもキューもない。ない、ない、ない。とりあえず、ぼくは真夏の虫になりにけり。
2013.8.9
親友のKくんが教えてくれた。きのうは昭和が88年だったので、88年8月8日だったのだと。そういう言い方も許されるなら、百年に一度の8月8日だったことになるか。昭和生まれのぼくにとってはそれも意味あることかもしれない。転機になればいい。じぶんでそう決めて、これからの余生を、満足のいく人生に仕上げていくために。原発ゼロも大事だが、原子爆弾ゼロ、水素爆弾ゼロ、すべての破壊兵器ゼロを目指して、ぼくらは歩みを再開しなくてはならない。12年後の昭和100年がひとつの目安になるだろうか。生活を着実に固めながら、地域社会に貢献できる一日一日を。じぶんの周囲の人に少しでも勇気を。じぶん発で出来ることをしたいのだ。仕事で失敗したり、家庭でいざこざがあったり、人間的な現象は相変わらず続いている。でも、ぼくは、最後はやっぱり詩人でありたい。だから、すべての現象を広い心で受け止めて、それを明滅させながら確実にともり続ける因果交流電燈として生きる。
うつつを ぬかす
うつつが ぬかす
うつつも ぬかす
うつつで ぬかす
うつつは ぬかす
うつつの ぬかす
うつつに ぬかす
うつつつ つつつ
つつつつ つつつ
うつうつ うつつ
うつつよ うつつ
うつつめ つつつ
うつつへ つづく
2013.8.10
げりりになりり、くるるし、くるるしい。夏の食あたりか、冷たいものを食べ過ぎたか、クーラーにあたり過ぎたか、夏の疲れがここに来て出てきたか、とにかく体調を崩したのは、じぶんの油断である。げりりをだししつくくして、はやくふとんにもぐりこもう。
2013.8.11
これから軽井沢へ向かいます。堀辰雄さんに会えるかな。室生犀星さんに会えるかな。立原道造さんに会えるかな。風立ちぬ。いざ関越自動車道。
2013.8.12
軽井沢の朝の涼しさ。一年分の熟睡をさせてもらった気分である。小鳥のさえずりで目が覚めた。森の空気。木々のざわめき。闇の深さに誘われて、ぼくは時間を忘れた。眠りは生きる力を蘇生させる。一日中、何も考えずに、呼吸することだけを楽しんだ。
2013.8.13
この夏、ぼくの周辺で不思議なことがよく起こる。きょうの午後は喫茶店であたたかい紅茶をすすりながら、富士川英郎『詩の雙生兒 朔太郎と犀星』小澤書店、を読んでいた。萩原朔太郎と室生犀星が仲のよい詩友であると共に良きライバルであったことを、それぞれの詩集の出自を語りながら、明らかにしていく素晴らしい論考だ。彼らの処女詩集『月に吠える』と『愛の詩集』が共にドストエフスキー体験に基づいて作られたという話や、ふたりの間に存在する北原白秋、芥川龍之介、佐藤惣之助などの文学者たちの証言によって同時代の人々がふたりをどう評価したのかが語られていく。うんうん、なるほど。読み進めては紅茶をすする。すると、突如、ぼくの目の前にひらひらと一匹の蝶が舞っているではないか。よりによってぼくの周囲を旋回している。他のお客がその様子を遠目でみながらコソコソ話をしている。ぼくは気にしない振りをして、活字に目を落とす。蝶は必死にぼくの気を引こうとひらひらと羽ばたく。紅茶に鱗粉が入るかもしれないと心配しながらも、ぼくは本を読む。断じて読む。これで二度目だ。喫茶店と蝶のエピソード。蝶がぼくを監視しているみたいで怖い。
夢をみながら わたしは幼な兒のやうに泣いてゐた。
たよりのない幼な兒の魂が
空家の庭に生える草むらの中で しめつぽいひきがへるのやうに泣いてゐた。
もつともせつない幼な兒の感情が
とほい水邊のうすらあかりを戀するやうに思はれた
ながいながい時間のあひだ わたしは夢をみて泣いてゐたやうだ。
あたらしい座敷のなかで 蝶が翼をひろげてゐる
白い あつぼつたい 紙のやうな翼をふるはしてゐる。
(富士川英郎『詩の雙生兒 朔太郎と犀星』108頁に引用されている萩原朔太郎の作品「蝶を夢む」の一部)
2013.8.14
今夜は、親友のKくんと六本木に出る。Kくんが予約してくれた高級レストランでイタリア料理を賞味するのだ。その前に、胃腸の調子を整えておかなくてはならないので、少し運動しよう。便秘ぎみなので、整腸剤も飲んでおこう。Kくんはぼくより5歳年下の独身。政治、経済、宗教、マスコミ、芸能、演劇、アート、哲学、どんな話もできる。話し相手としてはいちばん意気投合できる素晴らしい友達だ。六本木には、高校時代の親友Kくんが内装をデザインしたお店もある。こっちのKくんは同い年で、一級建築士である。今は世界中を飛び回って立派な仕事をしているので、どんどん雲の上に行ってしまう。でも、ぼくにとって永遠にKくんはKくんだ。ところできょうの議題は「恋愛革命」だ。Kくんのドラマチックな大恋愛について語り合うことになるだろう。ぼくはいつかKくんの小説を書かなくてはならない。つまり、小説の作者と主人公がレストランで食事をしながら、物語の構想を練るというわけだ。
2013.8.15
Kくんとの六本木での会談はおおむね次のような内容だった。大きな失恋を二度経過した結果、Kくんが辿り着いた境地は、先鋭化された耽美主義であった。とにかく、今後は「絶世の美女」以外は受けつけない。三次元よりも二次元の方がはるかに美しい。現実には美人は存在しない。そういう意味では、完全に差別主義者になってしまった。恋愛原理主義と云ってもよい。このような例外的な人物を主人公にして、その世界観を描くのはとてもエキサイティングなことだ。ぼくも知らず知らずのうちに彼の影響を受けて自分が差別的な発言をしていることに気がつく。恋愛に関してはヒューマニストではいられないのか。これも永遠の矛盾だ。口が悪くなる。毒舌が心地良い。人間は実に愚かだ。ふたりの会話を聞いていたギャルソンたちはどう思っただろう。女性をけちょんけちょんに貶す。じぶんを棚に上げて。何様だ? しかし止まらない。次から次へと、女性の醜態について批判、批評、非難。日頃の欲求不満が炸裂している。終戦記念日に、高級レストランで、フォアグラと牛肉、ビールにシャンパン、を口にしながら、よくもまあこれだけベラベラしゃべられるもんだ。じぶんでもあきれてしまう。食後は、麻布十番を散歩。13年前は、一緒にこの界隈で仕事をしていたことが思い返される。時が流れた。でも街はそこにあった。ぼくは妻子をもち、Kくんは独身だ。何のための人生か? 分からないまま共に生きている。
2013.8.16
息子の要望で、映画「ルーキーズ 卒業」のDVDを借りて、ふたりで観た。たまにはこういう真っすぐな青春映画もいい。俳優が、今をときめくイケメンばかり。友情出演も豪華なメンバー。日本人は、甲子園を目指す青春ドラマが大好きだ。夢をもって、それを目指すからドラマが生まれる。甲子園出場が一つのゴールであるというのは分かりやすい。14歳の長男は野球少年。夏休みもずっと野球の試合と練習がつづいた。今週だけゆっくりできるので、きょうは久しぶりに朝昼晩の食事を一緒にした。父と息子、ふたりきりの貴重な時間が流れている。
2013.8.17
フランス映画「天井桟敷の人びと」を観た。きのう「ルーキーズ 卒業」と一緒に借りたDVDだ。きょうはずっと家でひとりぼっちだったので、じっくり観た。ジャック・プレヴェールはやっぱり天才だ。素晴らしい筋書きだ。柏倉康夫『思い出しておくれ、幸せだった日々を 評伝ジャック・プレヴェール』左右社、には次のように書かれている。
《1943年8月16日、南仏ニースのラ・ヴィクトリーヌ撮影所で、プレヴェールの脚本、マルセル・カルネ監督の映画の撮影が開始された。製作はフレッド・オラン、撮影は名手ロジェ・ユベールをマルク・フォサールが補佐した。そしてこのときから映画のタイトルは、「フュナンビュル座」から「天井桟敷の人びと」へと変更された。》(381頁より)
奇しくも撮影開始から70年後の2013年8月16日に、ぼくはこの映画のDVDを借りたのだ。ぼくの人生はこの70年のなかにすっぽり納まっている。そして、映画「天井桟敷の人びと」の中にぼくの人生の謎を解くカギがあるのではないかとさえ感じる。「好いた同士にはパリも狭いわ、私たちみたいに深く愛し合っている二人には!」や「恋なんて簡単よ」など、映画のなかには名台詞がたくさんある。第一幕で恋に落ちた主人公のバティストとガランス。時を経た第二幕では、別々の家庭を持って生活している。そして、再会はひとつの悲劇をもたらす。ぼくの人生もどうやら第二幕に差し掛かっている。そう思ったら詩が書きたくなった。
◆あの時から「あの時」はずっと追憶だった 2013.8.17◆
ぼくが君に恋をしたのは
19の夏のこと
「遊びにおいでよ」
ぼくの誘いに君は快く応じてくれたんだ
S町にある小さな家の二階にぼくは下宿していた
将来のことは何も考えていなかった
気ままに
絵を描き
曲をつくり
詩を書いて
暮らしていた
ぼくは君と手をつないで散歩した
とっても幸せだったんだ
君はおぼえているだろうか
ぼくは大胆だったけれど
ほんとうは心臓が口から飛び出してしまいそうなくらい
ドキドキしていたんだ
君は手料理を持参してくれた
そしてこう言ったんだ
「ママにはお友達の家に泊まりに行ってくるってウソついてきちゃった……」
ぼくの幸福はピークに達していた
ひとりの少女がひとりの男子にすべてをゆだねる瞬間だった
ぼくは選び
そして選ばれたんだ
もう「あの時」以上のときめきは来ないだろう
君はおぼえているだろうか
そして
ぼくたちは「あの時」にいちばん近付いて
それからずっと離れて行ってしまった
なぜ?
ぼくには分からない
君にもきっと分からないだろう
でも
ぼくの胸のなかで
「あの時」
は
せつない
せつない
「あの時」
は
生き生きと
いつまでも
動きつづけているんだ
それは
あの時から
そして
もしかすると
それよりもずっと前から
追憶だったのかもしれない
2013.8.18
読書を続けていると、思わぬ箇所でハッとすることがある。柏倉康夫『思い出しておくれ、幸せだった日々を 評伝ジャック・プレヴェール』左右社から、引用する。
《デュアメルはすぐにホテル・リッツに駆けつけた。そしてドアマンに聞くと、たしかにヘミングウェイは泊まっているという。入り口の外で待っていると、一台のジープがやって来て、ヘミングウェイが降りてきた。デュアメルは勇気を出して、自分はプロの翻訳家で、ヘミングウェイの翻訳を出しているガリマール社を知っていると自己紹介した。ヘミングウェイは、鍵をボーイから受け取ると、デュアメルの方をじっと見ながら、「そう、ぼくの出版社を知っているって?」といい、返事を待たずに親しげに肩を叩くと、低く太い声で、「上に行って、一杯やろう」といった。/こうしてデュアメルは、報酬は年代もののシャンパーニュを飲ませてもらう条件で、ヘミングウェイの無給の通訳となり、毎朝九時にリッツの部屋を訪ねるようになった。やがてデュアメルは、ヘミングウェイにプレヴェールを引き合わせた。》(405頁~406頁より)
フランスがドイツの占領から解放される前後では、文字通り劇的な出会いがあったのだ。1944年の8月だ。解放後、様々な雑誌にプレヴェールの詩がいくつも掲載されてゆく。次の作品もそのうちの一つだ。
◇夜のパリ ジャック・プレヴェール(北川冬彦訳)◇
くら闇のなかで 一つ一つ擦られる三本のマッチ
最初のは おまえの顔をそっくり見るために
次のは おまえの眼を見るために
最後のは おまえの唇を見るために
そして真っくら闇が それらのすべてをわたしに想い描かせるために
おまえを抱き締めながら。
1945年の8月、戦後の日本で、「夜の東京」という詩が発表されたかどうかは知らないが、もし三本のマッチがあったら、同じように恋人たちはお互いに見つめあったのではないだろうか。そういえば、最近マッチを擦る機会が全くない。急にマッチが欲しくなった。
2013.8.19
過去のじぶんがぼくの首を絞めにやってくる。なんてことをしてくれたんだい? その時、ぼくは後悔している。反対に、今のぼくが過去のじぶんの頭を撫でる。えらい、えらい。その時、ぼくは幸福だ。1988年3月にぼくは高校を卒業した。春に父と一緒にアメリカのアトランタまで旅行した。帰国して、予備校に通った。S町にある祖母の家に下宿しながら、ぼくは浪人生活一年目をじぶんなりに生きた。あれから25年が経った。すごい話だ。建築家のKくんも同じ予備校に通っていた。ランチはいつも一緒。食後の煙草も一緒。あの頃は、煙草のない生活は考えられなかった。ぼくは授業について行けなくなり、受付のお姉さんとおしゃべりばかりしていた。お姉さんは三人いて、ぼくがいつも飲むヨーグルトを片手に現れるものだから、いつしか彼女たちから「ヨーグルト」と呼ばれるようになってしまった。予備校のキャンデーズ、今頃あの三人はどうしているだろう。のちに、そのキャンデーズの一人から、電話番号と住所が書いてあるメモを渡された。ぼくのことを気に入ってくれたのだ。何度かデートに誘ったが、彼女にはすでに前から付き合っている彼氏がいたので、ぼくの方から自然に離れていった。なぜ、ぼくは予備校でまじめに勉強しなかったのだろう。親の脛をかじりつづけて、結局翌年も大学進学を諦めて、浪人二年目に突入してしまった。そしてぼくはS町を離れ、実家に戻った。
2013.8.20
◆恋する暗号 2013.8.20◆
恋人からの暗号メールを解析ロボットC3POPが以下のように解読した。
↓
[fGvoB
1988年
もう25年も前の話なんだね
wA
lB
bB
��RAldbB
AFBAAB
B
地球が太陽の周りを一周するたびに
わたしたちの細胞は老いてゆく
そして
「あの時」からは遠く離れ
記憶もだんだん薄れてゆくのだけれど
bIA
uxbvAB
AfB
B
わたしこう思うの
じぶんにとって一体何がいちばん大切で
誰と過ごした時間が重要だったのか
OLADlB
luBvB
KB
uvvB
AbB
\ABCB
A��B
これまでの全ての経験の中から
砂のようにこぼれてゆく追憶をふるいにかけて
最後に残った金の粒のような「あの時」と共に生きること
それこそがどんなものにも代えられない「永遠」なのではないかと
ABDB
AlB
��}CiXB
sA}CiXvoBlB
voAAztAfGB
「永遠」は
時間のなかにはなくて
空間の制約も受けない
AAvBAvB
ああなんて素晴らしいのだろう
XA
A
voB
voLAmmAPB
あなたがいる
わたしと一緒に
いつまでも
A ` ttt c
AO��AA
vB
ずっとずっと
傍にいる
bAFBbAvoAB
AbvoB
NbAbAvoB
あなたといる「永遠」
それがあれば
ほかになにもいらないわ
2013.8.21
カミナリが鳴っている。雨の水曜日になりそうなので、大瀧詠一「雨のウェンズデイ」を聴こう。きょうはとても感動的な本を読んだ。山口淳『PAPA&CAPA ヘミングウェイとキャパの17年』阪急コミュニケーションズ、アメリカの文豪と戦争写真家との交流を描いた評伝である。企画としては、ロバート・キャパが撮ったヘミングウェイのポートレイトを紹介する写真集に詳しい解説が付いた本ができればと著者は考えていたようだが、単なる解説に終わらず、著者の二人への愛がじわじわと伝わってくる素晴らしい評伝となっている。全文引用したいくらいだが、たとえば次のような記述がある。
《ヘミングウェイがピカソと再会したのは、ヘミングウェイ作品のフランス語版翻訳者マルセル・デュアメルの案内で、ヘミングウェイ、レスター、キャパとパルチザンの仲間たち一行が飲み歩いていたある夜のことだった。セーヌ川沿いの小さなレストランを訪れると、そこに懐かしいスキンヘッドの芸術家がいた。互いを確認すると、ヘミングウェイとピカソはしかと抱き合い再会を大いに喜びあった。1920年代にパリで知り合い、南仏ではドス・パソス、フィッツジェラルド夫妻、コール・ポーター夫妻らと親交のあったジェラルド・マーフィー夫妻の邸宅やビーチで顔を合わせていたふたりは、すでに20年来の友人だった。レストランでは旨い子羊料理を味わい、ヴィンテージワインを次々と空け、遅くまで語らった、とレスターは書いている。》(106頁~107頁より)
それにしてもスケールの大きな二人だ。ヘミングウェイもキャパも、戦争の世紀に、世界を舞台に行動した。そして、ほんとうに多くの人々と出会い、交流し、歴史をつくった。ぼくらも、彼らのように、真剣に遊び、偉大な仕事をのこして21世紀を生き抜きたいものだ。
2013.8.22
きのうは満月を写真に収めようといろいろ試してみたが、満足のいく写真が撮れなかった。撮れなかったけれど、雲間に出たり隠れたりする、その荘厳な光を肉眼で見つめた。生きているんだ、やっぱり月も。ぼくは、じぶんが生きていることを誰かに知って貰いたいのだと思った。その衝動が表現となって、芸術が産み出されるのだろう。人間はみな同じなのかもしれない。表現方法が異なるだけで、人はそれぞれの環境で、表現者としてのじぶんに表現の場を与えてくれることを心のどこかで望んでいるのではないか。カメラを手にしながら、そんなことを考えていた。ロバート・キャパの撮った写真を何度も観ている。写真に撮れる世界は、リアルな世界のほんの一部でしかない。言葉によるスケッチも同様だ。どんなに長い長篇小説でも、リアルな世界と比較すれば、刹那をちょっとメモした程度になってしまうだろう。しかし、作品は圧倒的な存在感を示している。リアルな世界よりも、その本質に迫ろうとする芸術作品の方が強い。たとえば、歴史全部を記述した事典を読むよりも、ヘミングウェイの一篇の小説の方が遥かにインパクトのある印象をぼくらの心にのこしてくれるに違いない。今村楯夫『ヘミングウェイの言葉』新潮新書には、次のような言葉が紹介されている。
《 単純なことを永遠にとどめるためには、目を閉じては不可能だ。(『午後の死』より) 》
続いて解説にはこうある。
《ヘミングウェイにとって重要なことは、自分の目でしっかりと事実をとらえて書くということだった。人から教えられて、こう感じるべきだというようなこととは異なる、自分が本当に感じていることを書くことを心がけ、それによって書かれた文を「真実の一文」と呼んだ。》(175頁より)
2013.8.23
ジョン・リーランド『ヘミングウェイと歩くパリ』(高見浩 編・訳)新潮社に掲載されている年譜が面白いので、書き写してみる。
1899年 7月 ヘミングウェイ誕生。
1918年 5月 第1次世界大戦のイタリア戦線に赴く途中パリに立ち寄る。
マドレーヌ寺院にドイツ軍の砲弾が命中したさまを目撃。
1921年12月 新妻のハドリーを伴ってパリに到着。
1922年 1月 カルディナル・ルモアーヌ通りのアパートメントで暮らしはじめる。
以後、ガートルード・スタイン、エズラ・パウンドら、祖国を離脱した文学者たちと活発に交流。
カナダの『トロント・スター』紙の通信員をつとめるかたわら創作に励む。
1923年 8月 『三つの短編と十の詩』パリで出版。
10月 長男ジョン(バンビ)誕生。
1924年 2月 ノートルダム・デ・シャン通りのアパートメントに引っ越す。
4月 『ワレラノ時代』パリで出版。
1925年10月 『われらの時代』ニューヨークで出版。
1926年 8月 ヘミングウェイとハドリー別居。
10月 『日はまた昇る』出版。
1927年 4月 ヘミングウェイ、ハドリーと正式に離婚。
5月 ヘミングウェイ、ポーリーン・プファイファーと再婚。
9月 フェルー通りのアパートメントでポーリーンと暮らしはじめる。
10月 『男だけの世界』出版。
1928年 3月 アメリカに帰国。
6月 次男パトリック誕生。
1929年 6月 パリを訪ねたモーリー・キャラハンとボクシングの試合をする。
9月 『武器よさらば』出版。
11月 『武器よさらば』の売上げ、4万5千部に達する。
1931年 6月 パリを訪問。
1933年10月 パリを訪問。『勝者には何もやるな』出版。
11月 アフリカ行きの前夜、パリでジョイス夫妻と会食。
1937年 5月 スペイン内戦を取材中に、パリを訪問。この頃からマーサ・ゲルホーンと親しくなる。
シルヴィア・ビーチ救済のための朗読会に参加。
10月 『持つと持たぬと』出版。
1940年10月 『誰がために鐘は鳴る』出版。
11月 ポーリーンと離婚し、マーサ・ゲルホーンと結婚。
1944年 8月 パリ解放。リッツ・ホテルにメアリー・ウォルシュと滞在。
1945年12月 マーサと離婚。
1946年 3月 メアリー・ウォルシュと結婚。
1952年 9月 『老人と海』、『ライフ』誌に一挙掲載。
1953年 6月 メアリーとパリを訪問。
1954年11月 『老人と海』でノーベル文学賞を受賞。
1956年 9月 メアリーとパリを訪問。リッツ・ホテル滞在中に『移動祝祭日』のもとになる古いノートを発見。
1961年 7月 アイダホ州ケチャムで自殺。
結婚相手だけ見ても、ハドリー、ポーリーン、マーサ、メアリーの4人。いつも離婚が再婚の直前である。移動する男には、出会いの機会も多くなる。安定よりも刺激を求めて生きているからだろうか、結婚している間に新しい恋人が出来るというパターンを繰り返している。パリとの関連年譜であるが、アメリカの文豪のイメージからすると、パリ訪問が案外多く、また滞在が考えていたよりも長いことに驚く。しばらく、ヘミングウェイから目が離せないぞ。
2013.8.24
《周期ゼミとは、セミのうちMagicicada属に属する複数の種の総称。 毎世代正確に17年または13年で成虫になり大量発生するセミである。その間の年にはその地方では全く発生しない。ほぼ毎年どこかでは発生しているものの、全米のどこでも周期ゼミが発生しない年もある。周期年数が素数であることから素数ゼミともいう。17年周期の17年ゼミが3種、13年周期の13年ゼミが4種いる。なお、17年ゼミと13年ゼミが共に生息する地方はほとんどない。 》(ウィキペディアより)
ぼくは1987年、高校三年生の夏、素数の研究に没頭していた。素数の非法則性に心を奪われてしまったのだ。寝ても醒めても素数のことばかり考えていた。そうして、とうとう素数の方程式を見つけた、と思ったら夢だった。秋になり、ぼくはすっかりふぬけになっていた。受験生なのに受験勉強がまったくできなくなっていた。文化祭で、ぼくのクラスは映画を撮ることになった。ぼくは撮影・編集などを担当し、みんなで、撮りながらストーリーを膨らませていった。舞台は自分たちの高校。そこで主人公のYくんがクラスメイトの財布を盗んでしまう。担任の三十六(みそろく)は、なぜYがそのようなことをしてしまったのか、事情を訊くために家庭訪問をする。Yはある悪の組織(ベルベッタ団)にかつあげされていた。三十六はその組織に乗り込む。しかし、逆に捕まって閉じこめられてしまう。三十六はYに「かぼちゃを持ってきてくれ」と頼む。Yは八百屋でかぼちゃを買う。そして、三十六が閉じこめられている牢屋に、忍び込んでかぼちゃをわたす。三十六はかぼちゃをかじって「学園刑事カボチャマン」に変身する。そして見事ベルベッタ団をやっつける。こうして、学園に平和が戻る。しかし、三十六はじぶんが学園刑事であったことを生徒たちに告白し、みなのもとを去ることに。そして、多摩川土手をみんなで走りながら、エンドロール。この映画の撮影を通して、クラスの男女が非常に仲良くなった。ぼくは、あるクラスメイトから告白された。付き合うことになった。翌1988年3月、卒業。彼女からお別れの手紙が届いた。ぼくは浪人生となった。ぼくは以前から好きだった女子に告白した。彼女はぼくを受け止めてくれた。この年が、ぼくの発情第一期となる。それから13年後の2001年が第二期だ。前年の2000年には、世の中が、ミレニアム、ミレニアムと大騒ぎ。ぼくは1999年に地球は滅亡すると信じていたので、肩すかしを食らわされた気分だった。毎日、詩を書いていたのに、書くのをやめてしまった。でもそんな時、ひとりの女神が現われた。その女子はぼくの詩を読んでみたいという。そして、誰にもみせたことのないぼくの詩集の一部を彼女にわたす。翌日彼女から感想文が届く。この反応の迅速さに、ぼくはすっかり心を奪われてしまった。そして、もう一度詩を書こうと決意する。2001年の5月から、電子メールで詩を書いて送ることをはじめる。もうすぐ13年後の2014年がやって来る。ぼくは発情するだろう。13年ゼミなのだ。ぼくは13年ごとに鳴き叫ぶ13年詩人なのだ。
2013.8.25
◆オブセッション 2013.8.25◆
雨が降っていた
静かな日曜日の朝
車を公園の脇へ停めて
ぼくはひとり物思いに耽った
フロントガラスでは
いくつもの雨粒がダンスを楽しんでいる
くっついては流れ
またくっついては流れてゆく
傘もささずに肩を寄せあって歩いている男と女
男はぼくで
女はきみだ
と妄想する
カーステレオ
から
HALL&OATES
の
〈Possession Obsession〉
が流れている
そうなんだ
恋を恋する男には
センチメンタルな気分になる時間が必要だ
思い出は1988年にある
あの時のきみと
あの時のぼくが
雨のふる緑の森の中を
歩いてゆく
歩いてゆく
2013.8.26
ヘミングウェイの小説『武器よさらば』のヒロイン、キャサリン・バークレーには、モデルとなった実在の人物がいるという。その名は、アグネス・ハンナ・フォン・クロウスキー、ポーランド系ドイツ人を父にもつアメリカン人だ。ミラノのアメリカ赤十字病院に看護士として働いている時に、ヘミングウェイと出会った。日下洋右『ヘミングウェイと戦争』彩流社には次のように記述されている。
《ミラノのアメリカ赤十字病院の入院患者の第一号が、アーネスト・ヘミングウェイであった。アグネスがアメリカ赤十字病院に到着してから20日後の7月17日の早朝6時に、ヴェネチアの北のメストレから病院列車に乗せられたヘミングウェイは、ミラノ駅の貨車専用構内で降ろされ、そこからミラノに開設されたばかりのアメリカ赤十字病院へ運ばれてきたのである。ヘミングウェイが19歳の誕生日を迎える4日前のことであった。》(134頁より)
傷病兵運搬車の操縦士の任務についていたヘミングウェイは、志願して移動式売店の任務についた。
《ヘミングウェイは自転車に乗って、前線の兵士たちにホットコーヒー、コールドドリンク、タバコ、チョコレートなどの嗜好品や日用品を配って回った。7月8日の真夜中に、川向こうから発射されたオーストリア軍の迫撃砲弾が地面で炸裂して、塹壕に入っていたヘミングウェイは両脚を負傷した。彼の傍らにいた仲間のイタリア人のうち一名は死亡し、一名は両脚を失い、一名は重傷を負った。彼は負傷しながらも、重傷を負ったイタリア人を背負ってよろけながら、応急手当所へ向かって待避した。彼はその途中敵の機関銃弾を右膝に浴びたが、何とか無事に重傷者を引き渡した後、本人は気を失った。》(135頁より)
もう映画のなかの出来事のようである。そんな戦地で19歳のヒーローが同じアメリカからきた看護士と出会い恋に落ちた。それだけで物語は十分に出来上がっている。ところが、結婚の約束までしたにもかかわらず、退院したヘミングウェイがアメリカに帰国すると、二人の関係は破局してしまう。アグネスは年上で、まだ若いヘミングウェイを子ども扱いする面があった。恋人同士の横の関係のままであったら、年の差はあまり気にならなかったであろう。しかし、アグネスの母性は強かった。母親が息子を見守るような態度で、注意や指図が始まると、男は急に反発したくなるものだ。おいおい、おれを子ども扱いすんなよ。直情的な性格の持主であったヘミングウェイである。支配したいから結婚を申し込んだのに、その支配をアグネスは回避したのだ。
《「あなたとお別れしてから二ヶ月経った今なお、あなたのことがとても好きなのだとつくづく思います。でも、これは恋人というよりは、母親のような愛情です。……/……でも、私は今もこれからも年上過ぎますし、これは変わりようがありません。ですから、あなたが子供──うぶな若者にすぎないという事実を認めないわけにはいかないのです。/それから……私は近いうち結婚する予定です。十分ご理解のうえ、あなたがこのような私を許し、あなたがすばらしい人生のスタートを切ることができますことを切にお祈りしております。……/いつまでも敬服し愛をいだいて あなたの友人 アギーより」》(167頁より)
2013.8.27
大江健三郎さんが性別の意味のSEXをカタカナで「セクス」と表記していることに井上ひさしさんがとても感心していた。それで、少し調べてみた。「死者の奢り」には、次のようにある。
《死体に屈みこんでいた学生が注射器を持って躰を起すと、僕はそれまで学生の白衣の背にかくされていた少女のセクスがあけひろげに、僕の前にあるのを見た。それは張りきって、みずみずしく生命感にあふれていた。それは強靭に充実してい、健康でもあった。僕はそれに惹きつけられ、愛に似た感情でそれを見まもっていた。》
《あの布の下で、あんなに生命にみちたセクスを持つ少女が《物》に推移し始めているのだ、すぐにあの少女は、水槽の中の女たちと同じように堅固な、内側へ引きしまる褐色の皮膚に包まれてしまい、そのセクスも脇腹や背の一部のように、決して特別な注意を引かなくなるだろう、と僕は考え、軽い懊悩が躰の底にとどこおるのを感じた。》
「飼育」には、次のようにある。
《泉では、最も広くてなめらかな台石の上に寝そべった裸の兎口が、女の子供たちに、彼の薔薇色のセクスを小さな人形のように可愛がらせていた。兎口は顔を真赤にし、鳥の叫びのように笑い声をたてながら、時どき、やはり裸の女の子供のお尻を掌でひっぱたくのだった。》
《しかし、水浴から帰る裸の子供たちのなかにまじっている、歩くたびに腰をゆらめかせる女の子、潰れた白桃の不安定な色が覗いている皺よった貧しいセクスを剥きだした女の子が僕におずおずした微笑をむけるごとに、僕は罵声と小石とを雨とふらせて彼女たちをおびえあがらせたのだった。》
これらの描写のそれぞれに「セクス」という言葉がとても印象深く使用されていて、実に魅力的な表現が達成されている。もしこれが「セックス」という表記だったら、どうだろう。ぼくたちは「セックス」という音の響きに「性別」よりも「性交」をイメージしてしまう。それほど「セックス」は通俗的に使用され、流通している。逆に言えば、それだからこそ「セクス」という表記は救われていて、美しい響きを維持していると云ってもよい。その他にも、森鴎外の小説「ヰタ・セクスアリス」がある。ラテン語の「VITA SEXUALIS」、これは「性欲的生活」のことを意味するそうだが、森鴎外のこの「セクスアリス」という表記が、大江健三郎さんの「セクス」と関係があるかどうかはまだ不明である。こんなことを調べなくてはならなかったのは、今日ぼくが昼下がりのカフェで次のような詩を書いてしまったからだ。
◆カフェでの会話「それで」 2013.8.27◆
「それで?」と彼女は云った。
「もちろん君とセクス……、あ、大江健三郎の言い方を真似たんだけどさ……、セックスをセクスと書いたんだ。ぼくはその方が好きなんだよね」
彼女はコーヒーが半分入ったマグカップをそっとテーブルに戻すと少しため息をついた。
「ぼくの言い方、へんかなあ」
彼女の視線は、すみれ色に染まった空の彼方へ向けられていた。その横顔を見ているとKの胸の奥はいつもキュンとなる。
「いまさらって言葉は好きじゃないから言わないけど、やっぱり、もう、もどれないよ」
「もどらなくていいさ」
「はじめるつもりも……」
「なくていいさ」
「ぜんぜん、わかんなあい」
「コーヒーさめたでしょ」
「そうそう、さめちゃったわ……、すっかりね」
午後の風が心地好い。
テラスには10セットほどテーブルとイスが並んでいるが、座っているのは彼女とKの二人だけ。
Kは流れてゆくじかんを心から楽しんでいた。
生きていること自体が楽しいと思っているかのようにさえ見えた。
彼女はKのそんな微笑をたたえた揺るぎない表情につられて思わずクスリと笑ってしまった。
2013.8.28
◆1つのジレンマノペティ 2013.8.28◆
ノアはモコが好きだった
しかしモコにはすでに恋人がいた
だからいつもモコのことを遠くから見守ることしかできなかった
ある日「ノアが好き」とナミから告白されノアはナミと付き合うことになった
ナミは映画や散歩や公園にノアを誘った
ノアはいつも快くナミの提案に賛成した
しかしノアからナミを誘うことはなかった
いつしかナミは疑うようになった
ナミは年上の男にその不安を打ち明けた
年上の男はナミを奪ってしまった
「さよなら」を告げられたノアは仕方がないと思った
しかしあとから悔しさがこみあげてきてノアは一晩泣き明かし
それからナミを呼び出した
ノアはナミの気持ちを確かめたかった
今でもじぶんのことが好きならばノアはナミを奪い返すつもりだった
ナミは「ごめんなさい」としか言わなかった
ナミの涙を見たノアはじぶんの態度に責任があると思った
「いつか取り返しにいくから」とノアは言って別れた
ナミは年上の男と暮らしはじめた
ノアは不安定だった
じぶんの気持ちに整理がつかないままじかんばかりが過ぎていった
ノアはモコのことを思った
モコのことを思うことだけが安らぎだった
しかしモコはノアの気持ちには気づいていなかった
モコはすでに恋人と別れていた
その噂はノアの耳にも入った
ノアは迷った
道義的にはナミのことを第一に考えるべきだと思っていた
しかし
感情はいつもモコを欲していた
理性と感情は矛盾する
しかしほんとうは単に勇気のあるなしの問題だった
ノアはモコを部屋に呼んだ
そしてモコを抱きしめた
秋の終りにノアの家に一本の電話が入った
「ナミはお前の所にいる筈だ」と年上の男がわめいていた
ナミは男の家を何も告げずに飛び出したらしかった
年上の男は「ナミはずっとお前のことが忘れられなかったんだ」とノアに言った
ノアは心臓にくぎを打ち付けられる思いだった
ノアはどこにも行けなくなった
モコに行きたかったがモコにも行けない
ナミに行くべきだったがナミにも行けない
全部じぶんが蒔いた種だと思った
ノアには箱舟がなかった
誰も乗せることができなかった
やがてモコは別の男と結婚し
ナミは遠く離れてしまった
それでもノアはモコのことを思い続けていた
思い続けることだけが幸せだった
ノアの物語は今もどこかで続いている
2013.8.29
You know there's something you need right here and now
To fill the space inside of yourself, oh, with money, love or power
When you want to have the number one first run anyone
You're crazy 'til you own them, U ought to know better than that, girl
The more that you buy the less you get back, you could say
It's a case of possession obsession
It’s just a taste of possession obsession
Ooh, it brings of a case of possession, I hear you say gimme gimme
Now gimme gimme gimme, gimme gimme
The compulsion to count the percentage of time
Spent between two lovers
Can turn an hour into a crime, oh, all the good times suffer
Though you know it's only jealousy
But you can't help but be haunted by your passion
Now, don't you know it's a matter of fact
The more that you take the less you give back, I can say
It's a case of possession obsession
It’s just a taste of possession obsession
Ooh, it brings of a case of possession, I hear you say gimme gimme
Now gimme gimme gimme gimme gimme, yeah, possession
Ooh, gimme gimme, gimme gimme gimme, gimme gimme, yeah yeah
Ooh, it's a case of possession obsession
It’s just a taste of possession obsession
Ooh, it brings of a case of possession
And I hear you say, yeah yeah yeah yeah, possession
Now, don't you know it's a matter of fact
The more that you take (gimme some) the less you give back
Yeah yeah...Possession...Possession...Possession of...
Gimme some...Gimme some...Yeah yeah yeah yeah yeah...
Possession...Just a case of...Just a taste of...
Just a case of possession obsession of love...
Possession...Possessions of...Gimme some...oh ah...
『ヘミングウェイ短篇集』(西崎憲・編訳)ちくま文庫を読んでいる。そのなかの「密告」から一部引用する。
「そうか、オクトウパスがあんまり多すぎる」
「何が多すぎる?」
「オクトウパスだ」ジョンは真ん中にアクセントをつけて発音した。「脚が八本ある」
「ああ、蛸(オクトパス)か」
「オクトウパス」とジョンは言った。「おれは潜水夫もやってた。あそこはいいところで、金がたくさん入った。ただ、オクトウパスがあんまり多すぎた」
「蛸がいると困るのか?」
「どうなんだろうな。はじめてマガヤネスで潜った時、おれはオクトウパスを見た。オクトウパスは脚を伸ばして立ってた。こんなふうに」ジョンはテーブルの上に両手を置き、指を伸ばして脚と思しいものを作った。そして同時に肩をそびやかし、眉を吊りあげた。「そいつはおれより背が高くなって、まともにこっちを見た。おれは大急ぎでロープを引っ張って引きあげの合図を送った」
「そいつはどれくらい大きかったんだ、ジョン」
「はっきりとは言えないな。潜水帽のガラスってのは少し歪んで見えるから。けど、頭の大きさは四フィート以上あった。それにそいつは人間が爪先立ちするみたいに立って、おれをこんなふうに見た(ジョンはわたしを睨んだ)。水から出ると、みんなは潜水帽を取ってくれて、それでおれは言った。もう下には行きたくないって。仕事仲間は言った。『どうしたんだ、ジョン、おまえがオクトウパスをこわがるより、オクトウパスのほうがおまえをこわがっているはずだ』だからおれは『ばか言え』って言い返したんだ。このファシストの飲み物をもう少しやるってのはどうだ?」
「いいな」
マドリードのチコーテというバーで「わたし」とギリシャ人の友ジョンが会話をしている。何気ない会話だが、ぼくはほんとうにその店でジン・トニックを飲みながら、そんな話を聞いているかのような錯覚に陥った。なんだろう。前後の脈絡が無いのに、すっとその世界に入り込めるのは、やはり作家の腕の良さなのだろうか。詳しい説明や描写は少なく、ただ雰囲気だけはしっかりと伝わってくる。こういう書き方が、ヘミングウェイ以降、多くの作家に真似されたのだろう。真似したくなるよ。書いていて楽しいだろうし、どんどん書けるのだから。
2013.8.30
8月は激動だった。心も身体も動いて、揺れた。毎年、8月には何かが起こっている、ような気がする。親友が死んだ8月。大切な友人の誕生日のある8月。わが長男の誕生の月も8月。知り合いに殺されかけた8月。原爆の8月。終戦の8月。夏休みが終わろうとしている。子どもたちは宿題の追い込み。きょうは暑かった。いやあ異常に暑かった。読みたかった本が読めなかった。時間は無駄にできない。ぼくは20年前、8月に東北へ旅にでようと計画していた。宮沢賢治さんのふるさとを訪ねたいと思っていた。しかし、親友のエイスケが死んだという訃報が舞い込んできて、計画変更を余儀なくされた。あれから20年、東北への旅は延期されたままだ。エイスケはたくさんやり残したことがあった。ぼくはエイスケの手帳を形見として遺族から頂いた。そこにはたくさんの夢と願望が記されていた。生きていること、それだけで価値がある。生きていなければできないことばかりだ。命短し、恋せよ、諸君。恋も仕事も友だちとの交流も読書も勉強も、精一杯やって、生き抜こう。風が立った。生温かい風かもしれないが、確かに風が吹いたのならば、さあ生きること、生きること自体を楽しむのだ。
2013.8.31
8月のはじめに、聖子ちゃんの名曲「レモネードの夏」を紹介したので、締め括りも聖子ちゃんにしよう。テキストは、松本隆『秘密の花園 松本隆詩集』新潮文庫である。
◇ひまわりの丘 松本隆◇
黒い小さなラジオ耳にあてて歩く
ストライプのTシャツ憶えているわ
旧い海の家は青い岬のそば
裸足のまま海まで
あなたと歩いた
白い夏のイメージね
ひまわりの咲く丘に座れば
入江はエメラルド
風が吹きぬける
あなたの愛を失うことを
ただこわがっていた
あの夏の日
バスの時刻表を調べてるあなたの
背中に抱きついては困らせたわね
あなたのつけていたヘアリキッドの香り
今でも憶えている
私が哀しい
遠い愛のメモリーね
ひまわりの咲く丘で眠れば
寝顔にキスされた
あの日に戻るの
もう泣かないと約束するわ
空を見上げて咲く
花のように
入江はエメラルド
風が吹きぬける
あなたの愛を失うことを
ただこわがっていた
あの夏の日
この歌を聖子ちゃんが歌っているのを聴くと、とても失恋の歌には聴こえない。明るく、さわやかな夏の印象だ。そして、語尾のしゃくりが実に見事だ。ためしに真似しようとしても、あの声量からでる自然なしゃくりは真似できない。ほんとうに得がたい女性ボーカリストだとしみじみ思うのだ。作曲は、来生たかおさんである。この曲にあわせてバトンをまわしながら街を練り歩きたくなる。それくらい軽快な仕上がりで、楽器にピアノやバイオリンなどが使われているからだろうか、放課後のブラスバンドの練習風景がなぜか頭をよぎる。せつない恋の思い出をそれとなしに演出している。「エメラルド」の「ル」の音を出す時の聖子ちゃんのキャンディーボイスは絶品である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
