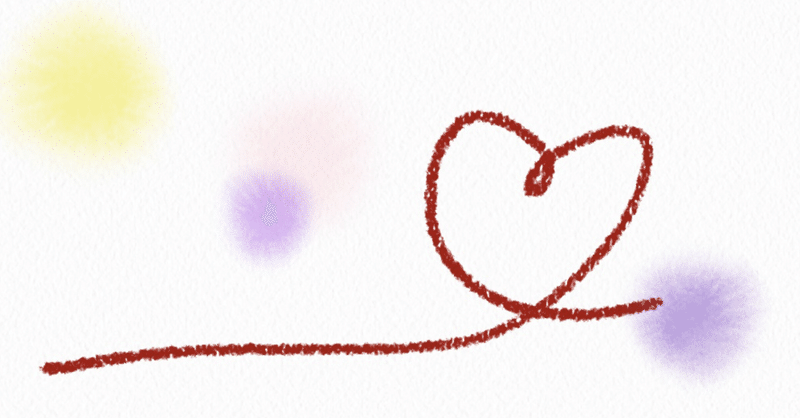
言語学に興味を持ち、優しくなれた
間違えも楽しもう
「日本語が乱れている」
誰もが一度は聞いたことはあるんじゃないでしょうか?
いわゆる”ら抜き言葉”であったり、”敷居が高い”という言葉や”雰囲気”のようなものまで。
去年までは明らかに間違えてる言葉や単語を聞いた時には、「間違えて使ってるなあ」という感じに指摘こそはしなかったけど、心の中で思うこともしばしばありました。
多分”誤った日本語”としての知識があるせいでそう思ってしまったのでしょう。そんなこと考えちゃう自分にも嫌気が差していながら、呪縛のように逃れることが出来ないでいました。
そんな時に言語学に関心が沸き、いくつか本を読んでいると面白い発見がありました。
音の位置が替わる?
まず『音位転換』です。
これは単語の中で音の位置が入れ替わる現象のことで、日本語だけでなく英語にもみられます。(ほかの言語もあるのかな?リサーチはできてないです)
先ほど例に挙げた「雰囲気(正しくは”ふんいき”)」ですが、これも
ふんいき→ふいんき このように入れ替わって定着しつつあります。
同じように「新しい(あたらしい)」もこれに該当します
「新たな」 この書き方の時は 「あらたな」ですよね?
なのでこれも あらたしい→あたらしい と音位転換が起きています。
正直これは僕も知らなくて軽い衝撃でした(笑)
意味の拡張
「敷居が高い」は僕の手元の辞書の語釈はこうです。
《不義理をしていて、その人の家に入りにくい。》
つまり借りたお金や物を返してないので、気まずいといった感じですね。
しかし今では、「あのフレンチのお店は敷居が高い」みたいな感じで使われることが多いと思います。(ハードルが高いというニュアンスでしょうか)
もう一つよく聞くのは「確信犯」でしょうか
気になる方は辞書を引いてみてください
体系の変化?
ら抜き言葉は、無意識に使っている気がします。
でも使う上で支障はないのでいいのでは、と思っています。
言語において文字を省略したり新しい造語成分が出てきたりはよくあることなので、これは自然な流れなのかもしれないですね。
今まで三つの事象について言及してきましたが、どれも時代の流れと共に言語も変化していくのを目の当たりにできているので、なんだかライブ感があって面白いですよね!
まさに言語のライブ感
こんな風に考えていたら、誤った使い方や新しい用法などを聞いた時になんだか面白くてワクワクするようになりました。
間違いを指摘するのも勿論正しいですが、自然な流れの中で言語使用の移り変わりを楽しむのもいかがでしょうか?
最後まで読んでくれてありがとうございます^_^
皆さんも一緒にコトバの成長を見守ってみましょう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
