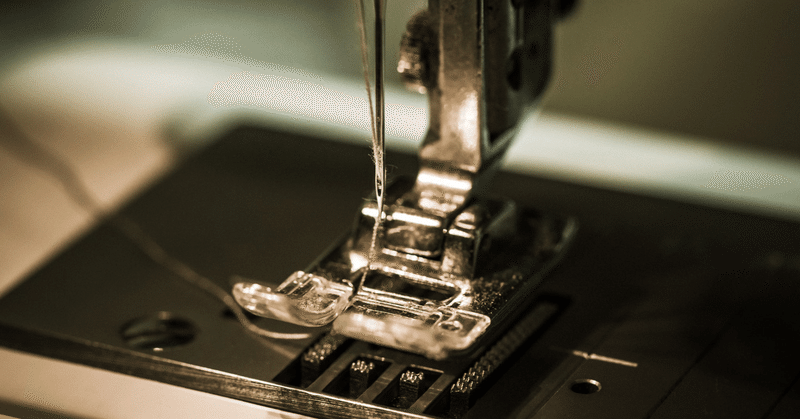
不器用な父が娘のエプロンを作る話。
私は裁縫が苦手だ。どれくらい苦手かというと、玉止めや玉結びは安定せず、ミシンのセッティングもろくにできない。
小学校の教員をしているとはいえ、家庭科専科におんぶに抱っこ状態でここまで生きてきた。
このまま死ぬまで裁縫には触れず、ほどよい距離感を保っておこうと思っていた。
そんな矢先に訪れた試練。保育園からのお便りには、こう書いてあった。
白いエプロンが必要です。見本をもとに各ご家庭で作成をお願いいたします。
目を疑った。エプロンを各ご家庭で!?そんな話が今の時代にあるのかと。ネットでポチって済ませることもできる。今まではお金で解決できることはだいたいそうしてきた。
しかし今回はどうだ。葛藤に次ぐ葛藤。その理由は、私の愛する娘のためという大義名分があるからだ。
自分でも不思議と意欲が湧いてきていた。小6の頃に家庭科で作った不恰好なナップザック以来の裁縫だ。18年ぶりにやることとしては、どう考えても難易度が高い。それでも、娘のためになら、一肌脱ごうと決心できたのだ。
人は大切な誰かのためになら、無理難題にも挑戦しようと決心できる。これは動機付けの大事な鉄則かもしれない。
よし、まず何からやろう。ミシンを買おう。ここからだから笑えてくる。ネットでエプロンの商品を通り過ぎ、ミシンをポチる。なぜだか自分のポチる指が勇ましく見えた。
次に、生地と基本的な裁縫セットを買いに行く。考えれば考えるほど、遠回りしかしていない。生産性を求めて生きてきた自分にとっては、新鮮で楽しくすら思えた。
楽しさは遠回りにこそ存在する。だから大いに無駄なことをして、遠回りをしながら生きていこう。そんな学びを得た。
さて、いよいよ道具や素材がそろった。最初にやることは、水通しと地直しを…。初耳すぎて分からない。ミシンに取りかかる前にやることがあるということすら初めて知った。
とにかくネット記事を研究し、基本的な知識を押さえた。水通しは、生地が縮んでしまうのを防ぐため。地直しは生地の歪みやたるみを整え、仕上がりを綺麗にするため。どちらも大切な下準備というわけだ。
満を辞して、ミシンのセッティング。が、しかし、分からない。今度はYouTubeと説明書で勉強して乗り越えた。できたときの達成感は忘れられない。
前に読んだスケボーのスカイ・ブラウン選手の記事に、すべてYouTubeで学んだと書いてあって、時代の変化を感じたのを思い出した。
YouTubeがあれば大抵のことは学べてしまう時代なのだ。学校での学びの在り方も、時代に合わせて問い直す必要があるとつくづく思う。
妻にチャコペンで下書きをしてもらい、サイズに合わせて裁つ作業をしてもらった。私はそれを受け取り、アイロンで折り目を付け、三つ折りで端の処理をした。
その後、縫い目を粗くしてギャザーを作る。もちろん、これもYouTubeで学んだ。我ながら出来栄えがいいギャザーができた。
下の部分、胴体の部分、紐をそれぞれ作り、つなぎ合わせる。一番下にはレースまで取り付けた。まっすぐ縫うのは難しいけれど、徐々に上手くなっているのも実感できた。
完成間近で最後の難関が待ち受けていた。Dカンと呼ばれる紐を通す部分を取り付ける作業。事前にDカンを通すことを考えて手を打っておけばよかったと思いながらも、どうにかDカンを取り付けなければいけない。
やはり、物事は見通しをもって取り組むことが最重要なのだ。初めてやることほど、見通しを誤ってしまうと大変なことになる。
お店で綾系という太めの生地を購入してDカンを取り付けた。短い距離のミシンは不器用な私にとって困難を極めた。2回失敗して、ようやくら3回目で成功した。
こんなそんなで、裁縫初心者である不器用な私でも娘のエプロンを作り上げることができた。あぁ、なんたるやこの達成感。ものづくりのやりがいとは、こういうことだったのか。(たぶんちがう)
できないことができるようになる喜びは、やっぱり何にも変え難い価値あるものだ。人生まだまだできないことに挑戦して、できることを増やせる自分でありたい。
できないことに意図的に飛び込む勇気の大切さを保育園は教えてくれたのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
