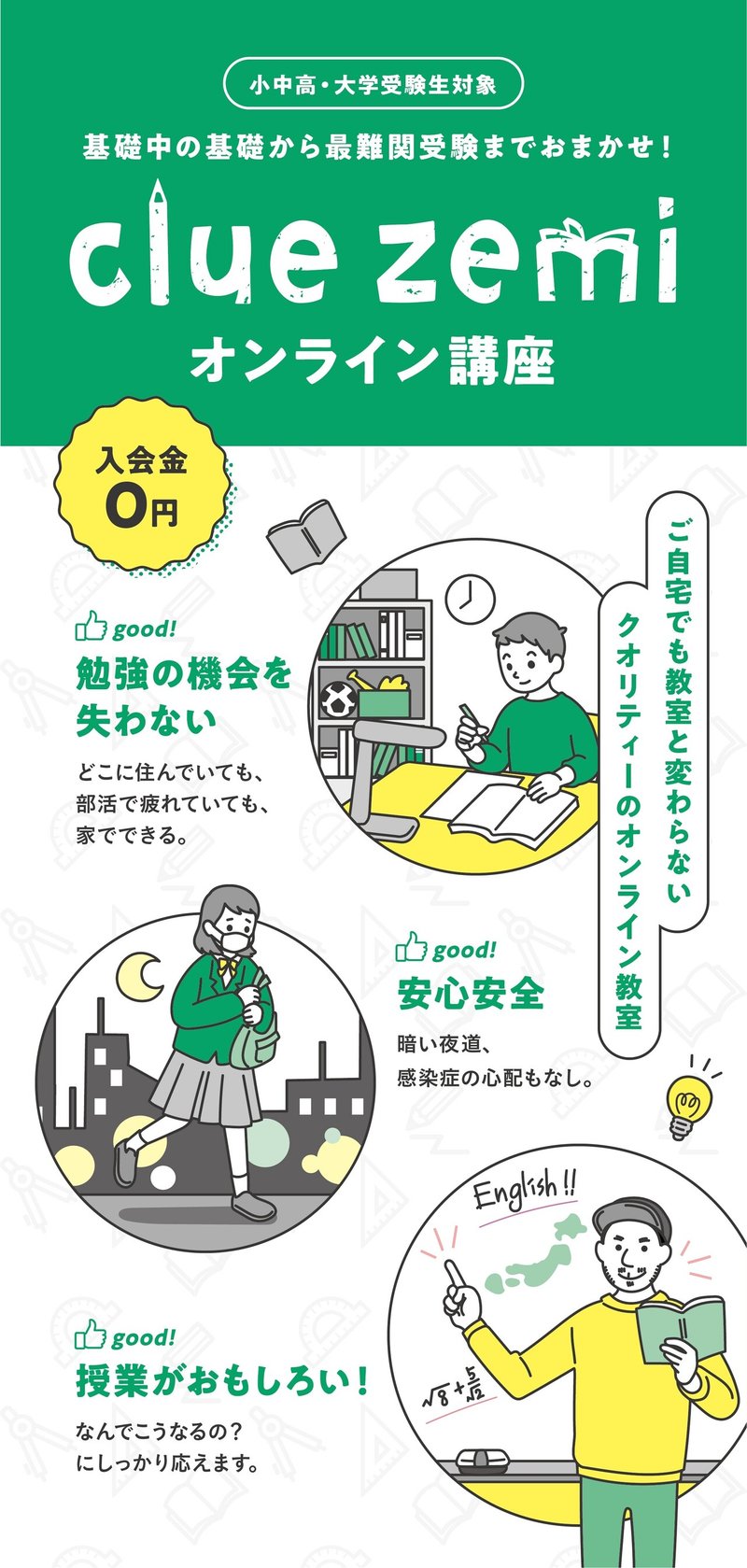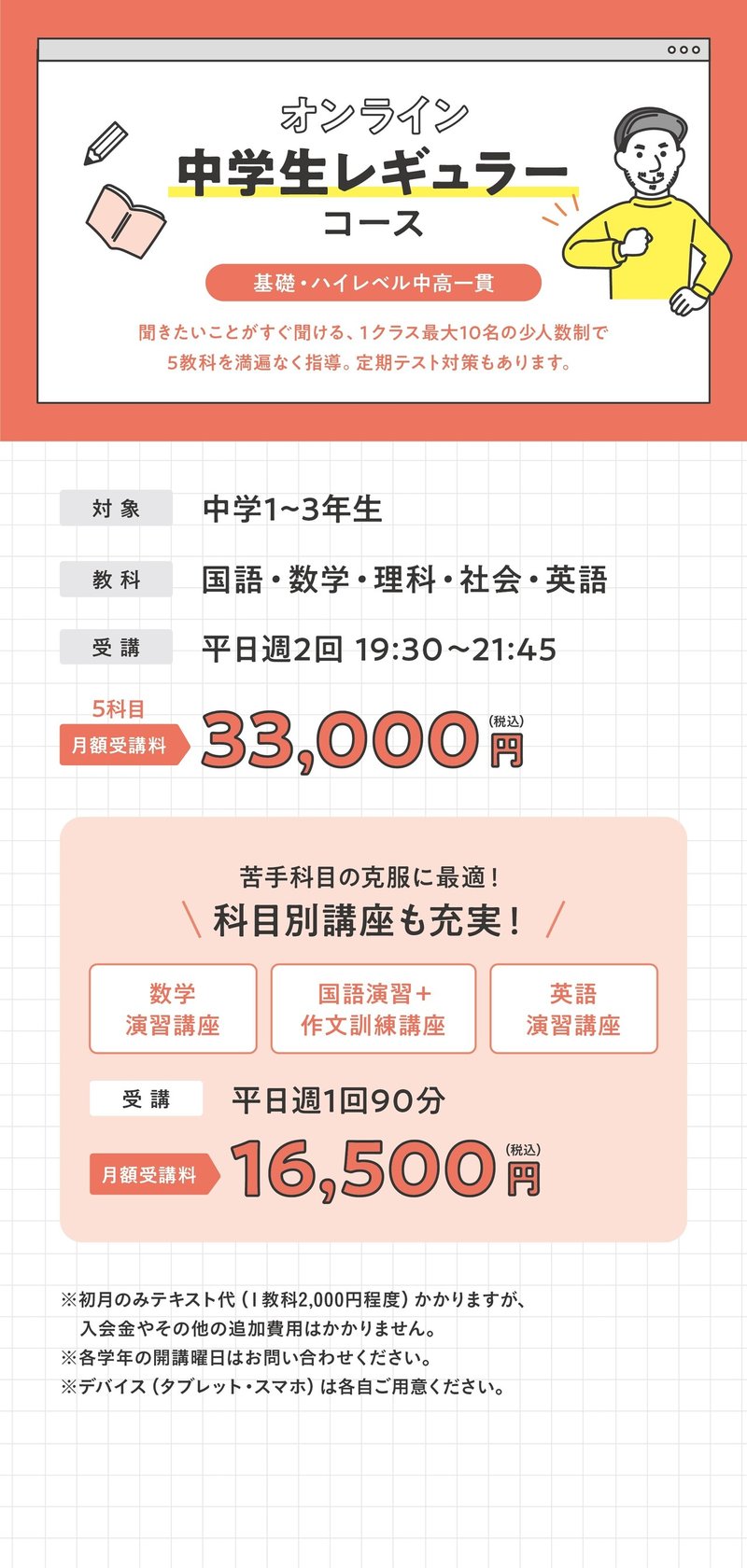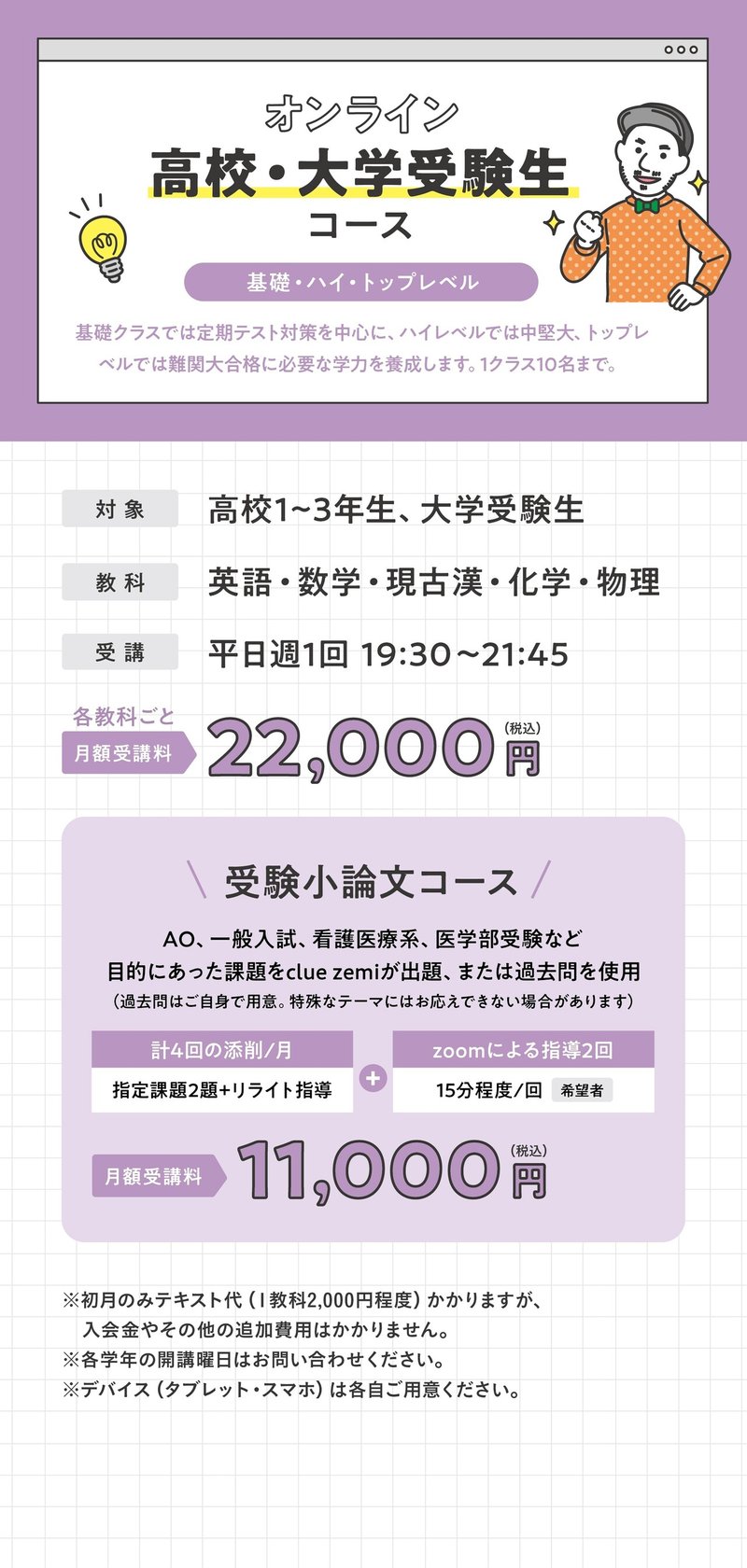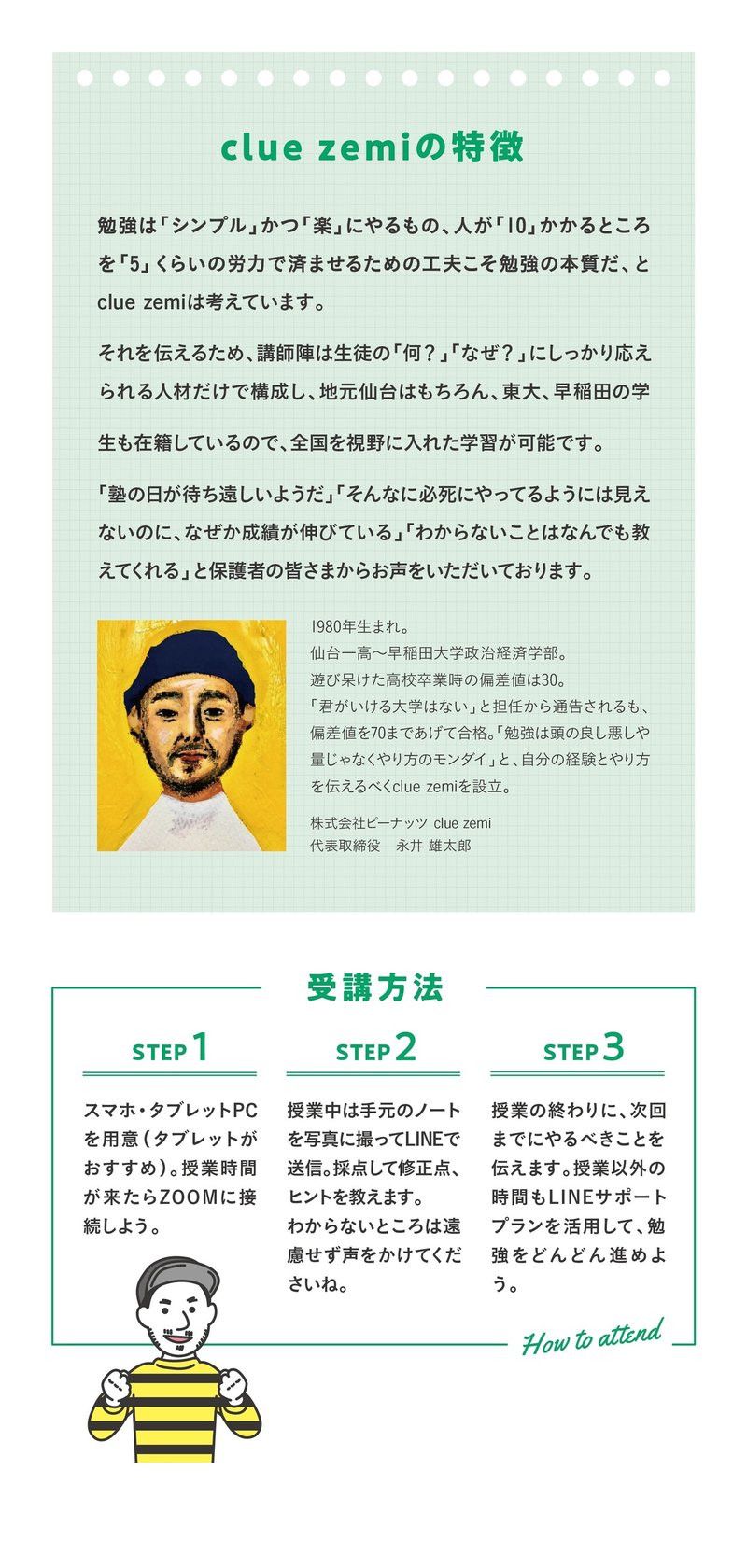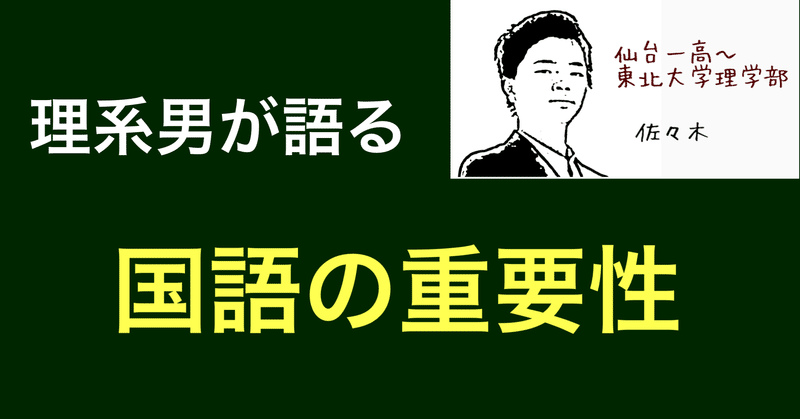
基礎練としての国語(後編)
こんにちは。
前回に引き続き、「基礎練としての国語」の話です。今回のテーマは「文法の理解」。
文法もやはり文章を正しく理解するのに必要です。特に、複雑な文章では「どこからどこまでが主部であるのだろうか」「述語は何」といった疑問が嫌ほど湧き起こるでしょう。そこで分かっておくといいのが日本語文法です。特に、どの修飾語がどこにかかっているのかを理解しておく必要があります。
実は理数系の問題や論述でもこの「修飾語がどこにかかっているのか」の解釈違いで間違いになってしまうことがあります。また、話すときは「後の文が最初から見えない」ことから悪い印象を与えてしまう例もあります。(筆者は経験者です。)
さらに、この「修飾語」を分かっていない人は英語などの別の語学でも苦労します。意味だけ読み取ると同じだからいいだろという言い訳は通じません。特に、複雑な文の構造を取れず、内容を最後まで読み取れないという展開には陥りがちで、筆者も何人か見ています。
他にも、助詞や助動詞からの(暗なる)意味の読み取り、接続語の理解は一層重要で、ここに「何か伝えたいものを隠して」文章を書く人もいるくらいです(本人は「隠す」とか考えてなさそうですが)。本質の読み取りのために一層注意を払って文章を読んでみてはいかがでしょうか。
「文法」を養うには、文法書の演習を行う、自分で文を書いて(ちゃんと分かる)大人に添削してもらう、話し言葉をそのまま文法だと信じない、という3個の具体的方法があります。(勿論他の方法もあります。これは極一部にすぎません。)
文構造を理解することが文章そのものの正しい理解であったり他の言語の構造の理解にもつながる(これがないと寧ろ難しい)ので「やはり国語は全ての基礎」なのだと思います。基礎練こそ至高。また次回。
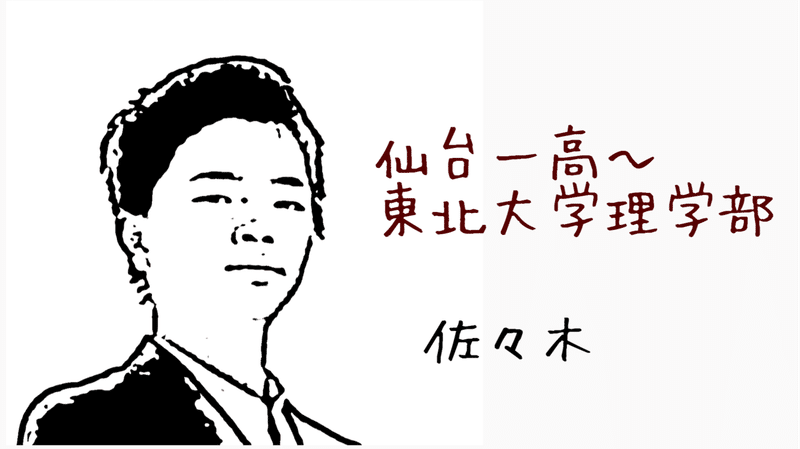
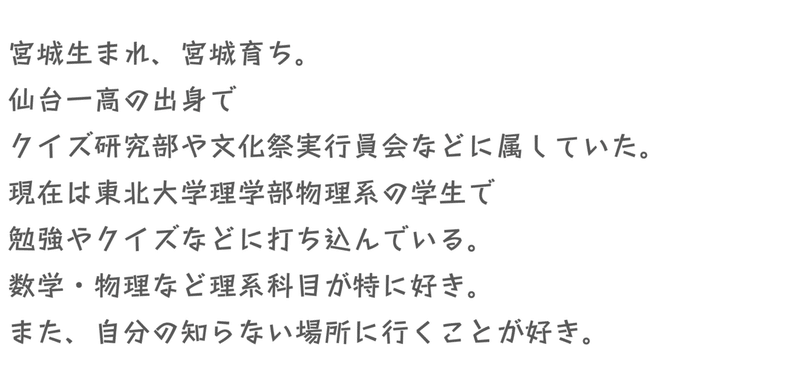
clue zemi の詳細・お問い合わせはこちら↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?