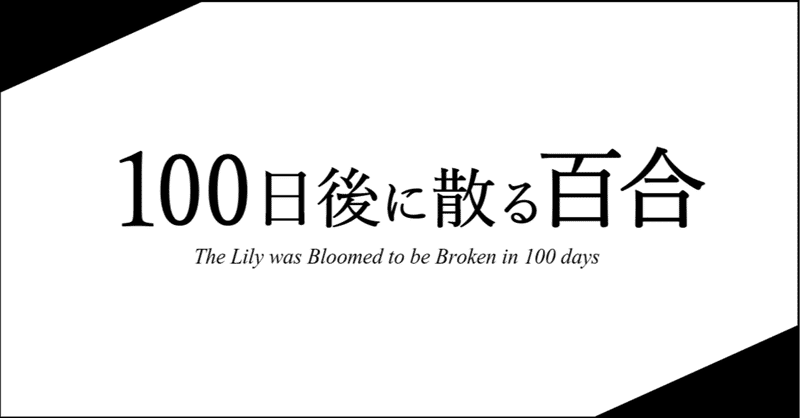
100日後に散る百合 - 52日目
「は、はじめまして!立川咲季です!」
緊張した面持ち。
誰に対しても堂々と、物怖じせずに話すコミュ障お化けの咲季だが、さすがに好きな作家の前ではそうもいかなかったらしい。
「あの、一斗リリ先生は、中学の頃からファンで、すごく好きです!」
「へ~、そうなの。嬉しい」
「えっと、あの、萌花さんとは、お付き合いさせていただいております!」
え、言うの早くない?
うわぁ、熱いな。改めて言葉にされると恥ずかしい。
2人から目を逸らす。
「不束者ですが、よろしくお願いします!」
礼儀正しい。別に咲季はフツツカではない。
「萌花ちゃんと仲良くしてくれてありがとうね、って私が言うのもあれなんだけど」
「いえ、萌花は可愛くて、優しくて、ちょっと不器用なところもあるけどそれがまた愛しくて―――」
「やめて恥ずかしい!!」
必死に止める。
何を言ってるんだ、この子は。
「咲季ちゃんは、萌花ちゃんのどこが好きなの?」
「そうですね―――」
「いずみさんも、やめてください!!」
2人して私を辱めたいんだな。
「それにしても本当に綺麗な子ね~」
いずみさんが骨董を品評するような目で、咲季を満遍なく見ている。
「きょ、恐縮です」
そんなこと言われ慣れているであろうに、さすがの咲季も少し照れていた。
それを誤魔化すように、いそいそと鞄の中を漁って、一冊の本を取り出す。
「あの、僭越ながら、さ、サイン頂けますか……!!」
固く、少し上ずった声。しかし、相変わらず音は通る。
「うん、いいよ~」
いずみさんは、一斗リリのデビュー本『切片』の裏表紙に慣れない手つきでサインをする。
「普段、あんまり書かないからさあ」
サイン会をやる作家も増えてきてるけど、私はあんまりね、と苦笑しながら、咲季の名前も添えて本人に返す。
「うわぁああああ!!ありがとうございますありがとうございます!!!ねえ、萌花、サイン貰っちゃったよ!!」
「よかったね」
咲季の笑顔がいつも以上に弾けている気がする。私もなんだか嬉しい。
「今度新刊出るから、よろしくね。あ、これまだ言っちゃダメなんだけど」
いずみさんはチロっと出す。普段ファンと対面することもほとんどないんだろう、サバサバしているいずみさんだが、テンションが上がっているのは何となく分かる。
その後も少し談笑して、
そろそろ勉強しようかという流れになる。
「いずみさん、この前頂いたっていう紅茶、結構飲んじゃってるけど、大丈夫ですか?」
「うん、いいよいいよ。私はコーヒー派だし」
「酒派でしょう」
「うっ……、その節はご迷惑おかけしました~」
いずみさんはお酒に強い方だが、飲むほどに調子に乗るので加減が分からなくなる。この前の会食で泥酔したのが良い例だ。
「ふふ、仲良いね」
咲季が笑う。その口ぶりは、義理の親子として、というよりは、普通に家族としての感想だったと思う。
「あ、それで、萌花」
「なに?」
はたと、また神妙な面持ちに戻って、私を見てくる。
なんだ。
「えと、お母さんにも挨拶して、いいかな…………?」
私は優しく頷き、咲季を仏壇へ案内した。
演劇のことはよく分からない。
なんとなく「敷居が高そう」というイメージだけある。
咲季から渡されたチケットを見て、そんなことを思った。
「演劇部に指導で来てた先生が出演するの。わざわざ今の住所調べて、チケット送ってくれたんだ」
咲季は、前の学校では演劇部に所属していたらしい。
「本当は、お母さんと観に行く予定だったけど、せっかくだから萌花と行きたいなって」
「うん、ありがとう。演劇って、全然観慣れてないんだけど、大丈夫かな」
「あんまり難しく考えなくていいよ。私もさすがに前衛的なのは分からないし」
そう言いつつ、腕を組んで
「でも確かに、映画とかドラマとは違うもんね。初めてってなると結構抵抗あるかもね」
「うーん、なんか、楽しみではあるけど、着いていけるか不安、みたいな」
「その辺は心配ないよ。観てたら自然と世界に引き込まれてるから。それこそ、映画とかドラマとかよりどっぷりね」
そういうもんか。
「演劇特有の表現とか、演出とか、いい意味でリアリティがないっていうのかな。そういうのは、無理に理解しようとせずに、雰囲気だけでも感じ取ってればいいよ」
語る咲季の目が輝いているような気がして、今の咲季は不満じゃないのだろうかと疑問に思う。
「もう演劇はやらないの?詳しくは知らないけど、スクールとか劇団とか、高校生でも出来るところあるんじゃないの?」
そんなところに答えがあるわけもないのに、咲季はノートをパラパラと捲り始めた。
「うーん、やらないかな。プロになりたいって程でもないし」
「うちの学校に演劇部があったら入ってた?」
「それもどうかな。演劇は好きだけど、部活って、また違うし」
なんか歯切れが悪かった。
あんなに楽しそうにさっきまで話してたのに。
「前の学校でなんかあったの?」
ノートを捲る咲季の手が止まる。
意味のない数式をじっと見つめた後、
「…………黙秘権。萌花は知る必要のないことだから」
私と目を合わせることなく答えた。
私たちのルールは「嘘はつかない。都合の悪いことは、その理由を伝えた上で、黙秘する」というものだ。
もう、私が咲季に踏み込める余地はなかった。
ドンドンドン!!!
突如として、静まり返った部屋にノックする音が転がり込む。
「え、何!?安さの殿堂!?」
「そんなわけないでしょ」
だいたい見当はついている。
「咲季、来たよ」
「えっ、もしかして」
「お姉、開けて」
行雲ちゃんだ。
自分で言うのもなんだけど、私の義妹・行雲ちゃんは、私のことが好きだ。どういう意味で好きなのかは分からないけど。
やや精神面で不安定な行雲ちゃんに、咲季のことを紹介するのは少し憚られた。この前も咲季のことを探られて、ただの友達と嘘をついてしまった。
最近になって咲季が家に来るようになり、鉢合わせしないよう、今まではなんとかなっていたが、もう帰ってきてしまったからには仕方がない。しっかり説明しなければ。
ドア越しに応答する。
「行雲ちゃん、おかえり。今日は早かったね」
「グラウンド、びしょびしょ。中で、筋トレ、部活、それで、終わり」
「そっか、そっか」
「お姉」
「なに?」
「開けて?」
「…………うん、分かった」
咲季には離れてもらい、ゆっくりとドアに近づき、開ける。
「……………………」
明らかな敵意。長く伸びた前髪から覗く目には、確実に何人かヤってきたラスボス感が漂っている。
「ひっ」
さすがの咲季もビビっている。
ここは私が少しでも行雲ちゃんを鎮めなければならない。
「その女、誰」
「こら、行雲ちゃん。初対面の人に向かって、”その女”はないんじゃない?」
「あぅ、ごめん、なさい……」
私も一応、お姉ちゃんだ。こうやってお叱りするのに適切な立場ではある。これで、ちょっとずつ行雲ちゃんの熱が冷めればいいのだが。
「じゃあ、ほら、紹介するから」
そう言って、咲季に促す。
いつの間にか正座していた。
「えと、立川咲季です」
いずみさんの時と同じくらい緊張してる。
適切な言葉選びをしないと、何を言われるか分からないので、打ち合わせは入念に行った私たちだ。
「おね……、じゃなくて、萌花さんの友達」
”お姉ちゃん”を使うと、「どの分際でお姉ちゃん言うとるんやワレ」みたいなことになるだろうと思って、避けようと打ち合わせた。
「そして…………彼女、です」
その瞬間、行雲ちゃんの顎がぐいっと上がる。瞳孔は広がり、完全に血走っている。
「お姉、彼女?ねえ、彼女?」
「そ、そうだよ」
指をさすな、指を。
「ゆくも、お姉、好き。離れる、嫌だ。取られる、泣く」
声はすっかり震えていて、決壊寸前のようだった。
「違うの、行雲ちゃん!」
そこで咲季が、少し攻めのトーンになる。
「確かに私は、萌花の彼女。だけど、それは行雲ちゃんから萌花を奪うわけじゃない」
行雲ちゃんに反論される前に、やや早口でまくし立てる。
「行雲ちゃんが萌花を好きなのは知ってる。でも私も同じくらい好き。でも、行雲ちゃんの心の拠り所として、萌花が必要なことも分かってる。だから、あなたが萌花に構ってほしい時は、正直に萌花に言って。その時は私も譲るから。私も萌花のこと大好きだから、行雲ちゃんの気持ちも少しは分かるの」
あれ、ちょっと待ってこれ。
「萌花が私と付き合っているのは、別に行雲ちゃんを捨てたわけじゃない。ちゃんと行雲ちゃんのことも大事にしてるよ。でも、萌花も私を選んだ。萌花も私のことが好きだから。萌花の選択を尊重したい気持ち、行雲ちゃんなら分かるよね!?」
これ、私がめちゃくちゃ恥ずかしいやつだ!!!
「し、知らない!!」
と、思いきや行雲ちゃん、必死の抵抗。
「ゆくも、あなた、知らない。フツツカ者。たわけ者。うつけ者」
「お漬物じゃないよ!!」
言ってねえよ。
「行雲ちゃんが大好きな萌花のこと、責任をもって私が幸せにする!!萌花を悲しませたりなんて、絶対にしない!!それは約束する!!病める時も健やかなる時も!!」
やめて、私で争わないで!!
「だから、行雲ちゃん、萌花を私にください!!」
「いやあああああああああああああああああああああああああああああ」
だめだ。
咲季は間違えた。行雲ちゃんは落ち着くどころか、ますます興奮してしまった。
「いや!!お姉!!私!!ずっと!!一緒!!一生!!永遠!!」
ワンフレーズごとに恐竜のように突進し部屋に入って来た!!
「ゆ、行雲ちゃん!!」
今にも咲季の首の根を噛み千切らんとした時、ユクモザウルスの健脚が、テーブルを蹴った。
パシャン。
パリーン。
「あ」
紅茶が盛大にぶち撒けられ、私のカップも割れてしまった。
しばらく私たちはどうすることも出来ずに、ただそれを見下ろしていた。
だが、
「いやあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ」
再び、いやさっきよりも悲鳴に近い戦慄きが、響く。
「ごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさい!!!」
行雲ちゃんはその場に跪いて、狂ったロボットのように謝罪を繰り返す。
咲季は何が起こったか分からず、戸惑っている。
「どうしたの!?」
すると、いずみさんが駆けつけてくれた。
「多分、カップです……」
行雲ちゃんは、いずみさんの元夫に虐待をされた過去がある。どこまでされたとか私は知らないのだが、彼女のこういう姿を見てしまうと、トラウマが少なからず残っていることは容易に想像がつく。きっと虐待されているときに、カップが割れるシーンもあったんだろう。
「ああああああああああああああああああああああああああああごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいううううううううううううううううううううううううううううう」
こうなると、私でもどうすることもできない。
「薬、持ってくる」
「お願いします」
いずみさんを見送って、さて、どうしたものかと。
「あ、ごめん、咲季」
「ううん、大丈夫…………」
まあ、初めて見たら衝撃だよなあ。
すると、おそるおそる立ち上がって、行雲ちゃんの傍に向かう。
「え、咲季?」
あんまり近づかない方が、と言いかけて、
「ごめんなさいごめんなさいごめんなさ―――」
咲季は、優しく行雲ちゃんを抱きしめるのだった。
すっかり落ち着いてしまった行雲ちゃんは、すべてを咲季に預けるように力を抜く。
私でもどうにもできなかったのに。
いや、私もこうしてハグをしたことはなかったか。
「何?なにごと?」
いずみさんが戻って来た。
「止まりました…………」
「えぇ」
咲季の胸の中で、行雲ちゃんは安らかに眠る。
「ママ…………」
明らかにいずみさんではなく、咲季に言ってる感じだった。
「いやそれは私が泣いちゃうんだけど」
「あはは」
咲季も苦笑いだった。
とりあえず、いずみさんは行雲ちゃんを連れて外に出た。走るのが好きな行雲ちゃんは、広いところの方が機嫌がよくなるからだ。
とりあえずは、一件落着した……のかな?
「ねえ」
「何?」
「恥ずかしい。あっち向いてて」
「ずっと思ってたけど、萌花っておっぱい大きいよね」
「うるさいなあ!」
「いや褒めてるんだよ」
「いいから、こっち見ないで。それか出てって」
行雲ちゃんの零した紅茶がブラウスにかかったので、着替えることにした私だが、咲季がひたすらに見てくる。やめてほしい。
もちろんスカートは履いている。
「ねえ、いくつ?」
「なにが」
「おっぱい」
「ええ……言わなきゃダメ?」
「うん。萌花のこと、もっと知りたいなあ」
そういうのは、こういう時に使うセリフじゃないだろ。
が、おかまいなしに近づいてくる咲季。
「ねえ」
「…………D」
「ちょっと、何で嘘つくの」
「なんでバレるの!?」
「レズの目なめんなよ~」
関係あるのか、それ。
「Eでしょ。いいなあ。Eだけに」
「からかってんじゃん!」
「ごめんって」
ぎゅ。
後ろから抱かれる。
「これで許して?」
「は、はぁ?」
とはいえ、ブラウスを脱いだ私の素肌には、衣擦れの感触とか、咲季の体温とか、いつも以上に感じられて少しドキドキしてしまう。
「萌花の身体、柔らかい」
「咲季みたいに細くないですからねー」
「ふふ、可愛い」
嫌味が通じない。
ふに。
「ひゃんっ!!」
「すごい、マシュマロみたい」
「さ、触んないでよ!!」
ブラの上から咲季の手が覆いかぶさる。
くっそ~、レズってこうなのか……
「萌花、好きだよ」
「そんなんで誤魔化されないから!!」
と言いつつ、私はニヤニヤしていた気がする。
「別に誤魔化したい訳じゃないよ。本当に好きだもん。愛してる」
やめろぉぉ。
「ね、重くないの?」
咲季が私の胸を下から持ち上げる。
「重いよ。肩凝る。走るのやだ」
「走るの嫌なのは、萌花が運動音痴だからでしょ」
「うるさい。怒るよ」
「ごめんね、萌花、好きだよ」
またそうやって…………
「ねえ、もういい?」
「何が?」
「ハグ」
「え~、もうちょっとこのまま」
「私、そろそろ着替えたいんだけど」
「萌花の身体、綺麗だよ?」
「そういうことじゃない」
が、一向に開放してくれる気配がない。
まあ、しばらくこうしてれば、気が済むだろう。
ていうか、早くしてくれないと、私も、その、キスとか、したくなっちゃうんだけど。
「そういえば今日、イヤリング着けてなかったね」
咲季がうちに来るようになってから、せめて2人でいる時は着けていたのだが、
「じゃあ、今、私が着けてあげる」
かぷ。
「ひぃんっ!?」
耳たぶを噛まれる。
「いっぱい着けてあげるからね」
かぷ。
かぷ。
「ゃん、さき、やめっ」
かぷかぷ。
はああ、何だこれ。
甘噛みされてるだけなのに、変な気分になってくる。
「もう、咲季、やめてってば」
「へけっ」
「へけじゃない!イヤリング着ける訳でもないし」
「ぎゅ~」
「誤魔化さないで」
「かぷ」
「かむなぁ」
「ぺろ」
「あぅ、な、なめるなあぁ」
粘っこく、柔らかい舌先が、耳の淵をなぞる。
囁きで、ハグで、キスで、覚えてしまった腰の疼きが、一気に蘇ってくる。
私の耳の味を確かめるように、ゆっくりと動く。
「萌花、おいしい」
少し荒くなった息が耳に当たるたび、頭の中の理性がどんどん吹き飛ばされていく。
だめなのに。こんなの、だめなのに。
「ぁぅ、ほんとに、待っ、さきぃ」
「もえか、かわいいよ。だいすき」
隙間だらけの脳内に、甘い言葉がどんどん染み込んでくる。
私の頭はスポンジみたいになって、嫌というほどそれを吸収して、自分に取り込もうとしてしまう。
「ねえ、もえかは?」
優しい耳舐めが絶えず続く。
ちょっと焦れったい、とさえ思う。
「もえかは、私のこと、すき?」
何だかよく分からなくなってるのに、はっきりとその言葉は浸透してくる。
考えなくても出てくる。
「ぅ、ん、すきぃ」
けどもう限界だ。
これ以上は、これ以上は。
「ね、もぅ、いいで、しょっ、そろそ、ろ、やめっ、ぁぅ」
「はぁ、はぁ、そうだね」
そして、
やっと、咲季の舌が離れる。
体感で5分くらいだったか。
「そうだよね、こんなに焦らされたら、萌花も我慢できないよね」
な、なにを言ってるんだろう。
「じゃあ、いくよ」
甘い、悪魔のような囁き。
「本気で」
「えっ!?」
束の間、さっきの舌とは思えないほど熱く、湿ったキスが耳元で繰り返される。
「ぃゃぁ、あぅ、だめ、だってばぁっ」
ぞりぞりと、溝と穴と耳たぶと耳の裏を這いまわる咲季の舌。
唾液のぴちゃぴちゃとした音がダイレクトに頭の中に響く。
ピンク色の液体を注ぎ込まれている。
「はぅあぁ、らぁ、ぅぅっ、あぁぅ」
「もえか、えろいね」
えろくない。反論したい。
けど、私もこんなに熱くなって、ぼーっとして、びくびくして、これで興奮してないなんて言えない。
ていうか、そうか、私は興奮してるんだ。
「ここ、すき?」
咲季はその一点に集中するように、細かく舌を動かす。
「ぁぁ!!それ、や、やばぃ、っ、はぁ」
それがもうどこなのか私にもよく分からない。分からないけど、とにかく気持ちが良いことだけ分かる。
息継ぎするのも忘れたみたいに、れろれろれろという音がずっと聞こえる。
咲季が、私の耳を舐めるのに一生懸命なんだ……
なんだかそれが少し愛らしく感じてしまう。
だから、いつの間にか身体を触られているなんて、気付かなかった。
「無理ぃ、むりだからあぁ」
舌は繊細に動いているのに、咲季の手は大胆に私の素肌を弄っている。
あんまり胸を触ってこないのが、本当にずるい。
ぐちょぐちょになった耳から飽和するぐらいに快感が与えられて、私の脳は完全に溶けてしまいそうだった。
「だめぇ、だめえぇ」
消え入りそうな声で、表面上の抵抗しかできない。
細く少し冷たい指は、お腹とか、お尻とか、背中とか、まるで花を扱うように丁寧に撫でた。
時折、太ももを触るために前かがみになるのが、咲季の本能的なものを感じさせる。少しドキドキする。
でも、なんだろう。本当にこのままだと自分がおかしくなりそうで、それを超えてしまうのが怖い。
「はぁはぁ、あ、ぃや、んっ」
こんなに発情してしまって、私は大好きな咲季の前でどうなってしまうか分からない。
本当に、もう何かが来そうになっている。
どうしよう、怖い。
「もえか、すきだよ」
激しい水音の渦に飲まれている。
溺れてる。
もう分かんない。
でも、怖い。
これ以上、咲季の前で壊れたくない。
だから、
「いやぁっ!!」
咲季の手が、私の胸に直接触れようとした瞬間、
強く、彼女を押しのけてしまった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
