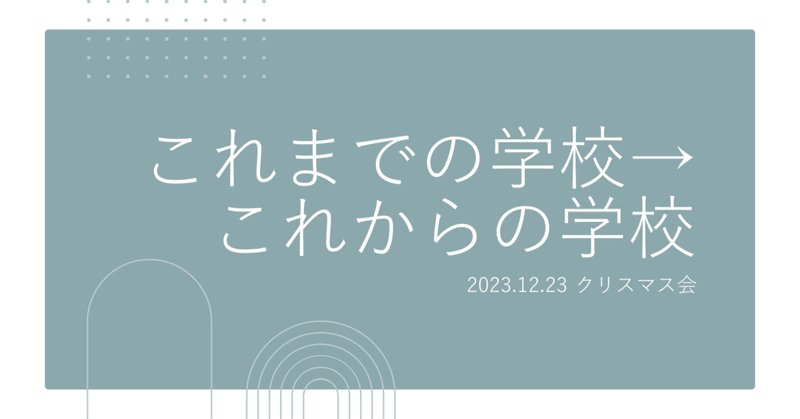
これまでの学校→これからの学校
また来たぜ、大阪。
12/23(土)に、
大阪(西区南堀江)のライブハウス鹿音のクリスマス会に参加した。
このクリスマス会には、
「お話会」
があって。
僕は学校教育について、
40分くらいの講演をしました。
持ち時間を少しオーバーしましたが、
無事に話し切ることができて、
ほっとしました。
あとで振り返ろうと、録音しようと思っていたんですけれど、録音ボタンを押すことを、すっかりと失念。ICレコーダーを用意して、目の前に置いたんだけどね。
お話会は勢いで
話すための、ベースになる資料は、
chatGPTも活用して用意しました。
でも話すときは、
話の勢いとリズムを大事に。
完全にアドリブなので、
再現はできないなあ。
ちなみに、
僕は、資料を
「頭の中の引き出しに置いておく」
というイメージで読み込みます。
話しているときは、
聴いている方の表情や様子を見ながら、
どの引き出しを使うか、
考えながら話をしています。

用意した資料の一部を公開
⒈ 総合的な学習・ゆとり教育
1945年頃、1990年代、および2020年代の日本における総合的な学習や探究のアプローチを比較する際には、各時代の教育政策や社会的背景を考慮する必要があります。
✅1945年頃の総合的な学習
1945年頃の状況
この時期の日本教育は、戦後の教育改革の最中でした。しかし、現代の意味での「総合的な学習」の概念はまだ確立されていませんでした。教育改革の焦点
教育の焦点は、民主的な価値観、基礎学力の強化、そして戦前の国家主義的な教育からの脱却にありました。
✅1990年代の総合的な学習
ゆとり教育の導入
1990年代後半にゆとり教育が導入され、その一環として「総合的な学習の時間」が1998年に設けられました。目的と内容
このアプローチの目的は、学生の創造性、自主性、思考力を育むことにありました。生徒が自らの興味や関心に基づいて学習する機会が提供され、カリキュラムは柔軟に設計されました。
✅2020年代の総合的な探究
アクティブラーニングの推進
2020年代の教育方針は、アクティブラーニングと主体的・対話的で深い学び(アクティブ・ラーニング)を重視しています。探究学習の強化
生徒たちは、実践的なプロジェクトや課題解決活動を通じて、総合的な探究能力を養います。このアプローチは、批判的思考、問題解決能力、情報リテラシーを重視しています。
これらの比較から、
日本の教育システムが時代とともに進化し、
学生の自立した『学習能力』と
『総合的な思考力』の育成に、
ますます重点を置くようになったことがわかります。
1990年代のゆとり教育における総合的な学習は、この動きの始まりであり、
2020年代にはさらに洗練された形で探究学習が推進されています。

⒉ 受験戦争・登校拒否・校内暴力
1970年代から1980年代の日本では、教育システムにおけるいくつかの重要な問題が顕在化しました。
特に、受験戦争、登校拒否、校内暴力といった現象が社会的な関心を集めました。
✅受験戦争(1970年代~1980年代)
背景
この時期、日本の大学進学競争は極めて激しくなりました。これは、高校生の数の増加と大学進学への志向の高まりによるものでした。結果
学生とその家族に多大なストレスをもたらし、学業成績の圧力、進学塾への依存、長時間の勉強といった現象が見られました。教育への影
この「受験戦争」は教育システムに対する批判を呼び、その後の教育改革の動機の一つとなりました。
✅登校拒否(1970年代~1980年代)
現象の増加
学校に対する圧力やストレス、学校環境に対する不適応などが原因で、登校拒否する子供たちが増え始めました。社会的認識:
当初は個人の問題として扱われがちでしたが、次第に社会的な問題として認識されるようになりました。対策と支援:
学校や地域社会において、登校拒否の子供たちを支援するための取り組みが行われるようになりました。
✅校内暴力(1970年代~1980年代)
問題の増加
学校における暴力行為が増加し、社会的な懸念となりました。原因
学校における圧力、教師と生徒間のコミュニケーション不足、家庭環境の問題などが原因として指摘されました。対応策
学校側では、カウンセリングの提供、教育環境の改善、教師の研修など、校内暴力を減少させるための対策が講じられました。
これらの問題は、
日本の教育システムと、
社会における深刻な課題を浮き彫りにした。
後の教育政策の変更や、
学校環境の改善の契機となった。
また、
これらの問題は子供たちの心理的な健康と
福祉に対するより大きな配慮を促しました。
こんな感じで、
実際に僕が持っている資料や、
ChatGPTを使って整理させた資料を用いた。
上記の内容だと、
2〜3分くらい
は、話していた気がするなあ。
いずれにせよ、楽しく話せたし、
ご感想をいたただきましたが、
みなさん、聞き入ってくださいました。
本当にありがとうございます!!!!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
