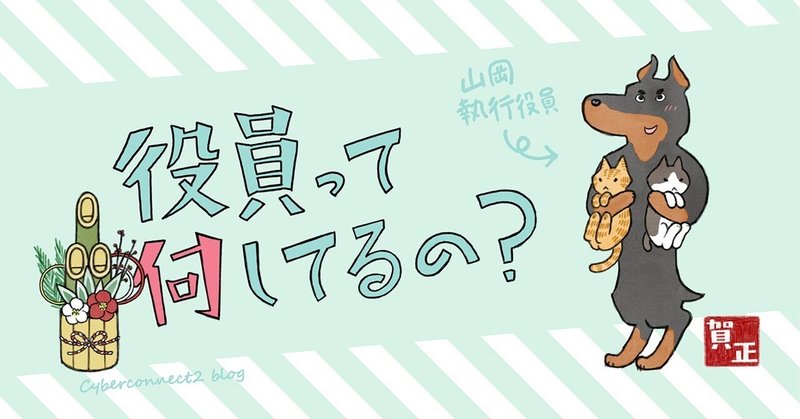
ゲーム開発のマネジメント「現状を正しく把握する」ってどういうこと?
こんにちは、サイバーコネクトツーの山岡です。
前回は『プロジェクトの火消し』に必要な7つのステップについてご紹介しました。
今回は「プロジェクトの火消し」の記事でも紹介した「現状を正しく把握する」を自身の経験をもとに整理、言語化しつつ、具体的に掘り下げてみたいと思います!
ただ、日頃マネジメントをされている方にとっては「あたりまえ」の話ばかりなので恥ずかしい限りですが、ゲーム開発に関わる方、駆け出しのリーダーの方のお役に立てれば幸いです!
1.正しい現状把握とは何なのか
まず「正しい●●」「正しく●●」というけれど、じゃぁその「正しい」ってなんだよ?ってなると思います。
正しい=理にかなっている、事実に合っている、正確である、と置き換えられるので、正しい現状把握=事実にあった正確な現状把握となります。
よく現場で起こる問題として
遅れを挽回するために人の投入を行ったが、いつまでたっても進捗が改善されないとか、順調と報告していた要素が一転ダメ出しになったとか、急転直下で仕様をオミットすることになったとか。
実は、物量の問題と思っていたのが体制の問題だった。
実は、商品担保が出来ていない状態だった。
実は、予算、スケジュールを考慮していない状態だった。
などなど、問題に対応したつもりだったけど実は他の部分が原因だった、実は重要なポイントを見逃していたということが多いです。
現状把握って出来てるようで意外と不十分なことが多くて、故に間違った指示や非効率な計画が進んでしまうのです。
*****
では、何を把握しなければならないのかですが、ゲーム開発のプロジェクトはざっくり以下の3要素で構成されています。
①与えられた納期、予算
②商品力を担保する物量とクォリティ
③上記を達成するための人(体制)
プロジェクトを成立させるには
物量 × クォリティ = 人 × スケジュール <= 納期・予算
が成り立たないといけなくて、プロジェクトの構成要素の状態が把握できている(できる)=正しい現状把握になります。
なので、それぞれの構成要素の状態や問題、課題を把握した上で判断やリカバリーを行えば脇道に逸れることなく解決に向かいやすくなるのです。
2.現状把握のための事前準備
さて、現状把握するにあたって情報を集めないといけないわけですが、やみくもに資料をあさったり、何も準備しないまま担当者にヒアリングすると時間ばかり掛かってしまい非常に非効率です。
まずは最低限必要な資料をあつめて、情報の過不足や実際との乖離などを把握、理解し、プロジェクトの全体像をつかむことが重要です。
各開発会社やプロジェクトによって呼び方や管理方法が異なるかと思いますが、ゲーム開発の構成要素の把握に必要な資料や情報は以下になるかと思います。
①与えられている納期、予算
・グランドスケジュール
・契約情報
・制作工数情報
②商品力を担保する物量とクォリティ
・タスクリスト、進捗情報
・制作スケジュール
③上記を達成するための人(体制)
・制作体制図
・スタッフリスト(内部、外部)
まずは全体像をつかむことが目的なので、資料が無いなら無いでOK。また、現状が反映されていない、乖離があるでもOKです。
逆を言えば、資料や情報が無かったり乖離していたりすることが、そのプロジェクトの問題となり、管理体制の課題を把握することができます。
3.資料の分析と課題、問題の洗い出し
資料や情報を集めたら、資料を読み込んで分析を行い、課題や問題の洗い出しを行います。それぞれの資料を分析する上でのポイントをまとめてみます。
●グランドスケジュール
グランドスケジュールとはクライアントとすり合わせた発売までのロードマップ、マイルストーンや制作に影響するローカライズやアフレコ、監修といったスケジュールが明記されたものを指します。
当然、プロジェクトの制作スケジュールはグランドスケジュールの目標設定を達成する為のスケジュールになっている必要があります。
なので、グランドスケジュールが最新でない、要素が不足している、成果物提出のスケジュールが明確でない場合は、現場レベルのスケジュールは怪ししくなりますし、セクションごと(横)の連携も取れていないことが多いんじゃないかなと思います。
●契約情報
ゲーム開発ではクライアントと約束している納期、予算、成果物設定が必ずあります。実際に制作する物量やスケジュールはそれらを果たすものでないといけません。
納期や予算の他に対応する言語数、プラットフォーム、リージョン情報も確認し、それらがタスクや制作スケジュールに反映されているかを確認します。
●制作工数情報
プロジェクトが想定している総予算と今までに消化した予算情報です。
肝心なのは「あとどのくらい予算が使えるのか」で、消化工数、想定の総工数が現状に即した内容になっているか、契約情報と差異が無いか、あたりを押さえておく必要があります。
●タスクリスト
●制作スケジュール
言わずもがなですが成果物を分解したタスクとそのスケジュールであり、開発スタッフはこれらの情報を元に日々制作を行います。
細かく確認したり完全な状態を求めると時間が掛かりますので、第一段階ではどの程度まで網羅できているかなど以下のポイントを確認すると良いです。
・どういった方法で管理されているか
・だれが更新をおこなっているか
・最新の状態に更新されているか
・タスクの洗い出しがなされているか
程度にもよりますが資料が存在しない、タスクの洗い出しや管理がなされていない場合はかなり深刻です。管理者やリーダー層の意識や体制面に問題がありますので、指示命令系統まで踏み込んだ確認が必要になります。
●制作体制図
●スタッフリスト
プロジェクトのチームは「人」で構成されており、ゲーム開発のコストのほとんどは「人」です。プロジェクトが炎上していたり、うまく進まない場合は必ず「人」の問題があります。
昨今のゲーム開発では50名、100名を超える規模の開発が多く、いわば中小企業を経営しているようなもの。企業経営で責任の所在や指示命令系統が曖昧な場合すぐに経営が傾いてしまいます。
なので、プロジェクトにおいても制作体制図やスタッフリストから、人数、役割、責任者やリーダー、指示命令系統を確認する必要があります。
物量に対して人が多すぎる場合は、非効率な開発になっている可能性がありますし、物量が減らないどころか増えている場合は、指示命令系統がうまく機能していない可能性があります。また、未決定項目が多い場合は、リーダー層の決定フローがうまく機能していない可能性があることが多いです。
また、体制図に存在しないがプロジェクトに大きく影響しているメンバーが存在する場合も、責任の所在や意思決定フローが曖昧になっていることも多いです。表に出ている体制と実際の体制との差異を確認することも重要です。
4.現状把握のヒアリングと注意点
資料や情報の分析と課題、問題の洗い出しができたら、プロジェクトメンバーへのヒアリングを実施して事実確認を行います。
この事実確認のヒアリングですが、いくつかの注意点があります。
やり方を間違えるといつまでも正しい現状把握に近づかず、解決に向けた判断を誤ってしまいます。以下にヒアリング時に注意すべきポイントを挙げてみます。
1.追及はしない
外見が強面の自分が言うのもなんですがヒアリング時は出来るだけ柔らかく、粛々と行うように心がけます。追及の姿勢でヒアリングしてしまうと問題追及されている意識から構えてしまい事実が出てきにくいことが多いです。
また、頭ごなしに「なにやってんだ?」という雰囲気でヒアリングすると保身の意識が強くなってしまい事実が出てきにくい状況になってしまいます。
あくまで、事実を確認し一緒に解決したい、良い方向に導きたいという姿勢で臨むことが大事だと思います。
2.ヒアリング結果を鵜呑みにしない
聞こえが悪いのですが、ヒアリングした内容を鵜呑みにしてしまうことは、結果正しくない現状把握をしてしまい間違った判断につながってしまうことが多いです。
たとえばヒアリングした内容が「進捗が遅れているのはスタッフのスキルの問題であり、スタッフを入れ替えないと改善されない」と聞いた時、それは問題だから早急に対処しよう、となることが多いのではないでしょうか。
しかし、このケースの場合、
「指示の出し方が曖昧になっている」
「明確な納期が担当者に伝えられていない」
「当初予定していたタスクと異なる内容になってしまっている」
が根本原因であることも多く、スタッフの入れ替えでは改善されない可能性もあります。
確かに「進捗が遅れている」という事実はあるものの、その原因が本当にスキルの問題なのかは担当タスクや進捗情報、制作体制図上の指示者などを総合的に確認することで裏付けることが出来ます。関連するタスクや進捗情報が無いのであれば、あくまで意見であり裏付けが確認できるまで判断は保留にすべきです。
*****
ヒアリングによる事実確認を行うことで、資料から洗い出した不明点の穴埋めや問題、課題の答え合わせが出来ますので、事実にあった正しい現状把握にかなり近づきます。そして、整理した問題、課題を「課題リスト」にまとめて、対策のフェーズに移行します。(ここからが問題解決の本番になります…)
まとめ
以上、ゲーム開発における「現状を正しく把握する」について経験やノウハウを元に見解をまとめさせていただきました!マネジメント論としては初歩的な内容ではありますが、問題解決に苦労しているリーダーも実際には多いのでヒントになれば幸いです。
実際の現場では様々な要素が絡み合っていて、一筋縄ではいかないし、うまくいかないことも多いです。ただ「事実を正確に把握する」ことで問題解決への選択肢が大幅に増えることも確かです。
本記事ではプロジェクト全体のスコープでしたが、セクションなどの小さな単位での管理でも有効だと思います。
本記事がゲーム開発に関わる方に一部でもお役に立てるのであれば本当にうれしいです!お読みいただきありがとうございました!

サイバーコネクトツー 執行役員
山岡 寛典
