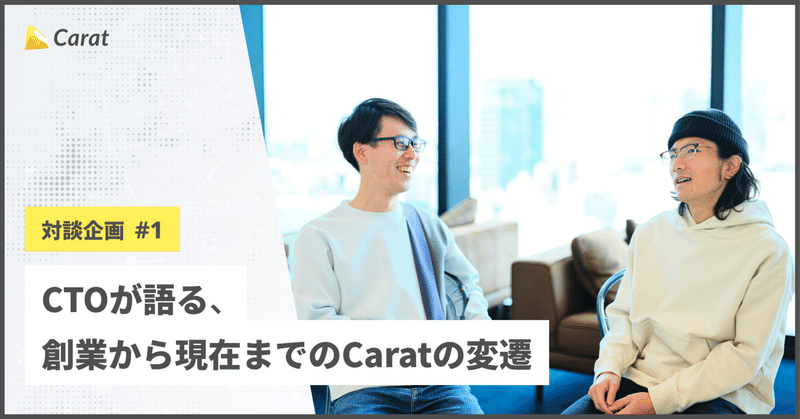
【対談企画#1】 CTOが語る、創業から現在までのCaratの変遷
株式会社Caratは「新たな価値を発明し続ける」をミッションに2023年12月から8期目を迎えました。7期目は会社としてミッションやバリューを一新し、ARRの伸びやLLMを用いた「AIジョブサーチ」のローンチなど多くの変化がありました。今回は創業期から現在までのCaratを知る、CEOの松本がCTOの斎藤に、Caratの過去、現在、そして8期目やその先の未来がどのように変化していくと考えているか、対談形式のインタビューを行いました。
対話者
CEO/松本(@Na0kiMatsumoto)
CTO/斎藤(@saitoxu)
松本:今日はよろしくお願いします。改めてだけど、簡単にこれまでの経歴から話してもらえますか?
斎藤:京都大学大学院を卒業して、新卒で松本と同じIT企業に入社して、最初のキャリアとしては業務用Webアプリの開発をしていました。その後2016年12月に株式会社Caratを共同創業して、現在に至るという感じですね。

松本:社会人になってからの社歴は2人とも同じだしね。最近はどの辺にAll in ※していますか?

斎藤:最近は昨年ローンチしたAIジョブサーチが6割、採用が1-2割、その他メンバーとの1on1や他プロダクトの活動という割合ですね。AIジョブサーチでの内訳は機能開発が5割ほどで、あとはレビューしたり、ミーティングやメンバーとの1on1に時間を使っています。
特にフルリモートでの環境なのでメンバーとのコミュニケーションを促進する1on1は大事にしています。頻度に差はありますが、正社員メンバーも業務委託メンバーも、エンジニアとは全員1on1を実施しています。
創業から現在まで。会社やCTOとしての変化
松本:Caratも創業してから現在が8期目。創業してから色々なことがあったと思うけど、CTOとしてどのような変化がありましたか?
斎藤:最近やっと会社っぽくなってきたなという印象。創業事業であるアグリゲーション求人アプリGLITから別事業へリソースを割き、求人Hubも伸びてきて最近はやっと経営っぽいことを取り組めるようになっています。GLITに集中していた頃はこれまでゼロから事業を立ち上げるという経験がなかったので時間がかかってしまいました。
創業期からGLITに注力していた時は会社経営というよりとにかくプロダクトにフォーカスしていた時期で、2022年頭くらいまではその状態でした。採用企業向けのサービスがあったり、GLITの中でも複数プラットフォームがありましたが、基本的にはGLITにフォーカスをしていました。
松本:CEOとしても資金調達のための仕事が今振り返ると多かったかもしれないです。まだ事業で稼げていない時期で売上も小さいから人件費もまかないきれない状態だったので、この時期は100%ユーザーを向いた仕事はしづらかった。今より朝令暮改も多かったと思いますね。今は事業も伸びてきて営業キャッシュフローも生み出せているのでしばらくはこのままでも、お金のことを強く気にしなくても大丈夫になってきたので、以前よりもユーザーを向いた仕事もできるようになってきたなと感じてますね。
エンジニアチームの変遷
松本:これまでの会社としてのエンジニア組織の変遷について振り返ってもらえますか?
斎藤:現在はエンジニア正社員が2名、業務委託が4名、自分入れて7名のチームです。創業してから今が一番多い人数で、今後も採用活動により組織は拡大していく想定です。創業後からしばらくの期間は、3〜4名でずっと推移していました。副業含めての人数で3−4名なのでスループットとしては今より少ない時期がほとんどでした。2023年に正社員のエンジニアメンバーとして、望月さん・脇山さんが入社してくれました。昨年くらいから、コミットメントの厚い人をなるべく採用する方針にしています。
松本:会社のフェーズが変わり、副業での働き方と親和性が以前より下がったのが大きな変化かもしれませんね。最初はやることがわからないから、探索フェーズで副業の人のフィットもあったと感じています。最近はやることがより明確になってきて、事業へのコミットが必要になってきています。そのためエンジニアに限らず社員でコアメンバーを揃えていこうとなったかなと思います。
あとはシード期に近い時は社員だとシニアなエンジニアの方は採用しづらかったが、業務委託で非常に経験が豊富な方に参画頂いて、事業も成長できています。そこにエンジニア社員メンバーが昨年から加わってくれています。自分の成長や取り組みが会社やプロダクトに直結するので、会社を伸ばすぞという考えを持ってコミットしてもらえるのは良い状態になっているなと思っています。

松本:エンジニア組織の話に戻すと、うちはプロダクトが複数あるけどエンジニアチームはどのように分けているか説明してもらえますか?
斎藤:現在は事業でチームを分けています。事業同士・開発チーム同士の連携については現在考え中。会社も今の規模だとチームが分かれていても全員の顔を認識できており、事業をまたいだ連携はそこまで必要性は感じていないですね。
例えばAIジョブサーチではメンバー同士でも相互1on1をして、チームビルディングの最低限のところは抑えられています。現状で強く課題がある訳ではないですが、今後メンバーが増えていく段階で検討していきたいと思っています。
松本:フルリモートの環境で1on1なども活用してチームビルディングもできている感じだと思うけれど、他に何か特徴的なことってありますか?
斎藤:フルリモートだからというのは特にないですが、2023年の11月末くらいに一度ハッカソンを実施しましたね。AIジョブサーチでOpenAIのAPIを使っているのですが、当時OpenAIが新しい機能をリリースしたので、早速使ってみようということでAIジョブサーチの開発メンバーで実施しました。メンバーが近くに住んでいたのもありオフラインで実施しました。
ハッカソンの言い出しっぺは自分でしたが、当時入社したばかりの脇山さんにも手伝ってもらって開催することができました。望月さんはあまりOpenAIのAPIに触ることが少なかったですが、LLMが関わる事業でキャッチアップするのにいい機会だなと思い、きっかけづくりとして開催できてよかったと思っています。今後も正社員エンジニアのメンバーが増えていく中で開催していきたいなと思っています。
CTO目線で各事業をどう見ているか
松本:CTO目線で各プロダクト・事業についてはどう見えている?
斎藤:HR DXは利益も出せており、堅実に進められていると思います。エンジニアのメンバー視点でも、直接的にお客さんと接点を持つ良い機会になっているのかなと感じています。
求人Hubはかなり順調だと思います。エンジニアは川口さん、高井さんが見てくれているので心配がなく、最近参画頂いた千田さんも含めてシニアなメンバーが揃っているのでいいエンジニアチームだと感じています。
※川口さん、高井さん、斎藤のインタビュー記事はこちら
AIジョブサーチは昨年10月に入社した脇山さんが早速活躍してくれています。フロントエンド開発を主に担当していた望月さんも最近はバックエンドの開発にも加わるようになり、チームとしてより良い状態になってきました。あとは事業・プロダクトをここから更にどう伸ばしていくかですね。
チームの展望としてはLLMを使っている以上、生成AI/LLM界隈でよりプレゼンスを発揮していけるチームにしていきたいです。プロダクトを作り込んでいく過程で結果的に使わなかったとなる可能性もあるけど、そこにチャレンジしていきたい。今はOpenAIのAPIを使っていますが、他のオープンソースのものを使ったり、もしかしたら自社で作ったりなど、必要性を持って取り組めると良いなと思っています。
松本:AIジョブサーチについては、この領域にいる人たちがまだまだ難さを感じていると思います。ChatGPTですら、まだまだマジョリティが使っているかというとそうではない。AIチャット系は使う人に依存するサービスなので、そもそもの難しさがあるとは感じています。
5年先のUXを作りに行くのか、既存のUXに合わせるのかという難しさ。成功事例や正解がまだない中で、数年先のスタンダードを作りに行っている感じですね。
各論ではAIに指示を与えればUXも可変にできるが、可変にすると難しいし、可変にしないと既存のプロダクトっぽくなっていくので塩梅を考えたりでUXの部分に難しさはあるものの、そのチャレンジ自体にプロダクト作りの楽しさがあると思いますね。
会社全体では、求人Hubが営業キャッシュフローを生み出せていて、有意義に新規事業にチャレンジできるようになったのが大きいです。安心感を持ってチャレンジできるようになったのはいい状態になってきた感じがしますね。あとは世にあるサービスをパクったものではない、会社のミッションに繋がる「新しい価値の発明」に繋げているのが、大変だけど面白い点だと感じています。
過去でいえばGLITにチャレンジしたからこそ求人Hubができたので、何も残らないことがないので、心配なくチャレンジできます。AIジョブサーチに向き合っていれば、今後の事業展開に必ずつながっていくと信じられているのが今の状態かなと思っています。

Caratで働く魅力
松本:Caratで働くやりがいや魅力について教えてもらえますか?
斎藤:事業の生死に直接関わる点が面白みで、このフェーズならではだと感じていますね。企画のところから関われるし、早く作れば早くユーザーに価値を届けられる。その分事業の成長に跳ね返り、自分の対価として返ってくる点が面白いんじゃないかなと感じています。 ヒリヒリする感じというか、事業が成長しないと自分たちの給与も上げられなくなってしまうので、この点が人に依ると思いますがチャレンジングで面白いのかなと思います。
あと、これから経験をより積んでいきたいという熱意のあるメンバーにとっては色々なことを学べる環境なのかなと思います。 自分も創業当時は若かったですが今はある程度経験を積んできた自負がありますし、他の経験豊富なメンバーもサポートしてくれるので、成長意欲のある方にとっては良い環境になってきているかなと思います。
松本:Caratでできるチャレンジについても教えてもらえますか?
斎藤:プロダクトや機能でこういうのを開発したい、というのが理にかなっていれば誰の発言であれ取り入れられるカルチャーなので、主体的にプロダクト開発に携われる点がチャレンジかなと考えています。 新たな価値を発明し続けるというミッションを掲げているので、全メンバーがプロダクト開発に主体的に取り組める組織づくりを心がけています。 その上で課題としては、このカルチャーをより浸透させていく必要があるとも思っています。実際に行動を起こしてもらうような仕組みだったり、どんどん意見を出してくれて良いよ、というような雰囲気作りは今後さらに行っていきたいです。
松本:子育てでも同じことを感じますね。出してくれたものに対してフィードバックをすることでは、あなたに対して一概にしゅんとさせたいのはなく、1つの事象に対する話をしていると。伝え方の問題もあるのですが、事象に対する話と捉えてくれて、2、3、4つ目を持ってきてもらえるようにしていきたい。人単位で任せて主体性を持たせていき、方向性が違う時は経営陣で止めに行く。1on1の機会も多いし、提案できるタイミングも今後多く作っていきたいですね。

今後Caratに入社してくれる方に向けて
松本:最後に、今後Caratのエンジニア組織をより強くしていくためにどんな人と働きたいか教えてください。
斎藤:事業の成長と自分の成長をアラインさせて取り組める人が仲間に入ってきて欲しいですね。年齢は関係なく、そういうエンジニアが各事業に入ってくれていて、事業を一緒に作っていけると良いかなと思っています。エンジニアリングのスキルだけではなく、ビジネススキルやプロダクトなどへの興味関心は必要になってくると思っています。
あとはスペシャリストでプロダクトのエンジニアチームをイネイブリングしていける人も今後必要になってくるかなと考えています。例えばLLMに詳しいメンバーがいて、各チームにこういうことができますよといったアドバイスをしていくなどのイメージです。縦串の事業のチームと、横串でプロダクトチームを支えるチームの両方を作っていけると会社としてもまた面白くなっていきそうなイメージを持てています。
今回は創業者の2人であるCEO/CTOのお二人の対談形式のインタビュー記事をお届けしました。記事を読んで興味を持ってくれた方に向けて、Carat では未来の仲間を積極採用中です。
様々なポジションで募集をしていますので、気軽にエントリーしていただき、まずはカジュアル面談から話しましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
