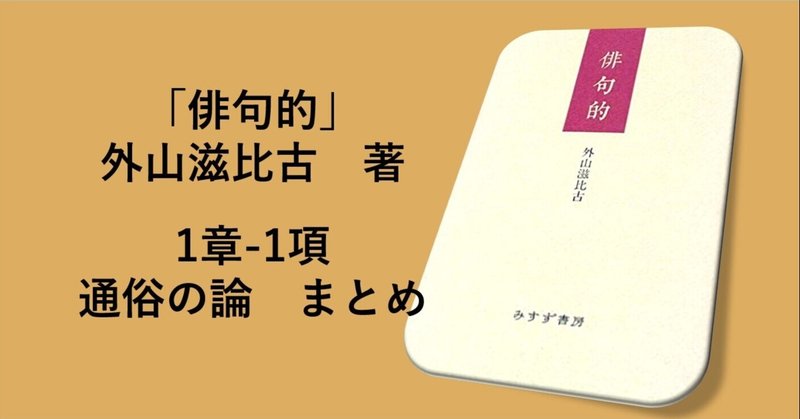
俳句的(外山滋比古著)を読んで(1章-1通俗の論のまとめ)
「思考の整理学」で著名な知の巨人、外山滋比古先生は、俳人であった。
本書は、そんな先生が、短詩型文学や俳句第二芸術論等についての見解を、様々な角度から論じたエッセー集である。
あまりにも面白かったので、自分用の記録として、時間をかけて各章各項毎にアウトプットをしていきたい。
俳句に限らず、その他の短詩型文学論、日本語論、日本文化論としても非常に興味深い一冊である。機会があれば是非読んでいただきたい。
・要点板書

・近代文芸=反俗(P3)
近代文芸は、エリートの営みである。いくらか一般の読者を軽蔑する。無知な人間は相手にしない。通人の約束の上に立っている。かいなでの初心者などにわかってたまるか、という自負がある。大方もそれになれて別におかしいと思わない。近代文芸の共和国はそれで平和を栄えることができた。
通俗ということを何よりも怖れる。反俗こそ芸術である。そう決まっている。
ヨーロッパの近代芸術に学んだ明治以降の文化がほかの方途に思い及ばなかったとしても致し方あるまい。さらには、伝統を棄てるのをよしとした。外来に就くことが高尚であり、価値のあることだと信じた。考えてみると、ずいぶん窮屈な所へ自らを封じ込めたものである。そして、それに気付いている人が少ないというのも不思議ではないか。
・短詩型文芸の共通点(P4)
俗をすて雅を求める。文語の中から雅語の体型をつくり上げる。これは短詩型文学に共通する点で、俳句を作るのは、その雅語のシステムをまがりなりにもわがものとすることに他ならない。もちろん、普遍的雅語などというものが容易に習得できるわけがない。めいめいの属するグループの方言とも言うべき雅語に習熟することから始まる。
その過程で、しらずしらずのうちに、現実から遊離した言語の世界に入って行く。反俗風雅が肯定されているところでは、それが反省されることは少なく、むしろ芸術的進境だと考えられる。このようにして詩語は確立する。
・雅語→言語解放→俗語の詩化(P5)
芭蕉はそれまでは和歌の守ってきた雅語の柵をとり外すことによって短詩型文学に新しい生命の泉を発見することができた。通俗を通じての風雅である。よく似たことはイギリスのロマン派の詩人ワーズワースにも見られる。十八世紀のイギリス詩もやはり典型的な雅語(ポエティック・ディクション)にがんじがらめになっていた。そこへワーズワースが現れて田夫野人のことばを用いて詩を作ると宣言したのである。ロマン派運動の活力の源泉はこの言語解放に求められるべきであろう。
俗語の詩化。ここで創造の火花が散る。手垢のついた常套的雅語では精神の根源を揺さぶるのは困難である。俗のことばに根をおろした雅の世界が待望される。
・俳句はより諺的であってよい(P5)
短詩型文学が小さな個性にこだわるのは賢明ではない。俳句をもっと民族的、ことばに即して言うならば諺的であってさしつえない。そうある勇気をもってよい。
・ちょこっと解説
・寺山修司も生前「俳句はもっと、祝詞のような、呪術的、祭事的な方面に活路を見出すべきではないか」と言っていた。これは外山滋比古先生の「俳句は諺的であっても差し支えない」という見解と、ベクトルを共にする。
・俳句という詩形が確立したのは、たかだか100年ほど前のことである。詩形としてはまだまだひよっこの部類である。ならば、一つの考えに固執しすぎるのはよくない。有季定型は詩を構築する上で、重要な要素であることに違いはないが、それだけではないかもしれないということを肝に銘じておく必要がある。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます!楽しんでいただけたら幸いです。また、小生の記事は全て投げ銭形式になっています。お気に入り記事がありましたら、是非よろしくお願いします。サポートやスキも、とても励みになります。応援よろしくお願いいたします!
