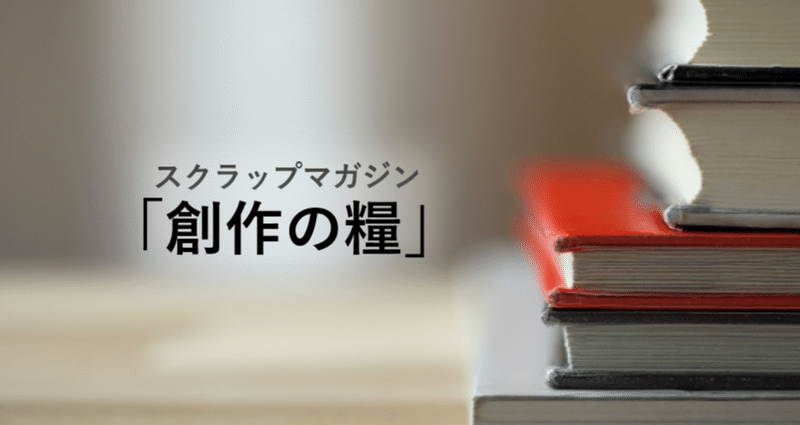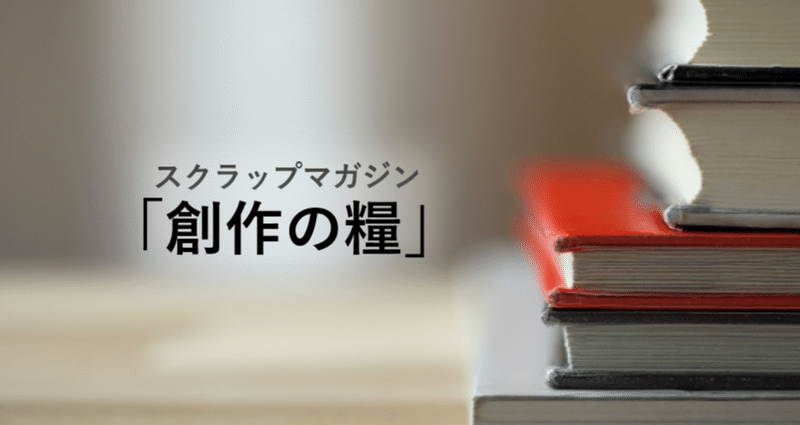『短歌タイムカプセル』東直子ほか編 (書肆侃侃房)
短歌のアンソロジー。ソフトカバーで軽くてカバンに入れやすい本。値段も手ごろ。通勤電車の中で読んだら良さそう。(わたしは通勤していないけどね。)わたしは俳句や短歌にはあまり縁がなくて、どちらかというと詩を読むことが多いのだが、このアンソロジーで短歌を集中的に読んでみて、五七五七七の短歌独特の言葉の空間がとても面白いと思った。狭すぎず、かといってそれほど広くないのでやっぱり不自由なのである。たくさん読んでいくうちに、自分でも詠めないものかと思ってしまう。でも五七五七七はけっこうき