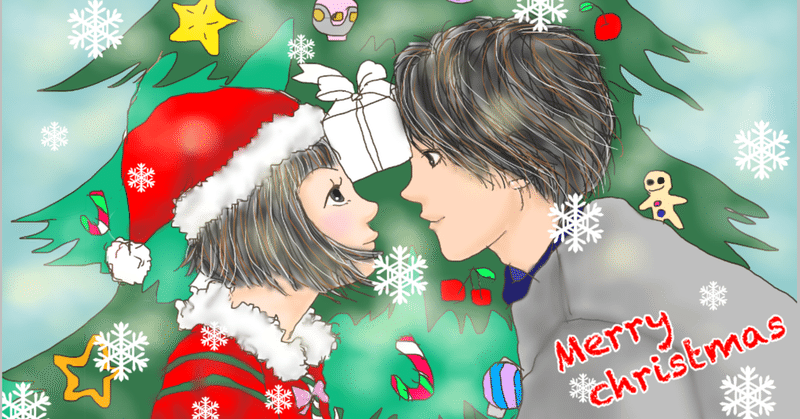
マリリンと僕9 ~クリスマスは終わらない~
目が覚めた時、時計は昼の12時を回ったところだった。カーテン越しでも外が晴れていて、陽が差しているのがわかる。体は朝方よりはスッキリしていて、頭痛や吐き気も無い。
マリリンのお父さんから誘われたクリスマスパーティは、想像を超える盛大さだった。それはまるで夢のような出来事だったし、戸惑いや緊張を抑える為に大量にワインを飲んだせいで、本当に夢だったんじゃないかと思うくらい実感を伴っていない。
昼過ぎまで倒れるように寝ていたから、さすがに空腹を感じた。
ベッドから降り、ひとまずシャワーを浴びて、髭を剃った。それから昨日コンビニで買っておいたらしい(記憶にない)、バターロールとサラダと缶コーヒーで簡単に食事をしながら、頭の中を整理することにした。
まずはマリリンとのこと。
マリリンはとんでもないセレブの令嬢だった。父は国内有数の大企業『城山グループ』の代表取締役CEO。松下幸之助を師と仰ぐことや、イチローと知り合いなのも合点がいった。母も世界的なデザイナーだった。
今まで通りに会って良いんだろうか。僕と彼女では、明らかに住む世界が違う。年齢だって20歳近い差があるし、その上僕の方が彼女を頼っているのも事実だ。マリリン自身はそんなことを思っていないようだが、僕はこのままで良いのだろうか。
ホテルで会った時もマリリンはやっぱりマリリンで、いつも通りの破天荒な少女だった。お父さんも初対面の僕を、Xmasパーティに呼んでくれた。でも、僕は甘え過ぎなんじゃないか。
幾ら思考を巡らせても、自分では整理がつかなそうだった。
もう一つ。昨日の帰り、桜井から「ありがとう」と言われた気がした。パーティの最中には小動物化していた桜井からの「ありがとう」。一体どういう意味だったのだろうか。
これはもう本人に聞くしかない。スマートフォンを手に取り、電話を掛けた。
「おぉ、やっと起きたか。お前昨日めちゃくちゃ酔ってたから、家まで送ったんだぜ」
そうなのか。全く覚えていない。
「そうだったんだ。ごめん、本当に全然覚えてなくってさ。でも、なんかサクに『ありがとう』って言われたような気がして、なんだっけって思って電話したんだ」
電話の向こうで桜井が笑っている。
「それは覚えてんだ。そりゃ理由なんか説明してねぇもん、覚えてるわけないよ」
そうだったのか。
「あんなパーティに予告も無く巻き込まれてさ、ふざけんなって始めは思ったけどな、あの娘…マリリンだっけ?連れ回されて、いろんなジャンルの有名人と挨拶してる間に俺、『自力でここまで来たい』って思っちゃったんだよ。笑うだろ?」
「いや、そう思えるサクはすごいと思う」
僕は率直に言った。悩んでばかりの僕とは大違いだ。
「あのな、お前大御所からも演技褒められてたじゃん。しかも、たった1年であんな異世界に迷い込んでるんだぜ。普通じゃない。なんかさ、お前となら出来るんじゃないかって、結構本気で思ったんだ。まぁ、お前はどう考えてるかわからないけどな。少なくとも、自分がそんなことを思えるようになったのがすげぇ嬉しくて、それで『ありがとう』って言ったんだ。酔っぱらいの超新星さんにさ」
そう言って桜井はまた笑った。そこまで想ってくれている桜井に、僕はなんだか申し訳なかった。無理に誘っておいて、あげく記憶が失くなるほど飲んで、家まで運んでもらって。
「さっき小山さんにも会ったんだよ。もらった機材、置きに行ったんだ」
小山さんは、僕らが所属している劇団壱厘舎の主宰であり、看板俳優だ。
「昨日のパーティのこと、話したのか」
実は小山さんには、マリリンやマリリンのお父さんのこと、パーティに参加することも話してあった。「嘘みたいな話だけど、嘘にしては出鱈目が過ぎるな」と言って、僕が主演を務める年始公演の稽古も休みにしてくれたのだ。
「あぁ、小山さん、お前らしいって爆笑してたぜ。どんだけ上手く行ってもずっとネガティブなお前が面白いらしいよ」
褒められている気がしない。いや、確実に褒められてはいない。
「でも、『そんな奴が成功しちゃうのも痛快で良いんじゃないか』って言ってたよ。実際努力してるのは知ってるから、俺もそう思うんだ。だからお前は…、ずっと自信持つな」
電話の向こうで桜井は一人爆笑している。
「お前は今のままが良い。そのままのお前と、俺は夢を追いかけたい」
一転して、真剣なトーンでそう言った。その想いが本気なのは、十分伝わってきた。
「うん。わかったよ。なんか釈然とはしないけどな」
そして、マリリンとの関わりで悩んでいることも桜井に話した。
「まぁな…、お前の気持ちはわからないでもないよ。だけど、あの娘は何も思ってなさそうな気がする。お前といるの、本当に楽しそうだったしな。それでもお前が気になるなら、直接会ってみて考えた方が良いんじゃないか」
僕もそう思う。
「そうだな、そうするよ。」
マリリンが公園に現れるのは大体夕方だから、まだ時間がある。今日がクリスマスなのを思い出した僕は、駅に隣接したショッピングモールでマリリンにプレゼントを買うことにした。
もう今年も終わりだ。マリリンと出会ってから1年以上が経つ。僕の人生の中で、とても大きな意味を持つであろうこの1年を振り返りながら、ブラブラと歩いて回った。
そのまま日が暮れるのを待って、公園に向かった。寒さも本格的に冬を感じさせるものになっている。途中、冷えた手を温める為に、自販機でホットコーヒーを買った。
マリリンは現れるだろうか。そして、どんな反応をするんだろうか。
「いーやーやぁっ、いーやーやぁっ!!」
「ちょっ、待っ、えっ、えぇっ!?」
僕が公園に着くと、既にジジとマリリンの姿があった。タイミングを見て、マリリンと会うことに悩んでいることを話した結果、拒絶反応を起こしたマリリンは、地べたに寝転び、手足を全力でジタバタさせながら泣き喚いている。のたうち回っている、という表現の方が適当かも知れない。
「そんなん絶対いややぁーっ!」
漆黒のゴスロリドレスは、既に砂利にまみれて、ボロボロだ。
「わかったよ、わかったって!落ち着いて、もう言わないから」
そう言うしか、選択肢がない。幸い周りに人はいなかったが、この光景を見られたら通報されかねない。
「ほんま?ほんまにほんま!?」
疑いの眼差しで僕を見つめている。
「ほーんーまっ!」
思わず関西弁がうつってしまった。
「約束やで?嘘ついたら針1億万本飲ますで?」
怖いよ。そして、そんな桁はない。
「うん、約束するよ」
するしかないだろう。
「ウチな、親が金持ちやってわかると、いっつも友だち離れてってまうねん。好きでそこに生まれたわけじゃあれへんし、自慢もせぇへんで。強いて言えば、ちょいちょいロールスロイスが学校まで迎えに来るぐらいや」
それだけで十分だし、友だちが出来ない理由がそのせいなのかは、ちょっと疑わしい。でも、きっと普通の子どもがしない苦労をしているのだろう。
「せやから、兄ちゃんまでそんなん言われたら、ほんまにかなわん。またぼっちになってまうやん」
「うん、大丈夫だよ」
そう言って、僕はマリリンの頭を撫でた。
「ほんま、約束破ったらウチ死ぬで。舌噛み切って、死んだるから」
いちいち怖いって。でも、マリリンは落ち着きを取り戻してニコニコしている。暴れるマリリンを見て距離をとっていたジジも戻ってきた。
「あ、コレあげるよ」
ショッピングモールで買ったマフラーを、マリリンの首に巻いてあげた。黒猫が首元に巻きついているようなデザインのマフラー。
「めっちゃええやん!この服にも合ってるし、最高やん!…って、なんでウチこんなボロボロなん?黒のドレスがまっちろけっけやん!?オカンに殺されてまう…」
今頃気づいたんだね。さすがに殺されはしないだろうけど、激しめのお説教は免れないね。
「なんか高い物もらっちゃったし、今日はクリスマスだから、クリスマスプレゼントだよ。サンタクロースじゃないけどね」
「めっちゃ嬉しい。兄ちゃん、ほんまにありがとう。兄ちゃんとの出会いが、ウチにとっては最高のプレゼントやけどな」
なんかすごいことを言われた。と思ってマリリンを見ると、「良いこと言うやろ」という感じで全力でドヤ顔をしている。そんなマリリンは、やはり可愛い。
「今日はホームパーティあるから、そろそろ帰らなあかん。オトンも明日からまた海外やって言うてたし」
「ほなっ!」と言って、一人と一匹がドタドタと帰って行った。
結局悩んでいた時間が無意味なくらいマリリンのペースに巻き込まれてしまったけれど、マリリンが望むならそれで良いかなと思った。いつまで続くかはわからないが、彼女が成長して飽きるまでは今のままでいようと思う。
すっかり冷めた缶コーヒーを飲み干して、家賃5万6千円のアパートに帰ることにした。なんだかんだで、僕は今年も一人ぼっちのクリスマスだ。
そう思いながら帰路につき、やがてアパートに辿り着くと、僕の部屋の前に、一人の女性が立っているのだった。
つづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
