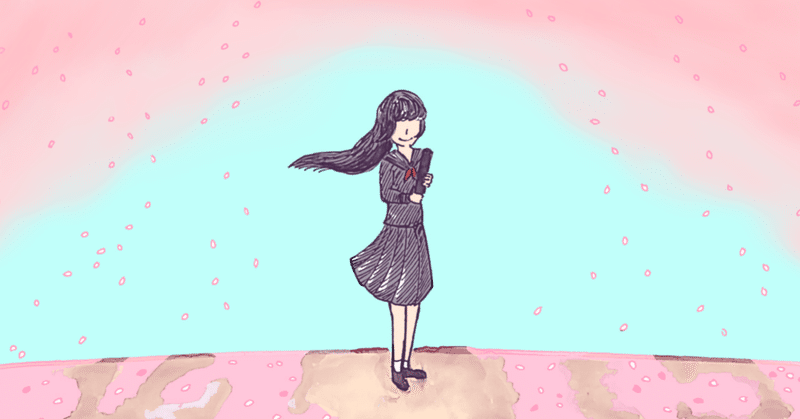
青春はいつまでも
「大人になるのが怖い。」
僕が彼らに想いを打ち明けてから三年の月日が経った。
「彼ら」とは僕の大切な友人二人である。僕のSNSのフォロワーの大半は友人と呼ばれる人たちだけど、二人は特別な友人で、一言でいえば親友だ。
そんな二人との出会いは高校生のときだった。といっても入学した瞬間から仲が良かったわけではなくて、意気投合したのは三年生の夏のこと。
僕らの高校の文化祭は夏休み明けの九月すぐで、文化祭の準備は例年夏休みから少しずつ行う。僕とケイとマリはたまたま文化祭実行委員に属していて、文化祭への準備を通じて仲を深めていった。
文化祭への準備をクラスメイトは皆やりたがらなかったが、三人で過ごした日々はかけがえのない時間であり、今でも鮮明に覚えている。
✳︎
セミの声がひしひしと教室の中まで入って来る。教室にクーラーはあるのだが、あいにく壊れているとかで窓を全開に空けていた。それにしても暑い夏だった。
作業の休憩中、マリは蝉の声に負けじと僕とケイに言った。
「コーラでも飲まない?」
一か月前までテニス部の現役選手だったケイは、こんな暑いときはスポーツドリンクだとか何とか言っていたが、マリの「夏はコーラ」という理論に押されて僕たちは足早に自販機へと向かった。
今思えば三人別々の飲み物にすればいいのに何故か皆全く同じ500mlのコーラを一本ずつ買って、溢れる炭酸と甘味を噛み締めた。
「ほら、夏はコーラなんだから。」
マリの言う通り夏のコーラは凄く美味しい。シュワっと弾けた炭酸と甘みが全身へ突き抜けていくのである。ケイも唸る程だった。
僕らはコーラを同時に飲むものだから、ペットボトルに口をつけているときは自然と沈黙が流れる。
しかし彼らとの沈黙は蝉の声と相まって至極心地良いもので、安心感さえ覚えた。
そんな沈黙を破るかのようにケイが口を開く。「文化祭なんて始まらないで、こうやってずっと準備だけしてたいわな。」
こんな時間がいつまでも続けば最高に幸せ。それはケイだけの想いではなく、僕たちの感情そのものだった。
文化祭は無事成功に終わった。
成功といってもその基準がないから、どこから成功と呼べるかはわからなかったが、僕たちの主観的には成功だったと思う。
しかし、文化祭が終わった後というのは達成感よりも心に穴が空いたような寂しさが強かった。
文化祭の終わった日の夜、クラスメイトたちと打ち上げでファミレスへ訪れた。その後、僕たちは三人で海へと向かった。
あのときの教室みたいな暑さはなくて、どこか涼しい浜風が吹いていた。セミの鳴く声もない。そこにはさざなみが砂浜に打ち寄せる音だけがあった。
僕たちは砂浜をローファーで歩いて、砂が靴に入ったとか言いながら、堤防に腰掛けた。
「ねえ、喉渇かない?」
別に喉なんて渇いていない。だけど、マリはそう言ってスクールバックから3本のコーラを取り出した。
「カバン、重くなかったのかよ。」
とケイは苦笑いをして言う。
「ちょっとね」とマリは声を出さずに右手の親指と人差し指でポーズをとった。だけど、あたりはもう暗いからマリの仕草がはっきりとは見えない。
マリから僕とケイにぬるいコーラが渡されて、僕たちは三人同時にコーラを飲んだ。飲んでいる最中は沈黙が流れる。さざなみの音が響き渡る。
ぬるいコーラだけど、この沈黙がやはり好きだ。
だが、もう彼らとコーラを飲むことも、これから受験やら就職やらであっという間に大人になってなくなってしまうのではないか。まして大人になってからも会えるのか。そんな不安ばかりが募っていく。
「大人になるのが怖い。こうして三人で会えなくなるかもしれない。」
気がつけば僕は想いを彼らに打ち明けていた。
「なあ、根拠なんてないけど俺らの付き合いはこれからも続くんじゃないかな。」
ケイは暗い海の遠くを見ながらそう言った。
✳︎
「久しぶりだね。」
マリの鞄は随分と小さくなった。コーラ三本どころか、きっと財布とスマホしか入らない大きさの鞄だ。あれから三年経った今はデパートで働いている。
ケイはスポーツインストラクターになった。仕事帰りだろうか、速乾のドライTシャツにタイトなジャージパンツを着ている。もちろん、ローファーではなく黒のランニングシューズを合わせている。夕方だからか、青髭が目立つ。
僕は四年制の大学へ進学したから、この中の僕だけが学生だ。
学生と社会人が入り混じった三人ではあったが、皆ハタチを過ぎ、酒は合法だ。僕たちは居酒屋で生ビールを注文した。
「俺、ビール苦手なんだけど。」
ケイはそうやって言ったけど、マリ曰く、「夏は生ビール」らしい。
「なあ、三人同じの飲まなきゃいけないルールなんてあるのかよ。」
ケイは不満を漏らしていたが、実は生ビールは初めてだったらしく、飲んだ瞬間美味さに唸っていた。
「ほら、言ったでしょ。」
マリの髪色は明るくなったし、化粧やファッションも大人っぽくなったけれど、そういうところは全く変わっていない。
二口目も皆で同時に飲む。
沈黙とセットなのは蝉の声でもさざなみの音でもなく、居酒屋の安っぽいBGMと隣の席のスーツを着た人たちの雑然とした笑い声だ。
それでも、この瞬間が好きだ。
「根拠なんてないけれど、俺たちの付き合いはまだまだ続くと思うよ。」
ケイは顔を赤らめて言う。
ケイの一言はなんとなく僕もそうであると思う。マリもそう思っているはずだ。
僕たちの青春は終わらない。
三人集まれば、青春はいつまでも。
「押すなよ!理論」に則って、ここでは「サポートするな!」と記述します。履き違えないでくださいね!!!!
