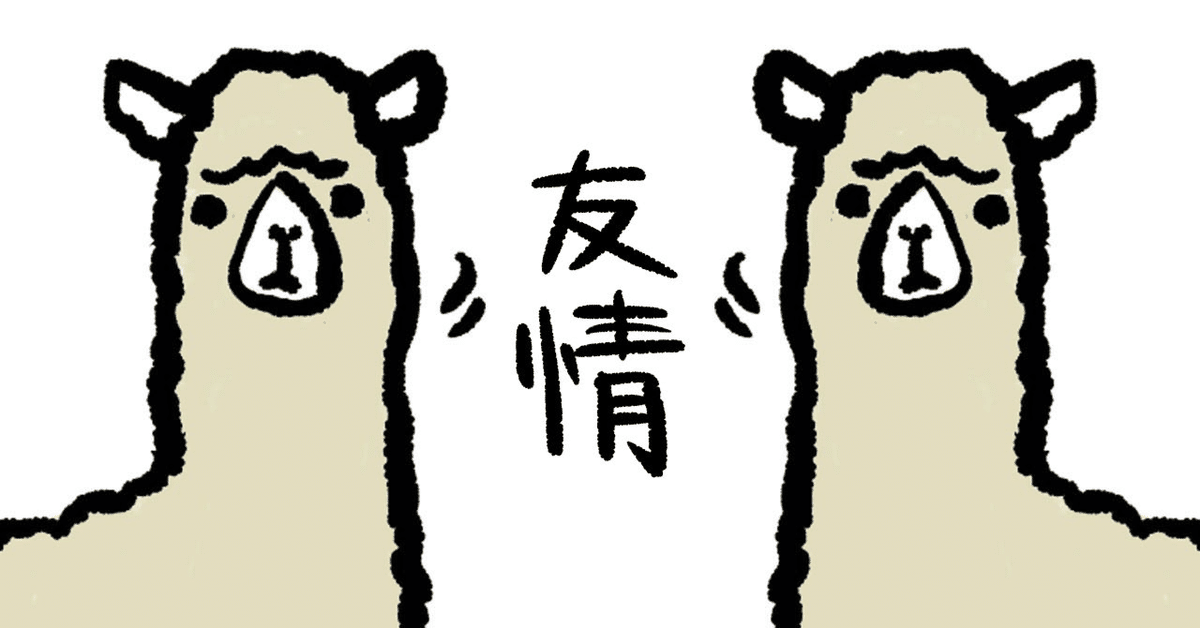
「特集:<友情>の現在」(現代思想Vol.52-9)を読んで友達とか友情とかなんやかんやについて色々考えた
友人から、現代思想の「<友情>の現在」の特集号の写真と共に、「めっちゃおもしろい……刺さりまくり」とLINEが来た。というわけで久々に「文字を読んで感想を書く」ということをしてみる。
そもそも、友人からそんなLINEが届くことが僕にとってはとても良い状態だ。というのも、明らかにこのメッセージは、「僕にも刺さるはず」という意味を含んでいるからである。本書に書かれているようなことを、その友人とはよく話しているので、「たぶん刺さるから読んでみてもいいかも」みたいな意味で連絡をくれた、のだと思う。
さて、冒頭でこんなことを書いているのには理由がある。というのもその「友人」は、「12歳年下の女性」だからだ。一般的に、「41歳の男」と「29歳の女性」との間には「友人関係」は成立しないと判断されるだろう。僕もそう思う。そもそも、「男女の友情が成立するか問題」もあるし、12歳という年齢差大きい(これが82歳と70歳みたいなことであれば年齢差は大した問題にはならないだろうが、やはり41歳と29歳の年齢差は結構大きいだろう)。
その「難しさ」については、ちょっと意味合いは異なるのだが、本作のこんな文章によって説明できる部分もあるだろう。
『第一に、アセクシュアルにとっての友情が恋愛と地続きの性的関係として誤読されてしまうケースである。例えば、アセクシュアルの男性が女性と恋愛的でも性的でもない友人関係を築こうとする際、女性への性的欲望を当然のこととする男性のセクシュアリティに対するステレオタイプによって、女性たちに警戒されたり、そうした意向を疑われたりすることがある(Cupta 2019:1206)。他方でアセクシュアル女性の場合、男性に性的魅力を与えるという伝統的な女らしさの期待のもとで、特定の服装やふるまいが一方的に性的な文脈に回収されて理解されてしまう(Cuthbert 2019:855; Cupta 2019:1206-1207)。』(佐川魅恵「親密さの境界を問い直す」)
「アセクシュアル」というのはざっくり、「他者に対して性的欲求を抱かないセクシュアリティ」と言っていいだろう(僕は「アセクシャル」と普段言っているのだけど、引用では「アセクシュアル」となっていたのでそれに倣った)。そして、アセクシュアルであるかどうかに関係なく、先程引用した文章の指摘は、「異性と友人になる場合の障害」として理解できるのではないかと思う。
僕は別にアセクシュアルではないのだが(少なくとも、そう自覚している)、ある時点から「恋愛を止めて異性とは友人になろう」と決めた。「『恋愛という関係性』に向いていない」という結論に至ったからだ。異性に対して性的に惹かれもするし、性欲も普通にあるのだが、「恋愛」というものに対する違和感というか、馴染めなさみたいなものが強く自覚されるようになり、「恋愛を追い求めない方が自分にとってプラスなのではないか」と考えたのだ。それが30歳ぐらいの頃のことである。そしてそれからは、「異性といかに友人になるか」というスタンスで関わるようになっていった。先述の友人は、そういう意識に切り替わってから出会った人であり、個人的に「結構仲良くなれたなぁ」と思っている相手である。
ちなみに、今書いているこの文章は、その友人に「現代思想読んで感想書いたわ」と言って送るつもりだ。普通に考えたら、「言及している本人に直接読ませるのは適切ではない文章」に思えるかもしれないが、僕としては「まあ大丈夫だろう」と判断している。もちろんそれは、僕が「友人」だと認識している人すべてに同じことが出来るみたいなことではない。まあそういう意味でも、割とその友人は特殊な存在と言っていいだろう。
さて、本作は「友情」をテーマに様々な言及がなされる作品だ。正直なところ、全部面白かったなんてことはない。後半に行けば行くほど、内容的に難しかったり、テーマとして興味が持てなかったりしたのだ。しかしそれはそれとして、「世の中には色んなことを研究している人がいるんだなぁ」と感じた。「バンドマンの友人関係」「沖縄の建設業に従事するヤンキー的人間関係」「合唱曲と卒業ソングからの友情分析」「ママ友のLINEのやり取りの分析」「ホストクラブの人間関係」などなど色んなテーマがある。中には、「オッペンハイマーと湯川秀樹の初邂逅」に言及する項もあって、その幅の広さに驚かされる。
その中でも個人的に最も共感させられたのが、本書冒頭に収録されている中村香住と西井開の対談「すべてを「友情」と呼ぶ前に」である。中村香住はレズビアン、そして西井開は「非モテ研究会」の発足人であり、それぞれジェンダー的な側面から社会学の研究を行っている。
その冒頭、中村がこんな風に話す場面がある。
『(前略)恋人・家族・仕事上の関係、地縁、血縁のいずれにも当てはまらない人間関係が、すべて「友情」や「友達」という言葉に押し込められていることに、小さい頃から違和感を覚えてきました。私はグループで仲良くすることもたまにはありますが、基本的には一対一で人との関係性を取り結ぶタイプなので、それぞれ異なるはずの関係がすべて同じ「友達」という言葉で説明されなくてはならないこと、いわば「残余カテゴリー」としてこの言葉が使われることに疑問を抱いてきました。(中村香住)』(中村香住+西井開 すべてを「友情」と呼ぶ前に)
僕も基本的に他者とは一対一で関わりたい人だし、「いずれにも当てはまらない関係が『友達』と呼ばれている」という話も納得で全体としては共感できるのだが、1つ僕とは違う感覚があった。それが、「『友達』という言葉が『残余カテゴリー』として使われていること」に対するものだ。彼女は、先の引用に続く言葉の中で「『友達』という言葉が不当に価値が貶められている」と言っていて、どうやら「残余カテゴリー」であることに不満を抱いているようである。
ただ、僕の捉え方は少し違う。「『残余カテゴリー』だったから良かった」という感覚があるのだ。その感覚を説明するために、こんな引用をしよう。
『恋って再生産に次ぐ再生産で、もはや恋をしたことがなくても型みたいなのがあって、とりあえず作り手も受け手もそれをどれだけ上手にその型のまま演舞できるかという、武道めいたものを感じる。恋愛武道が悪いわけじゃないけど、歌を聴いて「これは詞ではなく、型だよなぁ」と思ってしまうことも、正直ないわけじゃない。その模倣しやすい友情歌詞の「型」がまだ少ないから、まだまだ足りないのかなぁと思ったり。これは鶏が先か卵が先かみたいなもんだけど。(児玉雨子)』(児玉雨子+ゆっきゅん「ラブソングのその先へ」)
これは、作詞家であるらしい2人の往復書簡のやり取りの一部で、「歌詞を考える時に、恋の場合は型があるからいくらでも供給できるけど、友情の場合そういう型がないから供給が少ないのではないか」という分析をしているものだ。そして僕は、「だから『友人』っていいんだよなぁ」と感じるのである。
僕が「恋愛に向いていない」と感じた最大の理由は、この「型」にあると言っていいだろう。「恋愛」になると、「こういう時にはこういうことをした方がいい/しなければならない/すべきである」みたいな話が増える。しかもそれらは、「しなければ『相手のことが好きではない』というメッセージとして受け取られる」という要素も含んでいるのだ。僕にはどうしてもこの感覚が馴染めなかった。
例えば「プレゼント」1つ取っても、「あげたいと思ったからあげる」というのが、僕は一番良いんじゃないかと思ってるのだが、「恋愛」においてはそうではない。「誕生日」や「付き合って1周年記念日」みたいな時に「あげるべき」という話になるのだ。いや別に「あげたくない」なんて言っているのではない。ただ、「しなければならないからしている」みたいな違和感がずっと募っていくのだ。まさに「型を演じている」という感覚だった。
そして僕は、「友達」にはそのような「型」が存在しないことが素晴らしいと感じている。そしてまさにその理由こそ、「『友達』が『残余カテゴリー』である」からだと思っているのだ。
「恋人」や「家族」というのは、「こうであるべき」という「型」が存在するから「自立したカテゴリー」として成立している。しかし世の中には、そこから溢れる関係性もある。それはつまり「型が無いから」であり、そしてそれらに「友達」という名前を付けているということなのだと思う。だから僕は「残余カテゴリーであること」に心地よさを感じているのだ。
この点については対談中でも言及されている。
『(前略)境界画定の力学が働く集団では構成員の近密度は上がるけれど、誰もがそこからはじき出されないように互いに承認を求め続けなければならない。なので承認をめぐるしんどさを抱える人が安心して過ごすには、境界を曖昧にしたような集まりや関係性のあり方が模索されるべきだと思います。しかし、欠乏感を埋めるために、さらなる承認を求め、強く結びつきたいと思えば思うほど、境界線が太く濃く惹かれてしまう悪循環があります。(西井開)』(中村香住+西井開 すべてを「友情」と呼ぶ前に)
この指摘は一対一ではなく何らかのグループに関するもので、「集団が出来れば、『その集団の構成員として相応しい』という承認を常に得続けなければその集団には居続けられない」みたいな話である。確かにこれは「友達」にも関係する話だが、僕は今「『残余カテゴリー』としての『友達』」について言及している。そして先の引用で言及されている関係性は、明らかに「残余カテゴリー」に入ってくるものではないので、「型が存在する関係性」と捉えていいだろうと思う。
そしてこの対談では、そのような集団を「同質性が高い集団」と表記しており、西井開が、「自分が話を聞いてきた異性愛者の男性は、そのような『同質性の高い集団』に留まらざるを得なかったと話していた」みたいなことが書かれている。そしてその理由について、いくつか言及されていた。
『まず異性愛主義の問題があります。小学校低学年ぐらいまでは「男女の友情」という関係が成り立っているのに、高学年くらいになると周囲から「お前何あいつとイチャイチャしてるん」とからかわれたり、制裁を受けることで、異性との友人関係が切断されていく。(西井開)』(中村香住+西井開 すべてを「友情」と呼ぶ前に)
『加えて男性同士の一対一という関係も切断されていきます。男子が二人で仲良くしていると、ホモフィビア的制裁を受けてしまうのです。(西井開)』(中村香住+西井開 すべてを「友情」と呼ぶ前に)
『クラスメイト、そして教師からも「お前らできているのか」とからかわれた経験があると語る男性は少なくありません。そうして一対一での関係も作りづらくなると、自分が所属するのは男性集団しかないと思い込む/思い込まされていく。(西井開)』(中村香住+西井開 すべてを「友情」と呼ぶ前に)
男である僕も、この指摘にはなるほどなと感じる。僕もどちらかと言えば、そういう風潮に違和感を覚えてきた人間だ。
というか僕は、子どもの頃からどうも同性との相性が悪く、そのため高校時代ぐらいまでは「人間が苦手なんだな」と思っていた。しかし大学に入り、女性と関わる機会がそれまでと比べて増えたことで、「人間が苦手」なのではなく「同性が苦手」なのだと気付いたのだ。異性の方が関わるのが楽だなという感覚が強くなっていったのである。僕の場合こんな風に、「男性集団にしか所属できない」みたいな感覚からはするりと抜けることが出来たのはラッキーだった。そんな風に出来ていなかったら、今も「人間が苦手」という感覚のまま生き続けていただろう。
さて、別の項で、似たような言及がなされていたので引用しよう。
『「非モテ」をテーマに、当事者グループでの実践のフィールドワークを通した男性学研究を行う西井開は、「非モテ」男性の困難の根源が女性にモテないこと自体ではなく、男性コミュニティの中でからかいなどの緩やかな排除を受けていることにあると論じる。(中略)親密な関係を築くことへの価値づけ・期待の高さゆえに、周囲から尊重・経緯を得られず孤立しているという問題が、恋人ができるという、特定の誰かとの親密な関係の獲得によって解決するというふうに、誤って考えられてしまうというのだ。
社会の中で尊重を受けていないという問題を、恋人を得ることで解決できてしまうと考えることは、確かに問題の所在を取り違えている。』(筒井晴香 「友達問題」と「推すこと」)
ここで指摘されていることは、「『異性の恋人がいる』という事実が持つ価値」である。敢えて「異性の」と書いたが、「恋人がいる」という状態の価値が高いと認められているために、「自分の今の不遇な状態は、『恋人が出来る』という状況の変化によって改善するのではないか」と考えてしまうというのだ。これは「恋人」だけではなく「結婚」も同様だろう。
そのため、「非モテ男性」は自身のことを「異常独身男性」と評することがあるのだそうだ。この点について西井開は、「モテを重視していない人が仲間内での連帯のためにこの言葉を使っていることもあるだろう」としながらも、次のようにも書いている。
『(前略)その裏には家父長制に下支えされた異性愛規範・恋愛伴侶規範に縛られて「恋愛できなさ」について真剣に思い悩む男性が実在すること、その悩みを「異常独身男性」という自虐めいたテイストでしか表に出せない状況があることも忘れてはならないと思います。(西井開)』(中村香住+西井開 すべてを「友情」と呼ぶ前に)
さて、先程書いた通り、僕は「異性の方が楽に関われる」と気づくタイミングがあったり、あるいは「恋愛は向いていないから異性とは友達になろう」と発想を展開することにしたりと色々あったので、「モテない=異常」みたいな価値観を持たずに生きてこれた。これは今も同じである。「恋愛的にモテている」とか「結婚している」みたいな「状態」が、僕の自己肯定感を上げたり、生きていく上での自信に繋がるみたいなことは全然ないのだ。むしろ僕は、「『恋愛』より『異性と友達になる』方が難しい」とさえ思っているので、「異性の友人がいる」という「状態」の方が自分の気分を上げてくれるみたいな感覚さえある。
だから、僕は次のような指摘は非常に重要だと感じる。
『生きていくうえで友達の存在が極めて重要なもののように思われるのは、自発的な好意に基づく関係の価値が過大視されているせいも多分にある。むしろ、好意を伴う関係はなくとも、互いの嫌な点を受け入れ合って付き合いを続ける関係や、互いに尊重・敬意を保つ関係を得ることが重要である。それらが得られれば、互いの自発的な好意に基づく関係は、実はなくてもよいものなのではないか。』(筒井晴香 「友達問題」と「推すこと」)
筒井晴香はこの後に続けて、「でも好意を気に掛けずに生きるのは難しいよね」みたいなことを書いているので、上述の引用は「あくまでも1つの結論」として提示しているに過ぎないのだが、僕としては割と共感できる話である。そしてこの指摘こそが、この記事の割と最初の方で書いた「残余カテゴリー」の話に繋がると思う。
僕は中村香住の意図を分かった上で敢えて違う受け取り方をして導入に使ったのだが、彼女が「『友達』が『残余カテゴリー』であることに残念な気持ちを抱いている」というのは、決してそれが「残余カテゴリー」だからではない。むしろ、「『友達』と呼ばれる関係性の中には、『恋人』や『家族』よりも上位の関係もあるのではないか」と考えているのである。
彼女は、「私には『重要な他者』が数人いるのですが」と書いているのだが、この「重要な他者」という表記は僕にもとてもしっくり来る。ここには、「『恋人』でも『家族』でもないが、『友達』と呼ぶには収まりが悪い」という感覚が含まれている。つまりそれは、「『恋人』や『家族』と同列、あるいはそれ以上の関係だ」と示唆しているというわけだ。この感覚は、僕にもとても良くわかる。ちなみに彼女は、「自分が『重要な他者』だと感じている相手と突然連絡が取れなくなることもある」と書いているのだが、その際は「一旦身を引いて、数年後にまた縁があることを願ってなるべく何もしない」と書いているのだが、これも僕のスタンスとまったく同じでメチャクチャ共感できてしまった。
さて、話を戻そう。どうしても社会的に、「『好意』が含まれる関係性の方が上位」だという、ある種の”圧力”が存在するように思う。それ故に「恋人」や「夫婦」みたいな関係が重視されるのだし、それ故に辛さを感じてしまったりする人が出てきたりもするわけだが、別にそんな風に感じる必要はない。「『好意』が含まれる関係性の方が上位」というのは、言動でしかないと思うからだ。
その理由の一旦は、こんな文章から理解できるかもしれない。
『ただ、どのような関係性にも常に不安定性がつきものですよね。そうした不安定性を、例えば恋人なら「恋人」というラベルを貼ることによって覆い隠している側面もあるのだと思います。(中村香住)』(中村香住+西井開 すべてを「友情」と呼ぶ前に)
つまり、「関係性が不安定だからこそ、『強いラベル』を貼って安定しているように思い込みたい」という感覚があるというわけだ。「『好意』が含まれる関係の方が上位なんだ!」というある種の”虚勢”を張らないと怖くてやってられないということなのだろう。このように捉えると、少し見え方が変わってくるだろう。
さて、僕は「名前の付かない関係性」が好きである。先述した「重要な他者」のように、「便宜上『友達』という名前で呼ばれるが、実際には『友達』という概念では上手く括れない関係」という感じである。そして当然だが、「恋人」や「夫婦」などと比べると、そのような関係性はより「不安定性」が強いと言えるだろう。僕は「型が存在しないこと」が良いことに思えるのだが、恐らく多くの人にとっては「不安を増すもの」でしかないだろう。
そして僕は、「関係性に名前を付けることによっては不安定性を覆い隠せない関係性」の方が、「他者との関係性の強度」が高いように感じられるのである。「『好意』が含まれる関係性」の方が「名前が付きやすい」が、その「名前の付きやすさ」は「名前が付くことによる安心感を得たい」という気持ちが蓄積した結果であるはずだし、だとすれば逆説的に「関係性そのものは安定していない」ことを示しているとも言えるのではないかと思う。そして「名前の付きにくさ」は逆に、「名前が付かなくても成立している」ことの証であり、それはむしろ「安定している」ことを示していると言えるのではないか。
僕は割とこんな風に考えてしまうのだ。
そしてだからこそ、「『名前が付くこと』が安心」という”呪縛”から多くの人が解き放たれれば、「人間関係がもたらすややこしさ」の多くが解消するのではないか、と考えてしまうのである。
まあそう上手くはいかないことは分かっているが、しかし本作には、そのような変化の可能性を抱かせてくれるような話も載っていた。
『このことは、恋愛がロマン主義の中で制度的結婚の外部に生まれ、結婚と対立し結婚を脅かしてきたにもかかわらず、恋愛結婚の誕生によって結婚の条件となった歴史を思えば、驚くべきことである(加藤 2004:1章)』(久保田裕之 友人関係と共同的親密性)
『すなわち、地域共同体や親族共同体を通じた階級的地位・品性・資産を交換する家同志の政治・経済的打算であった結婚は、近代の配偶者選択における「愛の大転換」(Illouz 2012:41)によって全く別ものへと変容した。すなわち、階層構造から結婚が切り離されることで配偶者選択が性化・心理学化し、社会的規制(人種・国籍・宗教・階層)から自由な「結婚市場」と、感情的特質や性的魅力によって膨大な潜在的パートナーが競合しあう象徴闘争としての「性的界」(Illouz 2012:55)を誕生させた。』(久保田裕之 友人関係と共同的親密性)
この話は要するに、「昔と今では『結婚』ってまったく違う制度になっている」という指摘である。今まで「結婚」は「個人の意思」が入り込むようなものではなく、何なら「制度的結婚の外部」に生まれた「恋愛」が「制度的結婚」を脅かしさえしていたのに、今では「恋愛から結婚に至る」というルートが当たり前になっているというわけだ。これはかなり大きな変化だと言っていいだろう。
そして僕は、そのような「大転換」がまた起こってもおかしくはないと思っているのである。今は「『好意』が含まれる関係性」の方が「上位」のような扱いがなされているが、そのような価値観が転換される可能性だって十分にあるだろう。そしてその萌芽は少しずつ見えてきているのかもしれない。
『若者の友人関係はかつて理想とされた互いにぶつかり合い腹を割って話し合って築いていく人間関係から、高度に繊細な気配りを伴った「優しい関係」へと変化してきたと論じられた。この原因についても、制度的な地縁や血縁、学校や会社といった共同体に埋め込まれた友人関係は、その拘束力によって離脱や選択が困難であったのに対して、個人化により拘束力が弱まることで、友人関係が選択可能になる反面、一方的に解消されるリスクや、だれからも選択されないリスクにさらされることになったとされる。友人への頼み、悩みの相談、コンプレックスの吐露、相手のためを思っての忠告はもはや友情の絆を紡ぐ試練でも支援でもなく、明日自分が友人から切り捨てられるかもしれない悪手となる。こうした友人関係のリスク化は、恋愛関係同様、資源の多寡に基づく友人関係の階層化と孤立を生むとされる。』(久保田裕之 友人関係と共同的親密性)
僕はこの文章の中の、「◯◯、△△、□□は明日自分が友人から切り捨てられるかもしれない悪手となる」という部分が一番好きなのだが(若い世代ほど「分かるー」と感じるのではないだろうか)、この文章全体は、「友人関係は、恋愛関係と同じぐらい難しくなりつつある」と言及していると受け取れるだろう。
同じようなことは、「鈴木亜矢子 位置情報を交換する若者たち」で指摘されていた「Zenlyという位置情報共有アプリを挟んだ関係性」からも読み取れるだろう。
『そしてここでより興味深いのは、友だちとの合理的な接し方に、多重の配慮がなされている点ではないだろうか。』(鈴木亜矢子 位置情報を交換する若者たち)
『こう考えると、先に述べたBさんのアプリの使い方にも、空気を読んで「察する」配慮が見てとれる。まず相手がどこに何時間滞在しているかをアプリで確認し、相手の状況を推測する。そしてゲームや遊びに誘える状況にあると判断したら、そこで初めてLINEを使って相手にアプローチする。相手に直接打診する前に位置情報共有アプリで相手の現状を読み取り、誘うタイミングをうかがっているのだ。このように、位置情報共有アプリでは情報の受け手が能動的に働き方、配慮に基づく簡略化したコミュニティが行われている。』(鈴木亜矢子 位置情報を交換する若者たち)
最近の「マルハラ(LINEなどの文末を「。」で終わらせること)」などもそうだが、若い世代は特に「コミュニケーションからあらゆる情報を読み取り、相手に配慮する」というスタンスを強く持っている。そしてこれによって、「『恋愛』などと比べたらより気安いだろう『友達』という関係性」にも、強い配慮がなされるようになったのである。
このように「恋愛」も「友達」も同程度の配慮が必要な関係性になったことで、「わざわざ『恋愛』である必要があるのか?」という感覚にもなっていくのではないかと思う。「友達」とは違う関係性だからこそ「恋愛」に価値があるわけで、そこの境界が薄まっていくことで、「『好意』を含んだ関係性」の重要度が減じていくという可能性も十分に考えられるだろう。そんな萌芽が見え隠れしているように僕には感じられるのだ。
まあそんなわけで色々話は飛んだし何が結論というわけでもないのだが、久々にこういうことについて考えて言語化出来たことはなかなか面白かった。こういう話は一般的には全然通じないのだが、通じる人がいることは間違いないし、そういう人と関わっていけるといいなぁといつも感じている。こういう話が”当たり前”に通じる世の中になるといいなと思っているけど、そうなったらそうなったでまた新たな「マイノリティ(マジョリティに馴染めない人)」が出てくるだろう。そう簡単には「みんなハッピー」みたいなことにはならないだろうが、少しずつ世の中が変わっていくといいなぁ、と思ってはいる。まあ、とりあえずそんな結論にしてみました。
サポートいただけると励みになります!
