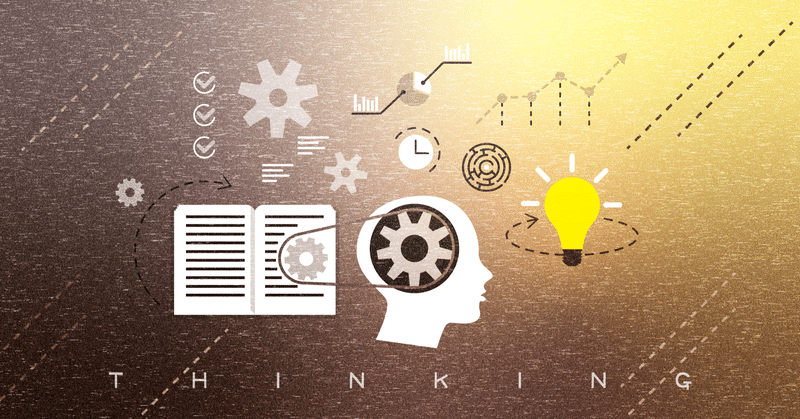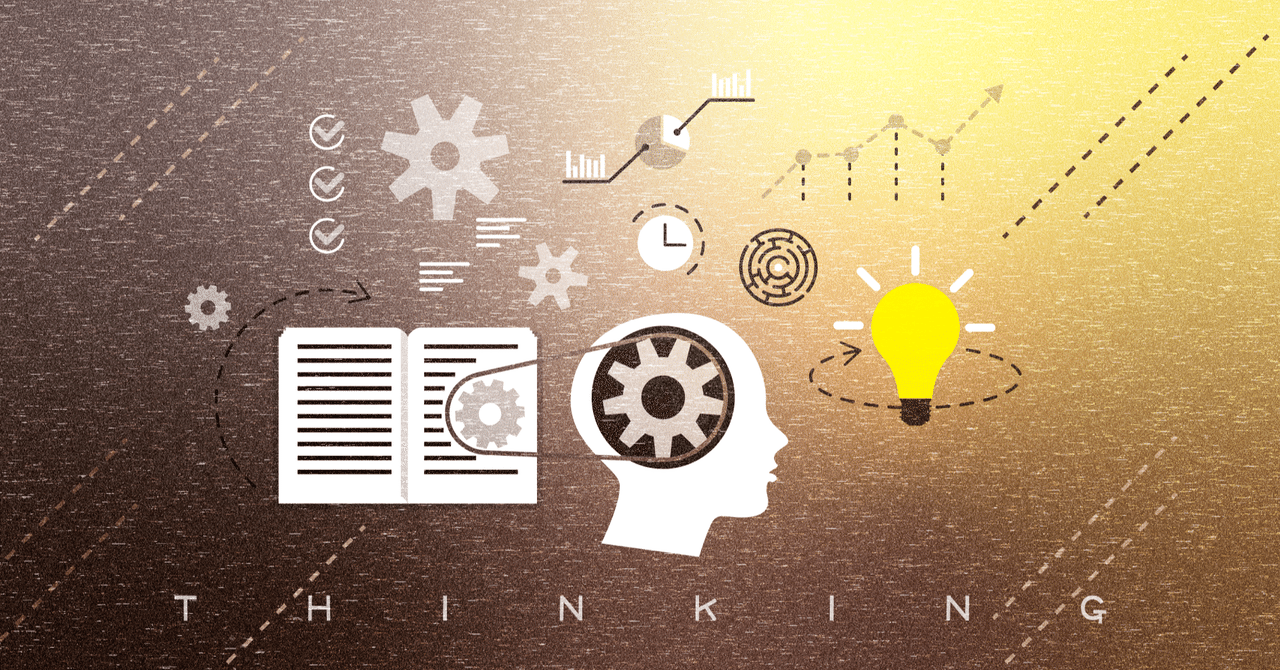最近の記事
- 固定された記事
【映画】「退屈な日々にさようならを」「街の上で」「サッドティー」を観に行ってきました(今泉力哉監督オールナイト上映『退屈な日々に街の上で』)感想・レビュー・解説
上映が始まる直前になっても、僕の前の席が空いていたので、もしかしたらここに今泉力哉が座るのか? と思った。というのも、少し前に観た「情熱大陸」で同じようなシーンがあったからだ。オールナイト上映の際に、客席の端っこに座っていた今泉力哉がそのまま登壇するというシーンだ。そして予想通り、今泉力哉が僕の前の席に座ったので驚いた。 というわけで、テアトル新宿で行われた「odessa Midnight Movies」の第19弾、「今泉力哉監督オールナイト上映『退屈な日々に街の上で』」を