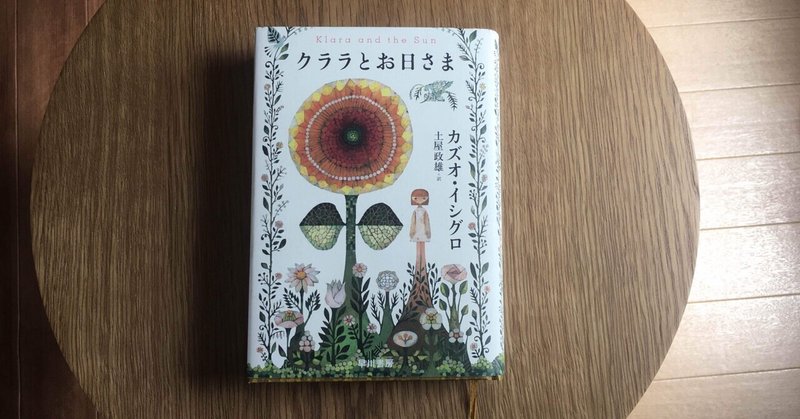
「クララとお日さま」で走った電撃。カズオ・イシグロを読むときは「ドM気質」があると良い
2021年に発表されたカズオ・イシグロの新作長編小説「クララとお日さま」を読んで、電撃が走った。それは、過去2作の長編小説「わたしを離さないで」「忘れられた巨人」からの布石とでも言うべき、カズオ・イシグロの思考の変遷が垣間見えたからだ。
本稿では「クララとお日さま」を読んで走った電撃についてと、カズオ・イシグロの小説世界の成り立ちやその魅力について語りたい。
※まだ読んでいない方でも小説を読む楽しみを損なわれないよう、物語の内容には触れずに書きます。ただ、一部文章の引用をしており、あらすじや展開を仄めかすことにはなっていると思うので、からっきしの情報ゼロで小説を読みたいと考えている方はお気をつけください。
「誰かが誰かを愛することはできるのか」を問う物語
カズオ・イシグロの小説では、「人と人との断絶」が描かれることが多い。カズオ・イシグロがノーベル文学賞を受賞したときの、受賞理由の文言がそのことを簡潔に表している。
壮大な感情の力を持った小説を通し、世界と結びついているという、我々の幻想的感覚に隠された深淵を暴いた。
私たちは友人や家族や恋人や会社の同僚など、多くのひとに囲まれているが、本当はとてつもなく一人なのかもしれなく、また、誰のことをも分かっていないのかもしれない。カズオ・イシグロを読むなかで、そんな考え方をするようになった。
「クララとお日さま」は、「愛」を描いた物語だと捉えている。カズオ・イシグロは過去2作の「わたしを離さないで」「忘れられた巨人」を通じて、誰かが誰かを愛することはできるのか、という問いと向き合っていたように思う。
「わたしを離さないで」では、臓器提供者として育てられてきたキャシーとトミーが、もし2人の愛が認められれば、自分たちは臓器提供の義務から開放され、生き続けられるのではないかという希望にすがる。「忘れられた巨人」では、老夫婦のアクセルとベアトリスが失われていく記憶を取り戻すために戦う。
しかし、彼らの人生をかけた闘争は物語的ハッピーエンドを迎えることはできない。生きることの不条理を突きつけられる結果となる。周りの環境が押し付けてくる制限が、彼らの願いを踏みにじる。
「わたしを離さないで」の語り手であるキャシーは、荒れ果てた草原の木の枝に、風で引っかかってはためいているビニールシートに自分を重ねる。彼らの戦いのあとには、どこへ向かうこともできないやりきれなさだけが残る。
カズオ・イシグロの小説世界で描かれる、決して届くことのない願い。それがカズオ・イシグロの小説のひとつの特徴であると言ってもいいくらいに、不条理に踏みにじられる個人が常に描かれてきた。
「クララとお日さま」は、AI(人工知能)を搭載したロボットのクララと病弱な少女ジェシー、そしてその恋人のリックの生を描く物語。そして「クララとお日さま」のなかにも、決して届くはずのない願いがあった。

淡々とした一人称の語りで進む小説世界
カズオ・イシグロの物語の特徴は、非現実的な、しかし全くのファンタジーとも言い切れない小説世界にある。さらに特筆すべきは、その小説世界を当然の前提としてその世界のなかで生きる主人公が、一人称で物語を綴っていくことにある。
たとえば、「クララとお日さま」の語り手はロボットのクララだ。「クララとお日さま」は、クララから見た世界が一人称で語られていく物語となっている。
当然、ロボットであるクララが切り取った世界は、わたしたちが知っている世界とは異なる。クララは機械学習によって人間の様々な行動様式や、目に見えている世界の不思議を日々学んでいく。
しかし、これまで目にしたこともない、自分の認知能力の限界を超えた出来事が目の前で広がっているとき、クララの視界は歪む。滑らかだった視界がいくつもの不連続な「ボックス」に分割されてしまう。以下は、クララが初めて車に乗ってドライブに行くシーンの語りである。
やがて、周囲の風景がどんどん変わりはじめて、変化の速さに整理が追いつかなくなりました。ある段階では、一つのボックスに車だけが何台も収まり、すぐ隣のボックスに道路と周辺の野原の断片が詰め込まれるようなことも起こりました。ボックスからボックスへの移行では、なんとか道路がスムーズな線状に保たれるよう努力しましたが、光景がこれほど絶え間なく変化していては不可能です。
(『クララとお日さま』p141〜142、土屋政雄=訳)
このようなクララが見た世界の描写は、さも当たり前のように語られる。「ボックス」という単語の説明は特にない。それは物語のなかでは極めて妥当である。なぜなら、クララの世界にとって「ボックスへの分割」という事象は、頻繁にではないものの、未知なるものに出会ったときにしばしば起こる、当たり前のものだからだ。
また、「クララとお日さま」のなかでは「AF」という単語が頻繁に出てくる。これも物語中に意味の説明はない。ただし、文脈のなかでこのAFという単語は、クララを含むロボットたちの呼称として使われている。そこで、この単語はおそらく「Artificial Friends(人工友人)」を示す略語だと推測できる。
カズオ・イシグロの小説では、わたしたちが現在見知っている世界とは違った世界が、一人称で語られていく。そのため、わたしたちの世界とは異なる世界を表すための、固有の単語が現れてくる。
ウィトゲンシュタインが「語の意味とは、その使用である」と言ったことを思い出す。先にあるのは単語ではなく、世界である。そのために特定の単語が必要になってくる。
「スマホ」という言葉は、スマホが出てきた世界でないと意味を持たない。江戸時代の商人にスマホと言っても、それは何のことやら理解できない。それと同じように、「AF」や「ボックス」といった単語は、「クララとお日さま」の世界のなかではじめて意味を持つ。
「ドM気質」が役に立つ
このような小説の特性上、カズオ・イシグロの世界に浸るまでには、多少の忍耐が必要だ。つまり、わたしたちが普段見知っている世界を相手にしていないので、主人公が最初は何を言っているかわからないのである。
だから、読み進めるには「ドM気質」とでも言うべきものが必要になってくる。つまり、「あ〜何言ってるか分からねえ、ぞくぞくするなあ」「興奮してきたな」といった、分からないことがキモチイイというドM気質が求められているのである。
そして、カズオ・イシグロの小説には極上の非日常の世界が広がっている。非日常的ではあっても、その世界のなかで不合理なところはない。辻褄が合っている。というより、物語を語る一人称の視点を固定し、淡々と目に映るものを写実、分析していくことで世界の合理性を保ちつつ、その一人称のなかの矛盾や不合理を同居させている。
つい何か小難しそうで分かっているっぽいことを書いてしまったが、言いたいことは、「分からないことも気持ちよいうえ、分かると最高にキモチイイ」ということである。丹念にひとつの情景を読み解き、それを手掛かりに次の風景を読み解く。こうしてパズルのピースをひとつひとつ集めていくように、語り手が見ている世界を丁寧に追っていく。
そうすることで、立体的に、そしてリアルに立ち上がってくる、カズオ・イシグロの非日常的世界。それは細部までほつれがなく、一度身を委ねてしまうともう戻ってこれなくなるほどの快楽を味わえる。それこそが、カズオ・イシグロの小説世界の大きな魅力なのである。
「クララとお日さま」の電撃
話は冒頭に戻る。「クララとお日さま」は「愛」を描いた物語だと思う。そして、決して届くはずのない願いが物語のなかにある。
生きることの不条理。叶わない希望。それを、今作を含めて過去3作、主人公たちは淡々と語ってきた。
その主人公たちのあり方は、「クララとお日さま」のクララにおいてひとつの帰結を見たように思う。そこに電撃が走った。雷に打たれたような気持ちになった。
回りくどい言い方になっているのは、まだ作品を読んでいない方を電撃の感覚から邪魔しないようにするためである。逆に、もし既に「クララとお日さま」を読んでいる方には、分かっていただけるのかもしれない。
「ドM気質」的見地から言えば、過去3作の間で焦らされてきたあとの帰結でもあったため、余計に気持ちよかった。だんだんと変態の文章になってきているように思うので、このあたりで終わる。
カズオ・イシグロの新作を、これまでずっと心待ちにしてきた。だから、「クララとお日さま」が発売されてとても嬉しかった。次はどんな作品を書いてくれるのか、今から待ち遠しい。
(終)
▼『クララとお日さま』
(追記)カズオ・イシグロをはじめて読む方におすすめなのは、非常に悩みますが、やっぱり「わたしを離さないで」かなと思います。
(追記の追記)筆者がカズオ・イシグロの世界に打たれたのは「日の名残り」を読んでからでした。(没落したイギリスの貴族に仕えてきた執事の話で、皇后陛下が心に残っている作品だという発言が沁みます)
(追記の追記の追記)カズオ・イシグロの「充たされざる者」は気持ち悪いくらいに人と人がすれ違い、話が噛み合わないという小説で、読むのはけっこう苦しいです。そして読み終わったあとも気持ちよくないという……。なのに、なぜか良いんですね。カズオ・イシグロ的世界観に浸かれるだけで良いのかも。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
