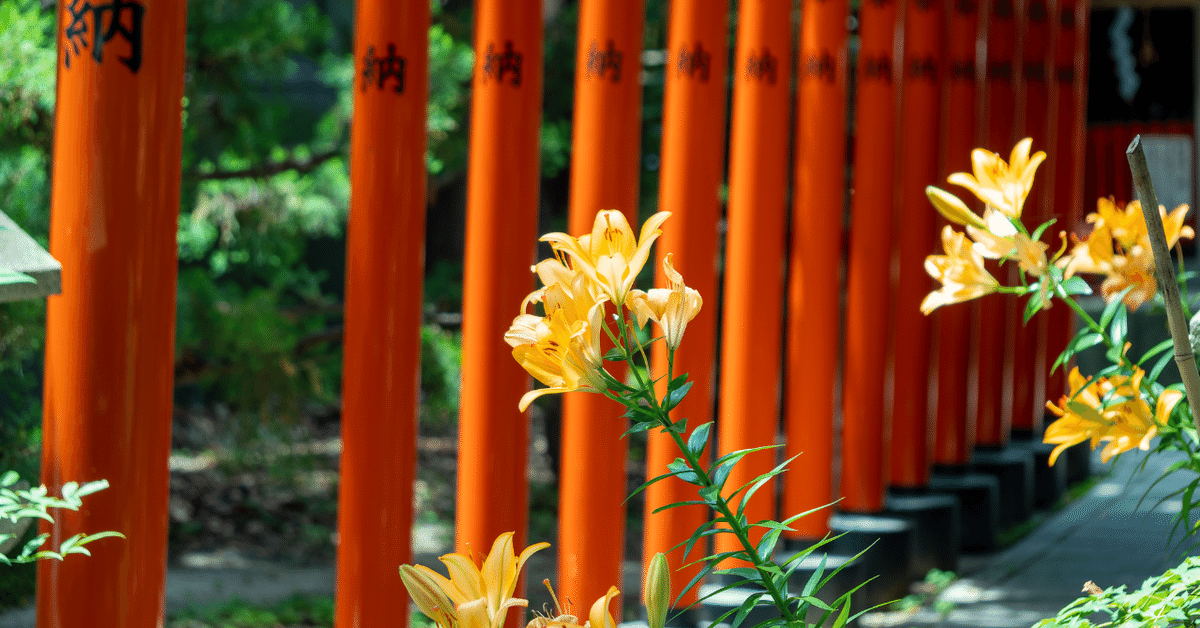
再魔術化するテクスト──カルトとスピリチュアルの時代の文化批評
第五回 コミューン主義の系譜 倉数茂
0 はじめに
前回までは、日本のカルト宗教について、オウム真理教と統一教会にフォーカスして考えてきました。その過程で見えてきたのは、カルトが日本と朝鮮半島の歴史的転変と深く絡み合い、かつ現在進行形の社会変容に根付いていることでした。
今回は「コミューン主義の系譜」と題して現代の「共同性」のイメージを検討します。これはまた、共同体についての問いを終生手放すことのなかった小説家としての大江健三郎を扱うための準備運動でもあります。
人と人が一緒にいる、それはごくありふれた事柄です。しかしその共同性のありかたは一様ではありません。現実で、そして想像力の領域で、どのように共同性のありかたが模索されてきたかが、今回のテーマになります。
宗教というと、我々はつい信仰対象(神か仏か、実在の人物か)や教義の内容に注目してしまいます。けれども人が宗教に入るのは、まず信仰ありきではなく、人とのつながりを求めてです。
そのつながりへの希求という点で、宗教は他の社会的実践と曖昧に混じり合っています。人はいつでも何らかのつながりを求めているからです。連載第三回「カルトはわたしたちの間に(2)」で述べたように、現代は「個人化」の時代です。そして宗教の問題はいつでも共同性への問いと結びついていました。
整理すると、戦後に飛躍した創価学会のような新宗教に入信したのは、高度成長の過程で故郷より流出し、都市で働くようになっていたバラバラの個人でした。彼ら・彼女らは、故郷での地縁血縁に代わる心の拠り所となる共同体を求めたのです。
その後、組織による拘束を嫌う「個人化」の趨勢が進展すると、教団としての一体性よりも、個々人の「ほんとうの自分」を重視する新新宗教が勢力を伸ばします。その極限が、集団生活を行いながらも個人的な修行による「解脱」を目指し、グル麻原彰晃との直接的なつながりが何よりも優先されると考えたオウム真理教です。
さらに占いやチャネリングのようなスピリチュアルになると、教団や教祖を否定し、個々人が自由に「自分自身」を追い求めるようになります。けれどもそのようなスピリチュアルでも、人とのつながりは否定されません。スピリチュアル・カルチャーを支えるのは、さまざまな領域・分野にびっしりと広がった人間関係のネットワークです。そしてまたどのような宗教でも信者同士のつながりを完全に断ち切ることはできません。宗教の内側と外側で、人は理想の共同性を探し続けています(注1)。
「個人化」の時代が始まる端境期である1970年代に注目を集めた共同体にコミューンがあります。今回は奥泉光のコミューン小説『葦と百合』を足掛かりにコミューンという共同体について考えます。
それは同時に80年代の文学に普遍的に存在していた「神話的想像力」について確認することにもなるはずです。この時代の優れた作家やクリエイターたちは、「個人化」の趨勢の中で、ありうべき「共同性」の輪郭を描くために、しばしば神話に近しい想像力を発揮したのでした。
コミューンとは、個人が自由意志に基づいて結成する契約共同体であり、参加者は同じ空間で生活しながら、労働と消費と家計の共同を目指すものです。
日本でも1960年代から70年代に全国にコミューンが設立されました。それらの多くは、同時代のカウンター・カルチャー、あるいはヒッピー・カルチャーに根ざしています。若者たちは、自然を搾取する近代文明や国家のあり方を否定して、コミューンに参加したり自ら設立したりしました。もっともその中で今も存続しているものはわずかです。
一方、ヤマギシ会のようにカルト性が指摘されるコミューンも存在します。カルトはしばしばコミューンを形成するし、コミューンはカルトに接近することもあります。どちらも外部世界から自立し、内的な一貫性を追求するからです(注2)。
とはいえ、コミューン運動が活気を持っていたのは70年代いっぱいくらいとみなしていいでしょう。80年代には行き詰まりが明らかになり、同時に若者たちの反体制運動もあさま山荘事件と頻発する内ゲバによって消耗していきます。
日本の小説の中に、国家創設やコミューンの問題が登場するのはこの頃です。
それらは、現実では敗北しつつあった60年安保以降の政治闘争と社会運動を総括し、想像力の水準で引き継ごうとするものでした。勢い、それは極めて両義的なものにならざるを得ません。
(注1)内閣府が行なっている世界青年意識調査では、「友人や仲間といるとき」に充実感を感じると答える若者の割合は90年代以降、一貫して70%以上と高いのに対して、2000年代以降友人関係が「悩みや心配事」の対象だと答える割合も増えています。この調査は18〜24歳の若者を対象にしたものですが、個人化が進んで他人に縛られずに生きられるようになればなるほど逆に他人との「つながり」を求め、同時に友人関係が悩みの種となっている様子がうかがえます。(土井隆義『つながりを煽られる子どもたち ネット依存といじめ問題を考える』岩波ブックレット、2014年)
(注2)ヤマギシ会は1953年に篤農家山岸巳代蔵により創設された農業団体。「自然と人為の調和を基調とした理想社会」を唱えて、共同生活、共同所有による農業・養鶏を行っています。70年代には鶴見俊輔、見田宗介など知識人が好意的に論じたせいもあって、世間の注目を集め、規模を拡大しました。農業法人としても成功し、今でも全国規模の販売網を持つトップクラスの農業共同体です。一方、入会時に全財産を寄付することや、特講という講習会が洗脳に近いカルト性を持つと批判されています。
1 「国家論的小説」と「ルネサンス的文学」
文芸批評家の斎藤美奈子は、1970年代以降を記述した数少ない文学史である『日本の同時代小説』で、1980年代を扱った章のタイトルを「遊園地化する純文学」としています。80年代のポストモダン文学が新奇さと面白さを追い求めた結果、なんだか非現実的なものになってしまったという揶揄の込められたタイトルです。
実際、小林恭二の『ゼウスガーデン衰亡史』(1987)では、「下高井戸オリンピック遊戯場」というみすぼらしい遊園地が、好況の波に乗って急成長し、ついには日本全体を乗っ取るまでになります。「ゼウスガーデン」と改名したのち、ありとあらゆる快楽・美食・驚愕・感動を提供する巨大テーマパークとして、世界中の人々が憧れる場所になるのです。1973年の『日本沈没』で小松左京が日本列島を水没させたのと比べれば180度の転換です。
経済に勢いのあった80年代、日本の都市文化に未来的なイメージをみるのはそれほど珍しいことではありませんでした。サイバーパンクSFを誕生させたウィリアム・ギブスンの『ニューロマンサー』(1984、邦訳1986)は「チバシティ」を舞台にしていましたし、SF映画『ブレード・ランナー』(監督リドリー・スコット、1982)でLAの夜景を彩るネオン広告は日本語でした。映画監督のアンドレイ・タルコフスキーは1972年とかなり早い時期に、『惑星ソラリス』の未来都市を東京の首都高速で撮影しています。
しかし共同性・共同体に注目する我々の観点からすると、斎藤美奈子の指摘で目を引くのは、80年代には小説による国家論が多数なされたという部分です。斎藤はそれらを「国家論的小説」と呼び、代表的なものとして『同時代ゲーム』(大江健三郎、1979)、『吉里吉里人』(井上ひさし、1981)、『裏声で歌へ君が代』(丸谷才一、1982)、『虚構船団』(筒井康隆、1984)を挙げています(ここに前述の『ゼウスガーデン衰亡史』1987を加えることもできます)。そして共通点は①架空の国家の創建と歴史が語られる、②架空の国家は日本と対立的な立場にある、③その結果として戦争が勃発する、の三つだとします。これらは架空の歴史を語るものですから「偽史的小説」と呼ぶことも可能です。
これらの「国家論的小説」には、「政治の季節」が終わったから可能になった、どこかひんやりとした感触があります。つまり、それらは国家という政治的存在を扱っているのにもかかわらず、現実の政治や権力からは距離を置き、いわば実験室で国家というものの成り立ちをシミュレーションしているようなきらいがあるのです。
一方柄谷行人は2004年に過去を回想した文章で、1980年代の日本の文学にはある種の「文芸復興」(ルネサンス)があったと書いています。「一九七〇年代後半に『日本近代文学の起源』を書いたときも、私は「日本近代文学の終焉」を感じていた。しかし、それは旧来の文学に代わって、別の文学が台頭するだろうという予感であった。事実、一九八〇年代には、近代文学の支配下で排除されていたような形式の小説が多く書かれたのである。」(注3)
柄谷はこのあと、「近代小説の観念への根本的な疑い」を持っていた夏目漱石が回復しようとしていたのもスターンやスウィフトのような「ルネサンス的文学」の可能性であったと言います。つまり80年代にはひそかにルネサンス=漱石的な文学が復活していたというのが柄谷の主張です。
しかしながら、その可能性は十分に展開されなかったとします。「予期に反し、一九九〇年代に入って、ソ連邦が崩壊しグローバルな世界資本主義の浸透が進むにつれて、文学は新たな力を持つどころか、急激に衰え、社会的なインパクトを失い、文字通り、「近代文学の終焉」が生じたのである。しかも、それは日本だけの現象ではなかった。」(注4)
では80年代の「ルネサンス的文学」とは具体的にどのようなものを指しているのでしょうか? この文章では具体的な名前は挙げられていませんが、過去の柄谷の批評を辿っていけば、盟友である中上健次や、ずっと注目し続けた大江健三郎、さらに『神聖喜劇』(1980)の作者大西巨人、『意味の変容』(1984)の森敦などが自然に思い浮かびます。彼らは皆、戦後文学や私小説の遺産を引き継ぎながら、そこを越えて近代リアリズムの外側に向かった作家たちです。そしてその際に活用されたのが文化人類学や民俗学の知見でした。そして確かにそこには『吾輩は猫である』や『トリストラム・シャンディ』にも通ずる博物学的なジャンル混淆性が見られるかもしれません。
さらに20世紀の学問的成果を大胆に取り入れつつ、ブッキッシュでスケールの大きな作品世界を作り上げるというのは、世界的な文学動向でもありました。膨大な知識を動員しつつ、寓意・風刺文学としてのポストモダン・メガノベルを次々に発表している北米の作家たちがおり(『V.』、『重力の虹』のトマス・ピンチョン、『やぎ少年ジャイルズ』のジョン・バースなど)、一方ホルヘ・ルイス・ボルヘスとガルシア・マルケスをツー・トップとしたラテンアメリカ文学のグローバルな「ブーム」がありました。それらは世界文学の最新形であると同時に、メルヴィルの『白鯨』やラテンアメリカ原住民神話への回帰でもありました(注5)。
大江や中上といった作家たちは、近代文学以前の「神話」や「物語」を復活させました。しかし、単に神話的なものの復興であれば、むしろ同時代のサブカルチャーにも見られたものです。そして柄谷はサブカルチャーに浸透された村上春樹以降の文学は強く否定しているのです。であれば、80年代の文学における「神話」の意味を注意深く見極める必要があります。同時代に、代表的な小説作品があまりに安易に「物語」の定型に淫していると「物語批判」の論陣を張ったのが蓮實重彦でした。
我々は、奥泉光をそうした80年代の神話作家の最終ランナーと位置付け、初期の代表作『葦と百合』を分析します。それは当時の文学的想像力が、人間の共同性の形をどのように描き出そうとしたかを検討するものになります。
しかし1990年代以降は、現実でも物語の上でも、コミューンの形象は消えていったように思えます。理由は、人々がイメージする共同性のあり方が変化したからでしょう。現代では、コミューンのような凝縮力の高い集団を維持することは困難です。むしろ今求められているのは、コミュニティの中にいかに差異を、あるいは隙間を導入するかです。共同体の内部に、多様性と自由を維持すること。しかしそれはどのように可能なのでしょうか。
(注3)『定本日本近代文学の起源』岩波現代文庫版、1ページ
(注4)前掲書、2ページ
(注5)ちなみに柄谷行人は1980年代から90年代にかけて大きな影響力を持った文芸批評家でしたが、2000年代の初めに文芸批評家廃業を宣言し、『トランスクリティーク カントとマルクス』(2001)、『世界史の構造』(2010)と、歴史と文化人類学と宗教学を組み合わせた独自の歴史哲学の確立に向かいます。これは柄谷にとって、80年代の「ルネサンス文学」の可能性の別分野での追及であったのかもしれません。
2 コミューンの時代
『葦と百合』は1991年に発表された奥泉光の初長編です。
作品は新潟に向かう新幹線の車中から始まります。そこで交わされる会話は、同年代の若者同士の気安い冗談交じりのものですが、しかしそこで言及されるのがロマン派の音楽であり、芸術についてであることは作品の主題と深く関わっています。やがて主人公の式根は、友人と別れて山中にあるコミューン「葦の会」へ単身向かいます。
30代の若い医者である式根には、高校時代、友人の時宗に恋人の翔子を奪われた思い出がありました。その出来事の舞台が「葦の会」で、式根と翔子は短期体験のつもりでコミューンの農作業に参加したのですが、翔子はそのまま「葦の会」に残ることを決意し、先に入会していた時宗と生きていくことになったのです。
しかし実際にコミューンがあった場所を訪れてみると、「葦の会」は無人になり、翔子と時宗は数年前に失踪しています。
打ち捨てられたコミューン跡に一晩泊まった式根は、幻めいた時宗から、翔子と時宗は「森の奥のコミューン」にいると告げられます。二人はそこで現代文明を完全に拒否して暮らしているというのです。さらに同行者の死にも遭遇し、式根はますます葦の会の謎に巻き込まれていきます。失踪した高校時代の友人と恋人に何があったのかというミステリーと、現実と幻想が入り混じる複雑なナラティブが物語を駆動していきます。
「葦の会」は生産手段一切の共同所有に基づく農業を行い、全員合議制による運営をしていた団体という設定です。けれども作中ではすでに破綻し、人々の矛盾する証言の中にしか存在しません。ダイレクトに「葦の会」の姿は描かれず、そればかりか謎は増殖し、語りは錯綜していきます。この作品はある種のアンチ・ミステリであって、式根が実像に近づこうとすればするほど、本当の「葦の会」は陽炎のように遠のいていきます。なぜか?
それは奥泉にとって重要だったのがコミューン運動の現実ではなく、むしろその理念性、あるいは神話性だったからです。奥泉はコミューンを、不可能だが、その不可能性において人を魅惑する夢のように描いています。その理由を理解するためには、まず同時代の社会と文学の状況を一瞥する必要があります。
コミューンとは生産と消費の共同に基づく平等なコミュニティであり、近代の分業と貨幣経済によって失われた稠密な人間関係の回復を目指すものです。
そもそも狩猟採集社会では、人々は数十名のバンド(集団)で移動しながら生活し、獲得した食料は平等に分配されることが知られています。生活と仕事はまだ分かたれておらず、家族も、現代の核家族のように周囲の人間関係から分離されていません。
農業が始まるとこうした小共同体は人類の傍流に追いやられますが、平等で疎外のない共同体への希求は、あたかも伏流水のように繰り返し登場します。16世紀の再洗礼派によるミュンスター蜂起、シャルル・フーリエの計画したファランジュ、ロバート・オーウェンのニュー・ハーモニーなど、歴史上に現れて消えていったコミューンは数しれません。
しかし現実社会から見れば、コミューンは火花のように儚い現象であり、「見果てぬ夢」のレベルを超えるものではありませんでした。
最初に述べたように、日本に「葦の会」のようなコミューンがいくつも生まれたのは60年代から70年代のことです。例えば新宿で生まれたヒッピー・グループ「部族」は1967年ごろから各地に散らばり、絶海の孤島から国分寺の街中まで、少なくとも6つのコミューンを設立したようです(注6)。
なぜ、当時の人々はコミューンに向かったのか。それはやはり、反体制運動が高揚した季節が過ぎ去り「革命」が不可能になったからでしょう。直接政治闘争に参加するにせよ、しないにせよ、60年代には社会を自分たちの手で変革できると信じる楽天的な雰囲気がありました。その空気が失われた時、もはや救済不可能な社会から独立して、新たな別の共同体を作るしかないと信じた人々が一定数いたということです。
社会からの撤退と敵対。これはまさに連合赤軍が辿った道でもありました。
1971年に共産主義者同盟赤軍派と京浜安保共闘革命左派という二つの新左翼セクトが合流して生まれた連合赤軍は、都市部での闘争に展望を見出せず、毛沢東にならって山岳ベースを設置します。群馬県の山中に作られた山岳ベースで共同生活をしながら軍事訓練を行う途上で、12名のメンバーがリンチにより死亡するという凄惨な事件を起こし、大きな衝撃を引き起こしたのでした。この事実が明らかになったのは、連合赤軍が長野県の山荘に立て篭って警察と銃撃戦を行った「あさま山荘事件」(1972年)の取り調べによってです。
大江健三郎の1968年の作品に『核時代の森の隠遁者』という短編があります。『万延元年のフットボール』の後日譚であり、四国の住職がアフリカにいる「蜜三郎」に送った手紙という形式になっています。そこに深い森に隠れすみ、時折里に降りてきて警告を発する隠遁者ギーという人物が登場するのですが、彼の言葉は詩の形をとっています。
核爆弾と人工衛星が撒きちらす/放射能の灰とラジオ光線の毒とに/ありとある市 ありとある村の/人間 家畜 栽培物が侵食される時/森におこっているのは驚くべき/生命の更新である。/森の力は強まり/ありとある市 ありとある村の/衰弱は 逆に 森の回復である。/放射能の灰とラジオ光線の毒こそは/樹木の葉と地面の草と湿地の苔に/吸収されて「力」となるからだ。/樹木と草の葉が炭酸ガスに殺されず酸素を生むことを見よ/核時代を生き延びようとする者は/森の力に自己同一化すべく ありとある市/ありとある村を逃れて 森に隠遁せよ!
森へ「隠遁」せよと説くこの詩も、社会を捨てて自然の中に立てこもるしかないというメッセージを発しています。空から降り注ぐ放射能、その毒を受け止めて、吸収し、ますます繁茂し領域を広げていく神秘の森。人は自然の支配者であるという驕りを捨て、森の奥に分け入り、自然に自分を譲り渡さなければならない、と、ほとんど二十年後の『風の谷のナウシカ』をそのまま予告しているようなイメージですが、大江の黙示録的な想像力の射程は、のちのエコロジーも越えて未来へ伸びていたと言っていいでしょう。
以上のように当時の「コミューン」という言葉は、ヒッピー風の文明を捨てて自然と共存する素朴なコミュニティというイメージと、国家に抗して打ち立てられた直接民主主義権力という政治的なイメージの間を揺曳しています。後者のモデルはマルクスが「労働の経済的解放を成し遂げるためのついに発見された政治形態」(『フランスの内乱』)と呼んだところのパリ・コミューンです。
新左翼の文脈で言えば、コミューンは、党や国家の官僚制支配(つまり現存する社会主義としてのソビエトや日本共産党)も、軍事力にものを言わせてベトナムを蹂躙するアメリカ主導の西側資本主義も、共に拒否できる第三の道として肯定されました。それは暴力も辞さず、国家と直接に対峙する民衆蜂起でした。
『日本浪曼派批判序説』で右翼思想の再検討から出発した政治思想家の橋川文三は、大政奉還直後の慶応4年、島根県の離島隠岐の島民およそ3000が、支配者であった松江藩の侍を追放し、81日間の自治に成功した「隠岐騒動」を「隠岐コンミューン」と呼んで次のような文章を残しています。
彼らは、天皇の心に直接に結びついた平等な人間の組織体として自覚し、その間に介在する中間的権力を否定することによって、自治的な政治共同体を樹立することになった。それはほとんど自由と平等と友愛を原則とする「ネーション」の純粋培養形態といってよいものであった。ただ、その正統性の根拠が具体的な天皇の自然意志に求められ、純粋な個人の意志の統一形態――あの「一般意志」という抽象的実体に求められたのでないことがちがっていたが。(注7)
橋川は自治的政治共同体としてのコミューンを最小のネーションだとします。土地と郷土愛に根ざし、藩と政府の抑圧を破砕する小さな「くに」としてのコミューンが、もしも維新前後に百も成立し、それらが緩やかな連合を組んでいたら日本はどうなっていただろうか、というのが橋川の問いかける可能性としての「歴史」です。
中国文学者の竹内好もまた『明治維新百年祭・感想と提案』(全集第8巻)(注8)という文章で「私は、明治維新はその結果である明治国家よりも大きいと考える」と書いています。理由は、明治国家は維新が孕んでいた「多様な可能性」――民衆が待ち望んでいた自由と平等――のごく一部しか実現せず、結果的にアジアを侵略する軍事国家に変貌していったからです。それゆえ、明治維新は「裏切られた革命」(トロツキー)であり、日本は維新の瞬間にまで立ち戻って民衆権力の可能性を追求するべきだというのが竹内好の言いたいことでしょう。橋川文三と共通する思考があるのがわかります。
つまるところ、コミューンへの関心には、ますます力を増大させていく国家から身を引き剥がし、近代とは異なる社会編成を探究するという動機があったのです。
ところで、奥泉光もまた、外部から孤立したコミュニティに関心を向けてきた作家でした。ただし、その際彼が注目するのは、新左翼運動と軍国主義の連続性です。
一般には奥泉光といえば『浪漫的な行軍の記録』や『神器 軍艦「橿原」殺人事件』など太平洋戦争末期の酸鼻な戦場を、幻想まじりに描く長編で知られています。太平洋戦争に拘り続けているという意味で、ほとんど戦後派の隔世遺伝のような作家なのですが、その戦争モチーフには同時代の社会運動への興味も伏在しています。そのことは作家自身が次のように語っていることからも明らかです。
1980年に大学の学部を卒業した自分にとって、70年代は中学生から大学生までの時期にほぼ重なる。七二年の連合赤軍リンチ殺人事件をはじめ、内ゲバの陰惨な暴力は、自分自身が直接遭遇することはなかったけれど、その匂いだけは存分に嗅いでいた。いわば自分の原風景ともいうべき七〇年代を、想像力のうちに捉えていく過程で、アジア太平洋戦争の時代が、また広く日本の近代が視野に入ってきたのであり、自分は、いくぶん散漫にではあるけれど、戦争の時代に関わる文献を読みはじめたのだった。(注9)
過激化した新左翼諸党派、軍国主義下の日本。いずれも外部との関係を失って視野狭窄に陥り、奔騰する死の欲動に突き動かされて血飛沫を撒き散らしながら破滅へ向かっていきました。その病的な心理の解明こそが奥泉のモチーフと思われます。そうした集団のことを「カルト的」と呼ぶことも可能でしょう。
奥泉が初長編の題材にコミューンを選んだのにも、そのような孤立した共同体への関心があったものと思われます。
(注6)雑誌『スペクテイター』第45号 日本のヒッピー・ムーヴメント、エディトリアル・デパートメント、2019年
(注7)『ナショナリズム その神話と論理』kindle版105ページ、ちくま学芸文庫、2015年
(注8)『竹内好全集全集』第8巻、筑摩書房
(注9)『石の来歴 浪漫的な行軍の記録』講談社文芸文庫版の「著者から読者へ」kindle版286ページ
3 「立てこもり」から「ひきこもり」へ
繰り返し述べているように、1970年代以降、日本社会では「脱拘束」志向のもと、「個人化」が進展しました。資本主義は自由になりたいという欲望を開発して引き受け、様々なサービスを提供することで、「個人化」を推し進めます。
しかしながら人間は自由とともに「つながり」も求める生き物です。その「つながり」を求める欲求はどうなってしまったのでしょうか?
社会学者石田光規は、「つながり」への欲求に対して、資本主義は二通りの解決を提供したと指摘しています(注10)。
ひとつは貨幣を介する対人サービス、典型的にはホストクラブやガールズバーなどです。そこでは飲食の提供を名目に、ホストやホステスとの会話・人間関係が販売されます。こうした業態が街に増加し、多様なニーズを受け入れるべく細分化していったのが21世紀です。(メイド喫茶は2000年の秋葉原に始まりますが、今ではさまざまなコンセプトカフェが存在します)。
アイドル産業もこうした対人サービス業に数え上げられるでしょう。21世紀になって変わったのは、それまでテレビなどマスメディアから発信する「特別な人」だったアイドルが多様化し、ユーザーの近くまで降りてきて、ある程度「個人的な関係」を結べるようになったことです。しかしそこにある種「宗教」的要素も内在していることは連載第一回で論じました。アイドルというのは半ばは実在する現実の他者であり、半ばは容易に手の届かない幻想のイマージュです。
そしてもうひとつはSNSに代表されるITサービスです。固定電話が携帯電話に変わっていくように、まさに情報技術は個人化に即応しつつ、人と人とを結びつけるよう発展してきました。ポケベル(1996年が利用者数のピーク)、携帯電話(一般化したのは90年代後半)、スマホ(iPhon発売は2007年)といった転換にその様子をまざまざと見ることもできます。今ではSNSは我々の人間関係の重要な、中核ですらある要素になっています。
とすると、コミューン運動は、1970年代という、個人化が始動しつつも資本主義的対応策が浸透する以前の時期に属していることがわかります。いわば端境期です。中間団体は衰退しつつあったけれども、まだネットは存在しません。面識のない人と、ITを通じて、親密なコミュニケーションをとるなんて思いもよりません。だからこそ、人々は、新たな「つながり」のあり方を構想する必要(あるいは余裕)があったのでしょう。
では、コミューン運動の時期と現代の間で何が変化し、何が失われたのか。答えは明らかです。失われたのは「集団」、或いは「共同体」であり、つながりへの欲望は断片化されたのです。70年代、人々のつながりへの欲望はまだ共同体の輪郭をまさぐっていました。現代のつながりにそうした集団性、共同性はありません。あるのは金銭とネットを介した、多様でにぎやかだけど、個人と個人のコミュニケーションです(注11)。
「集団」の形象が失われたことは、「立てこもり」小説を一瞥してみてもわかります。
1973年、大江健三郎は『洪水は我が魂に及び』という立てこもり小説を発表します。これは1968年に起きた在日朝鮮人二世の立てこもり事件(金嬉老事件)に想を得て執筆を始め、あさま山荘事件の報道を見ながら書き継がれたものでした。物語は、障害児の息子と暮らす中年の小説家が、「自由航海団」という少年グループと山中の別荘に立てこもり、やがて警察と対峙するというものです。障害児の息子を抱えた主人公の小説家大木勇魚は、自分は樹木と鯨の代理人であると自己規定しています。どちらも人間を超えた大きく尊い生命体ですが、捕鯨と環境破壊によって危機に瀕しています。彼がいる別荘にやってくる少年たちは、集団就職で東京に出たものの、職場を放棄して逃走し、大型船で海に出ることを望んでいます。実在の人物で言えば、集団化した永山則夫のような若者たちです。
水爆で人間世界がすべて滅びる戦争が始まれば、おれとジンとは核シェルターのおかげで 最後に死ぬ者になるだろうから、その最終の日には、地球上の鯨と樹木すべてに、きみたちを滅亡させようとしてきた人類がいま滅びる、それを君たちの代理人として歓迎すると送信しようと思っていた。(注12)
大木勇魚はこう言って、山荘を取り囲む警察隊に向かって銃弾を放ちます。彼は人類に対して「自然」の側に立ち、鯨や樹木の代わりに死んでいこうとしているわけです。
10年後に安部公房が発表した『方舟さくら丸』もよく似た内容を持っています。こちらでは山中の建物の代わりに、放棄された採石所が主人公たちのシェルターとなります。二つの作品に共通するのは、世界が核戦争の危機に瀕していると認識し、そこからの離脱=航海(ノアの箱舟のイメージです)を夢見つつ、核シェルターに逼塞するという筋立てです。しかし安部公房の作品ではもはや大江健三郎のようなパセティックさを維持できず、スラップスティック化しているという印象を受けます。主人公たちが対立するのも、国家権力ではなく、「ほうき団」という老人たちばかりの自警団(?)です。約10年が経ってあさま山荘事件の記憶もパロディの対象になったのでしょうか。(さらにエンタメ小説から「立てこもり」ものを一冊選ぶなら、宗田理のロングセラー『僕らの七日間戦争』(1985)でしょう。)
現実社会の総体を拒否してそこから離脱すること。少数の人間集団が、近代を捨てて、生き残りのためにオルタナティブな道を進むこと。こうしたモチーフが当時の社会には確かに広く共有されていました。コミューン運動もその一部であったといえます。
それに対して、2000年代に作家たちの創作欲を刺激したのは「引きこもり」でした。21世紀初頭には村上龍『共生虫』(2000)、阿部和重『ニッポニア・ニッポン』、滝本竜彦『NHKへようこそ』(ともに2001年)といった作品が書かれています。村上龍と阿部和重の主人公はともにある種の「テロ行為」を行うのですが、もはやそこに同志や仲間はいません。『NHKへようこそ』の場合は、敵さえ同定できず、自覚的に陰謀論に逃げこもうとして失敗します。「立てこもり」から「ひきこもり」へ。つまり社会からの離脱や抵抗は、「集団」とはかかわりのない、孤独で孤立した行為としてしかイメージできなくなったのです。抵抗の拠点としての「共同体」はリアリティを喪失しました。
ここまできて、なぜ奥泉光がコミューンを直接描くことがなかったかを理解できます。『葦と百合』は共同体が輝きを持ち得ない時代、コミューンが不可能な時代に書かれたコミューン小説なのです。それゆえ、物語の現在時で、「葦の会」はすでに廃墟になっており、式根がありし日のコミューンについて知ろうとすればするほど真相は遠のいて、幻想ばかりが膨れ上がります。
(注10)「資本主義システムにおける人間関係の外部性」『個人化するリスクと社会』勁草書房、2015年
(注11)2000年代にはネットでの「つながり」の集積(つまりは「ネットワーク」)が新たな政治的主体を立ち上げる可能性が肯定的に語られました。「集団」としての同一性などなくても、人々は協調して行動できるし、政治的選択も可能だというわけです。世界的ベストセラーになったネグリ&ハートの『帝国』(原著2001年、翻訳2003年)は接続された人民を「マルチチュード」と呼んで変革の可能性を託し、東浩紀は、いずれITが国民のニーズを人の介在なしにまとめ上げるようになると論じました。(『一般意志2.0』2011年)しかし、2010年代に入るとSNSが社会の分断を引き起こしているという論調の方が強くなり、ネットワークへの期待は萎みました。
(注12)新潮文庫版下巻140ページ
4 アジア主義と幻想の〈村〉
なぜ「集団」のイメージが欠落していったのか。
差し当たりの答えとしては、国家と個人の間に位置する中間集団(労働組合、政治党派、青年団、町内会など)が力を失っていったこと、さらに、新自由主義によって意図的にその解体が進められたことが挙げられます。ただし、そこにも1990年半ば頃を転機とする変化はあり、それまでは衰退する中間集団を補完するものとして「企業・職場」が機能していたのに対し、90年代以降はより直接的な「個人化」が進行したという違いはあります。55年体制下で社会保障の充実が図られるわけですが、欧米とは異なって福祉制度が企業に多くを肩代わりさせるものだったために、日本の福祉国家化は国家と企業、さらにそこに労働者を送り込むための学校が緊密に協力し、独特の集団主義的で男性優位の管理空間を構成することに帰結しました。(筆者は60年代の学生運動、ヒッピーイズム、80年代の反管理教育運動、90年代の悪趣味カルチャーと掲示板文化、小林よしのりらが主導した若者文化としての「ネトウヨ」などを、このような昭和晩期を覆っていた「息苦しさ」──とりわけ中流階層子弟にとって切実だったそれ──との関連で考察する必要を感じています。しかし今は60年代から70年代にイマジネーションのレベルで、新たな共同体のイメージが探し求められた、ということを確認するにとどめましょう。)
ところで柄谷行人は、竹内好と大江健三郎を論ずるなかで、「近代日本の言説空間」を国権(国家主義)と民権(民主主義)、西洋とアジアという二つの軸の交わる座標として考えることを提案しています。柄谷の考えでは、明治から現代にいたるさまざまな「思想」をこの座標に配置することができるのです。

この座標が示すのは、日本の近代が西洋とアジアという二つの極に引き裂かれたものとしてあったということです。日本近代の思想の「発展」や「転向」は、それぞれの象限を飛び移るようなものとして現れます。例えば福沢諭吉のような近代主義者は、脱亜論を唱えてのちに、帝国主義者に転じました。つまり第一象限から第三象限への移行としてありました。
しかし柄谷が強調するのは、太平洋戦争の敗戦とともに座標の左半分が言説空間から欠落したことです。
戦後の言論空間は、いわば右半分の第Ⅰ象限と第Ⅳ象限に閉じ込められている。左半分はタブーである、といってもよい。そして、一般に大江はこうした戦後の言説空間に忠実な旗手であるとみなされる。しかし、というより、それゆえに、小説において、彼は左半分にのみこだわっているというべきなのだ。『万延元年のフットボール』にかぎらず、語り手としての「僕」は、きまって第Ⅰ象限におかれている。「僕」は、戦後日本の状況そのものである。それは性的に不能で、非活動的で、自閉的である。そして、「僕」が怖れかつ惹きつけられる「弟」的人物は、いわば第Ⅲ象限にある。注意すべきことは、この第Ⅲ象限が言語的でないということである。それは、いつも「なにごとか狂気めいた暗く恐ろしいもの」である。いいかえれば、「僕」が意識にあるならば、「弟」はエス(無意識)にある。そして、後者は言語化(意識化)されれば、しばしば第Ⅱ象限としてあらわれる。(注13)
『万延元年のフットボール』における凄惨な出来事、暴力はすべて”アジア”と関わっています。それは太平洋戦争中の記憶であったり、在日朝鮮人の”スーパー・マーケットの天皇”の襲撃であったりします。つまりこの作品には「アジア主義」が横溢しています。これは”戦後民主主義者”を体現してきた言説人としての大江にはありえないことです。
柄谷は、1960年代の新左翼運動が一時的に「アジア主義」を回復させたとします。文化大革命への親近(毛沢東主義)がそのようなものです。そして我々の文脈に従えば、コミューン運動もそうだと言えるでしょう。
しかし戦後の文学・思想に目を凝らすなら、地下の鉱脈が露頭するように、あちらこちらに「アジア主義」が姿を見せていることに気づきます。むろん必ずしもアジア諸国と関わりがあるわけではありません。それは右翼と左翼、国家主義と個人主義が分かたれる以前の地点まで遡行し、前近代的で自生的な秩序・共同体の生成の現場に立ち戻ろうとする思考のことです。そして、共同体の起源を語る言説は、一般に「神話」と呼ばれます。
近代政治体制としての国民国家とそれを支える制度としての三権分立や間接民主主義「以前」に立ち戻る「アジア主義」の思想は、国家以前の自生的コミューンを評価します。例を挙げれば、戦前の農本アナキスト権藤成卿が唱えた「社稷」や、中国の基層社会に着目するものとなります。
また日本の近現代に範を取ると、世直し、維新の騒乱、尊王攘夷などへの民衆史的関心となるでしょう(注14)。
この「アジア主義」――必ずしもアジア諸国を論じているとは限らない――の系譜には、戦前の大本教弾圧をモデルに『邪宗門』(1966)を書いた小説家・中国文学研究者の高橋和巳や、被差別部落の「路地」に反近代の汚辱と輝きを見出した中上健次も挙げられるでしょう。
そして、こうした方向の先駆者としては、谷川雁、石牟礼道子、森崎和江といった北九州で活動する表現者たちが存在しました。それらの表現者たちは雑誌「サークル村」に集って、地方から強い言葉を放ち、現実の労働争議にも果敢に介入することで、形成途上にあった新左翼に大きな影響を与えました。
「サークル村」は1959年、詩人の谷川雁、森崎和江、記録文学者の上野英信ら、筑豊の炭鉱地域に居住する知識人によって創刊されました。1950年代には全国に思い思いに文章を綴り、ガリ版と呼ばれる簡易印刷機で刷り上げて同人誌を発行しているグループ(サークル)が多数ありました。それらの多くは小中学校の教員や工場労働者であり、乏しい時間や金銭を割いて、自分たちの日々の生活や感情を表現していました。その背中を押したのが戦後の解放感であり、自分たちも文化や表現に参与したいという切実な欲求であったのは確かですが、同時にそれらは日本共産党の労働運動・文化運動の一環でもありました。
雑誌「サークル村」は、そうした九州・山口のサークル活動のセンターとして創設されました。沈滞の兆しの見られるサークル運動を活性化し、相互につなぐことによって、新たな政治・文化運動を形成する、というのが谷川らの目論見でした。「サークル村」の面々は、作品で民衆の集団的闘争を描こうとしただけでなく、「サークル村」自体が共同で創作・表現活動を行おうというコミューン的運動体でした。
しかし石炭から石油へエネルギーが転換するなか、炭鉱地帯は合理化の嵐に見舞われます。谷川も身近な大正炭鉱の争議に「大正行動隊」という坑夫集団を組織して加わっていきます。一方首都では60年安保の反対運動が高揚し、日本共産党など既成左翼の権威は失墜していきました。日本共産党の若き造反者から、共産主義者同盟(ブント)が生まれ、安保反対運動をリードします。軌を一にするように、谷川も共産党を離党し、独自路線を進みます。
戦後の批判勢力は、マルクス主義者にしろ、丸山眞男のようなリベラル知識人にしろ、基本的に近代主義であり、個人の自立と自覚を求めます。充分な知的能力を備え、社会意識に目覚めた個人が対等な討論を通して、民主的な社会を造っていくというのが基本構想でした。そこでは農村のべったりとした人間関係や慣習に無自覚に従うようなあり方は、古臭いものでしかありません。そうするとどうしてもモデルになるのは、都会の高い教養を備えた知識人――それも男性、というのは、女性はどうしても家事や育児に忙しくてなかなか討論などに参加している時間はないでしょうから――ということになります。
それに対し、谷川らは貧しい流民や坑夫、漁民らの集団内部にすでに共産主義の萌芽があり、新しい社会のヴィジョンがあるのだと主張しました。高い教養や外国語の知識などは必要ない、民衆が無自覚に見せる無辜の優しさにこそ本当の共同性があるのだとしました。
谷川はそうした民衆の内部にある未来の種子を「原点」と呼び、一旦そこまで降りていくことを提唱します。
20世紀の「母達」はどこにいるのか。寂しい所、歩いたもののない、歩かれぬ道はどこにあるか。現代の基本的テエマが発酵し発芽する暗く温かい深部はどこであろうか。そここそ詩人の座標の『原点』ではないか。
「段々降りてゆく」よりほかないのだ。飛躍は主観的には生まれない。下部へ、下部へ、根へ、花咲かぬ処へ、暗黒のみちる所へ、そこに万有の母がある。存在の原点がある。初発のエネルギイがある。メフィストにとってさえそれは「異端の民」だ。そこは「別の地獄」だ。一気にはゆけぬ。(注15)
この「原点」は多重の詩的なメタファーのまま語られます。つまり「原点」とは、読者の想念の赴くままに、抑圧された無意識の世界であり、イザナギが降っていった黄泉の国であり、中国神話における目鼻を穿たれる前の神「混沌」であり、その他のあらゆる昏い力を秘めたものです。しかしそれは何よりもまず民衆の自生的な共同体です。
僕に愛の原型を示したのは形而上的観念ではなく、特殊部落民であり、貧農であり、娼婦たちであり、村の法則だった。彼等は一様に指している。何を。共同体(コミュニティ)を。はるか遠い記憶に沈んでいる村を。原詩(ウル・ポエジイ)を。(注16)
こうした引用からもわかるように、谷川雁の語る〈村〉はきわめてロマンチックな幻想のアウラを纏っています。これは詩人谷川の資質に基づくと同時に、戦略的なものでもあるでしょう。つまり、谷川が幻視する〈村〉=共同体は、やはり現実の封建的な日本の農村や漁村そのままではなく、地方の現実と都市の近代双方を否定するものだったのです。その意味で、それはまだ存在していない非現実の〈村〉です。そこに居住するのも柳田國男の常民(定住民)ではなく、地下の坑夫や底辺の労働者、被差別者といった社会と体制から疎外された人々であり、彼らの中にこそ連帯の契機を見出し、そこから一気に未来の革命の展望をひらいてみせる、というのが谷川の戦略だったからです。
この革命的ロマンティシズムこそが、谷川雁を「吉本隆明、埴谷雄高と並ぶ安保の時代を代表するカリスマ」(注17)としました。
とはいえ、ユートピアとしての〈村〉が現実には存在しない以上、目の前の地域社会に「原点」を幻視し、そこから新しい運動体を引き出すエージェントが必要になります。谷川はそれを「工作者」と名づけ、自分をそれになぞらえました。「工作者」というと普通は破壊活動に従事するものやスパイを意味しますが、谷川の用語では、都市と田舎、知識人と民衆を媒介し、双方を作り替えるトリックスター=挑発者です。「サークル村」そのものが、組織として「工作者」であろうとした試みでありました。
しかし、「サークル村」から現れて谷川雁以上に息長く、豊穣な成果を残したのは、森崎和江、石牟礼道子、中村きい子といった女性たちでした。彼女たちは、聞き書きという手法を使って、現実と幻想が渾然となっているような近代以前の共同性のあり方を忘却の深みから引き揚げ、女性史に新たな領域をひらきました。森崎らは、大文字の「政治」ではなく、男と女の関係、家族のかたち、漁や農作業のような暮らしでの女の役割、女が性の労働者として海外に売られていく様子などを問題にしました。いうまでもなくそれらはフェミニズムに合流する仕事です。後世までずっと読み継がれていくのはこちらの作品群かもしれません。
谷川の言葉は詩の言葉であり、同時にアジテーションの言葉です。〈東洋の村〉という詩的イメージは革命の向かう方角を指し示す「神話」でもあります。けれども、1970年代の終わりには、そうした直接政治行動を呼びかける言葉は困難になります。コミュニティはむしろ行政的なワードに変わります。
谷川自身も、大正炭鉱の争議に敗れたあと、九州を捨てて上京し、長い沈黙に入ります。「サークル村」も廃刊になります。そして「サークル村」の終わりから約十数年を隔てて、80年代を迎えるとコミューンの季節も幕を閉じます。
(注13)『終焉をめぐって』79ページ、講談社。なおこの論文が書かれたのが1988年であったことに留意しておく必要はあります。当時はまだ、アジア諸国、特に中国はまだ日本にとって”後進国”であり、経済上で、あるいは軍事的に日本を”脅かす”可能性はほとんど考えられていなかったからです。90年代には状況は劇的に変わり、日本の言説空間において「帝国主義」=中・韓を敵視し、危険とみなす論理は爆発的に拡大します。
(注14)さらに明治維新を領導した最大のイデオロギーとしての「国学」もまた、一面で審美主義的なアナキズムの一面を持つことにも留意するべきでしょう。というのも、国学は人の振る舞いをいちいち言挙げして、裁いたり、規制するような制度や道徳を賢しらな「漢心」と排して、自然に流露するような感情や欲求をおおらかに肯定するものだからです。橋川はこれを「人それぞれが己れの情の動くがままに行動して、しかも社会の共同性が損なわれることのないようなかんながらの世界」(『ナショナリズム』Kindle版86ページ)であったとコメントしています。「神は、ものごと大ように、ゆるさるることは大抵はゆるして、世の人のゆるやかに打とけて楽しむをよろこばせたまうことなれば、さのみ悪くもあらざる者までも、なおきびしくおしうべきことにはあらず。さように人の身のおこないを、あまり煩細にただして、窮屈にするは、皇神たちの御心にかなわぬこと」(『玉くしげ』)。つまり宣長が想像する古代神権社会は、治者も民草も最大限のケアと寛容を発揮して、お互いを配慮し合うような理想郷なのです。
むろん問題は、本居宣長の時点ではこのような肯定の哲学であった国学が、平田篤胤を経由して尊王攘夷に転換するなかで、どうして自己と他者の生命を軽んじ、天皇を奉じて容赦なく敵を殺戮するようなファナティックな思想に変化したかです。
(注15)「原点が存在する」(1959年発表)『谷川雁セレクション』1、日本経済評論社、2009年
(注16)「農村と詩」1957年発表、『谷川雁セレクション』2、日本経済評論社、2009年
(注17)大嶽秀夫『新左翼の遺産 ニューレフトからポストモダンへ』東京大学出版会、2007年
5 コミューン主義の終焉
これまでの論点を整理しておきましょう。70年代に人々は、硬直した現代社会から撤退し、生身の身体を持ちよって自然の中に直接民主主義の共同体を形成するコミューン主義に希望を託しました。しかし十数年でその基盤は失われ、80年代の文学は失われた共同体の可能性を、神話や国家論というフィクションで再考することを試みました。一方、人々の方はとめどなく進行する「個人化」の趨勢に、集団形成を諦め、ITなどを介した個人的なつながりによって生き延びることを選択しました。
最後にもう一度80年代文学としての『葦と百合』の終結部を見てみましょう。
ラストに近づくにつれ、叙述は断章化し、矛盾する記述が次々に連なっていくようになります。もはや誰の口から語られている言葉なのか、どの時空に属するものなのか曖昧になり、どこまでが現実でどこからが幻覚なのか読者にはわからなくなります。
こうした書法は奥泉が深く学び、自家薬籠中のものとしていたドイツ・ロマン派直系のものです。ロマン主義は、18世紀末から19世紀前半のヨーロッパを席巻した多様で複雑な美学思潮ですが、ドイツにおいては、カント、フィヒテ、シェリングらドイツ観念論哲学の影響のもと、シュレーゲル兄弟やノヴァーリスといった詩人たちが大変思弁的で複雑な文学理論と作品を生み出しました。ドイツ・ロマン派の文学者たちは、秩序や安定に重きをおいた古典主義者たちに対抗して、作品をあえて断片化し、「未完成」に止めることによって、作品を無限の生成状態におこうとしました。完成した作品、見事に表現されてしまった作品は、その瞬間に限定され、具体的な輪郭のうちに閉じ込められてしまいます。それならば、むしろ完成を先延ばしにし、作品に孕まれた欠落や亀裂に読者の想像力が介入して、作品をどこまでも発展させていくことをドイツのロマン主義者は望みました。『葦と百合』の後半部は、こうしたロマン派の手法を全面展開しています。
ドイツ・ロマン派が断章形式で捉えようとしたのは、言語と現実を超える「無限」であり「神話」でした。『葦と百合』もまた、理想的なコミューン=共同体についての「神話」を語る物語です。
ラストで主人公の式根は、失踪したはずの友人時宗や恋人の翔子と言葉を交わし、二人が消えた深い森の奥に踏み込みます。「夢の中心の場所」ともされるその森の奥で、式根は翔子が光り輝く金色の鹿と交尾しているのを見ます。人と獣、人間と自然がついにひとつに溶け合い、大いなる生命の流れの一部になるというヴィジョン。しかしそれは美と等量のおぞましさを湛えています。
翔子は、花園の中央で、鹿と戯れていた。衣服を脱いだ翔子は裸だ。金色に輝く四肢を、同じ光輝に包まれた鹿の身体に柔軟に絡み合わせる。繊細な産毛に被われた腕で、鹿の強い首を巻き締め、背から腹、脚から尾に至るまでを愛撫する。唇を顎の下の柔らかい部分に這わせ、頬を黒い眼のあたりに擦りつける。翔子は、百合の絨毯に、横たわる。下から、鹿の腹に突き出した尖塔を、掌で撫でさする。糸を紡ぐ女の手つきで。演奏前に鍵盤に軽く触れてみるピアニストの優雅さで。やがて、翔子は、這う姿勢をとる。興奮に息を荒げた雄鹿が、背中を前足の蹄で鋭く突いてのしかかった。(注18)
「始原」においては、神と人、また人と自然の間の垣根はなくなります。これは世界各地の創生神話に共通してみられるモチーフです。しかしそれは単なる無害な御伽噺ではありません。なぜなら、例えばファシズムは、近代では利害と経済関係によって外面的に繋がっているに過ぎない人々を、「民族」という煮えたぎる坩堝に投げ込むことによって一体化し、人々が喜んでともに戦い、ともに死ぬような社会を作り上げようとしたからです。戦争という巨大な惨禍を引き起こしたことを差し引いても、「個人」の輪郭を抹消してしまおうというファシズムの欲望には恐ろしいものがありますが、それは同時に現代人の密かな夢でもあります。神と人、人と獣、人と人とがひとつになり、同じ欲望と夢を共有すること、『葦と百合』のラストが描き出すのはそういう情景です(注19)。
実はロマン主義とファシズムの関係については、20世紀の政治哲学のなかに長期にわたる議論が存在します。嚆矢といえるベンヤミン『複製技術時代の芸術』以来、その多くは、ファシズム、とりわけナチズムにおいて、ドイツの美学・芸術思想が民族共同体の基礎づけにどのように活用されたかを分析するものでした(注20)。そこでは、詩人フリードリヒ・シラーの「美的国家」の構想、世界を神話に溶解させてしまうロマン主義、ニーチェ、ワーグナーのバイロイト祝祭劇といった系譜の中に、政治を単なる利害調整や権力闘争から創造行為へと進化させ、民族と国家それ自体を生成する「芸術作品」に昇華しようという思考が辿られます。この思考を全面的に受け入れて、かつてないほど大規模な祝祭=戦争国家を実現してみせたのがヒトラーだというわけです。
奥泉もまた、ナチスの第三帝国ではなく、大日本帝国を対象に、集団が狂気めいた神話(物語)に呑み込まれ、破滅していく様子を執拗に書き続けています。『葦と百合』もその構想を現代に置き換え、閉鎖的なコミューンが崇高な死へと向かっていく姿を、それ自体ドイツ・ロマン派の現代版とも言える手法で描いたものであり、そこにはコミューンへの憧憬と不信とが交錯する心情が伺えます。
1991年に発表された『葦と百合』はコミューンに賭けられた夢の終わりを示しています。
この時代以降、人々は明確な輪郭を持った「共同体」とは異なるかたちのつながりを探し始めます。求心的なコミューンとは違うつながりのかたち、それはときに、〈死〉を共有するという特異な現れ方をします。次回は、ネット自殺をも含むような新しい共同性のあり方を検討します。(第五回了)
(注18)Kindle版 ページ
(注19)あるいはスタジオ・ジブリの『もののけ姫』もまたこの「始源」を求めるファシズム的欲望が深く刻まれた物語だと言えるでしょう。サンの怒りは神(シシガミ様)とあらゆる森の獣たちがともに生き、ともに暮らすような原始の森を破壊しようとする人間に向けられているからです。一方、技術の力によって女やハンセン病者たちが平等に生きるコミューンを作り出そうとするエボシ御前は近代的なコミューン主義者です。つまり、闘う女性であるサンとエボシ御前は対立しながらも、似たような志向を共有しており、異なるのは神としての自然が人間生活よりも重要だと認めるかどうかという点であることがわかります。
(注20)ナチスにおける「政治の美学化」について簡便に読めるものとしては田野大輔『魅惑する帝国 政治の美学化とナチズム』名古屋大学出版会、2007年、があります。海外の代表的な研究としてはピーター・ヴィーレック『ロマン派からヒトラーへ ナチズムの源流』西条信訳、紀伊国屋書店、1973、ヘルムート・プレスナー『ドイツロマン主義とナチズム―遅れてきた国民』松本道介訳、講談社学術文庫 1995年など。フランスの哲学者ラクー=ラバルトはハイデガーの哲学との関わりからナチスの「国家審美主義」について思索を重ねています。
▶第六回「「ナショナリズム」というゲーム」は下記のリンクから。
▶倉数茂。1969年生。日本近代文学研究・小説家。著書に『黒揚羽の夏』(ポプラ社、2011年7月)、『私自身であろうとする衝動―関東大震災から大戦前夜における芸術運動とコミュニティ』(以文社、2011年9月)、『名もなき王国』(ポプラ社、2018年8月)、『忘れられたその場所で、』(ポプラ社、2021年5月)など。
*トップ画像はばっどばつまる「神社の境内に咲くオレンジのユリの花」、『photoAC』による。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
