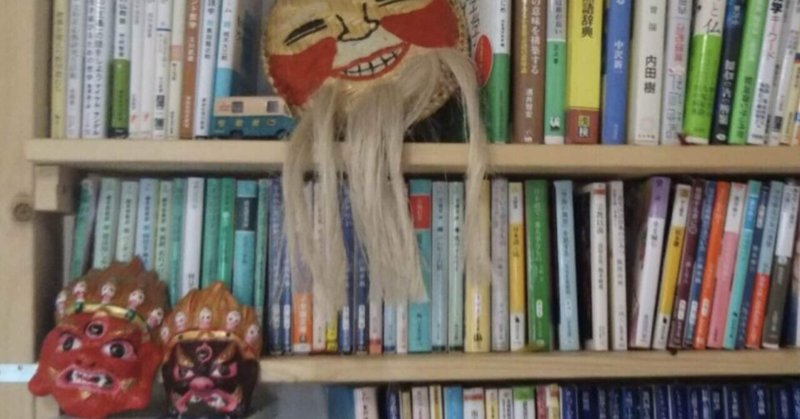
阪大「向陽寮」の思い出と小説『カレー夜話』
カレーを作っている時間はそれほどせわしないものではない。昔と今と明日を考えるだけの余裕がある。
はじめにー向陽寮と私
「向陽寮」は、かつて大阪大学旧箕面キャンパスに屹立していた男子寮である。
私は2015年〜2018年の四年間をそこで過ごした。もし仮に私がアナザースカイに出演することがあれば、思い出深いこの地を迷うことなく人生のアナザースカイに選ぶことであろう。
2020年の大学移転に伴い、向陽寮がその歴史に幕を降ろしたことは記憶に新しい。私は常日頃は極めて感受性に乏しい人間であるが、新箕面キャンパスに足を運んで新しい寮と思しきものを見物した際には、どうしても感傷を抑えることができなかった。大学寮がかくもピカピカとしていて良いものだろうか。いやそんなはずはない。
新キャンパスのピカピカの寮を見ながら思い出していたのは、まだ高校を卒業して間もない向陽寮入寮の日のことであった。管理人からの注意喚起も虚しく荒廃を突き進む我がユニットに足を踏み入れた時、私の母はその不潔さに悲鳴をあげた。しかし、その時、私の胸に何か去来するものがあった。奇抜さこそ無いが、確かな生活がもたらす安心感がそこにはあった。
小説『カレー夜話』について
さて、前置きが長くなったが、大阪大学向陽寮を舞台とした一編の小説が小説投稿サイトカクヨムで掲載されている。菅沼九民著の『カレー夜話』である。以下、著者の菅沼氏による紹介文を引用したい。
カレー讃歌の音がする
冴えない大学生である「私」が部屋の片隅に腐った玉葱を見つけたとき、「私」のカレー道は始まった。食、哲学、思想、歴史、あらゆる人間文化総体としてのカレー。カレーを極めることこそ人の道であると悟った「私」のカレー讃歌が幕を開ける。
繰り返しになるが、この作品の舞台は大阪大学向陽寮である。著者の菅沼氏は私と同じ2015年入学の寮生であった。作中において向陽寮(作中では浪速大学昇陽寮)は以下のように描写される。
二十一世紀初頭、四畳半帝国は、浪花大学昇陽寮の一室に誕生した。
国土は82082.25㎠の美しき正方形。地平から高度240㎝までが領空であった。内陸国であり領海を持たなかったが、国外の準領域として、国土の倍以上の面積を誇る湖の租借権を有していた。四畳半帝国は国外に領土こそ持たなかったが、この利権を以て帝国を名乗ったのである。湖は別名共用浴場とも言った。
諸君は、そのちっぽけさを以て、四畳半帝国を帝国とは認めないかもしれない。あるいは辛く悲しい浪人生活を耐え忍ぶなかで、妄想癖を獲得してしまった男子学生の末路に落涙しているだろうか。
あえて言おう。四畳半帝国は無限の地平であると!
そして認めよう。四畳半帝国とは妄想の産物であると!
四畳半というテクニカルタームから明らかなように筆者は恐らく小説家、森見登美彦氏の作品群に大きな影響を受けている。かくいう私も大学寮といった退廃的な学生文化に憧れるきっかけとなったのが森見登美彦氏の小説であり、この点においても私は菅沼氏へのシンパシーを感じるところである。このことから本書は森見登美彦の腐れ大学生小説を溺愛する読書家には、かなり楽しめるものとなっている。
また、本書は、大学生活における食生活の在り方に関する示唆に富んでおり、暮らし指南の書としての、実践的な側面を併せ持つ。その側面を紹介したい。
私にとってカレーほど好都合なものはない。
作り方は簡単、市販のルウを使えば失敗しない。失敗するような奴はよほどの馬鹿か天才である。私はそのどちらでもない、はず。
カレーは一度に大量生産でき、ある程度の日持ちがする。一度作れば一週間は生きられる。凡人を自認する私であるが、私になにか特異性があるとすれば、三食カレーと言う日が何日続こうとも、カレーを食べたときの満足感に微塵の曇りも生じぬことであろう。経済学を学ぶ読者があれば、限界効用逓減の法則には、私という例外があることを覚えておいて欲しい。試験にはでない。
こうして私は母の愛からカレー作りに目覚め、カレー道という大海へ乗り出すことになった。我が征くは咖喱の大海。熱き波濤の果てに、私が求めるものがある。
菅沼氏は大学生の自炊にはカレーが最適だと主張する。その理由として、下記四点を挙げていることは注目に値する。
①失敗しない
②大量に作れる
③日持ちする
④飽きない=限界効用逓減の法則の反例
これらは経験的に共有されている特徴かもしれないが、菅沼氏が改めてここで明示的にこれらの点を指摘した意義は大きい。初めて自炊を始める若者たちには是非とも本書を読んで頂きたいと思う次第である。
さて①の「(カレー作りは)失敗しない」については、私からも若干の補足を付け加えるなどしたい。
小説家の森見登美彦氏はエッセイ「カレーの魔物」で、『冒険図鑑』における野外の自炊ついて書かれた下記の引用部を「やわらかき脳味噌に深く刻み込まれた不滅の一節」だと高く評価している。
もっと複雑な味をというときは、カレー粉を持って行くといい。(中略)だがくれぐれも少量を。使いすぎると、みなカレーになってしまう
この一節を森見氏は下記のように解説している。
「使いすぎると、みなカレーになってしまう」という簡潔な表現の力強さはどうか。頼りになる大人が、「くれぐれも少量を」と念をおすほと危険なのであるカレー粉というものは!森のおくにひそむカレーの魔物を見る思いがする。
魔物とは一般的には怖いものである。しかし、裏を返せば、素材の味を活かすといった料理の技量がない我々にとって、カレーは極めて頼りがいのある存在なのではないだろうか。
どんな素材であってもカレーの魔物が「みなカレーにしてくれる」からである。カレーの魔物は素敵な食生活を我々(たとえ料理の技量がない男子大学生であっても!!)に約束してくれる。
菅沼氏の『カレー夜話』における「作り方は簡単、市販のルウを使えば失敗しない。失敗するような奴はよほどの馬鹿か天才である。」という記述はまさに先述したカレーの魔性を見抜いての洞察であると思われ、菅沼氏の慧眼にはただただ 感服するばかりであった。
自炊の軸としてカレーを据えるというのは、実は菅沼氏の大学時代の実体験がベースとなっているようだ。菅沼氏は、随筆「カレー夜話」で下記のように述べている。
これまでの学生生活の傍らには常にカレーがあり,これからも共に歩み続けるだろう。最早我が身の大半はカレーで成っているといって過言ではない。
「学生よ,カレーを作れ」とは私の至言である。
実のところ、大学時代、『カレー夜話』の著者である菅沼九民氏の作るカレーで、私が度々糊口を凌いでいたことはここに確と記しておかねばならない。最早我が身の大半は菅沼氏の手作りカレーで成っていると言っても過言ではないのである(過言)。
おわりに
最後に私のお気に入りの一節を紹介する。
カレーを作っている時間はそれほどせわしないものではない。昔と今と明日を考えるだけの余裕がある。
思えば、カレーを煮込む際の手持ち無沙汰は、茫漠とした時間の中で惰眠を貪るか、思索に耽って過ごす他なかった向陽寮での生活に極めて似つかわしいものであったと懐かしく思い出される。
大学移転に伴い向陽寮は姿を消すことになったが、かつてそこを覆っていた空気感が小説という形でありありと再現されたことを元寮生として寿ぎたい。
付記
カレー夜話/菅沼九民著
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
