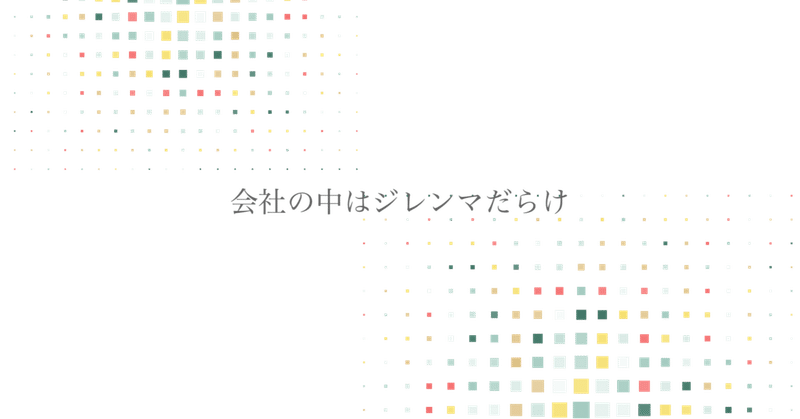
組織考[4]マネジメント・育成──『会社の中はジレンマだらけ』ほか読書感想文
組織がうまく回らない。
良いところが活かせず、先の見通しがつかず、悩みは堂々巡りで、焦りばかりがつのる。
うまくいっていない組織に対しての突破口はどこにあるのだろうか。
組織課題解決のヒントを得るための読書をした結果シリーズその4です(いったんこれで最後です)。
今回は、マネジメント・育成が主テーマ。
「企業が暗黙的に求めるマネジメント業務って範囲広すぎて無理ゲーじゃないですか?」って課題感から、読んでみたのは以下の2冊です。
以下、気になったポイントを中心に取り上げます。
1.会社の中はジレンマだらけ
※2016年刊行。
企業の人事制度改革担当執行役員(ヤフー(株)本間浩輔氏)と学者(東京大学総合教育研究センター准教授中原淳氏)の対談。
アサインとは何か
仕事を「振る」と「任せる」は違う。
マネージャーが、自分の部下たちが今どのような仕事をしているのかを「見て」、それぞれに任せる仕事を「決めて」、その仕事の内容を部下に「説明して」、任せた仕事の進捗を「管理する」という一連のプロセスだと思うんです。
企業では、マネジャーの業務内容を「部下を育てること」だとは定義していないじゃないですか。
正しく「任せる」には任せる方にも相応の負荷がかかる。たとえ組織が「育成」をミッションとしてマネージャーに与えていても、組織は往々にしてその分の工数を確保していないことが多いし、評価としても得づらい(プレイヤーなど他項目の評価のオプションにはされても、育成単体では評価されない)という構図があると私は思う。
(初期)育成コストが回収できない
組織を中長期視点で成長させるためには、人材の育成は必須。しかし……
このときややこしいのは、組織のメンバーの入れ替わりが早くなっていることです。最近は、有期雇用の人たちも多くなっているし、本人たちのキャリア意識も高い。だから、キャリアアップのために早く出ていく人もいる。そうすると、困ったことに「育成コスト」を回収できないんです。
[本間]育成をメインに考えるのであれば、部下の成長課題を上司が考慮したうえで、その部下にちょうどいい仕事を探して、任せるのが基本です〜
[中原]〜最近は仕事そのものが大規模化し、複雑化し、スピーディーな処理を求められるようにもなっていて、仕事を切り分けて部下に任せるのがますます難しくなっている。若手に仕事を任せたくても、任せる仕事がないという状況ですね。
プレイングマネージャーという無理ゲー
部下育成は難しいのだから、会社が管理職に対して、「あなたは、現場作業を一切やらなくていい。部下に正しく仕事をアサインして、コーチングやティーチングをしなさい」と言えれば、この「任せられない問題」は半減するかもしれません。
実際、現在の企業でマネージャーと言われている大半の人材は、“管理の役割を担っているプレイヤー”という意見に完全に同意。メインとなるプレイヤーとしての自身の仕事に加え(しかもトッププレイヤーであることが多い)、組織のフラット化により増加傾向にある部下の育成、組織の成長課題の解決、新規事業提案……これをすべてマネージャーの仕事であると定義するのは、あまりにも一人の仕事のミッションとして荷重であることがわかる。わかるのに、なぜか現場でこの“ふつう”がまかり通っている。
スパン・オブ・コントロールの古典的原則として「どんな上司も、連動する仕事に従事している五人以上、あるいは六人以上の部下の仕事を直接管理することはできない」という。
解消する術は、マネージャーとメンバーの中間管理を担うチームリーダーのような存在だと本書には書かれるが、私見を述べるとこの層の自立・自走の支援は「人材・取り組みへの期待値」がメンバーよりも高いだけに、一層難しかったりする。下手するとその先のメンバーを丸ごと引き受けることになり、結果マネージャーの荷重は変わらない。むしろ重くなる。
ミドル以降、人材の進路を指し示す
このあたりは自分にマッチした課題感。次にあげる『若手社員が育たない』で良い感じの示唆が得られたので詳しくは後述。
これまでの人材育成の研究って、新入社員をどう育てるとか、リーダーシップをどう開発するかといった「登山の研究」ばかりなんです。役職がなくなり、給料が下がっていく下降のプロセスをいかにうまくたどり、自分のキャリアをいかに収束させていくかという「下山の研究」がなかった。
所感・感想
組織はさまざまな性格・スキル・行動形態を持つ人で成り立つ。
仕事においての給与が適正か、評価が適正かは、「その人」ではなく「その人が成したこと」でその都度評価しなければならない。
年齢が上がることにより、スキルが市場とマッチしなくなる層は確実に出てくる。組織側も社員側も、それを踏まえて設計をしなければならないのだと思う。
それは、若い時から新しいことを学ぶ習慣をつけて現場で役立つスキルを磨くと共に、時代の変化に伴う影響の少ないスキルを磨くことを意識することで、対処できるのではないか。
例えば、組織の力となる後進を育てる「人材育成」の力、対クライアントや組織の潤滑油となるような「対人コミュニケーション」の力。各個人が自分の価値をシビアに見定め(私はこれこそが“自律”の行動だと思っている)30代までに、これらを獲得しておけば、組織からのニーズは一定量存在し、したがって給料の大幅なアップは見込めなくとも、少なくとも減額は避けられる人材になれるのではないか。
2.若手社員が育たない
※2015年刊行。
2-6-2の法則ではなく……
著者は人材の層について、5-15-40-40の法則を支持しているという。例えば日本でいうと国家を牽引するようなエース級の「すごい人材」が5%、すごい人材に次ぐキャリア人材が15%、一般的な大卒若手社会人が40-50%、フリーターやニートなど「彷徨える人材」が30-40%。救済措置を講ずる必要のなかった中間層が成長の危機に瀕しているというのが本書で鳴らされる警鐘である。
仕事の力とは?
未知なる状況に立ち向かい、構想し、意思決定し、人を動かす。仕事の本質とはそういうことだ。明示的に専門知識や技術・スキルによって構成されているのは、仕事の一部に過ぎない。
育成は評価されずらい
(社会の管理職の大半を占めるプレイングマネジャーは)プレイヤーとして難易度の高い仕事を担当し、成果を挙げれば高く評価してもらえる。部下が育っていなくてもさほど低い評価がつくことはない。となれば、部下の面倒を見るよりも自身の業績を高めることが向いている人が多くなるのは当然だ。
視野狭窄にならざるを得ない環境
専門化、細分化が進み、ビジネス環境が変化するスピードが速まる中、与えられた領域の砕身知識・技術・ノウハウを次々に獲得することが求められるが、それに対応し、「机上で学ぶ」ことが優先され、他部門、顧客、海外等の異なる視界、観点を持った人たちとの接点が現象し、視界が広がらない。
このような状況に置かれる人を「主体性がない」「責任感がない」と嘆いたり批判するのではなく、その無力感をぬぐい、視点を押し上げるにはという方向に考えたい。
一手として、他分野交流のできる「勉強会」を著者は挙げている。自分で余白を作り、積極的に働きかけない限りは変わらないというのは事実。
マネジャーの仕事多過ぎな件
管理職の負荷が高くなり過ぎていると著者は指摘する。
若手の育成、難易度の高い業務をこなすプレイヤーとしての働き、コンプラ強化による業務時間の管理まで……。さらに、同じ目線で組織文脈を理解し片腕となる層は、組織のフラット化により消失している。
この部分に対して、本書に書かれている「既存の管理職業務のスクラップ&ビルド」という打ち手は、ミドル層のキャリア形成のあり方としてとても参考になった。
ステップとしては次の通り。
まずは管理職業務をこのような形に分解する。
「何をやるか」の戦略デザイン
「どうやるか」の実行デザイン
└ a.自組織メンバーの能力を活用し成果につなげるメンバーマネジメント
└ b.メンバーレベルでは対応できない難易度の高い業務の実行
この3つをそれぞれキャリアのルートとして確立するというのが著者のアイディアだ。
[1]は幹部コース
[2]-aはマネジメントコース
[2]-bはスペシャリストコース
[1]に進める人材は限られる。
基本的に組織の大半は[2]のいずれかを歩むことになるが、現状はその業務2つのハイブリット化がいわゆるプレイングマネジャーという負荷が高く、長期的に見ればマネジメントも専門的職務も中途半端な成長しかしないという立場を生んでいる。
※プレイングマネジャーを7年以上続けると成長が停滞し、逆に専任化すると7年後には(それでも数年かかるので、この期間は精神的なサポートが必須かもしれない)成長実感が高まるというリクルートワークス研究所の調査データがあるとのこと。これは現場の実感値としての納得感がある。
[2]をマネジメントorスペシャリストの2コースに分けるのは、ミドル以降も「組織で活躍できる」キャリアルートとしてすごく腑に落ちる。(個人的には選択するとはいえ100とか50:50のような極端や中途半端はあまり良くなく、30:70とか20:80くらいの割合であるのが他視点の入手という点では望ましいのではないか)。そして、このようなキャリアのルートを若手のうちから示されることが、「自分はどちら(何が)が向いているのか」と未来の自分のキャリアを考えながら20代・30代を過ごすきっかけになると思う。
考え続けることで、もしかしたら自分にあった第三の道がひらける可能性だってある。
マネジャーの評価について、すばらしい内容の記事があったので、備忘録的にここにリンクを置かせていただきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
