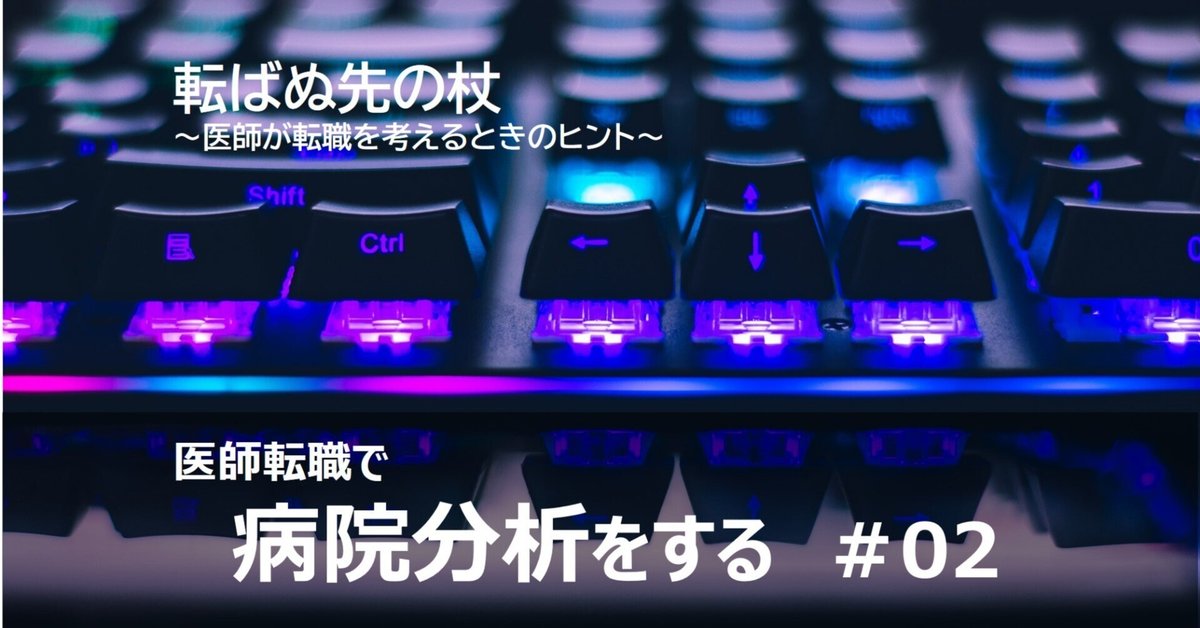
ソーシャルスタイルから職場の雰囲気を推測する
前回は、30分あればできる「病院ホームページの分析法」を書きました。今回は、上長のソーシャルスタイルを分析して、転職先の職場の雰囲気を考えてみます。本記事で扱う「ソーシャルスタイル」は、典型例をもとに「誇張した表現」にしています。実際に当てはまるケースはなく、実在する人物を想定したものでもありません。あらかじめご承知おきください。
働き方に密接に関わる要素なのに、求人票には表れないのが「病院のカルチャー」の情報です。「病院のカルチャー」とは、職場の雰囲気や人間関係などの情報で「働きやすさ」もその一つです。
これを転職エージェントに尋ねても「印象評価」を超えた情報は持ちあわせていないでしょう。見学面談に行っても、深い部分まではわかりません。働き始めるまでに知る方法はないのでしょうか。
「働きやすさ」は「定着率・離職率」で測れるが・・・
「働きやすさ」は転職先を決めるうえで重要な要素です。それを確認できる唯一の数値指標があります。「定着率・離職率」です。
定着率とは、入職から一定期間後に働いている職員の割合のことで、社員数と離職者数をカウントして算出します。逆に、一定期間内に退職した職員の割合を表すのが離職率です。
定着率が低く、離職率が高いなら、職員の入れ替わりが激しい職場です。定着率が低くなると採用や教育コストが嵩むだけでなく、定員を確保してから業績の安定までに時間がかかります。その間、現場は忙しくなり「働きやすさ」は損なわれます。
しかし「定着率・離職率」は外部公開されません。そのため比較自体が容易ではありません。ちなみに厚労省データでは、令和2年の医療、福祉分野全体の離職率は14.2%(定着率85.8%)でした。日本看護協会によれば、令和2年の看護職員全体の離職率は、正規雇用で11.6%、新卒採用で10.3%、既卒採用では16.8%です。
口コミは「情報バイアス」に注意
もし、事務やコメディカル、デバイス担当のCEやMEに知り合いや人脈があれば、病院の実情をリアルに聞けるかもしれません。ただ、それも「話半分」に聞いておきましょう。明らかなフェイクもありますし、情報提供者が無意識に「バイアス」のかかった情報を流すことがあります。
むしろ転職前に、その病院でスポットバイトを経験しておけば、病院「カルチャー」を肌で感じることができます。実際に機会を与える病院もありますが、まだまだ少数派です。
転職理由で多いのが「人間関係」
人が辞める一番の理由は「人間関係」です。
厚生労働省が発表した「令和2年雇用動向調査結果の概要」では、転職した人の理由で「職場の人間関係が好ましくなかった」と答えた人は、男性で8.8%、女性で13.3%でした。しかし、同時期に一般の転職会社が「ホンネの転職・退職理由」のアンケートをした結果をみると「人間関係」が48%を占めています。職場の人間関係が良好でなければ、仕事のやりがいや成果に悪い影響があることは別に調べなくても判ります。そこで、転職先の職場の人間関係、特に上長との関係を推測するコツ「ソーシャルスタイル」について紹介します。
「ソーシャルスタイル」とは?
自分の考えや感情をどう表現するかを「ソーシャルスタイル」といいます。特に上長の「ソーシャルスタイル」は職場の雰囲気や、メンバーとの関係性に大きな影響を与えています。
見学面談まで待てば、転職候補先の上長と直接話せるので確認できます。ネットにも口コミや評判はありますが、多くは退職者の意見なので当てになりません。ここはエージェントに直接取材してもらうのが手っ取り早いです。
ただ病院担当者は、自院のマイナス評価につながりそうな人物の情報は出しません。できるエージェントなら、部長のお人柄について伺いながら「自己主張」と「感情表現」を確認します。
「自己主張」と「感情表現」の2軸あれば「ソーシャルスタイル」が測定できるからです。部長の話し方が「断定的」か、感情表現は「豊か」か「控えめ」かが判れば、ある程度の推定ができます。
4つのソーシャルスタイル
「ソーシャルスタイル」は「自己主張」と「感情表現」の2軸で4つのタイプに分かれます。

「ソーシャルスタイル」は、1960年代に米国の産業心理学者のデイビッド・メリルとロジャー・レイドが提唱したコミュニケーション理論です。彼らは、人は他者に意見を「断言」するか「尋ねる」かのあと、感情を「表現」するか「控える」かの行動をとることに気づきます。その後の調査と実験で、この4タイプを定義しました。
もともとの調査目的は、経営や販売パフォーマンスの向上です。自分と相手のスタイルを知り、コミュニケーションの摩擦を減らすことに眼目があります。一般的な傾向を示すもので「理論」というより「ツール」という認識が適切です。ちなみに、自分と相手の象限が同じか、隣り合うならそれほど相性は悪くありませんが、対角だと相性が悪いようです。
次にそれぞれのタイプと職場の雰囲気について説明しますが、典型例を誇張した表現です。実際には2タイプの特徴を持つ人がいたり、どのタイプか判別しにくいことがあります。記事は参考程度に留めてください。
ドライビング・タイプ 活発で競争的な職場。常に結果が求められる雰囲気
自己主張が強く、感情を控えるのがドライビング・タイプです。目標志向が強い「リーダーシップ型」のタイプで、プロセスよりも結果を重視します。結果が出るなら手段は問わない剛腕型のリーダーとされます。
強い権力を発揮しており、負けず嫌いで、はっきりとものを言います。このため反感を買いやすく、メンバーから遠巻きにされているかもしれません。自分の決断に強くこだわるタイプなので、判断材料を用意して相手に決めさせたほうが上手くいきます。
早口です。要点を押さえた短い話を好みます。曖昧な言い方や雑談は嫌うのでエミアブル・タイプとは合いません。
このタイプがリーダーの職場の雰囲気は、活発で競争的で、体育会系の雰囲気が漂います。ただし結果には必ずコミットしてくるので「ピリッ」としていそうです。
エクスプレッシブ・タイプ 明るく創造的な職場だが規律が緩い
自己主張と感情表現がともに強いのがエクスプレッシブ・タイプです。感情表現は豊かで創造的、声や動作も大きい社交的なタイプです。人から好かれやすく、流行にも敏感で周囲から注目されるのが大好きです。
仕事では、新しいアイデアやチャレンジを重視します。細かな検証は嫌うので、説明資料は少なく簡潔にします。やや俯瞰的な観点から説明すると納得しやすいようです。理屈っぽい話や細かな事実を聞きたがらないので、説明をしたいアナリティカル・タイプはストレスを溜めそうです。
このタイプも早口ですが、話が長いのが特徴です。忙しい部下は関わり合いを避けているかもしれません。職場の雰囲気は明るく創造的ですが、感情の浮き沈みもあり、言うことがコロコロ変わります。職場の規律が緩くなりがちで、ルールを勝手に変える傾向があります。
エミアブル・タイプ 和やかで協調的な職場 家庭的な雰囲気だが率先垂範はしない
自己主張が弱く、感情表現が強いのがエミアブル・タイプです。
愛想が良くて、相手に合わせたコミュニケーションができるタイプです。人間関係を重視しており、サポートが得意です。ただ周囲の意見を尊重するあまり、何事も決定まで時間がかかります。
仕事では、チームワークや協力関係を重視します。すぐに結論を求められることを好みません。考えを受け入れ、結果を出すまで待つ忍耐力が求められます。また個人的な会話を楽しむ傾向が強く、ドライビング・タイプとの相性はよくありません。
口調は穏やかでゆっくり話をします。職場の雰囲気は、和やかで協調的でしょう。ただ急な変化への順応は苦手です。ストレスを溜めやすく、人間関係を固定化する傾向があります。決断力や率先したリーダーシップは期待できません。
アナリティカル・タイプ 静かで整理された職場。ミスは許されない雰囲気
自己主張と感情表現がともに控えめなのがアナリティカル・タイプです。
断定的な話し方はせず、論理的に淡々と話をします。マイペースで、人間関係より仕事や課題を重視します。エビデンスのある話題を好み、抽象度の高い「風呂敷の大きな話」は嫌うので、エクスプレッシブ・タイプを信用しないでしょう。
仕事ではデータや根拠に基づいた正確さを求めます。洞察力も高く、資料は事前準備を万全にしておく必要があります。慎重でミスも少ないので、部下にもそれを求める傾向があります。
話し方は、じっくりと冷静です。常に論理が優先していて、必要なら冷酷な判断も平気で下します。本人は大真面目ですが、部下には理解されにくいタイプでしょう。職場の雰囲気は、静かで整理された感じになります。
まとめ
求人票には、「どんな上司やスタッフがいて、職場の雰囲気はどうか」という情報はありません。入職したら2人常勤が確実なら、部長の「ソーシャルスタイル」は確認しておきたい情報です。
担当エージェントのヒアリング力が低くそうなら、部長の「話し方」と「感情表現」を確認させておきましょう。前述のように、早口なら「ドライビング・タイプ」か「エクスプレッシブ・タイプ」です。話が短くて、断言するようなら前者、話が長くて、喜怒哀楽を出すなら後者でしょう。
もし、会話が早口でなければ「アナリティカル・タイプ」か「エミアブル・タイプ」です。冷静で論理的で愛想がなければ前者、愛想がよければ後者です。
これであたりをつけて、面談で直接部長に会って確認します。もし自分と相手のソーシャルスタイルが近ければ、最初からスムーズな関係になれるでしょう。ただし、ソーシャルスタイルが対角の関係だと、少し工夫が必要になります。
求人側の視点からみれば、今いる常勤と同じものを先生に求めているとは限りません。むしろ、新しい何かを期待しているはずです。
ソーシャルスタイルの異なる部長とも「上手くやっていける医師」のほうが、違うパフォーマンスを期待できるので、高い評価や良い評判を得ることにつながると思われます。
「ソーシャルスタイル」は、自分の軸をずらさず、円滑な対応を可能にする「ツール」です。「病院のカルチャー」と自分の価値観との「フィッティング」に、上手く活用してみてはいかがでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
