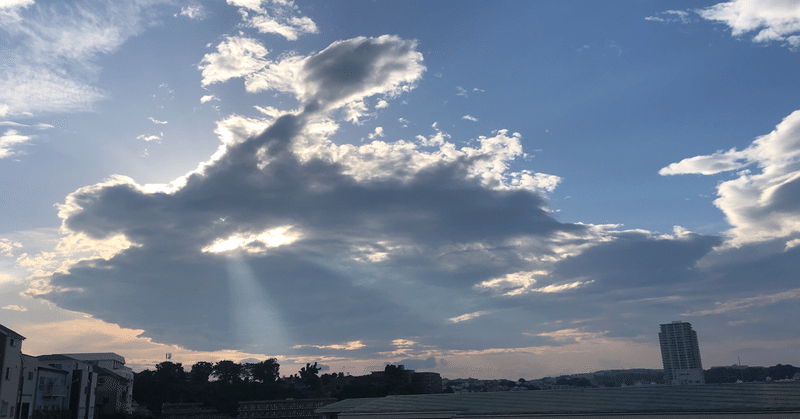
道徳を教えてくれる進学塾はない?
この文章を書くにあたり、今の教育現場を調べずに、34歳の自分が古い記憶を頼りに筆を進めています。今の日本の最新教育事情と齟齬がありましたら、深くお詫び申し上げます。
…………………
『いじめはいけない』と、
とかく強く言われている昨今かつ昔からあるこの議題だが、なぜいじめはなくならないのだろう?
そんな事を考えていたら、そういえば、週に1回1時間、学校でも道徳って授業があったな。。。とふと思い出したので、学習指導要領に記載されている単元として学ぶべき内容を調べてみる。
A主として自分自身に関すること
1.自主、自律、自由と責任
2.節度、節制
3.向上心、個性の伸長
4.希望と勇気、克己と強い意志
5.真理の探究、創造
B主として人との関りに関すること
6.思いやり、感謝
7.礼儀
8.友情、信頼
9.相互理解、寛容
C主として集団や社会との関わりに関すること
10.遵法精神、公徳心
11.公正、公平、社会正義
12.社会参画、公共の精神
13.勤労
14.家族愛、家庭生活の充実
15.よりよい学校生活、集団生活の充実
16.郷土の伝統と文化の尊重、
郷土を愛する態度
17.我が国の伝統と文化の尊重、
国を愛する態度
18.国際理解、国際貢献
D主として生命や自然、
崇高なものとの関わりに関すること
19.生命の尊さ
20.自然愛護
21.感動、畏敬の念
22.よりよく生きる喜び
なるほど。これ改めて調べてみると、
めちゃくちゃ大事じゃない?
人の成長や資質の基盤を培うにあたって、めちゃくちゃ大事な学問なのに、どうして、週1で1時間しかカリキュラムが組まれていなかったのか凄く気になってしまった。。。
ピンときたことは1つ。
受験の試験科目になんぞ、道徳という科目は出てこない。なるほど。だから道徳を教えてくれる進学塾なんて存在しないし、週に1時間のカリキュラムなのかと。だって進学塾なのだ。
受験戦争において生徒を合格させる事が進学塾の務めであるがゆえに、道徳が受験科目として出現をしない限り、それを教えなければいけない謂れは彼等にはない。それは進学校においても同じかもしれない。高い偏差値の学校への合格者を一人でも出すことがの、生徒へコミットすべき約束なのだ。道徳なんぞに割いている時間はきっとないのだろう。
むしろ競争社会の意識づけゆえに道徳に対するデメリットさえ生む構図かもしれない。
ではなぜ受験科目に道徳を取り入れた方が良い…という意見が出てこないのだろう。うーん。甲乙つけずらく、評価しづらいという理由かしら?という考えが頭によぎる。
多様性をよしとする学問の範疇で、マルバツをつけ、甲乙をつけるというのは、学問に対する矛盾ではないか?
学習指導要領の道徳の要素を部活動や学園祭などの学校行事で担保しているという考え方もあるかもしれないが、正直それは教育者側のエゴ的発想な気がする。学生の目線で、そんな視座をもちあわせて活動してる奴なんて、ほとんどいないのではないか。気づいたとしても、大人になって「あの頃」を俯瞰できるような心のゆとり出来てからだとしたら、学内で今巻き起こっている渦中の道徳的問題の対策にはならない。
そんな事を考えていると他の教科で、道徳的な要素を取り入れていくこともまた重要なのでは?なんてことも、ふと頭をよぎる。
ふむふむ。ネットで調べりゃ1発で出てくるこのご時世に、歴史の年号暗記なんて、なんてくだらない。。。そんな事も思ったし、何を学んでほしいかを突き詰めれば、テストの設問だって全然違うものになるのではないかと。
■ホロコーストが何年に起こったか
ではなく
■ホロコーストがなぜ起こってしまったのか?
起きないようにするにはどうすべきだったのか?国と人種いう規模だが、あれは一種のいじめだ。そういう視点で、あなたちの周りにいじめはないか?あればどうすべきなのか?過去の歴史から何を学び、考えて、どう今の生活活かすべきか?
そんな事を考えていると、
歴史は先生の黒板をノートにうつし、教科書を暗記し、「ここテストに出るぞー」なんてそんなものではなく、ディベート形式であるべきではないのか。
でもディベートってこれまたマルバツ評価がつけづらい。評価って難しい。そんな思考に及ぶ。
少し話は飛びますが、なんのために学ぶのか。
このアウトラインをはっきりさせた上で学問に臨むことで、取り組む意識は全く変わると思う。
これは僕の今になっての思いだが、数学の授業で関数やサインコサインタンジェントの数式を学ぶ前に、この数学の知識が、社会の、どんな場所で役立ち、貢献しているのか。
この学問を学ぶ事は、あなたのどんな未来に繋がる可能性があるのか。そんな授業を数式を学ぶより先に聞きたかったなーと思っている。
数学が本当に苦手で勉強しても赤点続きだった僕にとって、数学という学問は、将来それがどう役立つかもわからないまま、ただ苦手という理由だけで学ぶ事へのモチベーションを保つにはいたらず、将来の選択肢としての幕は、ゆっくりと閉じられてしまった。
そう言った視点では義務教育は、学問を通じて、将来の選択肢の1つ1つを、いかにイメージしやすくすることが出来るか工夫すべきで、それって命題だと思うのだけど、学校ではお金の稼ぎ方すら教えないのは何故だろう。
この話に結論はないけれど、
教育としての本質と、評価指標のあり方は、これはきっと根深い話なのだろうな。でも評価する側の都合で、教育を受ける側の幅と質が狭まるようなら、これは本末転倒だ。
道徳が受験の必須科目になったら、いじめは減るだろうか。
評価による視野の狭窄って、これって仕事にも言えるよな。。。会社が大きくなり、事業部が縦割りになり、それぞれの評価指標で動き、内側のセクショナリズムが働いたときは要注意かもしれない。
なんて事を
仕事帰りの電車でふと物思いにふけり、せっかくなら、ここにメモしておこうと筆を取る。
自分への戒めを込めてもう一踏ん張り。
教育というフィールドは
『学校に任せている』なんて意見はナンセンスで、親としてもまた、我が子に真摯に向き合い続ける姿勢が大切な気がする。
学校でわが子が、何を誰とどんな風に学んでいるかを親も学び、足りないと思うところがあれば、それは家庭でしっかり学ぶ機会をつくる必要がある。
学校は学校の都合と事情があり、大きな力が働いていて、ちょっとやそっとではシステムは変えられないという事実は、受け止めるべき環境だ。
それぐらい教育や学問という概念は広すぎる。
先生だって先生である前に、同じ人なのだし、迷うし、沢山の思春期な生徒たちに対して、体は1つで、自分のプライベートだってあるのだ。先生にまつわる労働環境のニュースや体験談を聞くに、先生もきっとヘトヘトだ。
まぁそんな事を偉そうにつらつらと書いた僕自身、子供と向き合えているかと言ったら、まだまだ赤点30点の発展途上か。
そんなことを、書いていると、
まもなく自宅の最寄駅だ。
タイトルの話とはなんだかそれた話になってしまったけれど
ここまで読んでいただいたあなたにとって、何かの気づきになっていましたら、これ幸いでございます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
