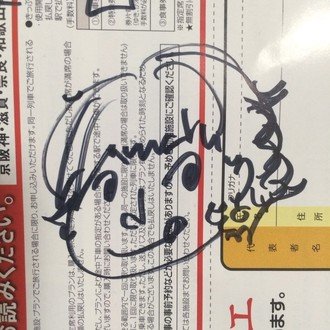【第1回】文芸翻訳での分詞構文や同格、言葉遊びの処理──Don DeLillo "MIDNIGHT IN DOSTOEVSKY"冒頭
英文を読むのと翻訳をするのにはかなり大きな違いがあって、読んでいるときの感覚を文章として可視化しないといけない点に翻訳のむずかしさがある。とりわけいつも困ってしまうのが、(初学者にはありがちな問題ではあるのだけど)「分詞構文や同格表現を複文で処理するか、それとも重文で処理するか」ということだ。その他にも「音を利用した表現」も厄介で、これはシンプルに言語の差異から不可避的に生じる問題なのでどうしても「解釈の問題」が絡んできてしまう。
最近読んだもののなかで、こうした問題について考えるうえで良い題材になると感じたのがドン・デリーロによる短編『ドストエフスキーの深夜(原題:MIDNIGHT IN DOSTOEVSKY)』だ。全文翻訳をここに公開するのは著作権的にアウトなので、今回は冒頭のみを引用して実際に翻訳し、また訳例として都甲幸治訳(『天使のエスメラルダ(新潮社)』収録)を参照する。
※なお、最初に断っておきますが、今回はぼく自身の翻訳(大滝訳)は実験・検証的要素が強い訳をあえて選んでいるので、その点はあらかじめご容赦ください。
ではまず今回あつかう文章を引用する。
We were two sombre boys hunched in our coats, grim winter settling in. The college was at the edge of a small town way upstate, barely a town, maybe a hamlet, we said, or just a whistle stop, and we took walks all the time, getting out, going nowhere, low skies and bare trees, hardly a soul to be seen. This was how we spoke of the local people: they were souls, they were transient spirits, a face in the window of a passing car, runny with reflected light, or a long street with a shovel jutting from a snowbank, no one in sight.
引用:THE NEW YORKER "MIDNIGHT IN DOSTOEVSKY"
冒頭の分詞構文の処理
We were two sombre boys hunched in our coats, grim winter settling in.
直訳的にいくと、
(直訳)
僕らはコートに身を包んだ二人の陰鬱な少年で、そのとき厳しい冬が定着しようとしていた。
という具合になるけれども、こんな文章だと読む気が失せる。分詞構文のむずかしさは学校のテスト的には接続詞が省略されてしまっているみたいなところにあり、文脈に応じて「時、条件、原因・理由、譲歩、付帯状況、結果」といった6つのどれかと解釈するして訳出しないといけないのだが、翻訳ではもちろんそれだけじゃない。パラグラフや作品全体が志向している表現、リズム、文体といった要素にも配慮する必要が生じる。
個人的に言語のちがいを強く感じるのが、「省略のしかた」だ。一般に、日本語だと主語の省略が独特なものとされていて、日本の小説でもその特徴を使って「本文中、『私は』に該当する一人称が一切使われない一人称小説」というのもある。一方、英文を読んでいると分詞構文がけっこう独特で、日本語だとごちゃっとしてしまう表現もわずかな語数で処理できてしまう。これにより文章のリズムがかなり変わってくる。
こうした場合、「句読点の打ち方」を考え直す。原則は原文の通りのコンマやピリオドに合わせるべきではあるけれど、それを頑なに守りすぎることで「文章の速さ」が変わってきてしまうのは困る。上の直訳の問題点はたくさんあるけれど、なかでも一番大きな問題は「原文に比べて文章が遅すぎる」ことだろう。そういう場合は、思い切って2文で訳してしまった方がいい。
(大滝訳例1)
僕らはコートに身を包んだ二人の陰鬱な少年だった。厳しい冬が定着しようとしていた。
あれ? さっきよりなんか悪くなった????
これはもちろんいうまでもないが、問題が句読点の打ち方だけじゃなかったからに他ならない。
もうひとつ考えなくちゃいけないのは、文章が目指す描写に即した語彙・文体の選択だ。映像としてこの文章を捉えると、「冬の寒さ」と「ぼくら二人の少年がコートに身を包んで(寒そうにして)いる」というふたつの事象は同時に発生しているのだが、文章という一次元表現ではどうしてもそれらの情報の出し方に時間差が出てくる。こうした場合、この表現においての強調のポイントを考慮する。
たとえば「grim winter settling in」について。特に分詞構文が使用され原文では手短に表現されているところなので、翻訳としてももう少し歯切れよくしておきたい。ということで、ぼくならここは「すっかり冬だ」と訳してもいい気がする。無論、進行形の文章を完了形に訳すのは如何なものか? という悩ましい問題も出てきちゃうわけだけれども、「コートを着てさみぃ」みたいな情景を考慮するなら「あーもうまじ冬じゃねぇか」みたいな感慨があっても自然だ。あと、「boys」も訳さず一人称の語りに若さを出すことで処理することにする。というわけで、
(大滝訳例2)
僕ら二人は暗い顔をしてコートに身を包んでいた。すっかり冬だった。
とでもすれば少しはマシになる。また、この2つの文の訳の順番も悩みどころではある。今回は第一文なので、物語の最初に生じる情景が「少年二人の姿」であることに注意するとたぶんこれはいじらない方が良い。ただ、今回はちょっとした研究的な意味でもあるので、「冬の寒さ」に描写のフォーカスを当てて順序を入れ替えてみる。というわけで、語順がそのままの都甲訳と比較してみて欲しい。
(都甲訳)
僕ら陰鬱な二人の青年は、コートを着て背中を丸めていた。厳しい冬がどっしりと腰を落ち着けようとしていた。
(大滝訳例3)
もうすっかり冬だった。僕ら二人は暗い顔をしてコートに身を包んでいた。
長く並列された同格表現の処理
次の文章はさっきよりもかなり手強くなる。
The college was at the edge of a small town way upstate, barely a town, maybe a hamlet, we said, or just a whistle stop, and we took walks all the time, getting out, going nowhere, low skies and bare trees, hardly a soul to be seen.
まずは直訳を。
(直訳)
大学は州北部の端っこの小さな町にあって、そこはかろうじて町といえ、もしかすると村落かもしれない、と僕らはいい、あるいは単に汽笛がなる場所(=小さな駅がある場所)かもしれなくて、それから僕らはずっと歩いていて、外に出たけど、どこに行くでもなくて、低い空と剥き出しの木々があって、人っ子ひとりいなかった。
いくら直訳とはいえもっとマシな文章を出せ! と怒られそうなのだが、原文の句読点に合わせるとかなりごちゃごちゃしている。ごちゃっとした感じの原因は「small town = barely a town = maybe a hamlet = just a whistle stop」の同格と「we said」という話法を想起させる挿入、そして区切ることなく町歩きの情景が「and」で続けられているところにある。ポイントは、このごちゃっとした感じをどの程度残すかという点だろう。
実作では接続詞を使って文章を一息につなげてしまうことで描写を重ね合わせるような印象をもたらすことができるけれども、今回の場合は日本語にすると少しうるさいし、「人っ子ひとりいない」という情景との解離を感じないでもない。後半は無理につなげずに意味単位で句読点をうち、この段落でもっとも重要な(後述)「hardly a soul to be seen」の輪郭を際立たせたい。
それに前半の「we said」は、挿入句として特に訳出しないという方向もあるけれども、原文の「ごちゃっとした感じ」はこれを話法的に処理することで反映させたいとおもう。ということで訳例。
(都甲訳)
州のずっと北の方にある小さな町の外れに大学はあった。いや、町とは言えない、もしかしたら村かもしれない、あるいは信号が灯ったときだけ列車が停車するだけの集落かもしれない、と僕らはいった。そして僕らはいつも歩いていた。外に出るだけで、どこに行くというあてもなかった。空は低く木々は裸で、人っ子一人(※「ソウル」とルビ)いなかった。
(大滝訳)
大学は州北部のはずれの小さな町にあったのだが、僕らに言わせればぎりぎり町ってところか、もしかしたら村かもしれなかったし、あるいはただのショボい駅でもありえた。とにかく僕らは歩き続けた。外に出たものの行く当てなんてなかった。低い空と葉を落とした木々があり、人影ひとつ見当たらなかった。
ここで「soul」を「人影」とあえて訳した理由は後述する。
※実験要素を含む。
あと「all the time」の解釈がぼくと都甲先生の訳ではちがっていますね。
言葉遊び的な要素の処理
ひとつ前の文であった「hardly soul to be seen」は「人っ子ひとりいない」という慣用句なのだが、ここで使われた「soul」が文章表現としてフォーカスされているのがこの段落を訳出するうえでの最大のむずかしさである。
This was how we spoke of the local people: they were souls, they were transient spirits, a face in the window of a passing car, runny with reflected light, or a long street with a shovel jutting from a snowbank, no one in sight.
ここは直訳を例示してもあまり意味がないので省略する。
都甲先生の訳では「人っ子一人」にルビをふることで処理している。言語がちがうのだから慣用句と単語の溝からこうした問題が生じることは少なくないし、ルビをふるというのは非常によく使われる解決手法で、ぼく自身も無理せず基本的にルビで処理するようにしている。だけど、こうした部分をルビに頼らず処理してみようとすることも翻訳の勉強なら重要なので、あえて今回はその方向性での解決を目指してみる。
前文でぼくは「soul」に「人影」という訳を当てた。「魂」と「影」はまったくちがう意味を持っているのだから、この部分は「誤訳だ!」と言われても仕方がないとおもう。しかし、人の虚ろな気配に質感を持たせることで文脈上「魂」を「影」と呼ぶことも可能なのではないか、とぼくは考えている。
また、後半の「a long street with a shovel jutting from a snowbank」は日本語にするとかなり不自然になるので、映像を細切れにすることで文体にスピード感をつくることで情景に遅れが出ないようにする。
(都甲訳)
僕らは地元の人たちをそう呼んでいた。彼らは魂(ソウル)だ、はかない亡霊だ。通り過ぎる車の窓に見える、反射光ににじむ顔。積み上げられた雪からシャベルが突き出ている長い通り。あたりには誰もいなかった。
(大滝訳)
影。僕らは地元の住人をそう呼んでいた。そう、奴らはうつろいゆく亡霊だ。光を弾きながら走る車の窓からのぞく顔。長く伸びた通り。その脇にある雪だまりから突き出たシャベル。視界には誰ひとり映らない。
やっぱ「魂」の方がいいですね……!
訳のまとめ
というわけで、今回の訳をまとめてみた。
(原文 再掲)
We were two sombre boys hunched in our coats, grim winter settling in. The college was at the edge of a small town way upstate, barely a town, maybe a hamlet, we said, or just a whistle stop, and we took walks all the time, getting out, going nowhere, low skies and bare trees, hardly a soul to be seen. This was how we spoke of the local people: they were souls, they were transient spirits, a face in the window of a passing car, runny with reflected light, or a long street with a shovel jutting from a snowbank, no one in sight.
引用:THE NEW YORKER "MIDNIGHT IN DOSTOEVSKY"
(都甲訳)
僕ら陰鬱な二人の青年は、コートを着て背中を丸めていた。厳しい冬がどっしりと腰を落ち着けようとしていた。州のずっと北の方にある小さな町の外れに大学はあった。いや、町とは言えない、もしかしたら村かもしれない、あるいは信号が灯ったときだけ列車が停車するだけの集落かもしれない、と僕らはいった。そして僕らはいつも歩いていた。外に出るだけで、どこに行くというあてもなかった。空は低く木々は裸で、人っ子一人(※「ソウル」とルビ)いなかった。僕らは地元の人たちをそう呼んでいた。彼らは魂(ソウル)だ、はかない亡霊だ。通り過ぎる車の窓に見える、反射光ににじむ顔。積み上げられた雪からシャベルが突き出ている長い通り。あたりには誰もいなかった。
(大滝訳)
僕ら二人は暗い顔をしてコートに身を包んでいた。もうすっかり冬だった。大学は州北部のはずれの小さな町にあったのだが、僕らに言わせればぎりぎり町ってところか、もしかしたら村かもしれなかったし、あるいはただのショボい駅でもありえた。とにかく僕らは歩き続けた。外に出たものの行く当てなんてなかった。低い空と葉を落とした木々があり、人影ひとつ見当たらない。影。僕らは地元の住人をそう呼んでいた。そう、奴らはうつろいゆく亡霊だ。光を弾きながら走る車の窓からのぞく顔。長く伸びた通り。その脇にある雪から突き出たシャベル。視界には誰ひとり映らない。
みなさんもぜひ、翻訳にチャレンジしてみてください!
頂いたご支援は、コラムや実作・翻訳の執筆のための書籍費や取材・打ち合わせなどの経費として使わせていただきます。