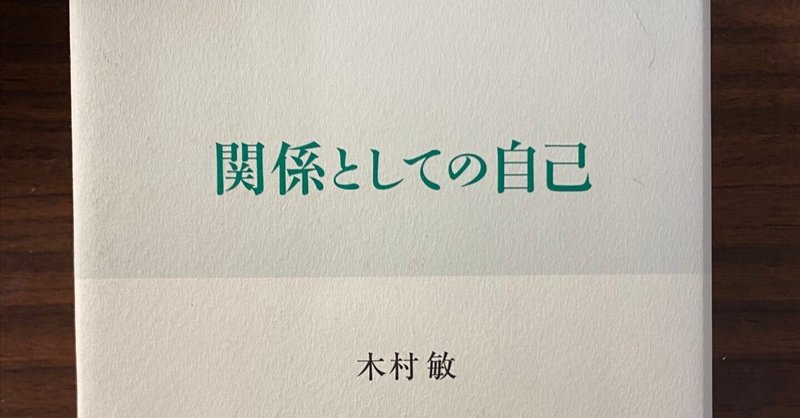最近の記事
人類学の道第六回「Making:Anthropology, Archaeology,Art and Architecture(3)」
前回までのあらすじ過程をブラックボックス化することにより「メイキング」という行為が人間のイメージをモノに転写する試みであると主張するHylomorphic modelに対して、インゴルドは「過程」を重視し、むしろ万物全てが「生成過程」の中にあると主張する(morphegentic process)。この考え方は「物質」に対する従来の概念をも批判する。物質には固有の性質はなく、それはmorphegentic processの中で現れる「歴史性」なのである。ゆえに「Making(
人類学の道第四回「Making:Anthropology, Archaeology,Art and Architecture(2)」
前回までのあらすじ 「人類学とは何か」の本質的な主張を、アバディーン大学の4Aカリキュラム(人類学、考古学、芸術、建築)を通して提示していく「メイキング」。前回はこの4Aが「参与観察」的実践で結びついているということがわかったのだが、また字数が足りなくなったので2回目に続いた。ところで「人類学とは何か」の方が多分発行年数が遅いから、「Making」を通して「人類学とは何か」を読んだ方がいいかもしれない。今回は4Aを通して「Making(制作)」という運動を西洋思想がどのように
人類学の道第三回「Making:Anthropology, Archaeology,Art and Architecture(1)」
はじめに私事ではあるが、5月11日に、前回紹介した「人類学とは何か」、そして今回から取り上げる「Making(邦訳:メイキング)」を著したティム・インゴルドの自宅にお邪魔することになった。自分としてはてっきり現在もアバディーン大学で教鞭をとっているものだと思っていたので、「授業やチュートリアルにお邪魔できれば幸い」程度に考えていたのだが、実はだいぶ前に退任しており(これだからウィキペディアは信用できない)、代案として本人から自宅にこないかと言われたのがことの始まりである。こん