
日本代表のサッカー観戦にデジャブを感じる。そう、これは自己啓発本の読後感と同じだ。
好きなんだけど嫌いってものがこの世には存在する。そんなコインの裏表みたいなものが僕の場合、自己啓発本だ。日本代表のサッカーの熱戦を見ていてふと思った。その場では感情が強く深く渦巻くが、現実には我が身には何も変化はない。物語を乗り越えて現実と戦うことが大事な気がする。
まだ産まれて1ヶ月弱の子どもにミルクを夜中にあげる関係でW杯の試合をよく観る。僕は「にわか」とすら呼べないぐらいのレベルのサッカーファンだ。深夜で眠いからテレビをつけていないとミルクをあげている最中にウトウトしてしまう。だから、日本の予選リーグも3試合とも観戦した。
国際試合を観戦していて感じたことがひとつあった。そう、これは最高かつ典型的な自己啓発教材だ。最高レベルで努力して国を背負った厳しい戦いを目の前のリアルとして実体験する。たった90分の試合の中に喜怒哀楽のすべてが詰まっている。声を枯らして応援することで自分もその一員になったような錯覚を覚える。様々な感情が渦巻く。そこには勝って嬉しい、負けて悔しいを超えた何かがある。そして、我が身に当てはめる。俺も頑張らなきゃと。
起業を決意してから結構な数の自己啓発本を読んできた。どの本も言っていることはすべてひとつだけだ。本の作者がどんな職業だろうが、どんな経験をしてようが、どんな性格だろうが一緒。すべての本が「Just Do It!」(=とにかくやれ!)と言っている。おおよその内容はすべて「行動せよ!」という読後感を手練手管を変えて言い換えさせただけにすぎない。

自己啓発本には作者の苦労や努力、成功がすべて実体験(または取材した話)として物語られている。読んでいると興奮したり安心したりする。あぁ、この人はこんな試練を乗り越えて成功したんだなぁ。こんなすごい人なのにイージーな失敗を繰り返して成長していったんだなぁなどなど。感情が高揚して自分も頑張らなきゃと思う。それが自己啓発本の使命だ。
経営者として自己啓発本からは学ぶべきところは山ほどあるだろう。でも本を読んで感情を沸騰させるよりも実際の事業のことを考えて考えて考え抜いて行動にうつしたほうがずっと有益である。考えてみれば簡単なことで自己啓発本には当然ながら現実を変える力なんてない。どれだけ感動しても、現実には何も変わらない自分がいるだけ。自己啓発本にはそういうどうしようもない空虚さがある。そこが好きなんだけど嫌いと思う所以だ。
よし!読んだから今日からやってやるぞ!俺は変わるぞ!と思うものの現実に何かを変えた人はどれだけいるのか。ホリエモンの本を読んで何人の野心を持った人間が現実の行動を変えて動き出したのだろうか。稲盛和夫の本を読んで何人の邪な心を持った人間が経営に仏教の精神を入れただろうか。統計を取ってみたい。自己啓発本は読んで興奮してそこで満足させてしまうことが多いと思う。
W杯を見ていて同じような感情がデジャブのように僕を襲った。自分以上に頑張っている選手に対して、我が身(と国)を重ね合わせて頑張れ!と声を張り上げている。勝てば街中で騒ぎ、負けたらネット上で批判しまくる。勝ち負け関係なく過剰反応する世の中の姿を見るととてつもない空虚さを感じてしまう。もちろんそんな姿はマスコミが切り取った一部の中の一部なんだけど。応援して叫ぼうが手のひら返しを繰り返そうが何をしようが現実は何も変わらないのだ。一喜一憂の先には何も変わらない自分がいるだけだ。
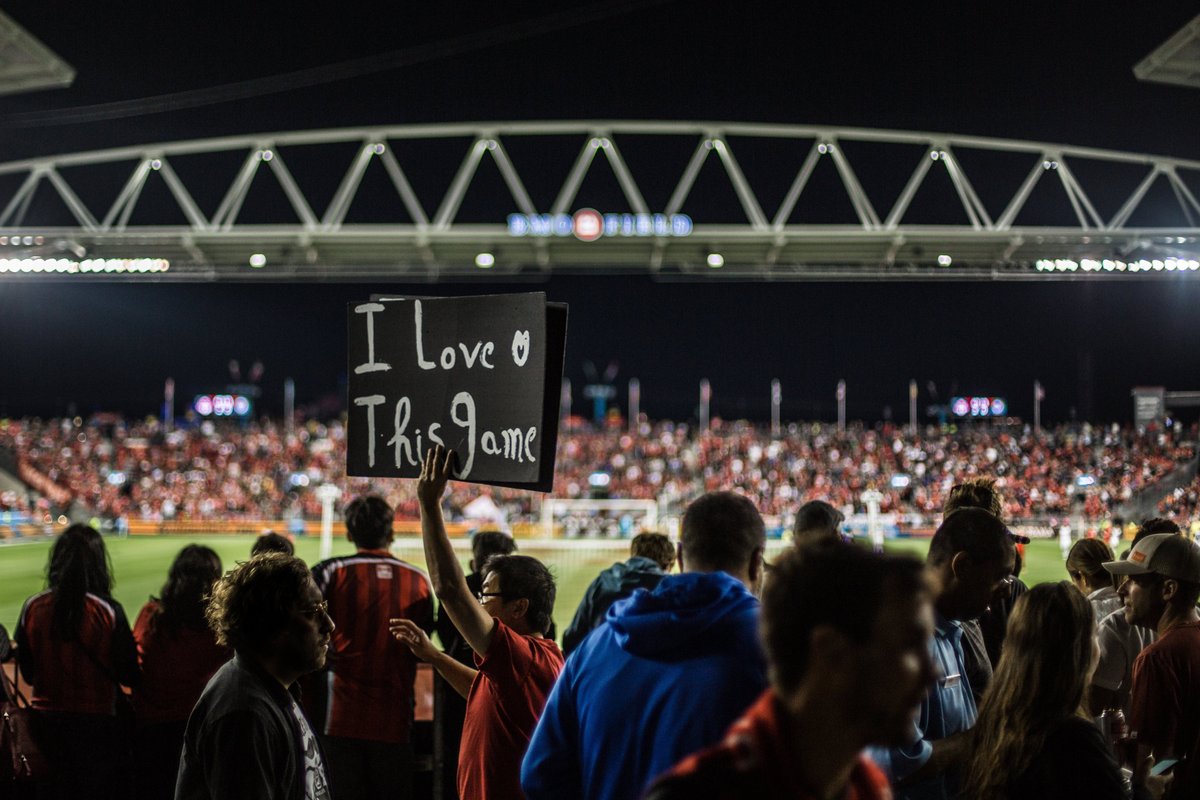
自己啓発本が強いる感情の渦と国際サッカー試合を見た後に強いられる感情の疼きはどこか似ている。体が比較的小さい日本の選手が体の大きな欧米の選手と国の威信を賭けて戦って勝つのはすごいことだ。国と国同士の戦いは個人の戦いを超えた物語を生み出すから単純に格好いい。でも、メディアが語る彼らの物語にはどうしようもない自己啓発本と同じ匂いを感じてしまう。
読書後に本を閉じて欲しい。試合後にテレビを消してみて欲しい。自分の半径1メートルの現実は何も変わっていない。本の作者が事業で成功を収めたとき、サッカー選手がゴールを決めて名声を得たとき、僕たちの現実には何の変化もない。物語によって昂った感情に現実を変える作用はない。物語は物語として高揚する感情に流されずに、目の前や心の中の課題に向かって日々行動したいと思う。
日本中が予選リーグを突破して喜び勇んでいるときにそんなことを感じてしまう自分はきっとHUBなんかで知らない人とハイタッチなんてできない人種なんだろうなと思う。
そう言えば、サッカー産業の一大メーカーNIKEの企業モットーも「Just Do It」だった。これが偶然なのかは知らないけど、きっとそういうことなんだろう。
