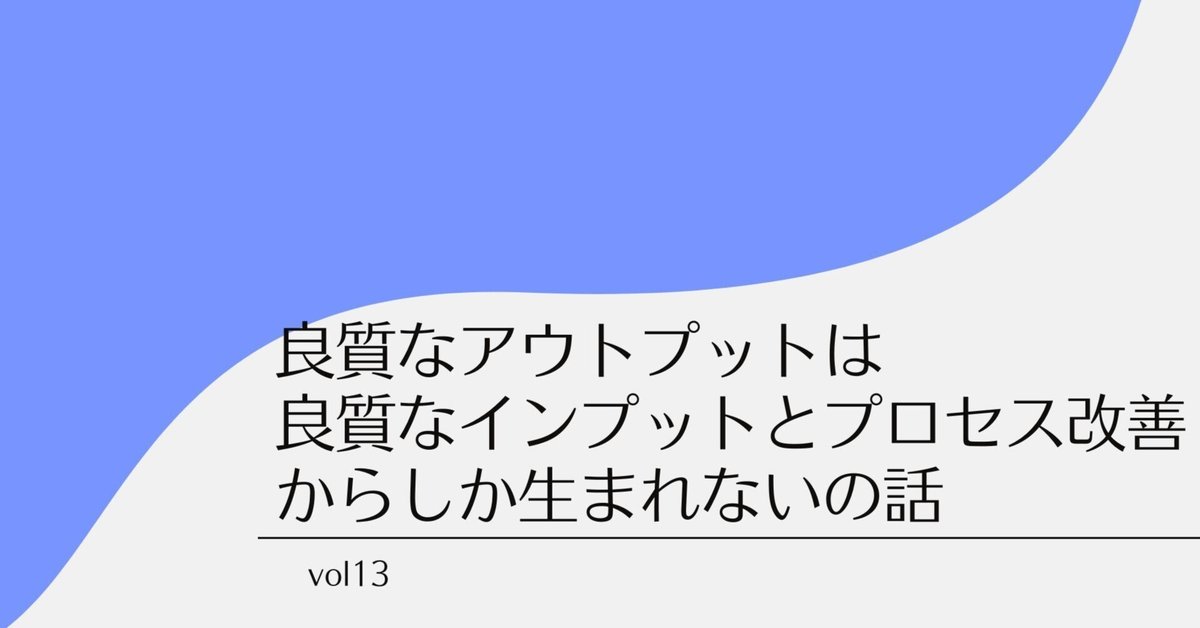
良質なアウトプットは良質なインプットとプロセス改善からしか生まれないの話
こんにちは、コンサル転職の中の人、「コン転」です。
現在、事業会社などで勤務されていて、未経験でコンサル業界に行きたい方(就活生含)を主な読者の対象にして、noteを投稿しております。
今回は、良質なアウトプットは良質なインプットとプロセス改善からしか生まれないというテーマについてpostさせていただきます。
コンサルに入社する誰もが意識したいのは、どれだけアウトプットの質を高められるか?だと思います。
先に言ってしまいますが、どれだけアウトプットの質を高められるか?は、マインドセット・インプット・プロセス改善の3つの因数に分解できます。
今回は、その中でもインプット・プロセス改善について詳しく説明していければと思います。(マインドセットについては、どれだけアウトプットの質を高められるか?で悩んでいる人は、マインドセットについては一定身についていると思われるので、ここでは割愛)
本noteを少しでも良いと思ったら、noteやTwitterでシェアいただけますと幸いです。
アウトプットの質を高める3要素
冒頭で述べてしまいましたが、アウトプットの質を高める3要素は、マインドセット・インプット・プロセス改善です。
本章では、それぞれについて簡単に説明して、インプット・プロセス改善について次章以降で詳説できればと思います。
マインドセットとは、ここでは「良質なアウトプットを出すためにどれだけの意識を持っているのか」のことで、ここでは2種類に大別しています。
1種類目は、個人の性質・原動力です。
例えば、「完璧主義だから、途中で手抜きをすることはありえない」「XXという夢を持っているから、XXという経験を積んでいきたい」「細かいことが好きだから、細部まで手を抜きたくない」といったものです。
2種類目は、コンサルタントというプロフェッショナルに求められる素養です。
例えば、「プロジェクトを成功させるために、アナリストだからと言ってリサーチに逃げてはダメ」「どんなにプロジェクトが忙しくても、クライアントには最高のアウトプットを出すべき」といったものです。
これら2種類の掛け合わせ(足し合わせ)で個人のマインドセット力が規定されます。
インプットとは、ここでは「良質なアウトプットを出すためにどれだけの質や量の知識・経験を溜め込んでいるか」、のことで、プロジェクト内のインプット・プロジェクト外のインプットの2種類に大別することができます。
プロセス改善とは、「良質なアウトプットにたどり着くために、どれだけの質や量の試行錯誤を行っているか」のことです。
仮に、マインドセット・インプットが十全であっても、いきなり良質なアウトプットを出すことはできません。
野球でも、どれだけ野球を上手くなろうと思っても、どれだけ野球に関する本を読んでも、いきなり1試合目でピッチャーで4番バッターになることはできません。
頑張って、(その時にしては最高の)アウトプットを出して、失敗しまくって、また改良版のアウトプットを出して、、、の繰り返しで、良質なアウトプットを出すことができます。
インプットの質や量を高めるアプローチ
前章では、マインドセット・インプット・プロセス改善の3要素が良質なアウトプットに強く紐づいているということを話しましたが、ここからは、インプットとプロセス改善について詳細を話していければと思います。
まず、インプットについてですが、プロジェクト内のインプット・プロジェクト外のインプットがあり、両方必要です。また、個人的には、後者の方が重要だと思っています。(前者は、コンサルタントであれば誰でもやることなので)
プロジェクト内のインプットとは、あるプロジェクトにアサインされた時に、そのプロジェクトに関係する業界の知識・業務の知識を習得することです。例えば、下記の本などですね。
https://amzn.asia/d/ay2q7hO
それに対して、プロジェクト外のインプットとは、プロジェクトのアサインに関係なく、自分が面白いと思ったテーマなど興味範囲に応じて読むことです。本当になんでも良いですが、例えば、下記の本などですね。(私の今の興味分野の本を記載しております)
https://amzn.asia/d/4vmLiSW
https://amzn.asia/d/6DsbfiF
https://amzn.asia/d/ay2q7hO
で、どうやってインプットの質や量を高めるのかですが、まずはたくさんの数の本を読みまくってください。
前提ですが、最初から完全に質を追うことはやめましょう。巷には質を追うアプローチについて書かれた本などが出回っています。もちろん、それを参考にするのは良いことだと思いますが、それだけでは完全に最短でインプットの質を高めることはできません。人から聞いたことや本だけを読んで、完全にその人の経験を追体験することはできないからです。
この時に、投下コストと求めるインプットの質を重視し、最短経路を探してしまうと結局何も得ることができません。(最短経路はあるはずがないので)
イメージとしては、「目的地に行くまでの最短経路はわかるはずがないけれども、大回りは避けよう」というイメージで、質を追うアプローチの本を読んでください。
話はそれましたが、まずは、たくさんの数の本を読みましょう。その後では、目的を決めて本を読んでみましょう。
同じ本を同じ時間読んでも、インプットの量に差が出る人がいます。何がこの差を生んでいるのかと言えば、能力と目的意識だと言えます。(受験勉強において考えるとわかりやすいかと思います)
能力については、今ここですぐには変えられませんが、目的意識についてはすぐに変えることはできます。
本文を読む前に目次を読んでみて、「この本から自分はどのような情報を取得したいか?」を考えてみてください。
で、実際に本を読む上で、取得したい情報が取得できそうな箇所に付箋を貼ってください。
また、読後には付箋を貼った箇所を読み返して、情報をまとめてみてください。そして、それが本文を読む前に考えた取得したい情報を一致しているかを確認してください。
これの積み重ねでインプットの質を高めることができます。
プロセス改善を行うアプローチ
プロセス改善の質や量についても、インプットと同じで、プロセス改善を回す回数が重要です。
プロセス改善とは、ある命題に対して、あるアウトプットを考え、それの検証・改善を繰り返し、最高のアウトプットを出すことですが、この繰り返しの回数を増やすことが第一に重要です。
また、検証・改善を繰り返す、つまり、違う観点から自分のアウトプットが正しいかを自分が判断することがプロセス改善において重要です。
プロセス改善の質を高めるためには、ここの「違う観点」が重要です。
できるだけたくさんの観点で、自分のアウトプットを判断しましょう。
例えば、マクドナルドが2023年冬に新しく発売すべき商品を考えるときに、最初に餅バーガーを考えたとしましょう。この時に、餅バーガーが2023年に新しく販売すべき商品に妥当かを判断する際、観点の数が少なく、例えば下記であるとすると、次に出すアウトプットの質がイマイチ高まりません。
・消費者が喜ぶ商品であるか
・技術的に開発可能か
一方、たくさんの数の観点(例えば下記)から、アウトプットを考えると、次に出すアウトプットの質を高めることができます。ここでは、次にアウトプットを考える際に、下記の観点が頭をよぎるため、その観点を自然とクリアしたアウトプットを出すことができます。
・消費者が購入するには妥当な値段設定にできる商品か
・多くの消費者が美味しいと感じる商品か
・今から開発を始めて、2023年冬の販売に間に合う商品か
・各マクドナルドの店舗の既存機械で販売可能な商品か
・(既存機械で販売不可能である場合)本部などから材料を輸送が可能か
・マクドナルドの既存商品との抱き合わせ販売が可能か
・消費者の安全上、問題ない商品か(誤嚥などがないか)
結論、プロセス改善においては、
・プロセス改善を回す回数が大事
・プロセス改善を行う際の検証フェーズの検証観点の数が大事
ということになります。
まとめ
今回は、良質なアウトプットは良質なインプットとプロセス改善からしか生まれないというテーマについて話しました!
良質なアウトプットは、常にマインドセット、インプットとプロセス改善に規定されます。1つだけ十分であってはダメで、3つ全てを高め続けなければなりません。
コンサルタントというプロフェッショナルな職業に就いたからには、ぜひ頑張って3つを高め続けてください!
面白いと思った方は、noteやTwitterなどでシェアしてください!
それでは!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
