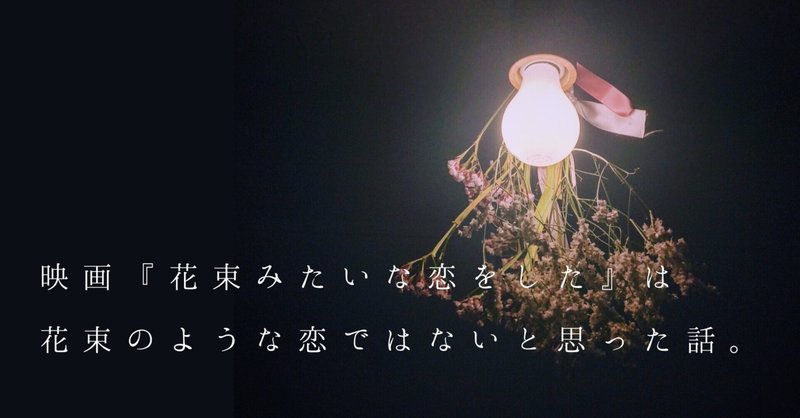
映画『花恋』は花束のような恋ではないと思った話。
■【はじめに】私が映画『花束みたいな恋をした』を観た理由
今話題の坂本裕二脚本のこの恋愛映画、昨今の日本映画の中でもかなり評価が二分されているものではないだろうか。鑑賞前にあまり他人のレビューは見ないように避けていたが、宣伝は頻繁に目にしていたし、何しろ「リトルモア」が配給で入っているので気になっていた。(私は最果タヒ氏が好きなのでリトルモアは結構チェックしてる。)
そして劇中にはAwesome City Club。これは私が大学1年生(3年ほど前)の頃によく聴いていたバンドの一つだ。自分でこんなことを言うのも滑稽だが、数年前から目をつけていたバンドや作家が流行ったり売れたりすることが多く、そういう先見の明はあるタイプだと思っている。そのため、またしても自分の好きなバンドが多くの人の目に留まると知り、Awesome City Clubの晴れ姿を劇場で観ておきたいなと思っていた。本映画が公開してすぐに観に行ったのであろう知人たち何人もが、SNSでインスパイアソングである「勿忘」をシェアしているのを見たときは感動すらした。(Awesome City Clubの中で特にお気に入りの曲を貼っておきます。)
こういう背景があって私は『花束みたいな恋をした』が気になっていたので、菅田将暉演じる麦と有村架純演じる絹の2人の恋愛模様には正直あまり興味がなかったのが本心である。
劇場に足を運ぶまでを少しばかり書かせていただいたが、この映画を観て私が感じたことについて触れていきたい。普段はこんなことをしないし、残すとしてもFilmarksのレビュー機能内のみなのだが、今回は観終わって「言いたいことがありすぎるだろ〜!!!」とツイートが止まらなくなった。そのため今回は以下のような観点から吐き出させていただけたらと思う。
■この映画における3つの嫌悪感
■勘違いしないで、坂本裕二は素晴らしい
■麦と絹は、”価値観が合っていた”のか?
■恋人と観に行かない方がいいって本当?
■【最後に】この恋は、どんな恋と言えるのか
■【おまけ】個人的なイチャモン
鑑賞済みの方に向けた内容になっているため、ネタバレを踏みたくない方はここでブラウザバックをお願いいたします!
■この映画における3つの嫌悪感
この映画について私は3つの嫌悪感があった。
① まず一つ目の嫌悪感は、映画内に登場する作品やそのチョイスに対する「あざとさ」である。おそらく初手で登場したのは芸人・天竺鼠だったと思う。最も、ここで気になったのは、天竺鼠の一般的な知名度であるのだが、 私は関西出身というのもあり、お笑いや芸人が好きな友人たちに囲まれ、知名度の低い芸人が出演する深夜のローカル番組などを横目に課題に泡を吹く中高生時代を過ごした。そういう私の立場からすると天竺鼠はどちらかというとメジャーな芸人の1人ではある。関西で育ち、関西の大学に通う若者2人が天竺鼠が好き!というのと、東京で暮らす若者が単独ライブに行くほど天竺鼠が好き!というのは何となく違う感覚というのが前提であると思う。
そして、そのギャップを脚本の坂本裕二氏が考えていないわけがない。つまり、意図的に「天竺鼠」のチョイスをしているわけだが、誤解を恐れずに言うと、天竺鼠を好きな人を、カルチャーもしくはサブカルチャーにおいて勝手にマイノリティとしてカテゴライズし、「この映画は、マイノリティに光を当てている作品ですよ」という一種のわざとらしさがあると感じたのだ。実際、天竺鼠は芸風として業界人・同業者ウケが強く、「常人ではわからないセンス」があると考える人も少なくない。だから、こういった作品の中で象徴的に「天竺鼠好き」が演出されるのも分からなくもないが…
なんかちょっとズルくない?という気持ちがうっすら浮かんだのは私だけだろうか…。それ本当に天竺鼠好きな人からしたら多分ちょっと嫌な気持ちになる使い方してるよ…。という気持ちにならざるを得なかった。他にも押井守監督がいきなり出てきたり、二人の共通の好きな小説家として今村夏子氏が挙げられたり、カラオケできのこ帝国を歌ったりと、サブカルの教科書で太字で書かれてるような固有名詞ばっかりが出てくるのである。
私自身も劇中の麦と絹が好んでるようなものを読んだり聴いたりするし、スポットを当てているバンドや作家自身に嫌悪感を抱いたのではない。ただ意図的に”いわゆるサブカル”を羅列していく序盤の流れにどうしても嫌悪感を覚えた。脚本の坂元祐二氏からすれば、登場人物の性格や彼らの社会的な立ち位置の紹介になる手っ取り早い名刺のようなものという意味で、そういった固有名詞を活用しているのだろうが、なんか…もうちょっと、その固有名詞自体とそれらを好きな人たちにリスペクトがある感じを、匂わせてもよかったんじゃないですか?と若造は思う。
極めつけは、冒頭の終電を逃したサラリーマンとOLと麦と絹の4人でカフェのようなところで談笑していたシーンだ。なんてことないサラリーマンが「俺、好きな映画、マイナーだねって言われるよ?」なんて現実で聞いたら笑ってしまいそうなセリフを吐き、最終的に出てきた好きな映画は「ショーシャンクの空に」だった。
いや、ショーシャンクの空にを馬鹿にして押井守だけを崇高とするその思考、どう考えたって嫌悪でしかないだろ!!と思ってしまったが、それはその会話を前に冷めた目をする麦と絹だけに言いたいのではなく、そういった演出を使って、一種の人物描写をすること自体にも言いたい。
② その次に抱いた嫌悪感は、最初に感じた嫌悪感から派生した。散々羅列された”大御所サブカル”固有名詞たちを「何故好きなのか」、麦と絹は語ってくれないのである。
居酒屋で意気統合するあのシーンでは、「○○が好きです。」『じゃあ△△は?』「それも好きです。」『やっぱり。私も○○と△△好きです。』といった調子で話が進んでいく。確かに、初対面の人と自分の好きなものについて深く語り合うのはハードルが高いとは思う。しかし、物語が進むにつれて麦と絹の仲が深まっていってもそういったシーンは描かれない。
というか、描く必要がないと考えられたのだろうか?現実に存在する作品や作家に対して、映画の中の登場人物たちが感想を述べあえば、その感想とは違う意見の鑑賞者が映画にマイナスなイメージを持つ可能性があるから、そのリスクを避けたのだろうか?麦と絹の好きなものに対する価値観がわかる描写があれば、それこそ二人の人柄がより受け手に伝わりやすいんじゃないかと私は思うし、登場人物と受け取り方が違ったからという理由でこの映画自体を低評価するほど鑑賞者は低俗じゃねえよとも思ってしまった。
そして、そこから感じたこの作品に対する嫌悪感は輪郭をはっきりとさせた。
押井守なのも、天日鼠なのも、今村夏子なのも、ゴールデンカムイなのも、きのこ帝国なのも、海外サッカーなのも、
— なにぬ🛸 (@lobotomysaveme) March 4, 2021
そこの理由が何もなくて悲しかった。
だからそれぞれが、細田守でも、かまいたちでも、川上未映子でも、キングダムでも、andymoriでも、
成り立つ話なのが本当に残酷だと思ったんだよ。
これは私のツイートなのだが、映画内で挙げられたサブカル固有名詞は結局、代替可能な名詞でしかなかったのではないかという落胆があった。二人が散々趣味や趣向について話を交わすのに、それらが劇中で語られなくてはならない理由が見つからなかったのだ。押井守監督が好き同士の二人だからこそ、たどり着く物語の終着点が、個人的にはあってほしかったのである。この映画のストーリーは本当に細田守監督好きの設定でも、andymori好きの設定でもきっと同じだったのだという嫌悪感がすごい。この嫌悪感は絶望にも似ている。
あと、私がその代替不可な感じがちょっとばかり好きという性癖もあるから嫌悪感を抱いたのかもしれない。サカナクションがスペースシャワーネットワークでやっていたNFパンチという番組にて、とある人の服装からどのバンド・アーティストが好きか当てるという企画があった。音楽における思想が服装においても反映されて、なんとなく直感的にわかる絶妙な雰囲気をゲームにした面白いものなのでぜひ見てほしい!!
この絶望のような嫌悪感から言えることは、「代替可能性への恐怖」だと思う。「結局、私らしさというのは私の思考で制御できるものではなくて、私といえる個性があろうとなかろうと、たどり着く未来に影響は及ばないのかもしれない」という無気力さが浮き彫りになったのだ。川谷絵音氏がサムネで笑っているので言わせてもらうと「私以外私じゃないはずなのに、私と私以外の人に大した差なんてない」といったところだろうか。
③ そして、最終的に感じた嫌悪感は恋愛観についてである。映画の中の麦と絹の、”陳腐でしょーもない恋愛”を私達は傍観したのちに、作品の要所要所だけでなく、5年に渡る二人の恋愛に嫌悪感を覚える。
物語のラストは麦と絹が別れてから、お互い違う恋人と出かけているときに遭遇するシーンだ。(映画の一番初めでもその遭遇は描かれている。)それぞれの新しい恋人は、あまりサブカルに対して詳しい人ではなさそうだったから、麦と絹は「なんだ。好きな小説家が一緒じゃなくたって、うまくやっていけるし、一緒にいて楽しいんだな。」と感じていることだろう。だから、好きなものや趣味が同じことだけがきっかけで恋に落ちた若かりし頃の恋を「バカだったな~(笑)」などと思っている可能性すらある。”陳腐でしょーもない恋愛”を本人たちは数年の時を経て”陳腐でしょーもない恋愛”だったと自覚しているかもしれないのだ。
そう。この”陳腐でしょーもない恋愛”、映画を観る前なら、私や傍観者たちも当然当事者になりうる可能性があったのだ。私はこの映画を観て5年に渡る”陳腐でしょーもない恋愛”を経験した感覚になったのだ。だからこそ、経験に対して「あの時はバカだったな。」という、思い出を振り返った時のような嫌悪感が残るのだ。すごい。ありもしない思い出に嫌悪感を抱いている。私は麦と絹のように5年を無駄にせずとも教訓を得たのである。これはありがたい。
■勘違いしないで、坂本裕二は素晴らしい
私はこの映画を「いい作品だ!評価したい!」と思えなかったが、抱いた嫌悪感たちというのは、坂元祐二氏が受け手に与えつけるためにそう演出したのかもしれないとすら思えてきている。
以下は私がFilmarksに追記したものだ。(4年間とあるが実際には5年間のストーリーだった。)

「もう二度と観たくないよこんな嫌な映画…」が褒め言葉になる瞬間である。映画を通して改めて、麦と絹のような恋愛に一ミリも憧れがないかと聞かれるとかなり答えに迷うと思う。憧れているとまでは言い過ぎかもしれないが、「私が憧れている恋愛象は、傍から見ればいかに寒く、また陳腐なものであるか」というのをこの映画から学んでしまったのだ。
というのも、私はこれまで、聴く音楽や好む作家に対して、周囲の人から共感されることが少なかった。簡単に言うと、趣味趣向が完全に合致するような人に出会ったことがなかったのだ。友達にも誰一人いなかった。しかし、それは私の趣味に対して風当たりが強かったと言いたいわけではない。似たようなジャンルを好む友人は多く、互いに好きなものを尊重していて、時には互いの好きなものを報告しあうような仲でもあった。ただ、リスペクトを込めているとはわかっていても、互いの価値観に不干渉すぎるあまり、距離を感じてしまうことが多々あった。だから、自分と似たようなものを好む人と恋愛関係になってみたいと思っていたのである。
それに、互いに好きな音楽や映画が一緒であれば、きっと互いの性格も似ていて、互いの価値観を共有しあうことができるのだろうと想像していた。が、そんなわけはないと坂元祐二氏は教えてくれた。
さらにすごいと感じたのは、終わり方である。昭和~平成のテッパンであった、壮大なラブストーリー感は全くなく、別れてもSNSでは頻繁に投稿をいいねしあってるよ~というような令和世代のラブストーリーになっているというのがただのオジサンでは書けない話だと思った。
そういった何気ない若者の何気ない恋愛をあまり盛らずにスクリーンに映しちゃうという作品としての素直さが若者の間で評価されFilmarks4.1という結果に繋がっているのかもしれない。(私はすみません、2.1をつけてしまいました。決して偉そうな気持ちで付けているわけではございません。)
■麦と絹は、”価値観が合っていた”のか?
Filmarksのレビューをスクロールしていると「趣味や価値観が合う人を大事にしたい」とか「価値観が同じでも小さなすれ違いが致命傷だ」というような内容のものが目立った。
果たして、あの2人は趣味や価値観があっていたと言えるのか?と私は疑問に思う。確かに趣味や好きなものは同じだったと思うけど、価値観については多分合ってなかったのでは…と感じる。というかお互いの価値観を剥き出しにして話すことは一切なく、価値観について確認することすらなかったような気がする。絹が麦に対して、「うちの本棚と全く一緒です。」と嬉しそうに言っていたが、その時の会話もそれで終わりだった。もう少し、○○は△△だから好きというような会話が生まれてもいいのではないかと私は不思議な気持ちだ。
よくよく考えると家庭環境もかなり二人は違いそうだ。麦は地方出身で決して裕福とは言えない家庭で育ち、大学をきっかけに上京してきたようだった。一方で、絹の親は広告代理店。そして、恐らく優等生タイプの姉がいた。両親の雰囲気を見ると電博どっちかにいそうな感じで、その姉も社会人としてしっかり働いてるようだった。この対比を見ると、麦が生活のために心を摩耗して働くという選択をするのは妥当な感じがしたし、絹が「ただ楽しく生きていけたらいい」と高給取りであろう親に今まで守られてきた次女らしい発言をするのも納得である。
家庭環境までを考えるとやはり二人は好きなものが一緒だっただけで、好きな理由まで一緒の”価値観が一緒”だった仲とは到底思えない。価値観が似通っていれば、生活のために余裕なく心を削って働くことに理解できなかったり、人生の中で趣味に比重をかけすぎる生活にあきれたりすることはなかったのではないか。
結局、絹と麦は見てきた世界(好きなもの・共感したもの)は同じだけど住んでる世界(価値観)が違った2人なのだと思う。だからこそ、物語のラストで、好きなもの・共感したものが同じだということだけで簡単に惹かれ合う恋は幼稚なのだと私たちに教えてくれる。
■恋人と観に行かない方がいいって本当?
レビューや感想の中には、これをカップルで見ると爆死するからやめておけという内容のものもかなり目立つ。そりゃそうだ。惰性的に付き合っているカップルは、自分たちと同じような人たちが別れる話を観るのだから、そりゃ気まずくなったり、今後を考え直したりするだろう。
だけれども、私は恋人と観に行くことで麦と絹にはできなかった価値観の共有ができるからこそ、この映画を選ぶという挑戦をしてもいいと思う。これを私のように「嫌悪感がすごい映画だな」とお互いが感じて、それを語りあえれば、麦と絹のような終わりは来ないのだと思うし、反対に二人ともがこの映画に感動して号泣しているのならば価値観が合っているのだと思う。一番まずいのは、「よかったね~」と二人で誤魔化してしまうことだと思う。これ完全に麦絹フラグでしょ。別れることになっても、少なくとも麦と絹のようにまた次の適当な人と付き合うのではなく、きちんと自分の価値観や考えをぶつけられる人を見つけてほしい。
■【最後に】この恋は、どんな恋と言えるのか
ド素人が散々、『花束みたいな恋をした』について褒めたり貶したりさせていただいたわけだが、つまるところ、この映画は何みたいな恋と言うことができるのか、私なりに考えてみた。
結論は、この恋を花束みたいな恋と比喩している間は成長できていない証なのではないか、ということである。花束が何を意味するのか人にとって捉え方は違うだろうが、私はやはり美しいものとしての側面が強く出ていると思う。つまり、"花束みたいな"と表現して、過去の向き合えなかった相手との恋愛を美化しているに過ぎないと思えてしまうのである。だから、花束みたいな〜なんて言わず、豆腐みたいなとか(豆腐は美味しいし、栄養価も高くて最高の食べ物だけど)、ワンカップ大関みたいなとか、そういう捉え方ができてこそ、この二人の恋が私たちのそして二人の未来に意味を成すと思いたい。
この映画に共感できたか・できなかったかは大事ではない。もちろん私はこの映画に共感できたどころか、何とも言えない嫌悪感をいくつか抱いたが、作品を観た2時間が全く無価値な時間だったとは思わない。この嫌悪感が自分にも向くかもしれないものだったと気づくことができたから。作品として私が受け取るべきメッセージを受け取ることができたと思っている。
そして、この映画に共感できたから・理解できたから偉いなどという基準は存在していなければ、制作陣もそんなものを設けているつもりはないだろう。反対に、この映画のダサいところを見抜いたから偉いなどという尺度もない。それぞれの作品を、自分の立場から噛み砕いて何を得られたかきちんと心に留めておくことが大切なのだろう。麦と絹のようにもならないためにも。
面白いかどうかは人によりけりとは思いますが、いい勉強になり、人によっては2時間ちょっとでかなり人生経験が積める作品だと思います!

■【おまけ】個人的なイチャモン
私は押井守より断然今敏の方が好きです!!!その時点で何となく馬が合わない気がしていました!!!
あと若かりし二人を思い出すきっかけとなったファミレスにいた学生役の子、長谷川白紙好きそうに全く見えなかったんですけど!!!
という冗談はさておき、「好きなこと・楽しいこと」を仕事にするということはそんなに難しくて、また幼い考え方なのかという部分が引っかかった。
絹が安定した事務職を辞めてイベント会社に転職した時、麦は「相談してほしかった」というだけじゃなく「せっかく資格まで取ったのになんで薄給なところにわざわざ行くのか」と怒っていた。
確かに絵で食っていくことを諦めた麦からすれば真っ当な主張なのかもしれない。しかし、絵を描くことが好きだった人が社会と折り合いをつけるための選択肢には、"物流系の営業職に就くこと"以外にも十分あったと思う。出版社であれば、漫画を描く人の気持ちもわかる編集者になれたかもしれないし、なんなら絵じゃなくてガスタンク好きだったことを思い出してエネルギー系の会社だってそこそこ楽しく働けたかもしれない。
そして何より、絹の両親がそれを実証していると思う。小説やその言葉が好きならば、広告代理店でコピーライトにまつわる仕事に関わることだってできたのだ。それなのに、絹は両親のスタンスを馬鹿にしきっている。いやいや、電博(知らないけど)でやっていける人って相当才能も体力もすごいと思うよ?
絹は結局なんてことない仕事ではあるがイベント関連に関わることができて、音楽ライブやアミューズメントに触れながら働いていた。それは自分の人生の豊かさを追求した結果である。それを見て、麦が自分の中での豊かな時間を捨てて二人の将来を思い描きながら日々食いしばっていたのである。この対比がなかなかキツい。
最近の映画を観ていると、やはりジェンダーに関する新しい捉え方などが含まれているものが多いが、ここでもまた男と女の覚悟の違いなようなものを感じる。無論、前で述べたように絹の実家はそこそこ太く、いざとなったら頼ろうくらいの気楽さで生きている可能性もあるから、性別だけでなく家庭環境が影響していることもあり得るのだけど。麦は男として絹を食わせていきたいという覚悟があったのに対して、絹は自分の生活だけを見つめていた。男尊女卑という古臭くなりつつある言葉があるが、そういう男女間で覚悟の違いがあることを、女性もしっかり見つめなければいけないと思う。
まあそんなことよりも、麦も絹ももっと視野を広く持てる人だったらよかったのになと思う。そのお二人がお持ちの崇高なたくさんの趣味たちを色々な切り口から見つめれば、イベント会社に就職する以外にも、楽しく生活を送ることができたんじゃねーのと思うわけ。
大人になること、社会人になることはただ我慢することだけじゃないと麦も絹も気づいていない感じがしんどい。自分の可能性を試さなかった人が、社会がどうとか大人はどうとか語っているのかと思うと寒気がする。
少なくとも、『ショーシャンクの空に』を好きな映画としてあげた男性と、話を合わせられる二人でいればこんなことにはならなかった。新しい恋人に、ただファミレスで居合わせた人から聞いた録音とミキサーの知識を、我が物顔で語るような二人じゃなければこんなことにならなかった。あれだけ趣味あって教養ありそうなのに、なんで?というのが最大のこの作品の嫌味らしいところである…。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

