
【新書が好き】夢の科学
1.前書き
「学び」とは、あくなき探究のプロセスです。
単なる知識の習得でなく、新しい知識を生み出す「発見と創造」こそ、本質なのだと考えられます。
そこで、2024年6月から100日間連続で、生きた知識の学びについて考えるために、古い知識観(知識のドネルケバブ・モデル)を脱却し、自ら学ぶ力を呼び起こすために、新書を学びの玄関ホールと位置づけて、活用してみたいと思います。
2.新書はこんな本です
新書とは、新書判の本のことであり、縦約17cm・横約11cmです。
大きさに、厳密な決まりはなくて、新書のレーベル毎に、サイズが少し違っています。
なお、広い意味でとらえると、
「新書判の本はすべて新書」
なのですが、一般的に、
「新書」
という場合は、教養書や実用書を含めたノンフィクションのものを指しており、 新書判の小説は、
「ノベルズ」
と呼んで区別されていますので、今回は、ノンフィクションの新書を対象にしています。
また、新書は、専門書に比べて、入門的な内容だということです。
そのため、ある分野について学びたいときに、
「ネット記事の次に読む」
くらいのポジションとして、うってつけな本です。
3.新書を活用するメリット
「何を使って学びを始めるか」という部分から自分で考え、学びを組み立てないといけない場面が出てきた場合、自分で学ぶ力を身につける上で、新書は、手がかりの1つになります。
現代であれば、多くの人は、取り合えず、SNSを含めたインターネットで、軽く検索してみることでしょう。
よほどマイナーな内容でない限り、ニュースやブログの記事など、何かしらの情報は手に入るはずです。
その情報が質・量共に、十分なのであれば、そこでストップしても、特に、問題はありません。
しかし、もしそれらの情報では、物足りない場合、次のステージとして、新書を手がかりにするのは、理にかなっています。
内容が難しすぎず、その上で、一定の纏まった知識を得られるからです。
ネット記事が、あるトピックや分野への
「扉」
だとすると、新書は、
「玄関ホール」
に当たります。
建物の中の雰囲気を、ざっとつかむことができるイメージです。
つまり、そのトピックや分野では、
どんな内容を扱っているのか?
どんなことが課題になっているのか?
という基本知識を、大まかに把握することができます。
新書で土台固めをしたら、更なるレベルアップを目指して、専門書や論文を読む等して、建物の奥や上の階に進んでみてください。
4.何かを学ぶときには新書から入らないとダメなのか
結論をいうと、新書じゃなくても問題ありません。
むしろ、新書だけに拘るのは、選択肢や視野を狭め、かえってマイナスになる可能性があります。
新書は、前述の通り、
「学びの玄関ホール」
として、心強い味方になってくれます、万能ではありません。
例えば、様々な出版社が新書のレーベルを持っており、毎月のように、バラエティ豊かなラインナップが出ていますが、それでも、
「自分が学びたい内容をちょうどよく扱った新書がない」
という場合が殆どだと思われます。
そのため、新書は、あくまでも、
「入門的な学習材料」
の1つであり、ほかのアイテムとの組み合わせが必要です。
他のアイテムの例としては、新書ではない本の中にも、初学者向けに、優しい説明で書かれたものがあります。
マンガでも構いません。
5.新書選びで大切なこと
読書というのは、本を選ぶところから始まっています。
新書についても同様です。
これは重要なので、強調しておきます。
もちろん、使える時間が限られている以上、全ての本をチェックするわけにはいきませんが、それでも、最低限、次の2つの点をクリアする本を選んでみて下さい。
①興味を持てること
②内容がわかること
6.温故知新の考え方が学びに深みを与えてくれる
「温故知新」の意味を、広辞苑で改めて調べてみると、次のように書かれています。
「昔の物事を研究し吟味して、そこから新しい知識や見解を得ること」
「温故知新」は、もともとは、孔子の言葉であり、
「過去の歴史をしっかりと勉強して、物事の本質を知ることができるようになれば、師としてやっていける人物になる」
という意味で、孔子は、この言葉を使ったようです。
但し、ここでの「温故知新」は、そんなに大袈裟なものではなくて、
「自分が昔読んだ本や書いた文章をもう一回読み直すと、新しい発見がありますよ。」
というぐらいの意味で、この言葉を使いたいと思います。
人間は、どんどん成長や変化をしていますから、時間が経つと、同じものに対してでも、以前とは、違う見方や、印象を抱くことがあるのです。
また、過去の本やnote(またはノート)を読み返すことを習慣化しておくことで、新しい「アイデア」や「気づき」が生まれることが、すごく多いんですね。
過去に考えていたこと(過去の情報)と、今考えていること(今の情報)が結びついて、化学反応を起こし、新たな発想が湧きあがってくる。
そんな感じになるのです。
昔読んだ本や書いた文章が、本棚や机の中で眠っているのは、とてももったいないことだと思います。
みなさんも、ぜひ「温故知新」を実践されてみてはいかがでしょうか。
7.小説を読むことと新書などの啓蒙書を読むことには違いはあるのか
以下に、示唆的な言葉を、2つ引用してみます。
◆「クールヘッドとウォームハート」
マクロ経済学の理論と実践、および各国政府の経済政策を根本的に変え、最も影響力のある経済学者の1人であったケインズを育てた英国ケンブリッジ大学の経済学者アルフレッド・マーシャルの言葉です。
彼は、こう言っていたそうです。
「ケンブリッジが、世界に送り出す人物は、冷静な頭脳(Cool Head)と温かい心(Warm Heart)をもって、自分の周りの社会的苦悩に立ち向かうために、その全力の少なくとも一部を喜んで捧げよう」
クールヘッドが「知性・知識」に、ウォームハートが「情緒」に相当すると考えられ、また、新書も小説も、どちらも大切なものですが、新書は、主に前者に、小説は、主に後者に作用するように推定できます。
◆「焦ってはならない。情が育まれれば、意は生まれ、知は集まる」
執行草舟氏著作の「生くる」という本にある言葉です。
「生くる」執行草舟(著)

まず、情緒を育てることが大切で、それを基礎として、意志や知性が育つ、ということを言っており、おそらく、その通りではないかと考えます。
以上のことから、例えば、読書が、新書に偏ってしまうと、情緒面の育成が不足するかもしれないと推定でき、クールヘッドは、磨かれるかもしれないけども、ウォームハートが、疎かになってしまうのではないかと考えられます。
もちろん、ウォームハート(情緒)の育成は、当然、読書だけの問題ではなく、各種の人間関係によって大きな影響を受けるのも事実だと思われます。
しかし、年齢に左右されずに、情緒を養うためにも、ぜひとも文芸作品(小説、詩歌や随筆等の名作)を、たっぷり味わって欲しいなって思います。
これらは、様々に心を揺さぶるという感情体験を通じて、豊かな情緒を、何時からでも育む糧になるのではないかと考えられると共に、文学の必要性を強調したロングセラーの新書である桑原武夫氏著作の「文学入門」には、
「文学入門」(岩波新書)桑原武夫(著)
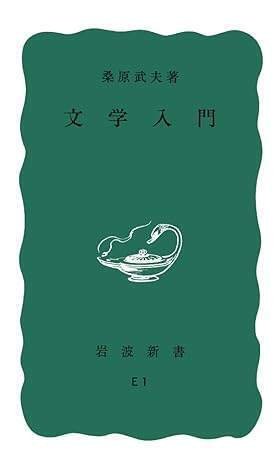
「文学以上に人生に必要なものはない」
と主張し、何故そう言えるのか、第1章で、その根拠がいくつか述べられておりますので、興味が有れば確認してみて下さい。
また、巻末に「名作50選」のリストも有って、参考になるのではないかと考えます。
8.【乱読No.26】「夢の科学―そのとき脳は何をしているのか?」(ブルーバックス)アラン・ホブソン(著)冬樹純子(訳)

[ 内容 ]
フロイトは間違っている!
脳の活動状態をリアルタイムでみられるようになって、夢の研究は大きく進歩した。
最新脳科学で探る夢の正体は、フロイトがいうような、抑圧された欲望が現れているのではなく、睡眠中に自己活性化した脳の正常な精神活動である。
[ 目次 ]
第1章 夢研究のパラダイムシフト
第2章 『夢判断』から科学へ
第3章 睡眠中の脳の活性化
第4章 夢みる脳の分子生物学
第5章 なぜ夢をみるのか?
第6章 睡眠障害・夢障害
第7章 夢と精神疾患
第8章 夢研究のための神経生理学
第9章 夢・学習・記憶
第10章 夢という“意識”
第11章 脳科学時代の夢判断
[ 発見(気づき) ]
意識が脳の状態であるとすれば、眠っているときの意識とも言える「夢」の状態では脳はどのような状態にあるのか?
それを解き明かせば、覚醒状態の意識と、夢との違いを明らかにできるだけではなく、意識の本質的な謎に迫ることができるかもしれない。
夢にはいくつか興味深い特徴がある。
夢はしばしば非現実的で、記憶にとどめることが難しい。
また逆に、夢を見ているときには記憶を引き出すことが難しい。
同じ夢を繰り返して見ることも多い。
また、非常に情動的である。
つまり、高揚感、怒りや不安など感情に結びついていることが多い。
また、夢を見ているとき「あれ、これはなんだったっけ…。思い出せないなあ」と思ったことがあるだろう。
ところが夢の中ではどんなに非現実的なことや矛盾があっても「ま、いっか」と思ってしまうことも多い。
この理不尽な納得、思考の欠落も夢の特徴だ。
夢は外部からの刺激によらず、脳内で自己発生する知覚や情動、そして“現実”である。夢は覚醒時とはまったく違う。
一部の感覚は眠っており、一部の感覚は覚醒時よりも強烈だ。
これはなぜだろう。
眠っているときに脳の一部が選択的に活性化されており、また抑制が外れていると考えれば理解できる。
このことはPET等を使った著者らの研究によって実際に確認されつつあるという。
またここを突っ込んでいけば、脳の働きの解明の一助となることは間違いない。
夢を見ているときは要するに脳の一部が障害されているのとほとんど同じ状態であり、夢もある種の精神疾患の妄想と似ているという。
ただし夢は、健常な人がみな、毎晩体験していることであり、自然な生理的状態なのである。
これ自体が非常に面白いことだと思う。
たとえば夢を見ているときには体は動いていない。
だが、確かに動いているような感覚を覚えることがある。
また、飛んだり走ったりすることもあるだろう。
このことは、脳がどれだけの能力を備えているのか示している。
脳は、実際の身体の運動や、知覚にかかわらず、知覚を“私”に実感させることができるのである。
夢は、生理学的に見れば、眠っている脳の自己活性の結果である。
ではそのとき、脳はどのような状態にあるのだろうか?
たとえばセロトニン系やノルアドレナリン系の活動が落ちてしまうことが知られている。ノンレム睡眠時には半分、レム睡眠時には活動を停止してしまう。
夢を見ているときの脳では「アミン作動系が遮断され、コリン作動系が過剰に活躍」しているのだ。
また、アミン作動系の働きが落ちる結果、体温調節機能もレム睡眠時には働かなくなる。レム睡眠が体温調節に関わっていることは間違いない。
断眠実験の結果から、人は眠るたびに体温調節機能を調節しなおしているらしい。
免疫系も睡眠に関わっている。
このあたりにおそらく睡眠と夢の謎を解くキーが隠されている。
なお、しばしば誤解されているが、夢はレム睡眠のときにしか見ていないわけではない。発達の観点から見た場合、夢はいつごろから見るのだろうか。
胎児はレム睡眠の状態にあることが分かっている。
本当に夢を見ているかどうか聞くわけにはいかないのではっきりしたことは言えない。
だが、そもそも胎児の脳は成人の脳のように発達しているわけではないので、見ていたとしても別物だろう。
夢は単なる結果であって、機能はないのだろうか。
この問いはさらに二つの問に分解することが可能だ。
夢そのものの機能はあるのか」という問いがまず一つ。
二つ目は「夢を見させる睡眠脳の自発的活動の機能は何か」という問いだ。
前者の問いに対しては、スペキュレイションならともかく科学的に答えることは難しい。だが後者に対してはアプローチすることができるだろう。
記憶との関連は昔から疑われてきた。
まだはっきりとはしていないが、いつかはクリアーな答えが出るに違いない。
もう一つ、夢をめぐる非常に面白く本質的な問題は、夢を見ているときの“私”の問題だ。
夢を見ている間の意識は、明らかに目覚めているときの意識とは別物である。
だが、確かに「私」の感覚そのものは存在する。
脳が部分的にしか働いていないにも関わらず、だ。
そのときの“私”の知覚は、いかにして生み出されているのだろうか?
“わたし”という主体性あるいは主観性は、動きの能力の一部として発達するという、そのことを問題にすべきだという。
動くこと・・・。
それと自己意識。
その関係は?
よって、睡眠や眠りの研究が、主観的な意識やクオリアの問題、あるいはいわゆるバインディング問題を解く上で重要な役割を果たすのではないかと考える理由はそこにある。
心の働き方に関するフロイト学説の中心にあるのが、夢には意味があるという考え方である。
ソームズをはじめとする研究者たちは、近年における脳の画像解析や病変部位の研究によって、フロイト学説が実証されつつあると主張している。
しかし、同様の方法を用いた他の科学的研究の結果は、フロイトの学説の主要な部分が、おそらくは誤りであることを示している。
現在、科学的な夢研究で有力になりつつあるのは、進化心理学などからの進化的な夢の見方である。
夢占いに限らず、文学芸術など広く文化的創造全般に影響を与えるなど、「夢文化」というもの備えない伝統社会は存在しない。
だから進化論的に、夢文化とは、人類にとって夢がなんらかの生存価値があったことの現われに違いないと考えるのである。
その一つとして、進化心理学者ハンフリーなどが唱えて有力なのが、シミュレーション説である。
夢の中で、現実では考えられないようなさまざまな危険な経験をする。
そういうシミュレ-ションによって、現実にそれに近い事態にあった場合に対応できるというわけである。
もっともユングに少しでもなじんだ人ならば、シミュレーション説とは、ユングの「想像力による問題の提起と解決」という説の変奏に過ぎないとみぬくだろう。
ホブソンなども夢の機能に関しては、一種のシミュレーション説を唱えた。
ホブソンは行動リハーサル説といって、幼児が夢で、成長してからの現実の行動のリハーサルをする、その名残が大人の夢だとしたのである。
じっさいホールに始まる夢の中の行動パターンの統計的分析によれば、われわれ普通の都会人が経験するよりはるかに高い割合で、単純な攻撃や逃走の行動が、出てくることが示唆されている。
乳幼児にレム睡眠が多いのは、夢の中で石器時代の狩猟生活に備えて、そういう攻撃や逃走のリハーサルをしているということで、辻褄が合ってくる。
さらに、夢研究の第一人者であるフランスのジュベーは、レム睡眠には、遺伝的行動のプログラミング機能があるという。
人間にはさまざまな生得的な行動プログラムがあり、その主たるものは、闘争や逃走、性行動のためのプログラムである。
そのスイッチを発達の初期に入れるのが、レム睡眠の機能というわけである。
だから、直接に経験がなくても、レム睡眠によって私たちは、大昔の祖先の経験のような夢を体験できるということになるのかもしれない。
ユングの元型説は、ダーヴイニズムからの逸脱であるラマルク説を背景としているので、科学指向の心理学者の間ではまず取り上げられることがない。
けれども、元型イメージが遺伝的行動プログラムとなにか関係があるのならば、元型説もあながち科学的に荒唐無稽でもないことになる。
[ 問題提起 ]
我々人間はなぜ夢を見るのか?
そして見る夢が支離滅裂で、覚えておくことが難しいのはなぜなのか?
フロイトが「夢は抑圧された願望の顕れである」と夢理論を唱えてから100年、最新の神経生理学の助けを借りて、現代の睡眠科学では夢の“内容”から夢を見ている脳の状態、すなわち“形”を注目するようになっていると言う、その観点の“パラダイムシフト”によってもたらされた。
良くミステリィでフロイト式精神分析が揶揄されることが多いが、どうやら最近ではフロイトの夢判断とその根幹をなす理論は科学的にも否定されているようである。
50年前にREM(急速眼球運動)睡眠が発見されてから、睡眠の研究は徐々に夢のストーリーではなく、夢を見ている状態すなわち“形”に注目するようになったことで夢の本質に迫りつつあるとのこと。
つまり寝ている時でも脳は部分的に活動をしていて、夢を見ているレム睡眠時は人の情動に関わる大脳辺縁系が活性化し、逆に人の行動を律する役割を果たす前頭前野背外側部が非活性化されるため、必然的に夢は情動的かつ奇妙で覚えていることが出来ないのは「あたりまえ」だから夢の内容に注目する必要は無い、と言うもの。
じゃあ夢を見る事自体の役割は?というと、それはまだ分かっていないものの、今後精神医学と神経医学が発達していけば、夢のメカニズムの解明も決して「夢」では無いとのこと。
以前、『Newsweek日本版』に「夢の謎を解く」という特集が出ていたが、ホブソンの「夢の内容に意味は無い」という主張も紹介されているものの、「夢の研究の足を引っ張った」と、どちらかと言うとネガティブなニュアンスで取り上げられていた。
しかもホブソンは、男女間で夢の内容に有意な差は無いと言い切っているが、「男性の夢は肉体的な攻撃性の強い夢が多く、女性は精神的な攻撃性が強い」とか、「母親になりたての女性は子供にまつわる夢を見がちだ」というデータもあるようだが、「夢が非常事態に備えた予行演習をしている」とか、「夢が能力向上に役立つデータがある」など、夢の内容には意味があるという研究も多いようで、ホブソンほどバッサリと「夢の内容に意味は無い」と言い切るほどには研究が進んでいない、というのが実状のようである。
[ 教訓 ]
「相対的に印象的な出来事は海馬に蓄えられ1週間は取り出し不能」など、ちょっと素直にうなずくにはデータが偏っている面も散見されるが、「ゲーム脳」のようなあからさまなトンデモ理論とは一線は画した科学的な論考ではあるようなので、黎明期の一理論と捉えて傾聴する分には全く損は無い。
また、MITのマシュー・ウィルソンはラットの海馬を調べて、迷路を走っている時のニューロンの発火パターンが睡眠中に再現されることを発見した。
どうやら、昼間に学習した情報を長期記憶に送り込む作業をしているらしい。
それも、エピソード記憶としてそのまんま焼き付けるのではなくて、意味のある情報だけ選び、過去の新皮質の構造を修正する作業が睡眠中に行われている。
人間の実験でも、昼間にやってたのが意味のある作業の場合は、睡眠時に同じ部位が活性化するが、意味のない作業の場合は活性化しない。
この実験を行ったニールセンによれば、夜の脳の任務は、ただ出来事を記録するのではなく出来事の意味を読み解く事なのだとか。
寝ながらえらくまた高度な事をやるものである。
起きてる間もそのぐらい賢かったらいいのにと思う。
おもしろいことに、日中の経験が夢に現れるにはタイムラグがあって、すぐに見る夢には経験がそのまま出てくるが、1週間後に感情を伴う夢を見るそうだ。
経験に伴う感情を自覚する方が情報の統合よりも時間がかかるらしい。
また、夢にはネガティブな感情を抑制する効果があるようだが、鬱病ではむしろ夢によってネガティブな感情が増幅されてしまう。
鬱になると、睡眠中には活動しないはずの前頭葉前部が眠らないそうである。
もう一つ、興味を惹いた事例に、視覚障害者でも経験を視覚化した夢で記憶が定着されるという話がある。
脳は莫大な情報を圧縮するために、視覚的なイメージを用いるのかもしれない。
あと、「ヒトはなぜ人生の3分の1も眠るのか?―脳と体がよみがえる!「睡眠学」のABC」著者ウィリアム・デメントによれば、寝だめはできないけど、睡眠不足は積み上がって行くのだそうだ。
眠くなるのは寝が足りてない証拠。
おつむを良く働かせたかったら、まずは寝ること。
日々、ぐーすかと実践中である。
[ 結論 ]
なぜ夢を見るのか?
この問いには二つの要素がある。
どうやって夢を見るのかというメカニズムの問題と、何のために見るのかという問題だ。夢に関する疑問は、人類始まって以来のものだろう。
近代的な研究は「夢判断」(1900年)で有名な心理学者フロイトがいる。
彼は「夢は深層心理や満たされない欲望の表れ」と考えた。
53年に「レム睡眠」が発見されると、生理学的な研究が活発化する。
レム睡眠は、脳波は起きている時と同形だが筋肉は緩み、眼球が盛んに動く。
人はこのレム睡眠時に夢を見ることが多い。
ネコなどほ乳類も夢を見ているらしい。
夢の研究が次の段階に進んだのは90年代後半以降、つい最近のことだ。
fMRI(機能的磁気共鳴画像化装置)やポジトロンCT(PET、陽電子放射断層撮影法)の登場で、睡眠中の脳の活動を画像として解析できるようになった。
脳の活動について、滋賀医科大学の大川匡子教授(精神医学)は「眠りをつかさどる中脳や橋などは脳の深い部分にあり、起きている時は脳の表面にある大脳皮質が活性化して外部の信号をキャッチしたり考えたりする。眠りに入ると中脳や橋などが活性化し、逆に大脳皮質は活動が落ちる。これが睡眠の初めに生じるノンレム睡眠の状態です。次いでレム睡眠になると、睡眠中枢が活性化しているのに、辺縁系と呼ばれる記憶や情動(感情の動き)に関係する部分、1次視覚野と呼ばれる見る機能に関係する皮質が活性化する。この時、私たちは夢の中で見たり聞いたりしているのです」と説明する。
一方、米ハーバード大学のアラン・ホブソン教授は、夢を見ている時は作動記憶、自覚、論理性などを担当する前頭前野背外側部の活動が低下していることを確認し、その著書「夢の科学」(講談社)の中で「夢の中で適切な状況判断ができず、『これはおかしいぞ』というチェックが働かないのは、こうした機能を支える脳の領域の活動が低下している
から」としている。
では、夢は脳の活動で生まれる単なるノイズなのか。
夢のはっきりした役割はまだ分かっていないが、こんな実験結果がある。
単語を20個覚え、翌朝いくつ覚えているかを測る。
その結果、4時間寝たグループの正答率は8時間寝たグループの半分から3分の2だっ
た。
「スキーやピアノなど運動に関する記憶も同じ傾向で、レム睡眠を取らないと記憶力が弱まる。つまり、脳は夢を見ながら記憶したり、記憶を選別する作業を行っている。嫌なことを一晩寝て忘れてしまう人は元気に目覚めるが、こだわって眠れない人はうつうつとした気持ちが続く。逃げる夢も多いが、逃げることは本能としての防衛機能で大切なこと。脳が万が一に備え、祖先の記憶を忘れないように夢を見せているとも考えられる」と大川教授は話す。
「夢分析」(岩波新書)などの著書がある京都大学大学院人間・環境学研究科の新宮一成教授によると、夢には「四つの働き」があると言っている。
一つは眠りの継続。
早起きして会社に行かなければならないが、脳は眠り続けたい。
こんな時に人は「既に仕事をしている夢」を見る。
二つ目は起きてから人を安心させる働きだ。
「試験で苦しむ夢」から覚めると、私たちはああ良かったと胸をなでおろし、現状を肯定できる。
三つ目は、自分自身の存在が肯定されていた子供時代に戻ること。
これは「自分の生存は意味がないことではない」と自分に納得させる働きがある、という。
ただ、自分が成人として登場したり、記憶が子供の言語に置き換えられて出現するため、とっぴな夢にもなる。
そして四つ目は、災害などの困難に直面した時、「これは現実ではない。夢だ」と思
うことで、脳にかかる生理学的な負担やストレスを軽減する働きだという。
この世は夢に過ぎない、という考えは世界に広く見られる。
この世が夢なら、“現実”のあの世もあるはず。
死ぬのは怖いが、あの世があるなら恐怖は薄れるでのだろうか。
また、夢の中では突拍子もないことが起きたり空を飛べたりもする。
そんな夢のストーリーや夢に出てくる物には意味はあるのだろうか。
空を飛ぶ夢や火事の夢など、多くの人が見る夢をフロイトは「類型夢」と呼んだ。
類型夢は、誰もが経験する幼いころの経験がベースになっている。
現在の生活でその経験を参照する必要が生じると、夢に出てくるのだそうだ。
例えば「空を飛ぶこと」は、精神分析では「初めて言語を獲得した時の全能感」を象徴していると考えられている。
進学や転職など、新しい環境や課題に直面する時に飛ぶ夢は現れ、「かつて言葉を覚えたように、今度もできるよ」とメッセージを送ってくれるのだ。
それでも最後に落ちる夢を見る人が多いのは、飛び続けていると、死者の仲間入りをするような不安が芽生えてくるからではないか。
私たちは夢に予知能力を期待しがちだが、むしろその時々の気掛かりとその解決が、夢でえん曲に表現されると考えた方がよい。
[ コメント ]
夢は、夢を見る人の過去の記憶、現在の状態、そして『空を飛ぶこと』のようないくつかの象徴で構成されており、夢を見た人と、それを聞く人の会話によって意味を見いだすことができる。
夢を見た人が自ら語ることで、その夢の意味を生み出すと言ってもいいのだろう。
夢の不思議は、奥が深いようだ。
9.参考記事
<書評を書く5つのポイント>
1)その本を手にしたことのない人でもわかるように書く。
2)作者の他の作品との比較や、刊行された時代背景(災害や社会的な出来事など)について考えてみる。
3)その本の魅力的な点だけでなく、批判的な点も書いてよい。ただし、かならず客観的で論理的な理由を書く。好き嫌いという感情だけで書かない。
4)ポイントを絞って深く書く。
5)「本の概要→今回の書評で取り上げるポイント→そのポイントを取り上げ、評価する理由→まとめ」という流れがおすすめ。
