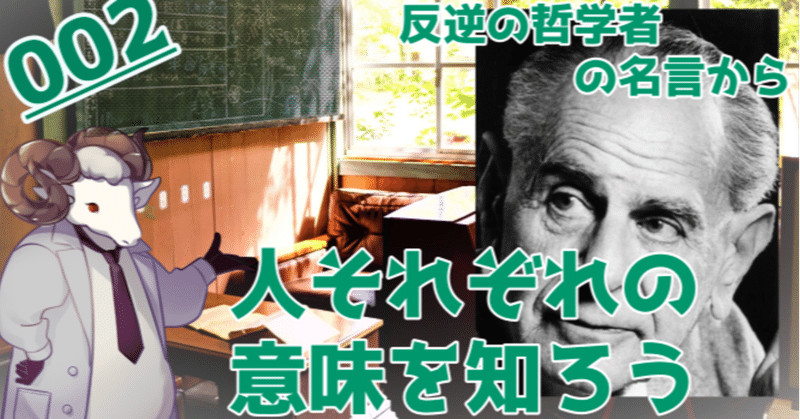
【哲学】002 ポパーの名言から『人それぞれ』の悪夢を学ぶ
本日もお越しいただきありがとうございます。
この記事は、私、巴アズラがYouTubeに投稿している「偉人の名言から〇〇について考える」のダイジェスト記事になります。
日々の生活で起こる些細な出来事や理不尽に感じた衝撃的な出来事について、偉人の名言に結び付けて哲学してみた。
というのが、このシリーズの試みです。
◎字幕・音声入りの動画はこちらからご視聴ください◎
◆以下本文◆
この記事の本題_人それぞれとは
今日はとある最強ワードについて考えたいと思います。
人それぞれという言葉は、皆さんはどのくらい使いますか?
あらゆる議論の最後に一言添えるだけで
強制的に議論を終わらせることのできてしまう
哲学の世界においてはまさに最強のカードです。
千差万別、十人十色、、、人の持つ個性の尊厳を尊重する
「人それぞれ」という考え方は
本来とても優れた概念なのですが、こと議論においては本当に厄介です。
まさに切り札、ジョーカー。言ったもん勝ち。
昨今は特に、多様性を容認しないものは問答無用で
悪だと言わんばかりの風潮もあるので、
どんなに荒唐無稽な主張でも「人それぞれだから」
という理由で押し通されたりします。
ということで今回は、
人類が生み出した究極の決め台詞であり、
哲学における最強の天敵である「人それぞれ」
という考え方について哲学したいと思います。
◆この動画をご覧の皆さんのほとんどは、
日本で幼少期を過ごした方々だと思います。
皆で同じ教育を受けて、同じ思想、同じ水準の人間に
仕上がるように育てられたはずです。
日本ってそういう国ですよね、みんなで同じようになる国。良くも悪くも
日本社会の暗部として揶揄される、村八分とか
出る杭は打たれるのとかの文化なんかは、
肯定的に捉えればより長く安寧の時を紡ぐために
必要な習性だったのでしょう。
しかし時が経ち、
私たち人間の営みは圧倒的に洗練され多様化し、
我々はコミュニティに属しながらも
個人の生き方を吟味できるようになりました。
これは、表面的には文明の進化っぽくて聞こえはいいんですが、
問題も生じます。
昔ながらのコミュニティの中で協力して生きてきた人の一部が、
コミュニティの中に属しながら、個人の理想的な生き方を追い求めて
変化していくと、そうじゃない人にとっては、
これまで積み上げてきた秩序や文明が脅かされると感じる場合があります。
自分が自分だけで変化するならば問題ありません。
しかし、自分の変化が他者の安寧を少なからず脅かしてしまう。
相手方の目線から見れば、自分たちの安寧の為に、
他人が変化することは好ましくない。
お互いに、なぜ「個人的な意思」を尊重するために
自分の理想を諦めねばならないのか?と考えます。
そうなってくると、いよいよあの言葉が首を擡げるわけですね。
「人それぞれ」という、相対主義論に属する考え方です。
相対主義とは読んで字のごとく、何か物事を定義づけるために、
他の何かと比べる考え方を指します。
そして本日のタイトルにもなっているカール・ポパーは、
この相対主義を否定する立場です。
相対主義とは、何でも主張できる、ほとんど何でも、
したがって何も主張しない
これがポパーが相対主義論を否定する理由です。
主観性と相対主義における哲学は、
最古の哲学者の一人プラトンにまで遡ります。
我々が日常で何かを論ずる際に主観性が根拠となる場合、
そこに「絶対的な真理」など無い。
というのが、遥か昔より議論されてきた問いに対する哲学者の結論です。
では人々はどうやって議論をまとめて結論を導いてきたのでしょう。
今度は「寛容さ」というキーワードが出てきます。
ここからは倫理学の領分です。
「相対主義が寛容と両立するか否か」について考えてみます。
こんなシチュエーションを想像してみてください。
皆さんが誰かと会話しているとします。
その会話の主導権は相手が持っていて、あなたは聞かされている立場です。
その会話について、、皆さんは3つの態度を示すことになります。
一つ目は無関心な態度。つまり「どうでも良い」
「どうでも良い」を正確に表現すると
「どんな内容であってもベターだ」ということであり、
実はこれは、相手の意見を全肯定したことになります。
選挙などで白票を投票する時はこういう扱いです。
二つ目は不寛容な態度。すなわち「どんな内容であっても絶対に認めない」
となり、ここには「絶対」という言葉が出てきます。
相対主義にあっても、自己の中だけなら「絶対」という概念が存在することになり、
これは相対主義的な議論がそもそも成立しません。
野党議員の審議拒否とか議会不参加とかはこのスタンスです。
三つめは寛容な態度。
これは三つのなかで一番相手の意見を積極的に取り入れる姿勢であり、
議論された内容に関して真理を求める態度となります。
しかしその為には自分の意見が相手の意見によって曲げられる
リスクを常に含んでいるということが分かります。
真理を追究するためには他者の客観的な視点が必要であるものの、
時には寛容な心で「お互いの意見を曲げていく」
まさしく「折り合いを付ける」という言葉の意味通りですね。
さて、この3つの態度を基準にして、
改めて「人それぞれ」を考えてみましょう。
「みんなそれぞれ違うのだから、一つの意見を押し付けるな」という意見も、全体から見たら一つの意見なので、それを押し付けることはできない
結局のところどちらか一方が寛容な心で折れなければ、
「人それぞれ」は成立しないということが分かると思います。
つまり「人それぞれ」を相手に突きつける時は、
その時点で相手に妥協を強要することと同じ意味になるのです。
それじゃあ結局、「人それぞれ」という考え方は悪なのかという話なのですが、一概には悪だと言い切ることはできません。
その根拠が自分の中の主観が基準であるから問題なのであって、
誰もが認める普遍的な価値観を根拠とした「人それぞれ」であれば、
その選択肢に行使権を得られるのです。
つまり我々が帰属する社会、コミュニティの価値観として共有されている範疇であれば人それぞれを行使することも可能だという事です。
我々現代人は、それぞれが個別の思想によって生きていると同時に、
公共性のある社会に存在している文明人であることで
ある程度の「共通のルール」に縛られながら生活しています。
人に危害を加えるのは自由だが、その制裁は「社会的な死」という罰を
与えられることになります。
逆にとらえれば、多少窮屈でも社会的に認められた我儘であれば、
その範囲内なら「人それぞれ」を行使してよいとも考えられます。
◆ところで話は変わりますが、「無関心である」も結構強くない?
と感じた方はいらっしゃるでしょうか。
結局関わりあう全員が「わがまま」で「非寛容」でも、
それぞれがみーんな相手に「無関心である」ならば、
全ての人間が自分勝手でも良いということにならないか?
その疑問は全くその通りです。そしてその結果生まれる惨事が
ファシズムや独裁者だと言われています。
ハンナ・アーレントというドイツの哲学者は
とある独裁者の誕生を目の当たりにし、次のような言葉を残しています。

無思想でいることが悪を生み出す
ドイツ…、独裁者…と聞くと、連想する人物は一人ですよね。
言わずもがな、あのチョビ髭のことです。
我々人間の私利私欲の根源は、限りなく本能に近い大変低俗なものです。
誰もが自由なままに振る舞う世界では、悪行が誰に裁かれることもない、
つまり善悪の概念が存在しない世界になります。
人間は外部から影響を受けないと自分の行動理念が快楽便りになります。
理由はこれまでお話しした通り、対人には「非寛容」で、
社会には「無関心」な態度でコミュニティを形成していることになるので、
自分のルールを糾弾されることが無いからです。
そんな時に、社会的な秩序の維持やインフラの維持管理など、
個人としてさほど興味のないめんどくさそうな仕事を進んで買って出たり、
意欲的に推し進める人間の耳障りの良い演説に触れるとどうなるでしょう。
気分良く任せてしまうのではないでしょうか
そうして人心を掌握し、理想郷の名の下に全ての裁量を託された者が現れたとき、独裁者が誕生するのです。その段階になってようやく人々は、
「個人の自由」以外の権利や尊厳がすべて奪われていることに気が付きます。
これが、ハンナのいう「無思想でいることが悪を生み出す」の正体です。
この繋がりご理解いただけたでしょうか。まとめるとこんな感じです。
●「人それぞれ」は大いに結構だしその通り
→ただしそれは、考え方の自由であり、
考えることの放棄を許されたわけではない。
●「自分の好きなように生きる」は大いに結構だしその通り
→ただしそれは、生き方の自由であり、社会の公共性を維持する意識
(責任、義務、仕事、努力、寛容さ、etc…)の放棄を
許されたわけではない。
●以上を放棄したければ、誰とも接触せずに無人島や深海、宇宙などで暮らすこと。もしくは、権力者になること。
人それぞれという考え方自体は悪ではありません。
むしろ我々人類が長い時間をかけて到達した最新の生の在り方であり、
もはや権利ですらあります。
同様に、自分なりの生き方を追求することも悪ではありません。
しかし、これらはあくまで追求することの自由であって、
放棄することを許されているわけでは無い
ということを常に意識していなければなりません。
理由は先ほど述べた通り、
自分の人生に関わるある一部を放棄するということは、
その部分は絶対に自分優位の結果を招くことはないからです。
放棄する場合、その後訪れる不利益は全て容認するという覚悟を持つこと。
これが責任であり、義務になります。
私たち日本人は、集団の中で協調性を重んじる民族であると見られる理由と、革新的なイノベーションや強力なリーダーが生まれない理由は
表裏一体の問題と考えられています。
スクラップアンドビルドが著しく少ない国、日本。
非常に安定している国でもあり、同時につまらない国であるとも言えますね。
ヴォルテールというフランスの哲学者は次のような言葉を残しています。

私はあなたの意見には反対だ。
だが、あなたがそれを主張する権利は命をかけて守る。
なんて言うか、「寛容」ですよね。美しいとすら思います。
啓蒙思想哲学というカテゴリーからも現れているように、
彼の言葉にはどことなく、人の理性を信頼し、
自由であることを尊重するような温かさが見えるような気がします。
社会の中に居ても人と深く接することをせず、一人で生き抜くと決意すること自体は悪くないと思いますし、時代の流れからしてもそういう人は多いと思います。
でも、別に一人で生きているからと言って他人と接触してはいけないわけでは無いので、その場合も前述のようにコミュニティでの在り方は意識しなければなりません。我々が日頃、対人関係で相手に優しくしたり、譲ったり尊重したりできるのも、その相手に対して少ないなりにも信頼感とか敬意みたいなものを抱いている表れだと思います。
ヴォルテールのように他者に対してポジティブな姿勢でいることは、
多少無理してでも維持していたいものです。
まぁ、人それぞれですけどね(笑)
という所で今回も終わりたいと思います。お相手は巴アズラでした。
ご視聴ありがとうございました。
【前回】【哲学】001 フランクルの名言から『生きる理由』に目を向ける
【次回】【哲学】003 ベンサムの名言から『他人の目』について考える
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

