
『揺蕩う素養』
◆Ⅰ.幸の調べより
豊かさや幸せを考えるとき、‘‘素養’’という言葉が脳裏を過ることがありました。
私たちは、日々の暮らしの中で見たものや感じたことを胸の中に記憶して、あるときそれについてふと考えることがあったりします。
あのとき、怒ったこと、笑ったこと、泣いたこと、感情には必ず理由があって、感情の向こう側に家族がいたり、友人がいたり、恋人がいたりします。
相手が笑うと、自分もつられて笑って、怒ってると嫌な気持ちになるし、泣いていると悲しい気持ちになるので感情の作用によって、誰しもいくつもの顔を持つものだと感じられることが度々あります。
ふとしたことで、面影に触れようとしても、それは触れられないものがあります。
触れようとしても、触れている感覚がそもそもないような感じがする。
私の記したエッセイに『泡沫の謠』と呼ばれるものがありますが、これらの断章には規則性はなく、その時々に思ったこと、感じたことを備忘録的に記したものであって、私は17の項目から‘‘幸福’’というものについて考え、まとめ記しており、以下の引用文から改めて考えることがありました。
■17 幸福とは何か
幸福というものについて、幸福の定義、幸福とはこうあるべきだとかという考え方、議論についてはあまり深く考えたことがなかった。
私にとって、幸せとは時間のある時に本を読んだり、映画を見たり、カフェに行ったりしてまったりして過ごすことが幸福だなと思えるひとときだったりする。
あとは、美味しいものを食べて、お腹いっぱいになってから好きなだけ眠るというような時間が幸せかなと思えたりするから、他者にとっては普通だなって思われるかもしれないが、普遍的な日常というものこそが大きな幸せだという認識があります。
幸せというのは、大きなまとまりを持った考え方で細分化すれば小さな日常の一つ一つの集合体であるのではないかと思ったりします。
自分だけが不幸だ、生きていても、何一ついいことがないと悲観する人もこの世には存在します。
私自身も、嫌なことがあった日には、幸せだという気持ちは完全に皆無であるし、むしろ地獄だとさえ思うこともある。
だが、幸福について考える時、私たちが思い描く幸せの在り方というものは、そもそも存在しないものなのではないかと考えることがある。
しかし、幸福によってもたらされるものは私たちの生きる糧になることは確かなことだと感じる。
普通の日常から幸せな気分を味わうことは難しい反面、私たちの日常は幸せが溢れだしているという感覚へと変えてみることは、とても大切なことのように思えます。
読書にしても、本を読むことだけではなく、本屋へ行って色んな本に触れて読みたい本を選んで買うことや読んだ本の感想を書くことなどもまた、違った楽しみの醍醐味だとも言えるのではないかと思います。
どんなものでも、むしろなんでもいいから自分が幸せだと思えるものさえ、一つでも見つけられたら人はどこまでも成長出来るし、幸せになれるものだと感じました。
◆Ⅱ.書く抽出力
認知特性というものを考えると、目で見たことや耳で聞いたことなど、あらゆる感覚器から入ってきた情報を脳内で整理し、記憶し、理解する能力のことを指す言葉でありますが、書くことと接点があるとふと感じました。
認知の方法には、対象者にとっての得意不得意があるもので、何が正解で不正解という明確な定義すらも定まってはいません。
私にとっての認知特性は、視覚的な読むことと書くことであるというのは自覚しています。
読むことは、本には限らず映画や音楽にも当てはめることができ、視覚以外に聴覚的にも働きがあり、脳内で作品を読み聴くということが無意識的に行われており、取り入れたものを抽出させることにより、理解へと繋げています。
抽出する度合いというものは、その作品によっては様々だと思いますが、例えば心揺さぶられるものに出会うと、すぐにそれにハマることがあって、抽出して純度を高く保った状態で書くことから感度へと変えることもまた、創作の面白さだと感じることもあったりします。
私にとって、これまで読書というものの在り方、考え方というのは日常生活の一部として組み込まれたものだという認識でいたのですが、そうした認識は書くことへと転換されて、ようやく今は読書と書くことは一つのものへと調和され、読むことも書くことも、物事を抽出するということが求められるのではないかと感じています。
映画でも音楽にしても、ものをつくるという情熱は創作へと価値を変えても変わるものはないと思えますし、抽出させることで新しいものへと変えることこそが創作の魅力だとも言えるのではないかと思います。
必要な要素を組み合わせて、そこから何を抽出するのか、これからの書くことにおいては抽出力というものが求められるだろうし、この数年間を通して気付いたことでもありました。
書いたものが、誰かのもとへと読まれるという一連の流れはnoteを続けていると、ごく当たり前の感覚として覚えるのだが、偶然の出会いや発見というのは運命的でもあり、そうした奇跡的な体験や経験は日々大切にしていかなければいけないことだと思いました。
そして、これまでに書き記したもの全般的に言えることなのですが、創作された作品は抽出され生み出されたものであって、それは言語化されるのだが、私の中には完全に忘却されたものとしての位置付けがあります。
ですが、忘却と言っても完全なる忘却ではなく、内在的にも感性は熟成されるものだと思っています。
創作と忘却、そして、熟成へ。
抽出された作品を読み、そこから創作へと繋げていくことで自ずと抽出力というものが育まれていくものだと思います。
感覚的で抽象的なものを書くことによって反映させる為には長い年月がかかるものだと感じます。
書くことの本質から、書く抽出力という概念に至るまで、これまでの私が書いてきたもの全てはあらゆるものから抽出してきたものであることは確かであります。
身体と精神によって編み出された言葉のかたちによるもの、自らを語る上では重要であるし、今もこの先もこの思いは消え失せることはないと思います。
何かを語ろうとすれば、きっと別の何かを語る為、私は同じように文章を綴るだろうと思いました。
◆Ⅲ.二分心
意識と捉えるべきか、あるいは意識的と捉えるべきかは相互の関係性が重要だと感じられた。
泣くと、身体の中のものが全て洗い出されるような感覚を覚えるのがいつもだった。
意識下の中に、確かにぼくの存在はあり、これが別次元の世界観という問題を投げ掛けているつもりはなく、目の前に存在するから存在するのであり、二分心の話をしているわけではない。
身体を擬態している、そうした擬態は精神の投影を意味するものであって擬態以前にあるのは身体の証明でもある。
ぼくの身体と精神は、まさに二分心とも呼べるものだと感じた。
感覚がそう感じるのであって、認知の問題でもそれはない。
思考の終わりはなく、思考し続けている間は、統合的であって、ぼくの存在は確かなぼくであって、不確かでは決してないと言える。
全てが揺れているようなそんな感覚、世界が揺れ動いているのか、ぼくの知覚の問題なのか、あらゆるものは溶けていき、やがてそれは凝固する。
泡沫、水鏡、そして二分心。
絶え間なく脳内には聞き覚えのある音楽だけが流れ出していく。
◆Ⅳ.心の遍在
2023年の12月16日に、プロフェッショナル仕事の流儀を見た。
その時の回は、宮崎駿氏であり、今年上映された「君たちはどう生きるか」の創作の舞台裏を描いたドキュメンタリーであり、「君たちはどう生きるか」については私自身も、映画館に直接足を運んで見に行きましたし、本作についての感想もネタバレはなしで書いた記事もあるのでぜひとも参照して頂きたいと思っています。
私の記した記事の【‘‘現在と未来の感度’’】においては、映画主題歌の米津玄師さんの「地球儀」を軸にして「君たちはどう生きるか」やその他のジブリ作品について簡単に言及しましたが、今回のドキュメンタリー番組を通して感じたことはこれまで気付けなかった、宮崎氏の新たな素顔について知ることが出来たことは大きな発見と学びだったと感じています。
そして、ドキュメンタリー番組で理解したことで言えば、本作に登場するキャラクターのモデルとして、眞人は宮崎駿氏であり、大伯父は高畑勲氏であり、サギ男は鈴木敏夫氏、キリコは保田道世氏ということが分かり、特に印象的だったのは宮崎氏による高畑氏への特別な思いを持っていたところは全く知らなかった一面を知れたのは自分の中では大きかったですし、『君たちはどう生きるか』で宮崎氏は、高畑氏と完全な決別を暗示しているところは胸を打たれる思いがありました。
そして、作品に対する解釈について考えると、これまでなかった宮崎氏のジブリで描かれるテーマ性というものがガラリと変わった印象を受けました。
キャラクター造形を実際の身近な人たちに当てはめながら、宮崎氏は映画の中で確かに高畑氏と対話した。
眞人=宮崎駿と大伯父=高畑勲は、確かに映画の中で共演し運命的な再会を果たしたと言えるものがありました。
現実から離れた宮崎氏は、遠い世界を見つめて、長い年月をかけて何かを常に探していて、今もそのようだと感じるものがあったりします。
虚構としての映画は、彼にとっては現実味のある世界であって、現実こそが虚構であるのではないかと実感させられました。
ジブリ作品を通して、彼の創作に対して向かう熱量は私たちの想像をはるかに越えたものがあり、また創造力というものも同様であると思う。
創作するという過程は、彼にとっては生きる上での原動力でもあって、何故いつまでも作品を作り続けるのかが、ドキュメンタリーを見終わって気付けたことが色々とありました。
「君たちはどう生きるか」を含め、過去のジブリ作品は、私たちの心の中で、永遠に生き続けることだろうと思いました。
◆Ⅴ.私語り
noteを続ける中で、私は自分語りということは出来るだけ避けようと思いつつ、趣味の読書の話や創作をテーマに絞って書いていければそれでいいと思っていました。
気付けば、この記事を書いている自分は20代最後の自分であり、自分が来年には30代を迎えようとしている実感も湧かないし、将来的に結婚をして子供を作って家庭を築き、生活していくということも中々想像出来ないところがあったりします。
もちろん、将来は結婚して子供を作って幸せな日常を過ごしたいと思っているものの現実はそうなってないかもしれないことは十分考えられるだろうと思います。
もし、結婚して子供が出来たら、恐らく今みたいに読書は出来なくだろうし、映画も色々と見たり、note活動も上手く両立は出来なくなるだろうということは理解出来ます。
仕事をしながら、家事や育児をする自分の姿はなんとなく想像出来るが、両立出来たとしても今以上に好きなことが確実に出来なくなるのは当然のことだと思います。
今でこそ、恋愛観や結婚観の価値観は大きく変わってきただろうし、私たち世代の人たちは結婚ということから離れてしまった人たちの方が多くなったと聞きます。
それは、金銭的な問題や自由からの束縛なども考えられ、生涯一人で生きるという選択肢も人生観としては幸せなかたちでもあると思いますし、結婚=幸せという価値観は既に薄れてしまったのではないかと思われます。
私自身も一人で過ごすことは、苦ではなく孤独感を抱えることは今はありません。
一人でいることでしか、気付けないことはたくさんあるだろうし、結婚してから家族を持つことでしか気付けないこともあるということもまた同様だと思います。
読書している時やカフェで過ごしている時よりも、ベッドに横たわって、目を閉じていると、より不安感や緊張感を感じることがあったりします。
そうした時間は、自分の存在と真摯に向き合っている証であり、向き合い続けることで思考は自分をより苦しめるものだと感じることがありました。
だからこそ、別のことに集中して現実から目を背けたくなるのかもしれないと思いますし、これがいつまで続くのかが分からないところがあります。
寝ている間だけ、自分の存在を忘れられるし、余計なことを考える必要がない。
私はもう少し、自分のことをしっかりと知っていこうとそう思いました。
◆Ⅵ.映画『ナポレオン』の考察
リドリー・スコット監督の最新作『ナポレオン』をついこの間、鑑賞しました。

ナポレオンを演じるのは、ホアキン・フェニックスであり、一人の軍人の生きざまであるナポレオンを通してフランス皇帝へと成り上がったナポレオンの人間ドラマとして焦点を当てたスペクタクル映画だと感じられました。
特に印象的だったシーンとしては、本作で描かれたアウステルリッツの戦いやワーテルローの戦いによる戦闘シーンは圧巻であり、大スクリーンであるからこその見応えがあり、ナポレオンの冷徹さや大胆さを窺えるものもあって、ナポレオンの人間性を垣間見ることができ、戦争の恐ろしさを映像によって実感させられるものがありました。
ナポレオンの人間像に迫る上で、彼が英雄的存在であったか、あるいは悪魔的な存在であったかということは解釈によって異なるものがあるのではないかと感じられました。
映画『ナポレオン』の構想は、スタンリー・キューブリックが映像化しようと思っていたのだか、その意志をリドリー・スコットが受け継ぐというかたちにより、映像化が実現されたものであり、彼の『ナポレオン』を鑑賞した後で感じたことは『ナポレオン』は歴史映画としての側面とナポレオンの人間像に焦点を当てたドキュメンタリー映画としての側面である両面を兼ね備えたものであり、特に後者であるドキュメンタリー要素が色濃く描かれていると感じられました。
それは、何よりもナポレオンの最初の妻であった、ヴァネッサ・カービーが演じるジョゼフィーヌに対する熱烈な愛情の描かれ方が戦争シーンよりも印象的だったからでありました。
愛に関して言えば、ナポレオンは彼女に対してはとても情熱的であり愛を育み、時にはマウントを取るジョゼフィーヌの人間像も彼との日常生活の中で理解出来たことが色々とありました。
作品論として解釈するならば、『ナポレオン』はナポレオンの内面性を深く描いているところが、リドリー・スコットの作品に対する特徴とも考えられるものがあって、事前知識なしでもナポレオンという存在はどのような人であったかということに触れる上でも楽しめる映画だと感じさせられました。
視点を変えれば、『ナポレオン』はまた違った作品としても描くことが可能であると思われるし、多角的な映画批評としても新たな解釈を加えることも出来る映画でもあると思いました。
◆Ⅶ.音楽の認識
ジャンルを問わず、私はちょっとした空き時間に音楽を聴くことが好きであります。
それも、気に入った曲を見つけると、一時期ずっとそればかり聴くのですが、それは感覚的に耳が自分にとっての癒しの音楽を求めているからだと思いました。
音楽を聴く前に、その音楽との出会いから始まるのだか、大抵はドラマや映画、アニメの主題歌などが多かったりしますが、そこからアーティストの存在を知り、交友のある他のアーティストもまた知ったりすることで、一曲との出会いによりたくさんのアーティストと曲の世界が自分の中で広がっていきます。
そこから私は、歌詞に込められたメッセージ性を気にするようになり、一人のアーティストの存在自体は私の中で忘れ去られてしまい、耳だけに集中して聴くことに努める。
それは、同じ曲を何度でも聴いてみることで、その歌詞による旋律や響き、リズム感などが意識下から音楽の世界へと肉体と精神が入っていき、耽溺する感覚はまさに音楽ならではの魅力だとも言えるのではないかと思います。
文学や映画にみる言語的な分野に対して、美術や音楽と比較されるであろう非言語的な分野、すなわち芸術性から何を感じて、そこから何を学ぶべきなのかということを具体的に説明することはかなり難しいことだと感じられる。
芸術分野においても、鑑賞する上では論理的な思考力や専門性の理論が求められるだろうと思われますが、状況に応じて展開される手段にすぎないものだと考えられます。
非言語的な表現を言語的な表現へと置き換えることには無理があると思われます。
非言語的な芸術性であるならば、言語的理解を必要としないことを自らが理解する必要があるのではないかと感じます。
こうした芸術に重きを置いた教育というのは、高等教育や大学での教育においても重要視すべきことだとは誰も主張しないことは当然であります。
非言語理解には身体性よりも精神性が深く関わるものがあるし、物事をしっかりと考えることは求めずに感じることが大切だと思います。
文法的な様式とそれに付随する理論的理解は、非言語においても、重要であることは確かではあります。
前提として、何故、人は音楽を聴くのか。
思考する以前に、精神が躍動するような表現を肉体は聴くことで求めており、表層的な感覚は多層的へとなっていくのが音楽を聴くことでの本質だと思うものがあります。
やがて、多層的な感覚は音楽を聴く喜びへと変わっていく。
◆Ⅷ.Carpe Diem
ヤマザキマリさんの著書『カルペディエム』という本を読んだ。
ヤマザキマリさんが記された著書の中では、初めて読む本でしたが、とても胸を打たれるものがありました。
本書の内容としましては、ヤマザキさんのお母様を通して、老齢の在り方から死との向き合い方を考えさせられるものがあり、人間として善く生きることとは何かを示すものがあって、私自身にとっても人生観を見つめ直すきっかけを与えてくれるものがありました。
特に印象的だったのは、機能と感性を使いきり、残された人に生きる糧を残すことを‘‘利他’’と言い換えたところは感慨深いものがありました。
終活という言葉がありますが、私にとってそのような言葉に実感が持てないのは、私の年齢としてはまだまだ若いからだと思います。
老年期を迎えてから、初めて気付くことは色々とあるのではないかと感じられますが、仮に残された時間の中で何をして、何を学び、何を楽しみたいのかと考えさせられるものがありました。
趣味としての読書を楽しむのもよしだし、映画や音楽を嗜むのも選択肢としては入っていますし、今のようにnoteに自分の思いや考え方を言語化させて言葉を記せているだろうかと思うこともあります。
たとえ、書いていなくても現時点で書いた私の記録は何年、何十年経ったとしても読み返すことは出来るので、あの時に書いた感性に戻って読み返すことの楽しみと喜びも私の中にはあります。
年々、読書量が減ってきており、それは物理的に時間が取れずに読めなくなってきたということではありません。
私自身にとっての必要な言葉を受容するという機会が減ってしまったと言い換えてもいいかもしれません。
今は、読むことよりも、書くことの方が優先順位として高くて、これまで蓄えてきたものも自分の言葉へと変えて表現する楽しさの気持ちが勝っているのではないかと感じられます。
そして、年を重ねれば重ねるほど、価値観というものは成熟化するように思えます。
カルペディエムという言葉は、ヤマザキさんの著書のタイトルにもある通り、今この瞬間を生きるという意味であり、生きていれば辛いことも、楽しいことも色々とありますが、先の未来のことを考えずに今この瞬間を生きることはとても大切なことだと改めて再認識させられました。
◆Ⅸ.妙諦の読書
妙諦という言葉を借りれば、読書にすぐれた真理を求めることは誤った判断なのではないかと思います。
読む行為自体に真理が内在することを意味づけすることは、非常に難しいことだと感じます。
言葉の奥底に潜む、真意を掴むことはやはり、読書しか思い浮かばないものがあります。
そもそも、私たちはこれだけの多くの書籍の中から、自分に見合った本を選ぼうとするのか。
端的に言えば、本を読まなくても生きていけます。
もちろん、これは書くことにおいてもそうである。
自分の中にある、モヤモヤとした感情やふとした思いや考えなどを世界中に公開する義務はなく、日記などに綴って自分の心の中に押し留めることも出来るはずなのであります。
何故、読むのか、そして書くのか、そうした行為全ては妙諦に近付く為なのではないかと感じます。
完璧な文章力、表現力というものはこの世には存在しないものであり、何故私たちは誰かの記した小説や評論などを読み、感動したり、感心したりするのだろうか。
それは、書き手一人一人には‘‘個性’’が文体に刻まれているからだと思っています。
個性には、様々な要素があり、要素には人を楽しませたり、幸せにしたり、悲しくさせたり、苦しめたりと、我々は言語を通して互いに心の内に向かって対話を行っているものだと感じています。
それは、対面式に会話をすること、メールでのやり取りでの会話など、方法的には異なるものであるがコミュニケーションを目的としている場合、伝えるという意味ではどれも同じであると思われます。
妙諦の読書とは、すなわち作者の心と対話をして、価値観を共有し合うということなのではないかと考えられます。
本には、その作者が伝えたいことがたくさん記されており、一冊を読み終えて、もう一冊、もう一冊と冊数を増やせば増やすほど、その作者の気持ちがだんだんと分かっていき、真の心の理解者へとなるものだと思っています。
読むことにおいて、私は毎度、読書術についての本や読書とは何かについての本を読むことがあるのだが、読み方など本来は存在しないものなのではないかと考えるようになりました。
これは、私が過去に記した【‘‘読書術の枷’’】の考え方に当てはまるものであり、術に縛られては本来のあるべき読書の価値を見失ってしまうのではないかと思います。
真理を求めた読書の在り方を築く為には、一文一文、または一語一語に込められた言葉の意図を汲み取り、純粋に読み進める行為こそが、読書のあるべきかたちなのではないかと考えさせられるものがあります。
◆Ⅹ.食について/一汁一菜から考える
食事することは、生きる上では必要不可欠なことであり、健康や暮らしにおいても深い関わりがあります。
食事をする為には食材を調理して、料理することが求められます。
私が食事や料理について、学ぶ上でとても参考になった書籍があり、土井善晴さんが記された『一汁一菜でよいという提案』には前述にもある通り、食事の基礎を学びました。
一汁一菜というのは、そもそも、ご飯や味噌汁、漬物を原点とする食事のことであり、本書では思想であり、時には美学、または生き方であることだと述べられています。
食事することというのは、大前提として食材を調達することから始まり、下ごしらえ、調理、料理からの食事であり、食べ終わったお皿を洗い、片付けるまでの一連の流れまでを踏まえての食事であるということも学ぶべきことがたくさんありました。
改めて考えると、食事は生きる為の持続的な生命活動であり、一汁一菜を通してご飯を中心とする味噌汁、漬物(おかず)を合わせるだけでも様々なレパートリーが考えられます。
料理から浮かび上がってくるのは、これからの生きる力を養う為の大切な教えであり、一汁一菜は生きる上での原点でもあると感じさせられるものがありました。
◆ XⅠ.バレエ表現の可能性
バレエとは、身体の動きを構成した芸術であって総合芸術の一つとされています。
文学や音楽、絵画、舞踏などの複数ある芸術表現を融合したものでありますし、極めて親和性が高いことが理解出来ます。
そして、ダンサーと作品もまた重ね合わされ、生命の芸術として表現することが出来るのもまたバレエの特徴だとも言えます。
バレエから分かることは、バレエを美学として捉えると、宗教や哲学、社会通念、風土などによっても形成されるものであり、作品から人々は感情移入して物語バレエからも過ぎゆく一瞬を鑑賞して感動出来ます。
それは、人によっての美の理想像が生まれるからであり、そこへ向けての規範が作られるからだと思われます。
言語的な芸術としては、文学や映画などが一般的に挙げられるし、分かりやすいものだと感じますが、バレエというのは生身の人間が踊りによって表現させたものであり、抽象的な美しさを言語化することは難しいものだと考えられます。
バレエから窺える超絶技巧は、いくつもの要素が組合わさることによって、そこに美しさによる芸術が体現されるのであり、こうした技巧の組み合わせ、連鎖のことをバレエ表現ではアンシェーヌマンと呼ばれるのだが、そうしたアンシェーヌマンは文学や映画でも同様に芸術性を見出だす為には表現技法として扱われるのは共通点があるのではないかと感じました。
ですが、バレエにはテクニックや表現の両者を掛け合わせることで成立する芸術であり、そうした魅力の虜になるからこそ、芸術としてのバレエは完成度の高いものだと理解出来るのではないかと考えられます。
萩尾望都さんの作品にバレエを題材にした漫画で、『フラワー・フェスティバル』という作品がありますが、バレエに親しみ奥深さを学ぶ上ではとても面白い作品でもあります。
超絶技巧としてのバレエの芸術表現は無限大であり、ダンサーが自らの踊りを見つけて、オリジナリティとして確立させるのは想像以上に難しいことだらけで、美への表現技法は様々な要素を吸収しながら、新しい美へと何度も、試行錯誤を繰り返しながら進化させることが求められるものだと考えさせられたり、バレエに限らずこれは芸術全般にも言える事だと痛感させるものがありました。
主人公みどりと兄の薫の会話で、薫が話した言葉で「何百もあるバレエの躍りのなかで一生のうちどれくらいのものを踊れると思う?」とみどりに聞くシーンがあるが、その都度新しい表現を魅せる為には自己変革を必要とするのがまたバレエ表現の役割であり、表現の可能性に終わりはないことが考えられます。
バレエとは、また違ってきますが、社交ダンスの世界を描いた「ボールルームへようこそ」という作品があります。
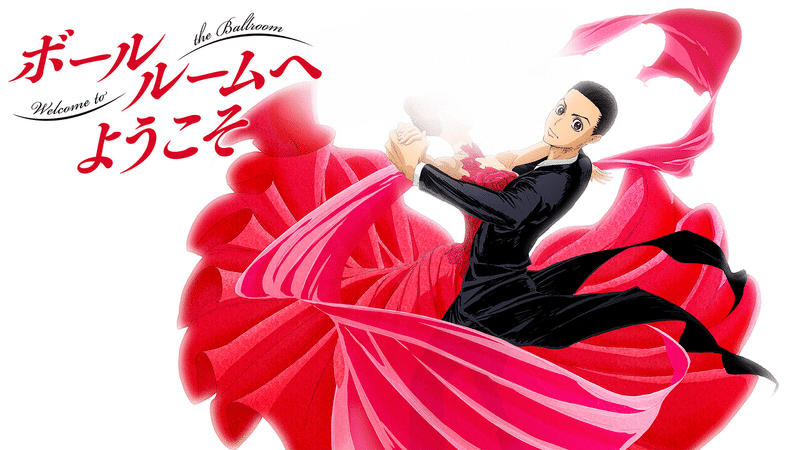
主人公の多々良という青年を通して、ダンスにかけた情熱や向き合い方から多々良は自らのダンスの形態を模索しながら成長していく物語であり、社交ダンスもまたバレエと同じく、テクニックや表現による調和性を生み出すことが求められます。
バレエ、舞踏の世界は漫画やアニメなどの媒体からエンターテイメントとして楽しむことが出来るものまた魅力だと思います。
ここでは、バレエを芸術論として語る上では人間の生命というものに焦点を当てることで、バレエは生きる表現だということが理解出来ます。
鑑賞者を感動させるバレエの本質的な素晴らしさに言葉はいらないものだと感じます。
バレエから、私たちは何を学び、何を感じるべきなのか。
見るものを魅了するバレエの可能性は更なる飛躍を見せてくれるものだと感じました。
◆ⅩⅡ.わかるとは何か?
養老孟司さんの記された『ものがわかるということ』という本を読みました。
ものがわかるということを考えると、私たちは理解するということと直結させて意味は同じだという認識を持ちがちではあるが、理解するとわかるとはまた違ったことだということを痛感させられるものがありました。
情報化社会において、あらゆる対象物は記号的だと考えられる。
文学や映画、音楽もまた記号のようなもので、集合体としての記号が溢れる中でSNSにおけるコミュニケーション機能もまた記号的であり、言語媒体は違っても紙や電子上に流れ出す記号を私たちは毎日触れていて、それを意識的に脳内で処理しています。
流れゆく記号は、必要なものか、または不必要なものかということを選別しないと脳内はパンクしてしまう恐れがあり、だからこそ忘却と整理の連続性が必要なことだと思われます。
ここで、わかるとは何かということを考える上では本書では映画を例に挙げて取り上げられていました。
映画を見るとき、作品の内容にもよりますが、一度見るよりも、二度見る方が作品に対する理解度は高まります。
作品を通しての登場人物たちの心理描写や作品に込められたテーマ性など、見る頻度を増やせば増やす度に気付けなかったことがより鮮明に浮かび上がってきます。
ですが、これがもし、十回や二十回も同じものを見続けることは苦痛でしかありません。
見ることが苦痛になる、作品の全体像、登場人物たちの決められたセリフ回し、場面ごとに切り替わる背景など、映画に込められた世界観は既に創作され完成されたものであるので、鑑賞者がいくら退屈でつまらなく感じても気分に応じて、映像が意識的に違ったものとして展開されることは物理的に不可能なことだと考えられます。
ここで、わかることが一つあります。
それは、映画という記号は変わらないのに対して、見る側には心の変化が窺えるということであります。
記号はやはり、記号であって人の心というものは記号ではないということが理解出来ます。
そこで、わかるという言葉をより広範囲に深く考察していると、創作物もまた記号であるのと同時に、創作する過程には思考するという行為が共存していることが分かります。
例えば、私が記した『思慮する読書』では、様々な本を関連させて一つの書評として成立させた構造は円環構造としての意図があり、円環構造の中には何度も連続性を見出だすことによって一見すると、無関係な解釈を意味的な解釈として価値転換させることでわかるということを内在させています。
一方の『虚無と結実』においても同様に、テクストを題材にそれとは無関係なテクストを読みとく為の作品解釈や理論入門の特性を加えることで、テクストによる新たな解釈と理解への発見を試みたものであり、両者を行き来することでこれもまた、わかることを目的としてた同様のものだと私の中では捉えています。
養老先生は、本書の中でものがわかるということは、結論的に根本は共鳴だということを述べられていました。
では、共鳴とはどういう意味なのだろうか。
私なりの解釈としましては、共鳴とはあるもの同士を互いに組み合わせて起きるものなのではないかと感じました。
記号としての作品と肉体と精神を持つ人の考えによって、それは共鳴する。
共鳴とはすなわち、独創性、あるいは創造性とも置き換えられるのかもしれません。
ものがわかるという上での‘‘もの’’というのは、曖昧で広範囲な意味を持つものであり、わかるまでに至るまでには長い年月を有するものがあると思いました。
人として、熟成するまでには、たくさんの知識や経験を積んでから、養老先生のような、ものがわかる人を目指していきたいと感じました。
◆ⅩⅢ.帷
時間も人も流動的に変化している。
決まった時刻に目が覚めて、いつものように朝食を食べる。
書きかけの小説がまだ途中だったが、週末に続きを書くことに決めた。
書き出しが決まらないのは、いつものことだった。
書く人にならなければ、書くことは出来ないと私はそう思うようになった。
読むときがくれば、読む人になるし、音楽を聴くときは聴く人へとなる。
個人的な自己弁明ではなく、ぼんやりとした感覚でそういう風に思うようになった。
スクリーン画面上に、文字を打ち込もうと思っても、思考は断絶しているので何も思い浮かばないでいる。
雑踏の中に、自分がいる。
そして、自分を見ている自分もいる。
何もかもが記憶のせいだと感じた。
記憶は、思い出と強く結び付き、月日が経てば記憶は剥がれ落ちてしまうが、いつのまにか剥がれてしまったところに綺麗にくっつくことがある。
目を閉じると、身体が深く沈み、感覚が自我を包みこむような気がする。
溶け込んでいくものは、記憶と感覚だけであり、あとは何も残らない。
文字の中に、何を溶け込ませるかは書き手の自由だし、表現の領域に制約はない。
そうした空間にいる時間は、私にとって生きていると心から感じるものがある。
偽りの中に、真実を織り混ぜると、それは真実ではなくなり、ただの嘘だけになる。
嘘をつかなければいけないことは何度もあったし、これからもそうしたことは度々起こると思う。
嘘をつくことで、その瞬間は逃れられるものだけど、それはいつか全て自分の見に降りかかってくるだろうと思う。
ーだいぶ、進んだ、そう感じながらコーヒーを一口飲んでは次の一文を考える。
書いては考えて、書いては考えることの繰り返し、連続性から何かが生まれることは決してなかった。
頭の中で、あらゆる思いが駆け巡っている。
そうした思いを私は溢れ落ちてしまわないように記録した。
記録は、思いや考えなどを閉じ込める為にも使われるようになり、いつしかそれを美化することで、エッセイや小説などが生まれたのだと思うようになった。
何故、残す必要があるのか。
形態としての記録が違っていても、それは単なる記録であり、性質そのものが失われてしまうことはまずありえない。
だが、記録と言えども、そのときに体感した現実は記録が出来ない。
過去と現実には、明らかな差異が生じている。
そうした、差異を埋め合わせる為に、何かを必ず書いてやるという気持ちは消え失せることはないものだと思いながら今があると感じた。
◆XIV.プラットホーム
書くことが与えられた場所があるということがどれだけの幸せなことなのかということについて考えることがありました。
私には、書くことは必要で感情の吐き出し口としてnoteの存在意義があるというわけではなく、生きる為であり、呼吸する為だという意味であります。
呼吸をするように、何かを書くこと、身体中から湧き上がる衝動は自らの魂によって命令するかのように、使命感のようでさえ思える。
私にとって、物を書くことを始めたのはnoteが初めてであり、noteをここまで継続出来たことは我ながら奇跡的のようさえ感じることがあります。
ブログという媒体は、note以外にもあるが、私がたまたま見つけたものがnoteであり、日記とはまた違ってジャンルにとらわれない形式で文章を書くことが出来るということは大きな魅力だとも思います。
日記とブログについての違いを考えることもありました。
主に日記は、その日の出来事について、自分の感じた感情の原液を言語化させて文章に落とし込むものに対して、ブログはそうした言語化する前の段階で加工させて、また違った視点で物事を派生させて言語化させたものなのではないかと思っています。
noteというプラットホームを通して、誰でも物書きになれるものだし、ブロガーとも名乗れたりするのが現代であります。
私の記したものは、全てが我流であり、文章作法に習ったものは全く意識していないし、そうしたハウツー本はどれも肌身に感じなかったところがあります。
ブログにしろ、noteにしろ、アクセスするだけのその人が記した記事から思念や世界観なども読みとくことができ、文章のスタイルもまた人によって違っているものがあり、文体からリズム感や躍動感が感じることも度々あって日々、発見と学びの連続で読んでいるだけでもとても面白く感じたりする。
言葉によって、人は感動し、時に救われることもある。
現実から閉ざされていた自分の居場所はここだけではなく、別の場所でも生き生きとしていいんだという爽快感は私を変えてくれたものがあったんだと思い返すことがあります。
時計の秒針を眺めながら、この先のことばかりを考え過ぎてしまう。
考えていても仕方がない、今出来ることはただ書き続けることだけなのだから。
筆意に揺らぎはなく、統一した心から私は自らを語っていく。
■あとがき
『揺蕩う素養』という作品は『泡沫の謠』では、書ききれなかったことを雑記的に記したものとなっています。
特に、目的意識を持って書いた作品でもなく、書きたい気持ちに身を任せて書いたものであり、私自身にとっても満足した出来映えになったのではないかと実感しています。
ですが『揺蕩う素養』を書き終えた後でも、私にとってまだ書きたいこと、書くべきことがあるということに気付かされることがありました。
生きていることは、すなわち思考し続けていることであり、思考することが継続出来ている間は、いつまでも書くことが出来るということでもあります。
『泡沫の謠』から『揺蕩う素養』へ、次に書くものはまだ何も決めていませんし、何も分からないところがあります。
何も分からないところから始めることが面白くて、行き着く場所に何を知り、そこから何を学ぶのか。
『揺蕩う素養』は、私にとっての現時点での私の全てでもあり、書くことによって記録され、記録された言葉の数々は読み手へと伝わっていく。
伝わった言葉をもとに、読んでくれた誰かが自分の言葉として表現していくことが、書き手にとっては何よりも嬉しいことだと思っています。
よろしければ、サポートお願い致します。 頂きましたサポート資金は、クリエイターとしての活動資金として使わさせて頂きます。これからも、宜しくお願い致します。
