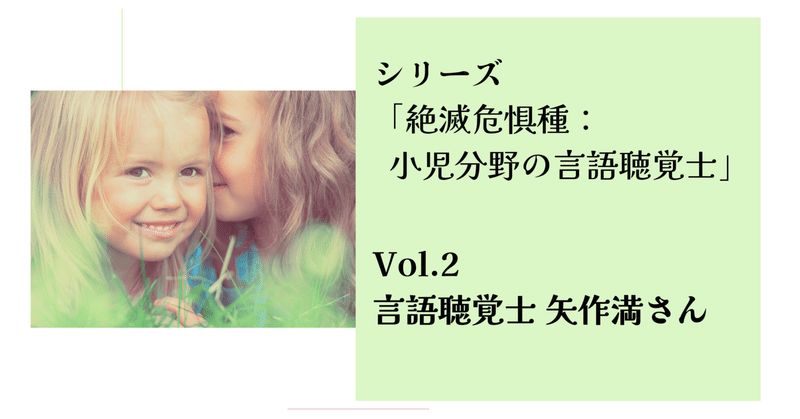
なぜ小児分野の言語聴覚士は少ないの?【Vol.2】東京医薬看護専門学校 矢作満さん
言語聴覚士。ことばによるコミュニケーションに難がある方に専門的サービスを提供し、自分らしい生活を構築できるよう支援する専門職である。
小さな子どもをもつ親は「子どもがなかなか言葉を話さない」「特定の発音が難しい」など、言語発達に課題や不安を感じたとき、彼らの支援を受けたくなるだろう。
しかし残念ながら、生活圏内でアクセスできる小児分野の言語聴覚士は非常に少ない。
そこでこの連載では、小児分野の言語聴覚士やその育成に関わる方に話を伺い、子どもの言語発達に関するトピックや、言語聴覚士としての活動内容などを紹介する。
子どもの言語発達に悩むすべての人に、この記事が届きますように。
* * *
今回お話を伺ったのは、東京医薬看護専門学校で言語聴覚士の養成を行っている、言語聴覚士の矢作満さんです。
小児分野の言語聴覚士が少ない理由や、職業としての言語聴覚士の魅力について、教えていただきました!

大学で心理学を学び、その後言語聴覚士資格を取得。言語聴覚士として働きながら大学院で心理学の研究も行っていた。リハビリテーション専門病院、国立病院、訪問看護ステーションなどを経て、現在は東京医薬看護専門学校言語聴覚士科で言語聴覚士の卵たちの養成している。成人・高齢者領域だけでなく小児領域の支援もできる言語聴覚士を養成したい!と奮闘中。プライベートでは二児の父。ハイキングやボルダリング、スキーを子どもたちと楽しんでいる。
勤務する中で小児分野に携わり「職業観」が変わった
——はじめに、矢作さんが言語聴覚士になった経緯や理由を教えてください。
矢作さん(以下略):私は大学で心理学を専攻し、人の発達に関する内容も勉強してきました。臨床心理士になることも検討しましたが、結果的にはすでに国家資格だった言語聴覚士の道を選びました。
最初は高齢者のリハビリテーション専門病院で働き、そのあと国立病院で2年ほど勤務。その病院にいた先輩が「言語聴覚士なら、成人だけでなく小児、言語聴覚障害のある方すべてを支援できるほうがよい」という方針だったので、そこで初めて小児分野に関する知見をたたき込んでもらって。
「もっと幅広い方を支援したい」「何らかの理由があって病院に来られない方の支援がしたい」と思って、訪問看護ステーションで10年ほど働きました。
それまで出会った言語聴覚士は、成人だけ、小児だけなど一部の領域に特化した方が多かったです。でも私は両方の支援ができたことで、自分自身の経験の幅や職業観が広がりました。
これから言語聴覚士になる方にも「一部領域にとどまらず、広い領域を担当する」というマインドを持ってほしいと思いながら、専門学校で教員をしています。
「知名度の低さ」や「一人職場の多さ」が大きな課題
——そもそもなぜ、小児分野の言語聴覚士は少ないのでしょうか。
大きな理由は2つあると考えています。ひとつは、言語聴覚士そのものの知名度の低さです。
例えば近い資格の理学療法士であれば、学生時代にケガをしたときなどに整形外科や接骨院でお世話になるので、比較的認知されています。
しかし言語聴覚士は、国家資格になるのが理学療法士や作業療法士より30年ほど遅れたために人数が少なく、その支援を受ける機会も少ないために知名度が低いままなのです。
学生からの知名度が低いと、進路の選択肢になりにくいですよね。これは養成校の受験者数が少ないことにも如実に現れています。
——たしかに、学生時代に「言語聴覚士になりたい!」という人は周囲にいなかったです……。もうひとつの理由は何でしょうか。
小児分野での言語聴覚士の求人数が少ないことです。
言語聴覚士は元々、病院で働くことを前提として資格化されました。これは「言語聴覚士は病院にさえいればよい」ということではなく、「病院にすら言語聴覚士がいないのはおかしいよね」という発想から来たものだと思います。
現在の人口比率も影響し、病院では小児よりも高齢者を対象とする支援が圧倒的に多いです。そのため小児分野の求人は自然と少なくなります。
近年、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスに言語聴覚士などの有資格者を置いた場合、特別支援加算がつくようになりました。
これによって言語聴覚士の活躍の場は広がりましたが、多くの人員を必要とするわけでないので、どうしても「一人職場」になりがちです。それでは新米の言語聴覚士は勤めにくく、周囲からのフォローが得られずに結局辞めてしまうという事象も起きています。
他にもいくつか理由はありますが、こうした小さな課題の積み重ねが小児分野の言語聴覚士が増えない理由に繋がっているのです。
——専門学校で生徒さんが小児分野にも目を向けられるよう、工夫していることはありますか?
言語聴覚士の養成過程では、どうしても高齢者向けの医療分野で働くことを想定した内容が多くなります。そのため、学校に付属した言語訓練室で、学生のうちから多くの利用者さんに触れられるような工夫をしています。
お子さんも訓練に受けに来るので、小児分野に興味をもつ生徒が増えたらいいですね。
また、もし就職先の施設で成人向けの支援・訓練しか行っていなかったとしても、小児の支援を行えば何らかの加算がつくことを伝えると、小児分野まで対応できるかもしれません。そういった知識やスキルも伝えるようにしています。
「話して思いを伝える」人間らしい活動を支援する言語聴覚士
——ずばり、言語聴覚士として働く醍醐味や魅力は何だと思いますか?
一番の醍醐味は「言葉とコミュニケーション」という人間ならではの営みを、専門家の立場から支援できることだと思います。
言葉は人間が自分の思いを伝えるために必要なもの。そして「ここで遊びたい」「あれを食べたい」「嬉しい」「もっと一緒にいたい」などと思うのは、人間ならではの心の働きだと思います。
そんな人間らしい思いを伝える機能について学んで支援するのは、キャリアを重ねてもなお興味深いことです。
小児領域ならそれを幼少期から支援できますし、高齢者支援なら嚥下のサポートによって生命維持にも繋がります。言語聴覚士はとにかく幅が広く、奥深い支援領域をもつ職業ですね。

また、働きやすさの面でいうと、求人数自体は常に多く、国家資格なのでキャリアを継続しやすい点もメリットだと思います。小児分野は求人が少ないのですが、成人領域の求人数は非常に多く、学生が働きたい地域で働くことができます。
言語聴覚士は女性が比較的多いのですが、正社員・パートともよく募集されているので、ライフスタイルの変化に合わせて柔軟に働きやすい点も魅力ですね。
——社会人を経て勉強に来る生徒さんも多いのでしょうか。
社会人経験のある生徒さんもいますよ。特に東京医薬看護専門学校は、元々夜間コースがあったせいか、社会人経験者がかなり多いほうだと思います。言語聴覚士科は高校卒業者を対象とした3年制課程と、大学卒業者を対象とした2年課程がありますが、2年制課程の生徒のうち3分の2は社会人経験者です。
社会人経験者は、「何か資格が取りたい」という方から、保育士や栄養士、介護福祉士などの関連職種に就いていて「周囲に言語聴覚士がいないなら、私がなろう」という方、家族に言語障害や聴覚障害がある方などさまざまです。
それぞれの思いを胸に、言語聴覚士の勉強や資格取得に励んでいます。
「子どもが言語聴覚士の支援を受けられること」を当たり前に
——最後に、子どもの言葉の遅れが気になる親御さんなどの読者に向けて、メッセージをお願いします。
子どもは千差万別で、皆が同じように成長するわけではありません。これまで、発音に少しクセのある子どもから、重い病気やケガの影響で話すこともままならない子どもまで、さまざまな子を見てきました。また、その親御さんによっても悩みが違います。
症状や発達の遅れが「軽い」からといって、その悩みが軽いわけではないですよね。だからこそ、言語聴覚士になんとか繋がって、適切な支援を受けてほしいと思います。
私はこれからも言語聴覚士の養成に携わりながら、地域の療育や当事者が集まる「友の会」のお手伝いなど、さまざまな活動をしていきたいです。
支援を必要とする子どもが言語聴覚士に繋がれないことは「異常事態」だと思います。一刻も早くスムーズに支援を受けられる世の中になるよう、微力ながら力添えしていきます。
いただいたサポートは取材代もしくは子どものおやつ代にします!そのお気持ちが嬉しいです。ありがとうございます!
