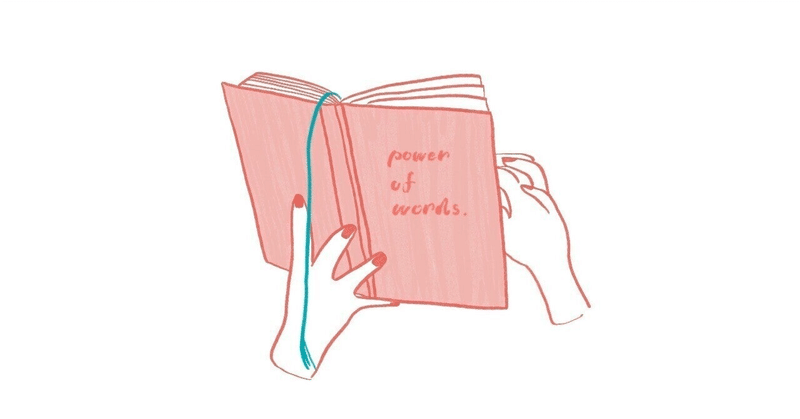
荒川洋治「文学は実学である」を読んで/本の話
荒川洋治「文学は実学である」 を読んでいる。

短いエッセイが86編。たくさんはいっている。 毎日少しずつ、 特に気に入ったのは音読したり、書写したりしている。ゆっくりゆっくり味わっている。
おしゃべりにもリズムがあるように、読書にもリズムがある。飛び石をかけるようにずんずん進むのが楽しい本もあれば、 大きな飴玉を口の中で転がしながらゆっくり溶かすようにじっくり味わうのが乙な本もある。
私にとってこのエッセイ集は後者にあたる。ひとつひとつは三ページほどで短く文も平易で読みやすが、内容はふっくら示唆にとんでいる。著者個人の具体的なエピソードが、読み手が立ち止まって一考したくなるような一般的な事柄へと滑らかに運ばれている。
中でも「会っていた」は特に好きだ。
読書や本との出会いについて書かれた二ページだけのエッセイ。初めて出会った時にそれがものにならなくても、自分でも気付かぬうちに布石となって、時を経てから二回目、三回目の出会いを導いたり、何かの触媒になったりするという内容だ。その一度目の出会いの意味合いを、「種」や「帯を緩める」といった日常の言葉で表現されていて、言い得て妙。思わず唸った。
この文字数と平易な言葉たちで、これだけのことが伝えられるのかと感嘆する。
文章の密度と言えばいいのだろうか、文字数と内容のギャップに初めて感銘を受けたのは、小野不由美「十二国記」だった。小野先生の文章は時に堅牢なと評される。「十二国記」は古代中国を基にしたファンタジーということもあり、漢字も硬い言葉も多い文章で、漢文っぽい。体積は小さくても高密度で重量がある。たとえるなら鉄球みたいなかんじ。
だから、それ以来、最小限の文字数で最大限伝えるならば、こういう文体になるのだろうと勝手に思っていた。
そこへきて、出会った荒川先生の文章。硬くはないし文字数も多くないのに伝わってくる情報の豊かさたるや。たとえるならば、濃厚なはちみつだろうか。ティースプーンひと匙分で十分甘く栄養たっぷりで、満たされるかんじ。
「こういうのはこういうのだ」と自分一人で決めてかかっていた愚かさよ。改めて文章って面白いなと思った。きっとこの世には私のまだ知らない文章がたくさんあるのだろう。
いい文章、上手い文章とは何なのかと、何とも壮大な問いが頭をもたげてしまう。
私に読書の習慣ができたのはここ数年のことで、読んだ本は多くない。でも、その本たちとの出会いが種となって「会っていた」に強く共感したのだ。きっとこの「文学は実学である」も、いつか何かに出会った折に、あ、あのとき会っていた、と思うんじゃないかと思う。
本を読むと「会っていた」の種が増えていく。その種は、それからの日々の暮らしの中で、ふとした拍子に発芽したりする。そのきっかけになるのは、人であったり本であったりいろいろだ。「会っていた」に出会うと自分の中の歴史に触れたような気がして、本のちょっぴり幸せな気持ちになる。だからまた本を読みたくなる。
本って面白い。
↓過去の「本の話」記事↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
