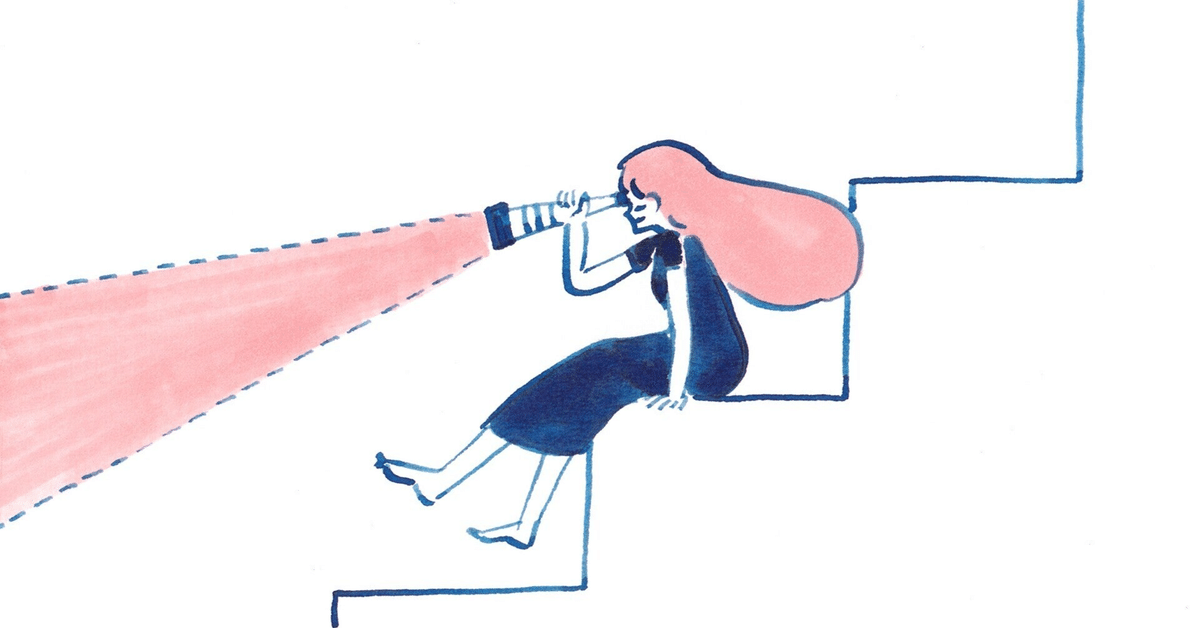
仕事を進める上で気をつけたい「認知バイアス」について
突然ですが、「バイアス」という言葉を聞くと、東日本大震災の時を思い出します。災害時などによく言われるのが「正常性バイアス」と「同調性バイアス」です。
「正常性バイアス」は例えば職場で非常ベルが鳴り響いたとして「訓練かな?」「そのうち止まるだろう」「自分のいる場所は大丈夫」と思ってしまう感情のことを指します。
「同調性バイアス」は非常ベルが鳴っても、誰も慌てたり避難したりしないから「大丈夫」と思い逃げずに居てしまう、集団の中にいるとついつい他人と同じ行動をとってしまう心理で、日常生活では協調性につながります。
避難の妨げになるので、いざというとき気をつけたいですね!
(私はオフィスなどで地震にあった際は、ドアが閉まりきっていたら開けるように動くことを意識しています。)
と、災害の話から始まってしまったのは、最近やたらと地震が多いからかもしれません。
これを読んでくださっている方、お家の備蓄などチェックしましょうね!
さて、本題です(笑)
災害時にも働くバイアスですが、これは「認知バイアス」という思考や判断の偏りのことです。仕事をする上で気をつけたい認知バイアスを学んでいきたいと思うので、記事にしていこうと思います。
認知バイアスとは
認知バイアスとは、自分の思い込みや周囲の環境などによって無意識のうちに合理的ではない判断をしてしまう心理現象のこと。 思い込みを持っていると、ほかにどのような情報があっても最初の考えを支持する情報ばかりが目に付きます。
認知バイアスは「脳が効率よく働こうとした結果、副次的に生じてしまったバグ」。多くの「これは●●●したほうがよさそうだ」といった反射的な直感は有益ですが、想定外のことが重なるとピントがズレてしまうのだとか。
ちなみにバイアス関連で検索すると、こんなに●●バイアス、●●効果、みたいなのがいっぱい出てきちゃいます…覚えられない…。
情動ヒューリスティック/ハロー効果/集団浅慮/サンクコストの誤謬
/自信過剰バイアス/ドッペルゲンガー/楽観バイアス/後知恵バイアス
/キャッシュレス効果/確証バイアス/後知恵バイアス/アンカリング/自己奉仕バイアス/ゼロサム思考/ツァイガルニク効果/偽の合意効果/コンコルド効果
/ダニング=クルーガー効果/内集団バイアス
自分の記憶は本当に正しいのか?「虚記憶」
たとえば…子どもの頃に迷子になったことがあると思っていたのに、家族に聞いたらそんな事実はなかった。そういうことは無いでしょうか?
仕事で、お客様から●●●という連絡を貰っていたと思っていた…など、それはもう思い込みか><
認知心理学者の実験で「実際には起こっていない経験」について話し合った被験者の25%にありもしない記憶が生まれたそう。これは「虚記憶(虚偽記憶)」という認知バイアスです。私たちは、経験していないことを、まるで経験したかのように思い出す可能性があるのだとか。
仕事上でも、お客様と話してそう決めたはず。など、記憶を作り出してしまう可能性もあるので、自分の行動記録や、打ち合わせの議事録なんかはちゃんと取っていきたいと思ってます。(もう全部録画したい…)
“みんな、わかってる” は勘違い「透明性の錯覚」
「透明性の錯覚」は、自分の感情や考えていることが、実際以上に他者に伝わっていると思う錯覚です。
たとえば…大勢の人の前でスピーチをしたとき、緊張ガクブル状態だったのに、周りの人には、とてもそうは見えなかったと言われる状態などです。
自分の緊張や、不安、怒りや口に出さない思いも、ニュアンスでみんなに伝わっちゃってるよね?ニュアンスでわかるよね?
こういう気持ちが「透明性の錯覚」を生みます。
心のなかは、さほど理解されていないので、ちゃんと説明することが必要ですね。。あうんの呼吸とか、以心伝心とか、バチッと決まったら気持ちいけど、そううまく行くものでも無いと思っていきましょう。
“また締め切りに間に合わない” 「計画錯誤」
たとえば…予定していたところまで仕事が終わらないまま、打ち合わせ当日を迎えてしまった。。。なんて恐ろしい状況になりたくないですが、ギリギリのところでなんとかやれている!そんなこともありませんか?ないですか?
人は、過去に計画どおりに進まずに失敗した経験が繰り返しあったとしても、新たな計画を立てる際に楽観的な予測をする傾向があるそうで、「大丈夫、これくらいあれば余裕でできる」などと楽観的に考えてしまうのだとか。これを「計画錯誤」といいます。
計画錯誤が厄介なのは、失敗した経験が活かされないことです。
(いつも資料作りが締め切りギリギリで死にそうな思いをするのに、うまく進行できず、を、繰り返してしまう…)
たいていの場合、物事は計画通りには進みません。予測しなかったトラブルが生じたり、ほかの仕事が舞い込んできたり!(あるあるですよね)
それでも新たな計画を立てるときに最善の状況を想定してしまいます。
気をつけたい…!
“それはあなたの思い込み” 「対応バイアス」
たとえば…電車にお年寄りが乗ってきたとき、近くの座席にいた高校生が席を譲らずそのまま座っていたという場面を想像してみてください。
電車の揺れに耐えながら立ち続けるお年寄りと、席に座ったまま動かない高校生。そのとき、あなたは高校生に対してどのように感じるでしょうか?
「お年寄りに席を譲らないなんて、思いやりのない人だ!」と考える可能性はありませんか?
「思いやりのない人」という考えは、高校生の性格という個別な要素に、行動の原因を帰属しています。
高校生にも席を譲らなかったなんらかの理由があった可能性があります。たとえば、高校生が体調不良のため立ち上がることができなかった場合や、高校生がそのお年寄りは膝の痛みのために座ることを好まない人だということを知っていた場合です。
第三者の視点からみたとき、そもそも、高校生やお年寄りがどのような人物なのか、どのような行動をとる人なのかをよく知らないはずです。知らないにも関わらず、行動の原因を個人の性格や特徴に帰属してしまうことは、根本的な帰属の誤りを起こしているといえます。
他者の行動の原因を考えるとき、本人の性格や能力のような内的特性を重視し、状況の影響力をネガティブに過小評価する傾向があります。これは、他者の行動の原因を考えるときに非常によくみられることから、「対応バイアス」(基本的な帰属のエラー)と呼ばれています。
電車の中の老人と高校生のシチュエーションは別の記事で紹介があったのですが、私はまんまと対応バイアスがかかっておりました。。。反省。
仕事の場面でも、初対面から対応バイアスをかけて人を見てしまわないように気をつけようと思います。。。
“思ったとおり!” は「確証バイアス」
自分にとって都合のいい情報ばかりが目に入り、都合の悪い情報が目に入りにくくなることを「確証バイアス」と言います。(あるある過ぎる。。。)
自分が正しいことを裏づける情報ばかりを集め、反証する情報を無視して仕事を進めると、のちに指摘されたり失敗したりで、詰めの甘さが露呈してしまいます。
また確証バイアスは、対人場面でも起きます。たとえば他者の性格について「社交的な人」といった事前情報を得ていると、社交的という自分の予想と一致する相手の言動により着目しやすくなります。また、その相手に対して、自分の予想を支持する答えが多く返ってきそうな質問(「あなたは友達とおしゃべりすることが好きですか?」など)を優先的に用いることが実験で確かめられています。
“身内びいき” は「内集団バイアス」
たとえば、知り合いのやっているカフェがあったとして、本当のところあまり美味しくなくても(?!)、同僚や友達におすすめしちゃったり、なんならお店に連れて行っちゃったり…なんてことはないですか?
同業他社の社員より、うちの社員の方が優秀だし!!とか。あるあるです私。笑
実際には優劣の差がない場合にも、自分と同じ集団に属するメンバー(友達・会社の同僚など)の能力を、それ以外の集団に属するメンバーよりも高く評価し、優遇しがちです。
自分が所属する集団(内集団)のメンバーの方が、それ以外の集団(外集団)のメンバーに比べて人格や能力が優れていると認知し、優遇する現象を「内集団バイアス」、あるいは「内集団びいき」と言います。
集団を区別する基準が無意味なもので、相手と直接的な相互作用がなく、自分がそれによって利益を得る可能性がないような場合でも、自分と同じ集団のメンバーだと認識した人には内集団びいきを示しやすいことがわかっているとか。。。
ひいきをしてもほとんど意味がないような状況であっても、私たちは内集団をひいきしたいと思うようです。むーん。しょうがないけど、時には気をつけないとですね。
“わたしたちは特別” は「外集団同質性効果」
先程の「内集団バイアス」に加え、「外集団同質性効果」という認知バイアスの存在も明らかになったそう。自分が属するグループ以外はみな、似たり寄ったりだと認識してしまうバイアスです。
例えば、自分と違う年代のタレントがみな同じ顔に見えるのも、そのバイアスがかかっているからなのだとか。
自分が所属する内集団のメンバーに対しては多様性があるように認知しますが、自分が所属していない外集団のメンバーに対しては、メンバー同士が互いに似ているように認知します。内集団の多様性を外集団よりも高く認識し、外集団をステレオタイプ化して均質な集団だと認識する現象が「外集団同質性効果」になります。
これも無意識にやりがちです。。。
さいごに
バイアスのことを調べると、自分の目にもだいぶフィルターがかかってしまっていたのだと痛感しました。。。
物事を決める際にはいったん立ち止まり、「この考え方に偏りはないか?」と自問してみることにします😫
バイアスについて調べていたら、面白いサイトを見つけたので、興味のある方は覗いてみてください★
デザイナーが気をつけるバイアスというものも!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
