
3年かけて採用広報を立ち上げたら、応募が爆増した0→1の秘訣
こんにちは、アウモの山口です。
私はおでかけ情報サービス「aumo」と実店舗向けマーケティング支援SaaS「aumoマイビジネス」を開発・運営するアウモ株式会社に、2018年5月に中途で入社しました。入社後は、セールス部門の採用の次にプロダクト部門の採用を経験し、現在はコーポレート部門含む全職種の採用と広報全般の業務を担当しています。
今回のnoteでは、自社の採用活動の基盤を作っていくほぼゼロの状態から、エンジニア、ディレクター、セールス、ライターなど複数の職種で毎月新しいメンバーが加わるようになるまで実際にやったことを振り返りました。
アウモが子会社化した2018年から2022年の現在までの『採用広報活動について』を「知る」「作る」「改善する」の3つにまとめてご紹介したいと思います。
~知ること~
1.自社の特徴を知る
採用広報の目的は、会社の情報を発信して多くの人に会社のことを知ってもらい、採用に繋げることです。
ゴールに向かうにはどんな情報を発信すれば良いのか、情報発信の方向性を決めるために、まずは自社分析から始めました。
■ 自社の状況を知る
・候補者の選考応募の理由
・候補者の志望度が高い/低い理由
・内定承諾の理由
・選考途中や内定辞退の理由
・自社の魅力の打ち出しポイント/ウイークポイント
2.採用市場の状況を知る
次に、自社に来て欲しい候補者がどのような企業を求めているのかを分析します。
時間をかけながら細かい情報を集めていくことになりますが、探さなければ目に入ってこない情報も多いため、とても重要な項目です。
■ 候補者が求める企業ニーズを知る
・候補者の併願企業をヒアリングする
・併願企業の選定理由(転職軸)を深掘りする
・競合と比較し、自社に足りないポイントを洗い出す
強み:差別化して訴求ポイントにする
弱み:隠さずに”現状の課題”として変化が必要なことも候補者に伝え切る
候補者のニーズに会社の印象を近づけるだけでなく、実態も受け止めて本質的に近づけていくことを目指します。
例えば、多くの候補者が求めている「制度」があれば、それを取り入れてみたりと、ニーズを把握した上で変化を加えていくことで、求められる会社像に近づいていきます。

3.ベンチマーク先を研究する
採用広報には、オープンな部分(他社を参考にできる部分)とクローズドな部分(自社流を見つける必要がある部分)があると思っています。
どの企業でも採用広報コンテンツは公開されているので、「インタビュー記事をつくる」や「サービス紹介記事をつくる」など、他社を参考にできる部分は多くあります。
一方で、自社のコンテンツに足りないものはなにかを分析して着手していくことも、他社との差別化という意味で重要視をしています。
■ ベンチマーク先の分析
・他社の求人票、会社紹介資料を研究する
・応募バッティングしそうな企業やその特徴を、社内・社外の両方ヒアリングする
・他社でエントリーが多い企業の特徴(事業内容/募集内容)を洗い出す
・他社が求職者に対してなにを打ち出しポイントにしているのかを知る
・給与水準、福利厚生、社内制度などを自社と比較する
・イベントや採用活動に関する施策など、他社が取り組んでいる手法を調査する
・事業競合と採用競合の両方の採用活動を分析する
社内で競合を分析することはもちろん、社外から意見を聞くことも採用広報をやっていく上では欠かせません。サービスや事業が異なる企業でも「意外にそことバッティングするんだ」という発見が実際にありました。
バッティングする理由を明確にすることで、競合と差別化できる部分や、候補者への訴求に必要な情報など、会社の強み/弱みを社内で共通認識できるようになりました。自社流の手法も取り入れていくことにより、運用開始時期と比べて募集記事PV数が132%、応募数が163%増加しました。

~作る~
4.どんな手順で、なにをやったのか
まず最初は、とりあえず「コンテンツを出す」ことを目標にしていましたが、徐々に自社でやっていくべきことが見えてきて、コンテンツ量を保ちつつ「どんなコンテンツを出すか」を重視するようになりました。
■ 実際にやったこと(ざっくりと時系列)
1.社員インタビュー記事をつくる
2.社内イベント記事をつくる
3.社員でSNSをはじめてみる
4.イベント登壇・開催のレポート記事をつくる
5.事業やサービスがテーマの対談記事をつくる
6.デザイナーnoteをはじめる
7.会社紹介資料を本腰入れてつくる
8.開発ブログをはじめる
9.アウモ社noteをはじめる
5.コンテンツ制作の流れ
特別なことはあまりないですが、「スケジュール設計」と「構成づくり」をしっかりやる、ということを意識しています。
■ コンテンツ制作の手順
1.企画・スケジュール設計
2.調査・構成づくり
3.コンテンツ制作
4.効果検証
5.改善
ただ実際のところは、調査しながらコンテンツを作り始めてみたり、また戻って企画を練り直したりと、手探り状態で試行錯誤していました。
せっかくコンテンツが完成しても、構成を作るときに目的や目標がブレていると、伝えたいことが伝え切れていない内容になってしまい、振り出しに戻る経験も多くしました。
実際にコンテンツを作り始めるときは、まず目的や訴求ポイント、参考記事のリンクなどの企画構成をドキュメントにまとめて、関係者にフィードバックをもらってから執筆にとりかかるようにしています。(出す媒体によって運用は若干異なります。ブログ系やnoteは自由度高くしています。)
■ 記事構成づくりの手順(自社流)
1.最初に「①自社分析」と「②競合分析」をして、「③今回のコンテンツに限った目的設定」し、「④記事構成」をドキュメントにまとめます
2.人事系のミーティングのアジェンダに採用広報を加え、経営メンバーと組織責任者を交えて2~3回ほど壁打ちをします
3.内容構成が完成したら、インタビューや撮影、記事執筆にとりかかります
4.記事を出す前に、関係者に「①中間確認」を依頼し、「②修正」「③最終確認」を実施します
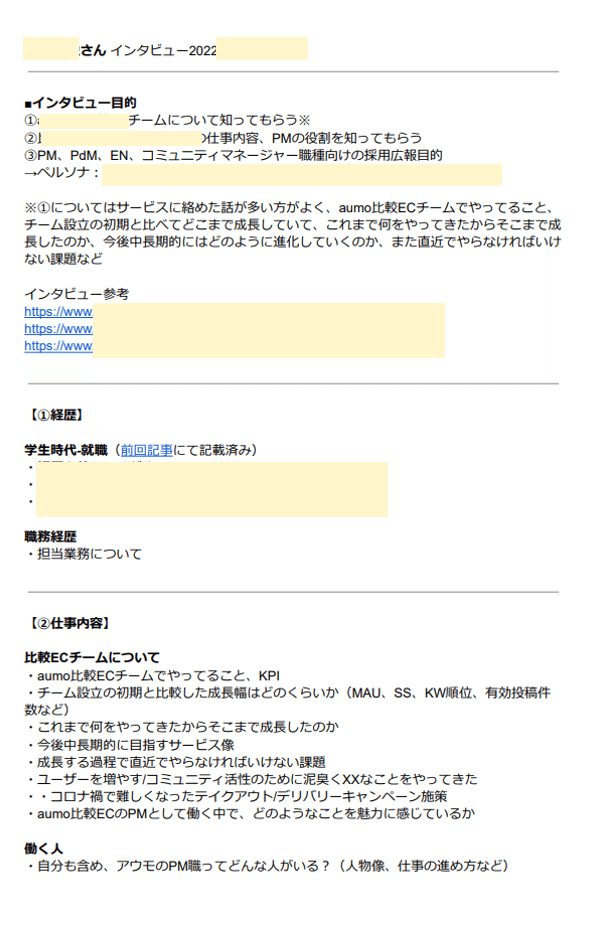
これだけの確認を重ねて方向性を軌道修正する理由は、「見せ方」だけでなく、その先の効果や、本質的な意図と内容に齟齬がないかどうかを確認するためでもあります。
6.3ヶ月ごとのスケジュールを決める
会社としてどういう情報を出した方がいいのか、一年の中でも1Qごとにマイルストーンを置くことで予定が円滑に進み、結果的により多くのコンテンツを出すことができるのと、先々の計画をすることで方向性を明確にすることができます。
採用広報は効果が見えづらいと言われますが、逆にやらなかったときの効果も見えづらいです。そのため採用広報業務と他の業務を兼務している場合でも、必ずスケジュールへの意識は高く持つべきだと思いました。
アウモでは広報全般を一括管理していて、「プレスリリース」「Wantedly」「Techblog」「note」「designer note」「会社紹介資料」のマイルストーンをスプレッドシートで管理しています。

7.社員全員でつくる
最近は、他社でも採用広報担当者以外のメンバーの発信がとても増えている印象がありますが、アウモでも事業責任者や社内メンバーなど多くの人が社外発信に参加しています。
自分が求職者だとしたら、その企業のよりリアルな部分まで知りたいと思うので、「より価値のあるコンテンツ」にするため役割分担をしながら社内全体でコンテンツづくりを進めています。
関係者からフィードバックをもらったり、公開したらパチパチ👏称賛し合うことで、2~3年前に比べて採用広報に限らずコンテンツの社外発信が活発化しました。
発信者にプロダクトメンバーも加わり全社的にコンテンツを出し続けた効果から、以前までは苦戦していた開発職種の応募数が2~3倍に増加しました。

(aumo TechBlog はこちら)
~改善~
8.失敗した話(気づいてよかった)
採用広報は記事のPVやUUなど数値化できるところもありますが、目に見えない効果も多くあります。だからこそ迷走して抜け出せなくなることがあったりします。(体験談)
■ 失敗例🙅
・目標を高く設定し過ぎてしまう
・質にこだわりすぎてリリースが遠ざかる
・コンテンツづくりで固めていくという考えから、構成の内容が薄くなる
・気づかないうちに「綺麗な枠」にはめようとしてしまう
『誤字はチェックするけど言い回しや伝え方は発信者に託す』というやり方のほうが、執筆者によって特徴が異なり、人間味のあるコンテンツになるので、読み応えがあるように感じます。
アウモでも、「Techblog」や「designer note」では執筆者の個性が出ているところが個人的に好きです🥰
9.一番大事にしていること
大事にしているのは、シンプルですが少しずつでも積み上げていくことです。最初は特に、小さなPDCAをぐるぐると回し続けていました。改善点を”もう見つけられない”ってくらい細かく出して、それが次の企画に活きたりしているので、とにかく数を経験することは必要でした。
とは言っても、改善点を見つけようと記事を修正の視点で見過ぎると、赤ペンの沼※にハマってしまうので注意です。
※赤ペンの沼=修正が必要ない文章でも、修正が必要に見えてきてしまうこと
量は大事ですが単発でコンテンツを出すだけではなく、『出したら振り返る』ことを繰り返し、次回に活かす点をできるだけ多く見つけて反映させていくことで、自社が得たい効果により近づけるようなコンテンツを作ることができるようになっていきました。
10.採用広報を隠している会社はない、とにかく勉強!
自社の情報を出すだけではなく、より高い効果を狙うことや、トレンドに沿って受け手に飽きられないようにするために、他社の手法も参考にしています。
一度決めたフローをずっと回していくのと、新しい発見を反映させ続けていくのとでは、すぐには違いを実感しづらいですが、半年後やさらにその先の採用数に大きく影響してくると思いながらやっています。
採用広報に関する新しい発見があったら社内チャットで共有したり、社内メンバーから「この記事参考になるね」「今度こんなイベントあるよ!」と共有してもらったり、全社で情報を共有・収集していくことも定着してきています。(ありがたや~)
日々勉強することは必要ですが、他社の活動をウォッチするだけでなく、複数の視点を持つことで気づきが増えるようになりました。
■ 多角的な視点で疑問を持つ
・どんな背景から企画されたコンテンツなのか
・目的やゴールはどこに設定されているのか
・制作段階で課題になりそうなこと
・その先に得られる効果はなにか/どのくらいか
・どんな問い合わせがありそうか など
~最後に~
11.この先に挑戦したいこと
最後に、立ち上げから広報まわり全般を担当していて、今後やりたいと思っていることを書きます。
・企業ブランディングをもっと勉強する
・”誰もが知るサービス「aumo」にしていく”を、広報の力で加速させる
・アウモに携わったことが価値となる未来のメンバーを100人採用する
この辺りはまたnoteにも書きたいと思います。”100人採用”というのは中長期的な視点ですが、実際いまもめちゃくちゃ採用を強化しています。社外に発信した情報を見て会社に興味を持っていただき、サービスや事業の楽しさを感じてもらえる人がこれからも増えていくと嬉しいです。
そして、どれだけやっても時間が流れている限り採用広報活動は続いていくので、これからも全社でコツコツと着実にやっていきたいと思います。
▼会社紹介資料
▼カジュアル面談の応募
▼aumo採用について
▼aumo Techblog
