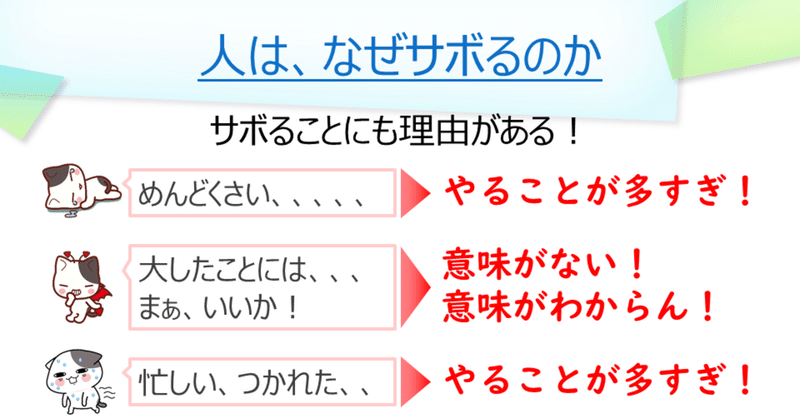
安全に必要な倫理観? ~サボらせないって難しい~
こんにちは! あたたけ です。
前々回、『Safety-Ⅱ』を実現するためには、
人に『専門知識』と『倫理観』が必要という話をしました。
※前々回記事はこちらです。
今回は『倫理観』というものを考えていきます!
と言ったところで、あたたけ的には
『やることをキチンとやる(≒大事なことはサボらない)意思』で
終わりなんですけどね。
では、『どうすれば人はサボらないのか』ということを考えてみましょう。
こういう、『気持ちの問題』を解決する時、
ありきたりですが、私は以下のような流れで考えます。
①まずは自分に当てはめる
(自分はどのような時にサボるのか・サボらないのか)
②それが一般にも通用するか考える
人の気持ちに関わることは、あまり理屈通りになりませんので、
まずは、『自分という人』をベースに考えてみようということですね。
(行動経済学の話を参考にすることもありますが)
さて、自分がサボる時のパターンですが、だいたい下のようなものです。
①メンドー(ルールが多い)
②サボっても大したことにならない
(ルールの重要性が低い、意味がわからない)
③忙しい、疲れた(他にすることが多い≒ルールが多い)

さて、この『あたたけの感じ方』を元に考えると、
『やることをキチンとやる意思』を『維持』するには、
次の2つが大切ですね。
①やることを絞り込む
②やることの意味を理解させる

『やることを絞り込む』については、
過去のSafety-Ⅱの記事で書いていますのでそちらをご覧ください。
(簡単には、以下のイラストです。)
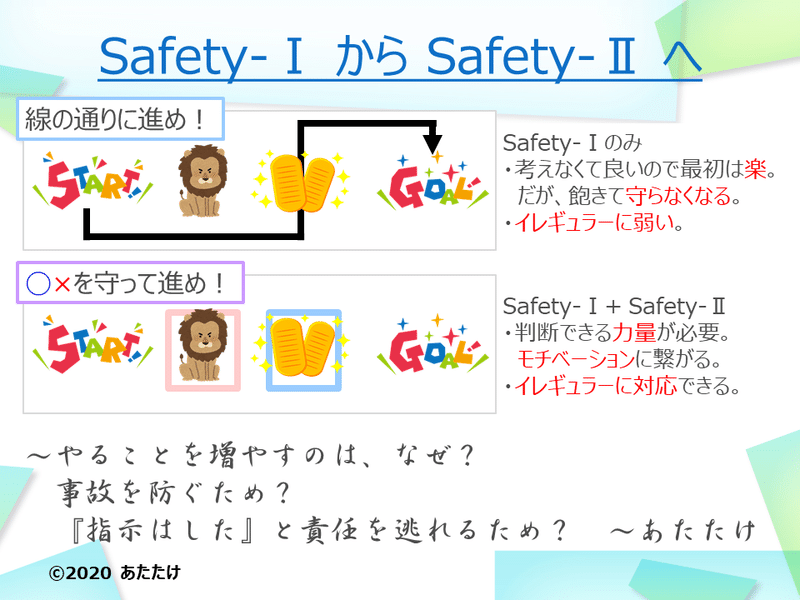
『やることの意味を理解させる』についてですが、
これも、Safety-Ⅱに必要な能力として以前の記事で書いていますね。

※ちなみに、前回記事はこちらです。
ということで、倫理観と言っても、
『自分が原因で事故は起こしたくない』というのは当然の感覚ですので、
ムリをさせないようにすれば、まぁ、大丈夫でしょう。
この辺りもSafety-Ⅱのポイント、『相手に任せること』の効果ですね。
では、ルールを守る側にムリをさせないため
『ルールを作る人、守らせる人』はどうすることが望ましいのでしょうか?
一言であらわすと『清濁併せ吞むこと』だと思います。
もっと言えば、『濁(≒現実)』を良い感じに呑むこと、
濁を呑む覚悟を持ち、呑みすぎない判断ができることです。
だって、『清(≒理想)』は、正しいことなので誰でも呑めますから。
まずは、
『安全を確保するため(かつ、法律に違反しないため)に、
どこまでギリギリのレベルでルールを設定できるか』
ということが大切だと思います。
『今までやってきた』『他所もやっている』とかに対し、
『そんなのいらない』と言い切れる知識と度胸を持ちたいものです。

あと、ルールは守っていないが、安全性は確保できているという時に
『ルールを守っていないこと自体をどこまで許容できるか』ということも
心掛けたいものです。
鬼の首を取ったように批判するのか、
次は気をつけてねと注意を促すのか、
その後、キチンと守るようになればどっちでも良いんですけどね。
(ルールが過剰なだけ、ということもありますが。。。
過剰なルールを放置しているのは、誰の責任でしょう?)

それでは、今回はこの辺りで!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
