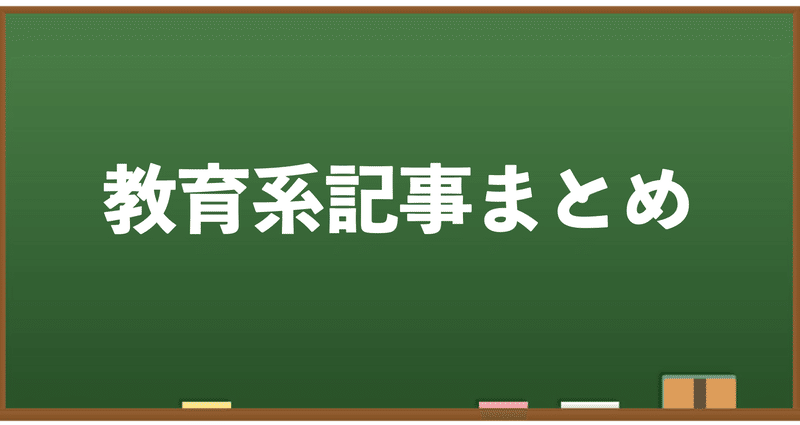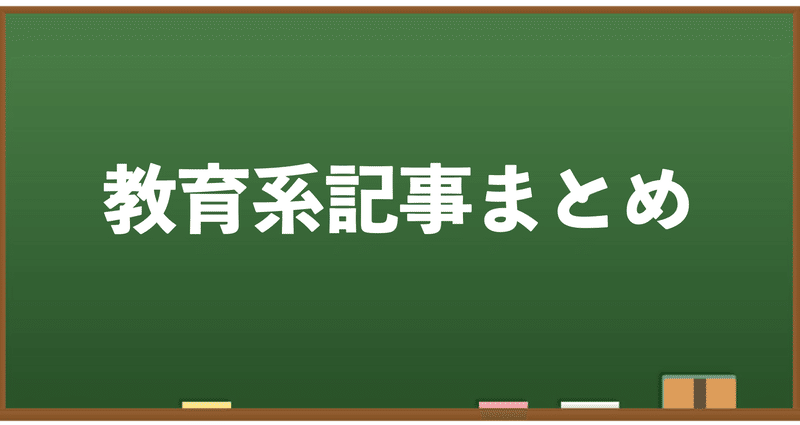ゆとり高校教員が考える「学校の未来」と「不安」
こんにちは。クマです。私はゆとり世代のアラサー高校教員です。
私は数年間、教員として高校で働いてきて、学校について様々なことを考えて来ました。ここでは、私の予想する学校教育の未来についてお話したいと思います。そして、私の最後に私の「不安」について書いていきたいと思います。
ちなみにここに書くのは、あくまで、私の個人的な予想や願望が入り混じった身も蓋もないストーリーです。的中するかどうかは全く保証できませんので、ご了承ください。
高校教員の仕事 現状、高校教員の仕事は大