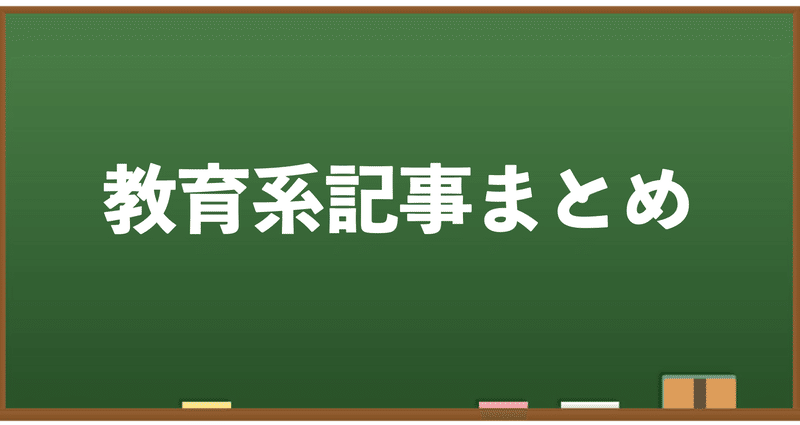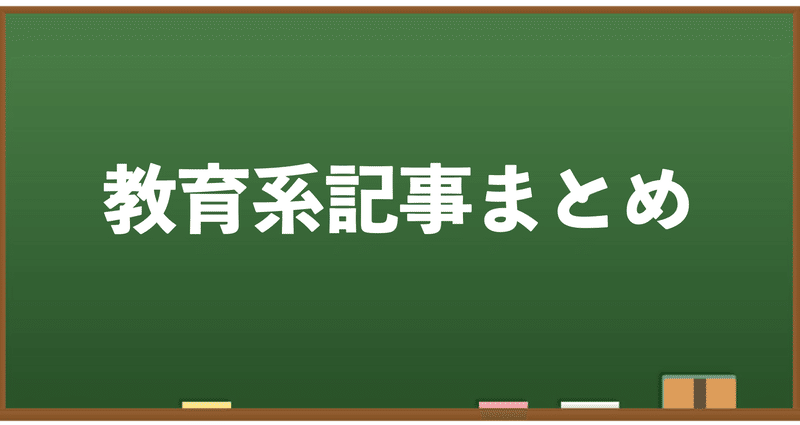教員は”Googleフォーム”で働き方が変わる。
読んでいただきありがとうございます!
今日はタイトルの通り、Googleフォームを紹介します。
おそらくこれを紹介する記事やブログはたくさんあると思います。
なので、この記事では基本的な使い方を紹介した後、
教員に特化した具体的な活用事例を紹介したいと思います。
【1】本校のICT環境❶ 教員1人1台の公務用PC
❷ 教員1人1台のiPad(第6世代)校内Wi-Fiに接続
❸ 教員間での共有のChromebookが数台
❹ 生徒用貸し出しiPadが1学年あたり約40台
【