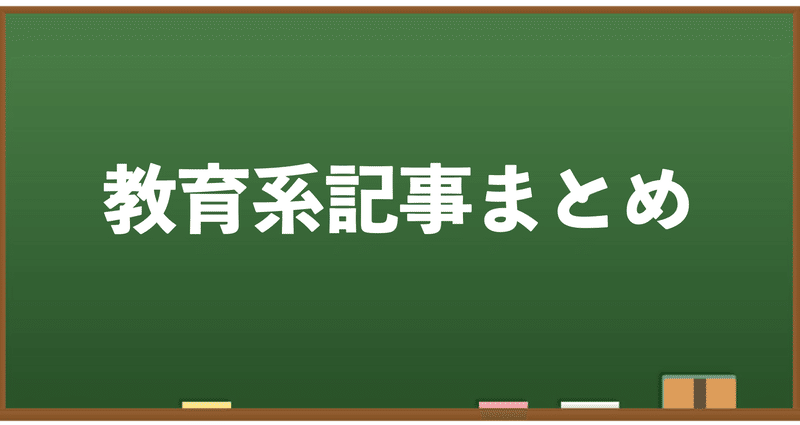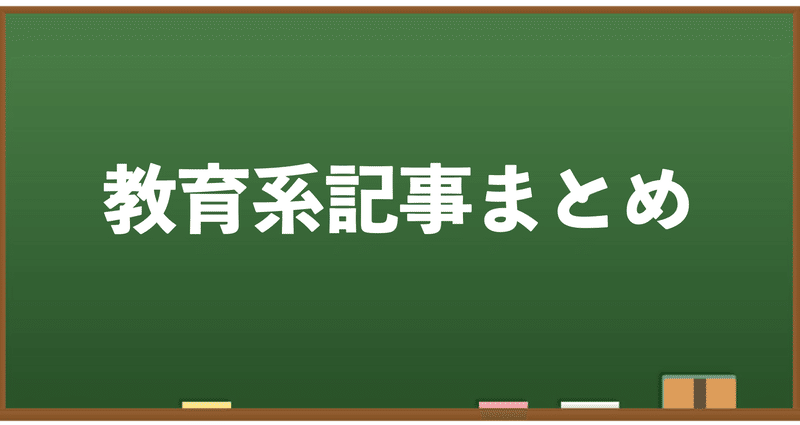学校の先生が毎日の授業で意識していること
小学校教員は基本的に毎日6時間授業がある。その一つ一つの授業を入念に準備して臨んでいる先生は、全国にどのくらいいるだろうか。おそらく、1パーセント以下だろう。あ、もちろん僕はできてません。だから、そんな僕みたいな先生でも、少しでも子どものためになる授業をするためのポイントを紹介したい。
教材研究指導要領を読み込み、きっちり教材研究して、指導計画を練って指導することはもちろんある。でも、常に出来るかと言ったら、それは不可能。独身時代のように、放課後の時間が無限にあれば話は別だ