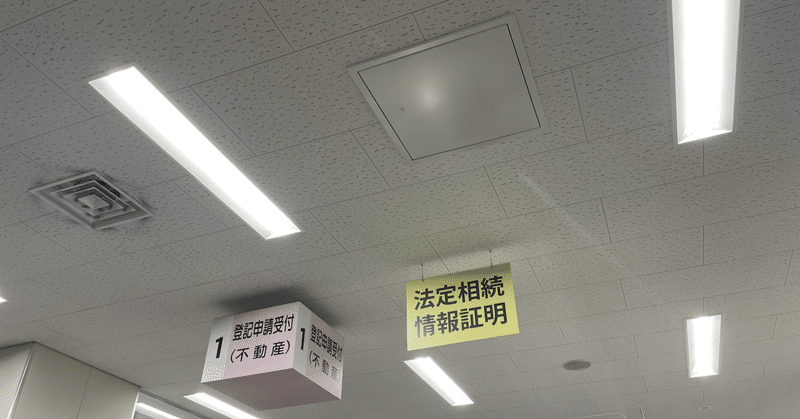
50代・行政書士副業開業の記録(22)~家族信託と任意後見制度の違い~
こんにちは。
今回は家族信託と任意後見制度の違いをまとめてみます。
(法定後見制度は認知症等で「使わざるを得ない」要素があるため今回は除外します。)
こどもがいない人の場合、自身の老後を真剣に考えるとどちらかを利用する(もしくは併用する)場合があります。
<共通点>
・自身が元気なうちにできる。
・売買・賃貸ができる(任意後見制度の場合は効力発生後・つまり本人が認知症等になった後)
<家族信託>
「贈与でない方法で財産管理を家族に任せる方法」・管理人のイメージ
〇初期費用のみ(30~50万円が目安)、ランニングコストなし
〇対象は財産(不動産・預貯金など)のみ
〇修繕借入・建て替えなどの財産の積極的な運用が可能
〇遺言機能をつけられる(財産の引継ぎ可)
〇効力は原則、契約締結時から
〇契約書式は自由(公正証書が望ましい)
△田んぼや畑は原則信託できない(実際宅地で使っていれば可能な場合が多い)
△相続「税」対策には特にならない
〇「持ち家がある場合、介護費用に使う意思があるか」はひとつのポイント
<任意後見人>
「認知症発症後から亡くなるまでを、介護サービスなどの生活サポートも含め任せたい」・代理人のイメージ
〇初期費用(10~20万円が目安)、監督人報酬(2万円~/月)が発生
〇対象は財産以外も含む
〇財産の積極的な運用ができない
〇遺言機能なし(財産の引継ぎ不可・死後は対象外)
〇上記に備え、遺言、死後事務委任契約も考慮にいれる
〇家庭裁判所が関与する。監督人報酬も家庭裁判所が決める
△判断能力喪失時、任意後見は自動的にはじまらない(家庭裁判所への任意後見監督人選任申立が必須のため)
〇上記に備え、「見守り契約」や「財産管理委任契約」の締結が望ましい。「任意後見監督人の選任義務」を明記することでスムーズな後見運用につながる
△任意後見が開始されると亡くなるまで途中でやめることが難しくなる。任意後見開前に相性や対応の質をチェックしておくのがよい
〇効力発生時(認知症発生時等)に監督人を家庭裁判所が(弁護士・司法書士から)選任
〇契約書式は公正証書のみ
△本人の自主性を尊重するため、任意後見人に契約の取消権がない
(代理権目録に取消権行使の条項を明記しておくとよい)
〇「ピンピンコロリ」なら初期費用のみですむともいえる
〇信頼できる監督人候補(専門家)を考えておくとよい
△は特に注意すべき点の意味です。
個別事情が大きく影響し、オーダーメイドの面が多々ある。制度的にも未成熟な点も実際あると思われるので、制度の変更を注視しつつ、慎重な運用が求められる。本人と家族が元気なうちに可能な限り「どうしたいのか(どうされたくないのか)」しっかり話し合っておくのがやはり一番大切である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
