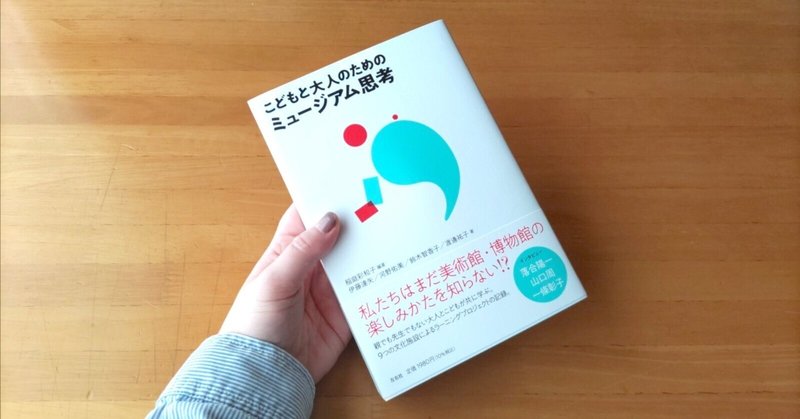
最新のお仕事|『こどもと大人のためのミュージアム思考』(左右社、2022年)
東京都美術館と東京藝術大学が推進し、上野公園にある9つの文化施設が連携して行っているラーニング・デザイン・プロジェクト「Museum Start あいうえの」というプロジェクトをご存知でしょうか?
複数のミュージアムが集まる上野公園の立地を生かし、実際に絵画や彫刻、化石や標本などを目でみて、ワークショップなどで手を動かして、こどもたちのミュージアム・デビューを応援しよう!というものです。
2022年度で10年目を迎えることを記念して出版された本書には、「あいうえの」の紹介はもちろん、参加者の声、学芸員やアートコミュニケーターといった関係者の声、有識者へのインタビューを収録。ミュージアムに馴染みのないこどもや大人の方に向けて、ミュージアムという場所の楽しみ方を提案する一冊です。
私は、東京国立近代美術館で教育部門を務める一條彰子さん、その東近美にてビジネスパーソン向けの鑑賞ワークショップの講師も行う研究者・著作者の山口周さんのインタビューをまとめさせていただきました!
(インタビューは学芸員さんと別のライターさんが担当されました)

一條さんは、作品を観察して感じたことを言語化するクリエイティブな思考や、意見を出し合って違いを認め合うディスカッションの技術は、文化財が収集・保存され、研究の蓄積もある美術館だからこそできる学びだと述べています。
学校の授業では、学校の問題や振る舞いなど、正解・不正解がはっきりと決まっているものが多いでしょう。
一方、美術館にあるアート作品は、必ずしもわかりやすいものではなく、(作品の解釈はともかく)感想や感じ方、楽しみ方に正解はありません。
一度だけ東近美でガイドスタッフによるギャラリートークに参加したことがあるのですが、「この作品の描かれた時間帯はいつだと思いますか?」という問いに、「空の明るい感じが朝だと思う」「いや、影の長さが夕方ではないか」など、さまざまな意見が出ました。みなさんよく観察しているな、気付けるなと感心しました。
美術史の勉強をしてきた人であれば、作家の画歴や様式、当時の時代背景などから作品を読み解きますが、そうした知識がなくとも、じっくり鑑賞して自覚的に脳を働かせることで、一歩踏み込んだ鑑賞ができるのだと実感しました。

山口さんによると、ビジネスでは「Aという事象にBで対処する」といったパターン認識で課題を判断・解決しますが、それでは未だうまく把握できない未知の事象、たった今、その先に起こる問題に対処できないそうです。アート作品や自然には言語化・記号化されていない情報がたくさん詰まっており、そうしたものに触れることで、頭や心のコリをほぐし、未来を生き抜くセンスが養えると説明しています。
さらに、こどもたちには「普通がいい病」にはかかってほしくない。人との違いを認めることで自己肯定感も高まり、クリエイティブ・コンフィデンス(創造力への自信)につながるとも述べていました。
私は小学生の頃、どんな問いに対しても教科書が定めた、あるいは先生が望む答えがあって、道徳の授業や国語の記述問題でも「こういう意見が正解だろう」と思って回答していました。
しかし、現実には立場が違えば正解と思う/思いたいことも違いますし、作家が何を言いたかったのかも研究者によって見解が違います。短い時間で限られた情報から自信を持って判断するというのは、容易ではありません。
ミュージアムやフィールドの中など、学校の外に学びの場があることで、既存の概念や考え方に縛られない頭や心の動かし方を身につけることができます。そうした体験は、物事を見極めるトレーニングになるかもしれません。

一條さんは、人によっては美術館や博物館に行く習慣がないため、義務教育でミュージアムに行く機会をつくることが大事だと言います。
親に関心があれば普段のお出かけや家族旅行などでミュージアムを訪れますし、「ミュージアム=楽しい場所」と認識するでしょう。しかし、学校の行事や宿題で仕方なく行った、親も面倒くさそうだったとなれば、「ミュージアム=つまらない場所」と苦手意識を持ち、そのまま大人になってしまうかもしれません。
ミュージアムは、学問的な知識でがんじがらめにするところではなく、むしろ既成概念から解き放ってくれる場所です。
こどもやこどもを持つ親だけでなく、何かに行き詰まっている大人にも、ぜひ身構えずに読んでいただきたいです。
よろしければサポートをお願いいたします。いただいたサポートでミュージアムに行きまくります!
